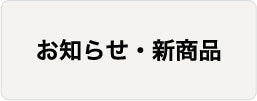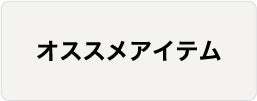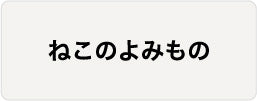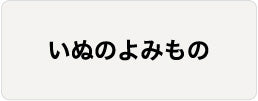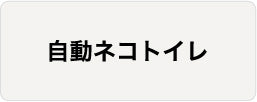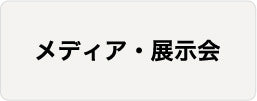OFT STORE BLOG

実は間違えている?愛犬のお手入れ方法
愛犬のためにと思って日頃から熱心に行っているお手入れですが、その方法は本当に正しいでしょうか?良かれと思っていても、実は間違っていたという事は少なくありません。私は大丈夫!なんて方も実は要注意かもしれませんよ。今回は意外と知らない、ワンちゃんの間違ったお手入れ方法についてご紹介いたします。 ドライヤーの温風のみ使用する 愛犬のシャンプー後、一番大切なのはタオルでしっかりと水分を取ることです。しかし、タオルで拭いただけでは蒸れて皮膚病になってしまう可能性があるため、シャンプー後はドライヤーを使用してしっかり乾かしてあげましょう。この時ドライヤーの温風のみ使用していたりしませんか。実はドライヤーの温風だけではワンちゃんの血行が良くなりすぎて、かゆみを招いてしまうのでNG行為なのです!ドライヤーの距離にも注意し、被毛を(スリッカー)ブラシなどで起こしながら、皮膚ではなく被毛を温風・冷風を使い分けて乾かしてあげましょう。特に、アトピー性皮膚炎などの皮膚病をお持ちの場合は様子を見ながら行ってください。温風の熱がこもってしまうため仕上げに冷風をかけてあげるのがおすすめです。 毎日シャンプーする お散歩の後など、愛犬が汚れてしまったからと毎日シャンプーをしていませんか?私達にとっては普通のことかもしれませんが、ワンちゃんの場合は違います。毎日シャンプーをしてしまうと必要な油分まで流れてしまい、乾燥や皮膚トラブルの原因になってしまう可能性があるのです。特にすすぎ残しは皮膚炎の原因の一つとなることもありますので、しっかりとすすいであげることが大切です。普段は出来る限りタオルで拭き取ってあげたり、どうしても汚れが気になる場合はドライシャンプーを使用したりしましょう。また、全身でなくとも散歩後に足裏を洗う行為も同様です。濡れたタオルで拭き取る程度にして下さい。 耳掃除を綿棒でする 愛犬の耳を掃除する際、もし綿棒を使用しているのであればすぐに辞めましょう。耳の穴はL字型に曲がっているので、無理に洗ってしまうと綺麗にしてあげるはずが、知らないうちに耳を傷つけてしまい、最悪の場合は炎症を起こしてしまうこともあるのです。ワンちゃんに多い、外耳炎の原因にもなりかねません。奥までゴシゴシ掃除する必要はありませんので、耳掃除はコットンや柔らかいガーゼで耳の表面を優しく拭いてあげて下さい。掃除ではなく耳の中の状態を日ごろからチェックしてあげましょう。 毛を引っ張ってブラッシング 愛犬の健康を保つため、毎日のブラッシングは欠かせませんが、やり方によっては愛犬を傷つけてしまいます。ヨークシャーテリアやプードルなど長毛や毛が柔らかい犬種の場合、毛玉になりやすくお手入れも大変ですが、毛先から徐々に取ってあげましょう。また、短毛、長毛種に合わせてブラシやコームを選んで下さいね。絡まったりもつれたりしているからと無理に引っ張ったり、力を入れすぎると皮膚を傷つけてしまううえ、ワンちゃんも痛いので、優しく丁寧に行ってあげて下さい。抜け毛の多い時期には、ラバーブラシを使うのも良いですよ♪本来、血行促進やリラックス効果のあるブラッシングが、ワンちゃんにとって苦痛なものになってしまわないよう気をつけましょう。 正しいお手入れで愛犬とコミュニケーションを 間違ったお手入れ方法は、愛犬を傷つけ苦痛な思いをさせてしまいます。ワンちゃんのためにと思って行っていたのに、病気やお手入れ嫌いになってしまっては本末転倒ですよね。お手入れはコミュニケーションの1つです。正しいお手入れ方法で、ワンちゃんと楽しい時間を過ごしましょう。 ▼ この記事を書いたのは ▼
実は間違えている?愛犬のお手入れ方法
愛犬のためにと思って日頃から熱心に行っているお手入れですが、その方法は本当に正しいでしょうか?良かれと思っていても、実は間違っていたという事は少なくありません。私は大丈夫!なんて方も実は要注意かもしれませんよ。今回は意外と知らない、ワンちゃんの間違ったお手入れ方法についてご紹介いたします。 ドライヤーの温風のみ使用する 愛犬のシャンプー後、一番大切なのはタオルでしっかりと水分を取ることです。しかし、タオルで拭いただけでは蒸れて皮膚病になってしまう可能性があるため、シャンプー後はドライヤーを使用してしっかり乾かしてあげましょう。この時ドライヤーの温風のみ使用していたりしませんか。実はドライヤーの温風だけではワンちゃんの血行が良くなりすぎて、かゆみを招いてしまうのでNG行為なのです!ドライヤーの距離にも注意し、被毛を(スリッカー)ブラシなどで起こしながら、皮膚ではなく被毛を温風・冷風を使い分けて乾かしてあげましょう。特に、アトピー性皮膚炎などの皮膚病をお持ちの場合は様子を見ながら行ってください。温風の熱がこもってしまうため仕上げに冷風をかけてあげるのがおすすめです。 毎日シャンプーする お散歩の後など、愛犬が汚れてしまったからと毎日シャンプーをしていませんか?私達にとっては普通のことかもしれませんが、ワンちゃんの場合は違います。毎日シャンプーをしてしまうと必要な油分まで流れてしまい、乾燥や皮膚トラブルの原因になってしまう可能性があるのです。特にすすぎ残しは皮膚炎の原因の一つとなることもありますので、しっかりとすすいであげることが大切です。普段は出来る限りタオルで拭き取ってあげたり、どうしても汚れが気になる場合はドライシャンプーを使用したりしましょう。また、全身でなくとも散歩後に足裏を洗う行為も同様です。濡れたタオルで拭き取る程度にして下さい。 耳掃除を綿棒でする 愛犬の耳を掃除する際、もし綿棒を使用しているのであればすぐに辞めましょう。耳の穴はL字型に曲がっているので、無理に洗ってしまうと綺麗にしてあげるはずが、知らないうちに耳を傷つけてしまい、最悪の場合は炎症を起こしてしまうこともあるのです。ワンちゃんに多い、外耳炎の原因にもなりかねません。奥までゴシゴシ掃除する必要はありませんので、耳掃除はコットンや柔らかいガーゼで耳の表面を優しく拭いてあげて下さい。掃除ではなく耳の中の状態を日ごろからチェックしてあげましょう。 毛を引っ張ってブラッシング 愛犬の健康を保つため、毎日のブラッシングは欠かせませんが、やり方によっては愛犬を傷つけてしまいます。ヨークシャーテリアやプードルなど長毛や毛が柔らかい犬種の場合、毛玉になりやすくお手入れも大変ですが、毛先から徐々に取ってあげましょう。また、短毛、長毛種に合わせてブラシやコームを選んで下さいね。絡まったりもつれたりしているからと無理に引っ張ったり、力を入れすぎると皮膚を傷つけてしまううえ、ワンちゃんも痛いので、優しく丁寧に行ってあげて下さい。抜け毛の多い時期には、ラバーブラシを使うのも良いですよ♪本来、血行促進やリラックス効果のあるブラッシングが、ワンちゃんにとって苦痛なものになってしまわないよう気をつけましょう。 正しいお手入れで愛犬とコミュニケーションを 間違ったお手入れ方法は、愛犬を傷つけ苦痛な思いをさせてしまいます。ワンちゃんのためにと思って行っていたのに、病気やお手入れ嫌いになってしまっては本末転倒ですよね。お手入れはコミュニケーションの1つです。正しいお手入れ方法で、ワンちゃんと楽しい時間を過ごしましょう。 ▼ この記事を書いたのは ▼

ペットと赤ちゃんのいる暮らし
ペットと赤ちゃんが一緒にいる姿はとても癒されます。これから始まる新しい共同生活に、わくわくしている妊婦さんもいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし、その反面、どのような生活になるのかが想像できず不安に思う方もいますよね。お互いが快適に暮らすために知っておくべきことについて、ご紹介したいと思います。 ペットと赤ちゃんの同居について ペットと赤ちゃんが同居することで、様々なメリットとデメリットがあります。 ■メリット【心の発達】ペットと一緒に成長していくことで、感情が豊かになり心の発達をサポートしてくれます。また、毎日ペットのお世話をすることで、責任感を持ち、命の大切さを学びます。ペットも母性本能が育つので、赤ちゃんが泣いた時や危険が迫っている時など、急いで駆け寄り守ろうとする姿勢が見られるかもしれません。お互いの心の発達に良い影響をもたらしてくれるのです。【脳の発達】子ども達の脳は10歳でほぼ出来上がります。それまでの時期に、人と人、人と動物、人と自然とのふれあいで、感受性豊かな脳へと発達すると証明されています。【免疫力アップ】赤ちゃんのうちからペットと接すると様々な菌に触れるため、免疫力がアップし、アレルギーになるリスクが低くなると言われています。 ■デメリット【感染症のリスク】アレルギーのリスクが低くなるとお話ししましたが、100%という訳ではありません。体質によってはパスツレラ菌やトキソプラズマ症など犬の持つウィルスでの感染症や、犬アレルギーになってしまう可能性もあるため注意が必要です。【ケガや事故の原因】どんなにしつけをしているペットであっても、予測不能な言動をする子供相手では、何が起こるかわかりません。ケガや事故につながらないよう、目を離さず注意し、ベビーベッドやサークルを活用しましょう。 ペットの気持ちを理解する 新しい家族が増えた時、ペット達も急な環境の変化に戸惑います。飼い主さんを取られたと勘違いし、 嫉妬で赤ちゃんに攻撃をしたり、 落ち込んで食欲が低下してしまう子もいます。今までとは違い赤ちゃんのお世話に忙しくなりますが、先に住んでいたペットが不安やストレスを感じないよう日々しっかり観察して、たっぷりの愛情をそそいであげましょう。 同居で注意すべきこと 仲良くお互いがベストな環境で生活するにはどうしたら良いのか、注意すべきことについてご紹介いたします。■しつけ甘噛み、飛びつき、トイレなどペットのしつけはとても重要です。甘噛みや顔を舐める行動は、赤ちゃんを傷つけるだけでなく感染症の原因になってしまうことがあります。赤ちゃんが生まれてからの生活を想像し、出産前から準備することによってしつけトラブルを未然に防ぎましょう。■ペットのケア日々のケアを怠ってしまうと、ペットの抜け毛やダニ等が原因でアレルギーや病気になってしまう可能性があります。また、薄い幼児の皮膚を傷付けないように、爪のケアなどにも気を付ける必要があります。 ペットも散歩に行けず運動不足でストレスを感じ病気になってしまうため、忙しくても日々のケアはしっかりしてあげましょう。■目を離さないペットと赤ちゃんを無理やり近づけると、普段大人しいペットでも、環境の変化によりストレスがたまり、思わぬ事故に発展する可能性があります。子供が理解できる年齢になるまでは、ペットと子供だけの空間を避けた方が良いでしょう。特にはじめて小さなお子さんとペットが触れ合う時には、保護者が監視する前で触れ合わせることが必要です。 子供がいる家庭で飼いやすいペット 子供がいる家庭でも飼いやすいと言われる犬や猫以外のペットの中から、おすすめの3種類のペットをご紹介いたします。■モルモット モルモットは、子供のいる家庭にとって、飼育しやすいペットの代表格です。 初心者の方でもお世話がしやすく、飼育スペースもとりません。ケージの掃除やエサあげ等はありますが、散歩が不要なので比較的飼育しやすいペットです。トイレの場所もしっかり覚えられるうえに、体臭も少ないため衛生面も心配がいりません。■うさぎ可愛らしい見た目で子供にも人気なうさぎ。飼育スペースとお世話の必要はありますが、一緒に遊ぶ事もできるため良いパートナーとなるでしょう。声帯がなく、鳴き声が気にならないので近所の目を気にする必要もありません。ただし、ウサギは後ろ脚の蹴り上げる力が強烈なため、後ろ脚の近くに顔を近づけないで下さい。ウサギと顔を見合わせるように抱き上げましょう。 ■鳥飼育スペースもとらず、鳥はペットとしても人気です。特に手乗りインコなどは、懐くと手や肩に乗ってくるため愛着が湧くこと間違いなしですね。鳥は短命なイメージもありますが、大型の鳥になると「インコは親が選ぶのではなく子供に選ばせなさい」という言葉があるように、親の寿命よりも長生きする種類もいます。小さなお子様との関係を専門家に相談しながら作っていくことができれば、最高のパートナーになるでしょう。 良い影響がたくさんあるペットと赤ちゃんの同居ですが、感染症やケガなど注意すべき点もあります。新しい家族にペットが混乱してしまわないように、事前にしっかりと準備をしていきましょう。ペットも赤ちゃんもお互いに尊重し合いながら、楽しく成長してくれたら嬉しいですね! ▼ この記事を書いたのは ▼
ペットと赤ちゃんのいる暮らし
ペットと赤ちゃんが一緒にいる姿はとても癒されます。これから始まる新しい共同生活に、わくわくしている妊婦さんもいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし、その反面、どのような生活になるのかが想像できず不安に思う方もいますよね。お互いが快適に暮らすために知っておくべきことについて、ご紹介したいと思います。 ペットと赤ちゃんの同居について ペットと赤ちゃんが同居することで、様々なメリットとデメリットがあります。 ■メリット【心の発達】ペットと一緒に成長していくことで、感情が豊かになり心の発達をサポートしてくれます。また、毎日ペットのお世話をすることで、責任感を持ち、命の大切さを学びます。ペットも母性本能が育つので、赤ちゃんが泣いた時や危険が迫っている時など、急いで駆け寄り守ろうとする姿勢が見られるかもしれません。お互いの心の発達に良い影響をもたらしてくれるのです。【脳の発達】子ども達の脳は10歳でほぼ出来上がります。それまでの時期に、人と人、人と動物、人と自然とのふれあいで、感受性豊かな脳へと発達すると証明されています。【免疫力アップ】赤ちゃんのうちからペットと接すると様々な菌に触れるため、免疫力がアップし、アレルギーになるリスクが低くなると言われています。 ■デメリット【感染症のリスク】アレルギーのリスクが低くなるとお話ししましたが、100%という訳ではありません。体質によってはパスツレラ菌やトキソプラズマ症など犬の持つウィルスでの感染症や、犬アレルギーになってしまう可能性もあるため注意が必要です。【ケガや事故の原因】どんなにしつけをしているペットであっても、予測不能な言動をする子供相手では、何が起こるかわかりません。ケガや事故につながらないよう、目を離さず注意し、ベビーベッドやサークルを活用しましょう。 ペットの気持ちを理解する 新しい家族が増えた時、ペット達も急な環境の変化に戸惑います。飼い主さんを取られたと勘違いし、 嫉妬で赤ちゃんに攻撃をしたり、 落ち込んで食欲が低下してしまう子もいます。今までとは違い赤ちゃんのお世話に忙しくなりますが、先に住んでいたペットが不安やストレスを感じないよう日々しっかり観察して、たっぷりの愛情をそそいであげましょう。 同居で注意すべきこと 仲良くお互いがベストな環境で生活するにはどうしたら良いのか、注意すべきことについてご紹介いたします。■しつけ甘噛み、飛びつき、トイレなどペットのしつけはとても重要です。甘噛みや顔を舐める行動は、赤ちゃんを傷つけるだけでなく感染症の原因になってしまうことがあります。赤ちゃんが生まれてからの生活を想像し、出産前から準備することによってしつけトラブルを未然に防ぎましょう。■ペットのケア日々のケアを怠ってしまうと、ペットの抜け毛やダニ等が原因でアレルギーや病気になってしまう可能性があります。また、薄い幼児の皮膚を傷付けないように、爪のケアなどにも気を付ける必要があります。 ペットも散歩に行けず運動不足でストレスを感じ病気になってしまうため、忙しくても日々のケアはしっかりしてあげましょう。■目を離さないペットと赤ちゃんを無理やり近づけると、普段大人しいペットでも、環境の変化によりストレスがたまり、思わぬ事故に発展する可能性があります。子供が理解できる年齢になるまでは、ペットと子供だけの空間を避けた方が良いでしょう。特にはじめて小さなお子さんとペットが触れ合う時には、保護者が監視する前で触れ合わせることが必要です。 子供がいる家庭で飼いやすいペット 子供がいる家庭でも飼いやすいと言われる犬や猫以外のペットの中から、おすすめの3種類のペットをご紹介いたします。■モルモット モルモットは、子供のいる家庭にとって、飼育しやすいペットの代表格です。 初心者の方でもお世話がしやすく、飼育スペースもとりません。ケージの掃除やエサあげ等はありますが、散歩が不要なので比較的飼育しやすいペットです。トイレの場所もしっかり覚えられるうえに、体臭も少ないため衛生面も心配がいりません。■うさぎ可愛らしい見た目で子供にも人気なうさぎ。飼育スペースとお世話の必要はありますが、一緒に遊ぶ事もできるため良いパートナーとなるでしょう。声帯がなく、鳴き声が気にならないので近所の目を気にする必要もありません。ただし、ウサギは後ろ脚の蹴り上げる力が強烈なため、後ろ脚の近くに顔を近づけないで下さい。ウサギと顔を見合わせるように抱き上げましょう。 ■鳥飼育スペースもとらず、鳥はペットとしても人気です。特に手乗りインコなどは、懐くと手や肩に乗ってくるため愛着が湧くこと間違いなしですね。鳥は短命なイメージもありますが、大型の鳥になると「インコは親が選ぶのではなく子供に選ばせなさい」という言葉があるように、親の寿命よりも長生きする種類もいます。小さなお子様との関係を専門家に相談しながら作っていくことができれば、最高のパートナーになるでしょう。 良い影響がたくさんあるペットと赤ちゃんの同居ですが、感染症やケガなど注意すべき点もあります。新しい家族にペットが混乱してしまわないように、事前にしっかりと準備をしていきましょう。ペットも赤ちゃんもお互いに尊重し合いながら、楽しく成長してくれたら嬉しいですね! ▼ この記事を書いたのは ▼

シニア犬との老老介護について考える
愛犬との生涯を考えていく中で切り離せない問題となっているのが、人とペットの高齢化ではないでしょうか。シニア犬との生活は成犬と異なるため、日々の変化に対応しながら世話をしていく必要があります。しかし、飼い主さんも同じく高齢となると、家族の一員であるペットに最後まで寄り添う事が時として困難になります。「老老介護」問題がペットでも深刻化しているのが現状です。そこで、老老介護で必要なことは何か、注意する点も含め解説いたします。人とペットの高齢化が進む今、どんなことを意識して愛犬との生涯を過ごしていくべきなのか改めて考えてみましょう。 ペットの高齢化 私達人間と同じようにペットも高齢化が進んでいます。平均寿命も年々延びており、犬・猫ともに約14歳。人間で言うと70歳以上にあたります。そんなペットの高齢化の背景には様々な理由が考えられます。食事の品質向上市場ではペットの健康を考えて作られた良質なペットフードが増え、栄養バランスも考慮されるようになりました。また、手作り食やプレミアムフード、無添加フードなど愛犬の健康を考え食事の管理をする飼い主さんも増えているのです。環境の変化愛玩動物として手厚く飼育されるようになり、ペットのストレスが軽減されていることも大きいでしょう。飼育の際、困った時はすぐにインターネットで検索できたり、便利な飼育グッズが登場したりと、私達が生活する環境にも変化が出ています。ペット医療の発達最新の医療により病気の予防から治療まで幅広く対応できるようになったことも深く関わっています。難しい病気にも対応できる高度な技術でペット達の寿命も延びているのです。 シニア犬との生活 ペットの高齢化により重要になってくるのが、シニア犬との過ごし方です。シニア犬の場合、老化による体への負担も増えるため十分なケアが必要になります。食事や排泄など当たり前にできていたことが当たり前ではなくなってしまうこともあるので、日々の体調管理もかかせません。また、普段できていた階段の上り下りができなくなったり、段差のあるベッドにあがれなかったりと急に筋力が衰えてしまうこともあります。愛犬が高齢になってきたら今まで通り安心して生活していけるよう、飼育環境の見直や工夫をしてあげることが大切です。 ペットとの老老介護 ペットの高齢化についてお話してきましたが、人間も高齢化が進んでいます。そこで深刻なのが「老老介護」です。飼い主もペットも高齢の場合、食事の管理や散歩にケアなど日々のお世話が十分にできないだけでなく様々な問題がでてきてしまいます。中でも、■ ペットが病気になった際、すぐに病院へ連れていけない■ 自分が病気やケガをした際、ペットが取り残されてしまうなどは非常に難しく、互いの生命に関わってしまいかねない状況です。現に、飼い主さんから取り残されてしまったペットが年々増加しているのです。愛犬との幸せな生涯のためにも、老老介護問題は事前にしっかりと考える必要があります。 老犬(介護)ホームとは 老老介護が増えている中、需要が高まっているのが「老犬ホーム」です。老犬ホームは、事情により介護が難しくなってしまった飼い主さんの代わりに、愛犬を介護してくれる施設で、人間とペットの高齢化が進んでいる今、残されたペットが幸せに暮らせるようにと注目されています。介護なしでは生きていけないペットが安心して暮らせるよう、このような施設も視野に入れておく必要があるでしょう。さらに需要が高まりそうな老犬ホームですが、本来は家族の一員である飼い主さんが最期まで介護し見届けてあげることがペットにとっては一番です。老老介護が増えている今老犬ホームは必要不可欠になりつつありますが、初めから視野に入れての飼育はペットにとっては寂しいところです。愛犬と共に過ごす幸せな生涯を考えた場合、将来まで見据えてペットを迎えることが何よりも大切ではないでしょうか。 ▼ この記事を書いたのは ▼
シニア犬との老老介護について考える
愛犬との生涯を考えていく中で切り離せない問題となっているのが、人とペットの高齢化ではないでしょうか。シニア犬との生活は成犬と異なるため、日々の変化に対応しながら世話をしていく必要があります。しかし、飼い主さんも同じく高齢となると、家族の一員であるペットに最後まで寄り添う事が時として困難になります。「老老介護」問題がペットでも深刻化しているのが現状です。そこで、老老介護で必要なことは何か、注意する点も含め解説いたします。人とペットの高齢化が進む今、どんなことを意識して愛犬との生涯を過ごしていくべきなのか改めて考えてみましょう。 ペットの高齢化 私達人間と同じようにペットも高齢化が進んでいます。平均寿命も年々延びており、犬・猫ともに約14歳。人間で言うと70歳以上にあたります。そんなペットの高齢化の背景には様々な理由が考えられます。食事の品質向上市場ではペットの健康を考えて作られた良質なペットフードが増え、栄養バランスも考慮されるようになりました。また、手作り食やプレミアムフード、無添加フードなど愛犬の健康を考え食事の管理をする飼い主さんも増えているのです。環境の変化愛玩動物として手厚く飼育されるようになり、ペットのストレスが軽減されていることも大きいでしょう。飼育の際、困った時はすぐにインターネットで検索できたり、便利な飼育グッズが登場したりと、私達が生活する環境にも変化が出ています。ペット医療の発達最新の医療により病気の予防から治療まで幅広く対応できるようになったことも深く関わっています。難しい病気にも対応できる高度な技術でペット達の寿命も延びているのです。 シニア犬との生活 ペットの高齢化により重要になってくるのが、シニア犬との過ごし方です。シニア犬の場合、老化による体への負担も増えるため十分なケアが必要になります。食事や排泄など当たり前にできていたことが当たり前ではなくなってしまうこともあるので、日々の体調管理もかかせません。また、普段できていた階段の上り下りができなくなったり、段差のあるベッドにあがれなかったりと急に筋力が衰えてしまうこともあります。愛犬が高齢になってきたら今まで通り安心して生活していけるよう、飼育環境の見直や工夫をしてあげることが大切です。 ペットとの老老介護 ペットの高齢化についてお話してきましたが、人間も高齢化が進んでいます。そこで深刻なのが「老老介護」です。飼い主もペットも高齢の場合、食事の管理や散歩にケアなど日々のお世話が十分にできないだけでなく様々な問題がでてきてしまいます。中でも、■ ペットが病気になった際、すぐに病院へ連れていけない■ 自分が病気やケガをした際、ペットが取り残されてしまうなどは非常に難しく、互いの生命に関わってしまいかねない状況です。現に、飼い主さんから取り残されてしまったペットが年々増加しているのです。愛犬との幸せな生涯のためにも、老老介護問題は事前にしっかりと考える必要があります。 老犬(介護)ホームとは 老老介護が増えている中、需要が高まっているのが「老犬ホーム」です。老犬ホームは、事情により介護が難しくなってしまった飼い主さんの代わりに、愛犬を介護してくれる施設で、人間とペットの高齢化が進んでいる今、残されたペットが幸せに暮らせるようにと注目されています。介護なしでは生きていけないペットが安心して暮らせるよう、このような施設も視野に入れておく必要があるでしょう。さらに需要が高まりそうな老犬ホームですが、本来は家族の一員である飼い主さんが最期まで介護し見届けてあげることがペットにとっては一番です。老老介護が増えている今老犬ホームは必要不可欠になりつつありますが、初めから視野に入れての飼育はペットにとっては寂しいところです。愛犬と共に過ごす幸せな生涯を考えた場合、将来まで見据えてペットを迎えることが何よりも大切ではないでしょうか。 ▼ この記事を書いたのは ▼

知っておきたい「ペットの熱中症」と予防
今年5月、「自動車の中に取り残された場合、短時間であっても熱中症のリスク、命の脅かされるリスクが非常に高い」と、ペットの熱中症について初めて環境省から注意喚起がありました。年々暑さも厳しくなり、毎年5月から8月にかけてペットの熱中症が急増しています。今回は意外と知られていない「ペットの熱中症」について解説していきたいと思います。 熱中症にかかりやすいワンちゃん ワンちゃんは、屋外で過ごすことが多く、散歩にも出かけるため、特に気を付けてあげたいところです。 ハァハァと息遣いが荒かったり、ヨダレを垂らす時は、まず熱中症を疑いましょう。初期症状であることが多いです。 重症化した場合の30%は死亡のリスクがあり、極めて危険です。特に心臓が悪い、循環器が弱い、または肥満気味の子も肺や呼吸機能が低下して重症化しやすくなりますので、初期症状の段階で気付いて対処してあげることが大切です。 熱中症を疑う時は・常温の水を体にかける・水で濡らしたタオルなどで包む・風通しのよい場所に移動させて、うちわ等で風を送るなどとにかく体温を下げてあげて下さい。 熱中症対策をしましょう 気温が上がりだしたら、ワンちゃんのお散歩は日差しが強い日中は避けて早朝か日没の時間を選びましょう。また、ワンちゃんは地面との距離が近いので、人間よりも熱を感じてしまいます。お散歩の前に地面を触って熱さを確認して下さい。1番問題視されているのが子供やペットの自動車内での放置です。ワンちゃんは人間より体温が約2度高く、体温調整も苦手なため、たとえ15分ほどであっても車内の急激な温度上昇に体がついていかず、命を落とす危険性があります。車でお出かけする時は、ワンちゃんの様子をよく観てあげながら、エアコンで温度調整をしっかりし、短時間であってもお留守番をさせないようにしましょう。 ▲中に水を凍らせて遊ぶ、冷たくて気持ちがいい玩具「ソフトクリーム」 自宅のお部屋の場合は、通気性が良く、温度25度、湿度50%が推奨されています。ひんやり冷たい玩具など与えてあげるのも良いですよ♪また、水分補給がいつでもできる環境を整えてあげてくださいね。 猫ちゃんの熱中症対策は 猫ちゃんは、ワンちゃんよりさらに自分で体温調節する事が苦手です。気温が低すぎるのも体調を崩す原因となりますので、室内の気温は27℃~28℃くらいを保てるように調整してあげましょう。また、扇風機を使用する場合、直接風をあてるのではなく、室内の空気を循環させる事を意識してあげてください。もし、お気に入りのスペースがあれば、そこが日陰になる様に工夫して、直接日が当たり気温が高くならないように気を付けましょう。ブラッシングでアンダーコートを取り除いてあげると、熱がこもらず通気性も良くなるので、体温調整もしやすいですよ。 ▲水分補給も大切なので数か所水飲み場を設けてくださいね。「自動給水器 Pawbo Spring」 特に気を付けてあげたい品種 ワンちゃんは、短頭種(パグ、フレンチ・ブルドッグ、ボストン・テリア、チワワ、シー・ズーなど)や、北欧犬種(シベリアン・ハスキーなど)、また毛が黒い子が熱中症にかかりやすいと言われています。 特に鼻が低い犬種(パグやブルドッグ)は気道が狭いために体温調整が難しいので気をつけてあげて下さいね。 猫ちゃんでは、短頭種(ペルシャ、エキゾチックショートヘア、ヒマラヤン)や、長毛種の子の熱中症が多く、ウサギ、モルモット、ハリネズミなどの小動物も要注意です。 最後に ペット達は、体調不良を自ら言葉で伝えることはできません。動物の強さは我慢強さと言われるように、見た目がいつも通りに見えても我慢している時があるようです。 私たち飼い主も、日常生活からペットをよく観察し、健康管理をすることにより、少しでも異変があればかかりつけの病院に相談しましょう。 ▼ この記事を書いたのは ▼
知っておきたい「ペットの熱中症」と予防
今年5月、「自動車の中に取り残された場合、短時間であっても熱中症のリスク、命の脅かされるリスクが非常に高い」と、ペットの熱中症について初めて環境省から注意喚起がありました。年々暑さも厳しくなり、毎年5月から8月にかけてペットの熱中症が急増しています。今回は意外と知られていない「ペットの熱中症」について解説していきたいと思います。 熱中症にかかりやすいワンちゃん ワンちゃんは、屋外で過ごすことが多く、散歩にも出かけるため、特に気を付けてあげたいところです。 ハァハァと息遣いが荒かったり、ヨダレを垂らす時は、まず熱中症を疑いましょう。初期症状であることが多いです。 重症化した場合の30%は死亡のリスクがあり、極めて危険です。特に心臓が悪い、循環器が弱い、または肥満気味の子も肺や呼吸機能が低下して重症化しやすくなりますので、初期症状の段階で気付いて対処してあげることが大切です。 熱中症を疑う時は・常温の水を体にかける・水で濡らしたタオルなどで包む・風通しのよい場所に移動させて、うちわ等で風を送るなどとにかく体温を下げてあげて下さい。 熱中症対策をしましょう 気温が上がりだしたら、ワンちゃんのお散歩は日差しが強い日中は避けて早朝か日没の時間を選びましょう。また、ワンちゃんは地面との距離が近いので、人間よりも熱を感じてしまいます。お散歩の前に地面を触って熱さを確認して下さい。1番問題視されているのが子供やペットの自動車内での放置です。ワンちゃんは人間より体温が約2度高く、体温調整も苦手なため、たとえ15分ほどであっても車内の急激な温度上昇に体がついていかず、命を落とす危険性があります。車でお出かけする時は、ワンちゃんの様子をよく観てあげながら、エアコンで温度調整をしっかりし、短時間であってもお留守番をさせないようにしましょう。 ▲中に水を凍らせて遊ぶ、冷たくて気持ちがいい玩具「ソフトクリーム」 自宅のお部屋の場合は、通気性が良く、温度25度、湿度50%が推奨されています。ひんやり冷たい玩具など与えてあげるのも良いですよ♪また、水分補給がいつでもできる環境を整えてあげてくださいね。 猫ちゃんの熱中症対策は 猫ちゃんは、ワンちゃんよりさらに自分で体温調節する事が苦手です。気温が低すぎるのも体調を崩す原因となりますので、室内の気温は27℃~28℃くらいを保てるように調整してあげましょう。また、扇風機を使用する場合、直接風をあてるのではなく、室内の空気を循環させる事を意識してあげてください。もし、お気に入りのスペースがあれば、そこが日陰になる様に工夫して、直接日が当たり気温が高くならないように気を付けましょう。ブラッシングでアンダーコートを取り除いてあげると、熱がこもらず通気性も良くなるので、体温調整もしやすいですよ。 ▲水分補給も大切なので数か所水飲み場を設けてくださいね。「自動給水器 Pawbo Spring」 特に気を付けてあげたい品種 ワンちゃんは、短頭種(パグ、フレンチ・ブルドッグ、ボストン・テリア、チワワ、シー・ズーなど)や、北欧犬種(シベリアン・ハスキーなど)、また毛が黒い子が熱中症にかかりやすいと言われています。 特に鼻が低い犬種(パグやブルドッグ)は気道が狭いために体温調整が難しいので気をつけてあげて下さいね。 猫ちゃんでは、短頭種(ペルシャ、エキゾチックショートヘア、ヒマラヤン)や、長毛種の子の熱中症が多く、ウサギ、モルモット、ハリネズミなどの小動物も要注意です。 最後に ペット達は、体調不良を自ら言葉で伝えることはできません。動物の強さは我慢強さと言われるように、見た目がいつも通りに見えても我慢している時があるようです。 私たち飼い主も、日常生活からペットをよく観察し、健康管理をすることにより、少しでも異変があればかかりつけの病院に相談しましょう。 ▼ この記事を書いたのは ▼

猫ちゃんの爪をとぐ理由と対処法
近年、コロナ渦により新たにペットを家族として迎え入れる人が増えました。しかし、そのペットの特性や正しい飼育方法を知らないまま飼い始めてしまい、ペットの問題行動に頭をかかえたり、飼育を放棄してしまう人がいるのが現状です。今回は、特に悩みの多い猫ちゃんの爪とぎ行動について、すでに飼育されている、もしくはこれから飼育を検討されている方へ詳しくお伝えしたいと思います。 爪をとぐ必要性 実は、爪とぎは猫ちゃんの本来の狩猟本能により生後2ヵ月頃から始まる行動なのです。■縄張り主張のマーキング手の肉球付近に臭腺があり、爪をといで自分のニオイをつけて自分の縄張りを周りに知らせるという意味があります。猫ちゃんが好んで背伸びをしながら高い位置で爪をとぐのも、自分の力強さをアピールするためなのです。■ストレス発散何か失敗したときや気持ちを落ち着かせたい時に、爪とぎをすることで安心感を得ています。また、遊んで欲しい時やかまって欲しい時にも同じく爪とぎをすることもあります。■古い爪の角質を剥ぎ落とし常に鋭く保つ野生の猫は普段から土の上を走って狩りをしたり木に登ったりするので自然と角質がはがれていきますが、室内飼いの猫は自然に角質が剥がれることがほとんどありません。そのため、自ら爪をといで古い角質を落とそうとします。このように猫ちゃん本能からくる行動として爪をといでいるのです。 問題行動への対処 ▲思いっきり伸びながら爪がとげるキャットタワーHIDAMARI とはいえ、壁や障子、襖、家具等をどこでもガリガリして傷つけてしまうので、飼い主様からすると困ってしまいますよね。まずは、飼い主さんが猫ちゃんに爪をとげる環境を用意し、対策することが大切です。あらかじめ部屋の至る所に爪とぎ器を設置してあげましょう。決められた場所で爪をとげた時は、優しく声をかけながら撫でたり、おやつをあげることを繰り返すことで、正しい場所を認識させていきます。また、壁に防止シートを貼ったり、家具をゲートやアクリル板などで囲うなど事前に防止してあげることも大切です。 ▲猫ちゃんの爪とぎから事前にガードできるディフェンスパーテーション 中には抜爪手術をされる飼い主さんもいらっしゃいますが、慢性的な痛みなど猫ちゃんへのデメリットがたくさんある為、あまりオススメはしません。猫ちゃんをしつけることは難しいですが、少しずつ学んでいきますので、焦らずにゆっくり猫ちゃんのペースで対処していきましょう。マーキングが主な原因で爪をといでしまう時は、不妊手術を行うことで軽減する猫ちゃんもいます。あくまで個体差がありますので、まずは動物病院へ相談しましょう。 猫に人気の爪とぎ 猫が好きな爪とぎ器の素材として人気なのは、ずばり段ボール素材です!柔らかいけれども程よく固さもある段ボールが猫ちゃんにとってはたまらないようです♪オーエフティーでは、エレガントな雰囲気漂う見た目と、猫ちゃんのソファとしても使える段ボール素材の爪とぎソファカリカリーナを販売しています。 ▲カリカリーナLuce 研ぎカスが出にくいのも人気の秘訣です♪ 「猫ちゃんのお気に入りの場所になった」「丈夫で研ぎカスもほとんど出ず、長く使える」と、飼い主さんからも好評を頂いています。是非チェックしてみてください。 おわりに 爪とぎは、猫ちゃんにとって、食事や排せつ、睡眠と同じくらい大切な行動です。思う存分させて、本能欲求を満たしてあげましょう。オーエフティーではペットと共に快適な暮らしができるよう、お客様をサポートさせいただきます。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。キャットタワーHIDAMARIの詳細はこちらカリカリーナの詳細はこちらディフェンスパーテーションの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼
猫ちゃんの爪をとぐ理由と対処法
近年、コロナ渦により新たにペットを家族として迎え入れる人が増えました。しかし、そのペットの特性や正しい飼育方法を知らないまま飼い始めてしまい、ペットの問題行動に頭をかかえたり、飼育を放棄してしまう人がいるのが現状です。今回は、特に悩みの多い猫ちゃんの爪とぎ行動について、すでに飼育されている、もしくはこれから飼育を検討されている方へ詳しくお伝えしたいと思います。 爪をとぐ必要性 実は、爪とぎは猫ちゃんの本来の狩猟本能により生後2ヵ月頃から始まる行動なのです。■縄張り主張のマーキング手の肉球付近に臭腺があり、爪をといで自分のニオイをつけて自分の縄張りを周りに知らせるという意味があります。猫ちゃんが好んで背伸びをしながら高い位置で爪をとぐのも、自分の力強さをアピールするためなのです。■ストレス発散何か失敗したときや気持ちを落ち着かせたい時に、爪とぎをすることで安心感を得ています。また、遊んで欲しい時やかまって欲しい時にも同じく爪とぎをすることもあります。■古い爪の角質を剥ぎ落とし常に鋭く保つ野生の猫は普段から土の上を走って狩りをしたり木に登ったりするので自然と角質がはがれていきますが、室内飼いの猫は自然に角質が剥がれることがほとんどありません。そのため、自ら爪をといで古い角質を落とそうとします。このように猫ちゃん本能からくる行動として爪をといでいるのです。 問題行動への対処 ▲思いっきり伸びながら爪がとげるキャットタワーHIDAMARI とはいえ、壁や障子、襖、家具等をどこでもガリガリして傷つけてしまうので、飼い主様からすると困ってしまいますよね。まずは、飼い主さんが猫ちゃんに爪をとげる環境を用意し、対策することが大切です。あらかじめ部屋の至る所に爪とぎ器を設置してあげましょう。決められた場所で爪をとげた時は、優しく声をかけながら撫でたり、おやつをあげることを繰り返すことで、正しい場所を認識させていきます。また、壁に防止シートを貼ったり、家具をゲートやアクリル板などで囲うなど事前に防止してあげることも大切です。 ▲猫ちゃんの爪とぎから事前にガードできるディフェンスパーテーション 中には抜爪手術をされる飼い主さんもいらっしゃいますが、慢性的な痛みなど猫ちゃんへのデメリットがたくさんある為、あまりオススメはしません。猫ちゃんをしつけることは難しいですが、少しずつ学んでいきますので、焦らずにゆっくり猫ちゃんのペースで対処していきましょう。マーキングが主な原因で爪をといでしまう時は、不妊手術を行うことで軽減する猫ちゃんもいます。あくまで個体差がありますので、まずは動物病院へ相談しましょう。 猫に人気の爪とぎ 猫が好きな爪とぎ器の素材として人気なのは、ずばり段ボール素材です!柔らかいけれども程よく固さもある段ボールが猫ちゃんにとってはたまらないようです♪オーエフティーでは、エレガントな雰囲気漂う見た目と、猫ちゃんのソファとしても使える段ボール素材の爪とぎソファカリカリーナを販売しています。 ▲カリカリーナLuce 研ぎカスが出にくいのも人気の秘訣です♪ 「猫ちゃんのお気に入りの場所になった」「丈夫で研ぎカスもほとんど出ず、長く使える」と、飼い主さんからも好評を頂いています。是非チェックしてみてください。 おわりに 爪とぎは、猫ちゃんにとって、食事や排せつ、睡眠と同じくらい大切な行動です。思う存分させて、本能欲求を満たしてあげましょう。オーエフティーではペットと共に快適な暮らしができるよう、お客様をサポートさせいただきます。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。キャットタワーHIDAMARIの詳細はこちらカリカリーナの詳細はこちらディフェンスパーテーションの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

ペット用サプリメントとの付き合い方
サプリメントとは 近年、人だけでなくペットへの健康志向が高まり、できるだけ無添加の手作りフードやオヤツを与える飼い主さんが増えてきました。 その中でペットフード業界は苦戦の一途をたどるのですが、その反面、手作りでは補えなかった栄養を手軽に摂取させることが出来るペット用のサプリメントや健康食品の需要は急増しています。 自宅のワンちゃんや猫ちゃんに健康維持や病気の予防で飲ませるほか、皮膚病、関節炎、白内障や腎臓サポートなど与える理由は様々です。特にサプリと関連づけるワンちゃんの症状が2つあります。 ホルモン反応性尿失禁 避妊手術や去勢手術をしたワンちゃんは、ホルモン値が減少するために、自分で尿意をコントロールする外尿道括約筋の低下により、睡眠時や無意識な時に尿もれ、いわゆるおねしょをしてしまうことがあります。 治療法の一環として、ホルモン剤の投与がありますが、やはり中には化学製品に抵抗がある方もいらっしゃいます。そういった方は、漢方やサプリメントでも手助けになるかもしれません。ただし、サプリメントや健康食品は薬ではなく食事で不足した栄養を補う栄養補助食(食品)ですので、病気が治るわけではありません。しっかりと摂取目的を明確にした上で、用法容量を守って正しく付き合いましょう。 また、納豆、豆腐には症状が緩和される『エストロゲン』が多く含まれるため、日々の食事に気をつけてあげるのも良いですね。 コロナ禍の思わぬ影響 コロナ禍でストレスや不安を感じる人も多く、単なるペットというより、『伴侶』『家族の一員』としてペットを迎え入れる方が増えました。 今まで以上にペットをよく観察してあげられる飼い主さんも多くなり、ペットの異変にすぐに気づかれる方もまた増えました。 その中で、特に目立って多いのが分離不安症を発症するワンちゃんです。本来は、社会性があり群になって行動するワンちゃんも、コロナで飼い主と過ごす時間が増えたことで、飼い主の外出時に、『一人きりでお留守番する』という習性との違いから必要以上に不安やストレスを抱え込んでしまうのです。 分離不安症とサプリ ワンちゃんの分離不安症の改善策として、飼い主さんと共に生活の見直しから行う行動療法や、薬物療法が主な治療方法となります。薬物療法は、動物病院から処方されるものから、市販でも簡単に手に入る抗ストレス系のサプリやリラックスさせるオイルやスプレータイプまで様々です。よく分離不安で耳にするCBD(カンナビジオール)も産業用大麻から抽出したオイルから出来ているため、THCという精神作用を引き起こす成分を違法とする日本では入っていないものを選ぶ必要があります。 決して安価に惑わされず、きちんとした品質のCBDオイルを選んで下さい。 また、効能はワンちゃんによって様々ですし、人と同様賛否も分かれます。分離不安症を疑う場合は、まずは動物病院に相談しましょう。 分離不安症は、不安からくる精神疾患です。ワンちゃんが『自宅は安心して落ちつける場所』と認識できるまで、ゆっくりと時間をかける必要があります。薬物療法は一時的に症状を抑えるだけで根治はしません。症状が軽い場合や改善の余地がある時は、ワンちゃんへの接し方やしつけを変えることが一般的です。 まずは自宅で短時間のお留守番の練習から一緒にスタートしてみましょう。 サプリメントとの付き合い方 サプリメントは、食事で足りない栄養分を補う『健康補助食品』ですので、栄養がきちんと摂れているペットには必要ないとされています。 しかし、実際に効果を実感できるサプリメントは市場に多くあり、症状の緩和や生活の質の向上も期待されています。これからペットの高齢化が進むにつれて、どんどん流通もしていくでしょう。 しかし、必要以上の量のサプリメントは症状を悪化させることもありますので、しっかり飼い主さんの目で安全性、有効性を判断してからの使用をお勧めします。 ワンちゃんと飼い主さんにとって上手くサプリメントとお付き合いができればいいですね。ペットフード解説記事一覧はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼
ペット用サプリメントとの付き合い方
サプリメントとは 近年、人だけでなくペットへの健康志向が高まり、できるだけ無添加の手作りフードやオヤツを与える飼い主さんが増えてきました。 その中でペットフード業界は苦戦の一途をたどるのですが、その反面、手作りでは補えなかった栄養を手軽に摂取させることが出来るペット用のサプリメントや健康食品の需要は急増しています。 自宅のワンちゃんや猫ちゃんに健康維持や病気の予防で飲ませるほか、皮膚病、関節炎、白内障や腎臓サポートなど与える理由は様々です。特にサプリと関連づけるワンちゃんの症状が2つあります。 ホルモン反応性尿失禁 避妊手術や去勢手術をしたワンちゃんは、ホルモン値が減少するために、自分で尿意をコントロールする外尿道括約筋の低下により、睡眠時や無意識な時に尿もれ、いわゆるおねしょをしてしまうことがあります。 治療法の一環として、ホルモン剤の投与がありますが、やはり中には化学製品に抵抗がある方もいらっしゃいます。そういった方は、漢方やサプリメントでも手助けになるかもしれません。ただし、サプリメントや健康食品は薬ではなく食事で不足した栄養を補う栄養補助食(食品)ですので、病気が治るわけではありません。しっかりと摂取目的を明確にした上で、用法容量を守って正しく付き合いましょう。 また、納豆、豆腐には症状が緩和される『エストロゲン』が多く含まれるため、日々の食事に気をつけてあげるのも良いですね。 コロナ禍の思わぬ影響 コロナ禍でストレスや不安を感じる人も多く、単なるペットというより、『伴侶』『家族の一員』としてペットを迎え入れる方が増えました。 今まで以上にペットをよく観察してあげられる飼い主さんも多くなり、ペットの異変にすぐに気づかれる方もまた増えました。 その中で、特に目立って多いのが分離不安症を発症するワンちゃんです。本来は、社会性があり群になって行動するワンちゃんも、コロナで飼い主と過ごす時間が増えたことで、飼い主の外出時に、『一人きりでお留守番する』という習性との違いから必要以上に不安やストレスを抱え込んでしまうのです。 分離不安症とサプリ ワンちゃんの分離不安症の改善策として、飼い主さんと共に生活の見直しから行う行動療法や、薬物療法が主な治療方法となります。薬物療法は、動物病院から処方されるものから、市販でも簡単に手に入る抗ストレス系のサプリやリラックスさせるオイルやスプレータイプまで様々です。よく分離不安で耳にするCBD(カンナビジオール)も産業用大麻から抽出したオイルから出来ているため、THCという精神作用を引き起こす成分を違法とする日本では入っていないものを選ぶ必要があります。 決して安価に惑わされず、きちんとした品質のCBDオイルを選んで下さい。 また、効能はワンちゃんによって様々ですし、人と同様賛否も分かれます。分離不安症を疑う場合は、まずは動物病院に相談しましょう。 分離不安症は、不安からくる精神疾患です。ワンちゃんが『自宅は安心して落ちつける場所』と認識できるまで、ゆっくりと時間をかける必要があります。薬物療法は一時的に症状を抑えるだけで根治はしません。症状が軽い場合や改善の余地がある時は、ワンちゃんへの接し方やしつけを変えることが一般的です。 まずは自宅で短時間のお留守番の練習から一緒にスタートしてみましょう。 サプリメントとの付き合い方 サプリメントは、食事で足りない栄養分を補う『健康補助食品』ですので、栄養がきちんと摂れているペットには必要ないとされています。 しかし、実際に効果を実感できるサプリメントは市場に多くあり、症状の緩和や生活の質の向上も期待されています。これからペットの高齢化が進むにつれて、どんどん流通もしていくでしょう。 しかし、必要以上の量のサプリメントは症状を悪化させることもありますので、しっかり飼い主さんの目で安全性、有効性を判断してからの使用をお勧めします。 ワンちゃんと飼い主さんにとって上手くサプリメントとお付き合いができればいいですね。ペットフード解説記事一覧はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

ブリリアントパッドで失敗しないトレーニング方法
世界初の犬用自動トイレBrilliantPad(ブリリアントパッド)がバージョンアップして登場しました! 従来の使いやすさ、便利さはもちろんのこと、新タイプではアプリ操作が可能となり、いつでも簡単にワンちゃんのトイレのお掃除ができます。 また、カメラ機能も付いているので、ワンちゃんの姿がいつでも確認でき、留守時もひと安心です。 一度使えば『もとのトイレに戻れない』ほど実用的なブリリアントパッドですが、ワンちゃんからすると急に今までのトイレがなくなった代わりに巨大ロボットが現れた!と怖くて近づけないかもしれません。 そこで、今回は飼い主さんとワンちゃんが快適に自動トイレライフを送れるための、有効なトレーニング方法をお伝えします。 怒らない!叩かない! まず、日頃のしつけから、ワンちゃんが失敗したり、悪さをしても決して強く怒ったり、叩かないように気を付けて下さい。 ワンちゃんは、トレーニングによって自分で考えて行動することができますが、その反面、善悪については理解が難しいと言われています。 飼い主が何に対して怒っているのか理由がわからないため、何度も繰り返します。 強く怒られた時は、恐怖の方が強く残り、やがて飼い主さんへの信頼も失ってしまうこともあります。そうなってしまうと、しつけやトレーニングはさらに難しくなります。 その分、少しでも何か出来た時は、大袈裟なくらいたっぶり褒めてあげて下さい。そうすると、喜んでもらおうと同じ事を繰り返すので、結果トレーニングへとつながるのです。 怖がり屋さんのワンちゃん もしワンちゃんが、ブリリアントパッドを見てビクビク怖がっていたり、吠えたりすることがあれば、強要せず、一旦移動させて落ち着かせましょう。 ブリリアントパッドの上にお気に入りのブランケットや、従来のおしっこシーツをかぶせて、ワンちゃんが慣れるまで、少しづつ出したり移動させたりを繰り返します。 まずは、ワンちゃんにブリリアントパットの存在が怖くないと教えてあげることが大切です。置いていても気にしない様になれば、いよいよトレーニングのスタートです! 子犬からトレーニングをスタートする時 好奇心旺盛な子犬は、家中のものに興味津々!ついつい興奮しておしっこをもらしてしまう…なんてよくある話です。 また、トイレの認識もないため、どこでも自由気ままに排泄してしまいます。 そのため、子犬の場合は、出来るだけサークルなど限られたスペースを作り、その中でトイレトレーニングをしてあげる方がいいでしょう。 サークル内にブリリアントパッドを設置し、同じスペースに、水やフード、そしてベッドを置きます。 犬の習性で、食事場所と寝床は清潔を好むため、こまめに清掃してワンちゃんにとって、居心地のよい空間を作ってあげて下さい。 ・起床時、食後、また遊びはじめから10分から15分後 ・旋回したり、クンクン匂っていると気づいたとき このタイミングは高確率で排泄に成功しやすいので、ブリリアントパッドの上にワンちゃんを乗せてあげましょう。また、2時間置きに乗せるとより効果的にトレーニングができます。 成功しても、しなくても、ブリリアントパッドに乗れたことを沢山褒めてあげることが大切です! もし、うんちが出来たら、すぐに手動で巻いて、掃除します。サークル内でニオイが充満してしまい、ワンちゃんがニオイ元を特定できなくなるのを避けます。 おしっこが出た時は、しばらくニオイを識別させるために少し汚れたところを残して置いて下さい。 衛生面が気になる方は、市販の犬用トイレしつけスプレーも売っていますので、そちらをトイレシートに含ませてもいいですね。 飼い主さんがワンちゃんをしっかり世話ができる時はサークルの外に出してあげても大丈夫ですが、外出の時、またお休み際は特に、サークル内に入れて安全を確保してあげて下さい。 すでにトイレシートを使っている時...
ブリリアントパッドで失敗しないトレーニング方法
世界初の犬用自動トイレBrilliantPad(ブリリアントパッド)がバージョンアップして登場しました! 従来の使いやすさ、便利さはもちろんのこと、新タイプではアプリ操作が可能となり、いつでも簡単にワンちゃんのトイレのお掃除ができます。 また、カメラ機能も付いているので、ワンちゃんの姿がいつでも確認でき、留守時もひと安心です。 一度使えば『もとのトイレに戻れない』ほど実用的なブリリアントパッドですが、ワンちゃんからすると急に今までのトイレがなくなった代わりに巨大ロボットが現れた!と怖くて近づけないかもしれません。 そこで、今回は飼い主さんとワンちゃんが快適に自動トイレライフを送れるための、有効なトレーニング方法をお伝えします。 怒らない!叩かない! まず、日頃のしつけから、ワンちゃんが失敗したり、悪さをしても決して強く怒ったり、叩かないように気を付けて下さい。 ワンちゃんは、トレーニングによって自分で考えて行動することができますが、その反面、善悪については理解が難しいと言われています。 飼い主が何に対して怒っているのか理由がわからないため、何度も繰り返します。 強く怒られた時は、恐怖の方が強く残り、やがて飼い主さんへの信頼も失ってしまうこともあります。そうなってしまうと、しつけやトレーニングはさらに難しくなります。 その分、少しでも何か出来た時は、大袈裟なくらいたっぶり褒めてあげて下さい。そうすると、喜んでもらおうと同じ事を繰り返すので、結果トレーニングへとつながるのです。 怖がり屋さんのワンちゃん もしワンちゃんが、ブリリアントパッドを見てビクビク怖がっていたり、吠えたりすることがあれば、強要せず、一旦移動させて落ち着かせましょう。 ブリリアントパッドの上にお気に入りのブランケットや、従来のおしっこシーツをかぶせて、ワンちゃんが慣れるまで、少しづつ出したり移動させたりを繰り返します。 まずは、ワンちゃんにブリリアントパットの存在が怖くないと教えてあげることが大切です。置いていても気にしない様になれば、いよいよトレーニングのスタートです! 子犬からトレーニングをスタートする時 好奇心旺盛な子犬は、家中のものに興味津々!ついつい興奮しておしっこをもらしてしまう…なんてよくある話です。 また、トイレの認識もないため、どこでも自由気ままに排泄してしまいます。 そのため、子犬の場合は、出来るだけサークルなど限られたスペースを作り、その中でトイレトレーニングをしてあげる方がいいでしょう。 サークル内にブリリアントパッドを設置し、同じスペースに、水やフード、そしてベッドを置きます。 犬の習性で、食事場所と寝床は清潔を好むため、こまめに清掃してワンちゃんにとって、居心地のよい空間を作ってあげて下さい。 ・起床時、食後、また遊びはじめから10分から15分後 ・旋回したり、クンクン匂っていると気づいたとき このタイミングは高確率で排泄に成功しやすいので、ブリリアントパッドの上にワンちゃんを乗せてあげましょう。また、2時間置きに乗せるとより効果的にトレーニングができます。 成功しても、しなくても、ブリリアントパッドに乗れたことを沢山褒めてあげることが大切です! もし、うんちが出来たら、すぐに手動で巻いて、掃除します。サークル内でニオイが充満してしまい、ワンちゃんがニオイ元を特定できなくなるのを避けます。 おしっこが出た時は、しばらくニオイを識別させるために少し汚れたところを残して置いて下さい。 衛生面が気になる方は、市販の犬用トイレしつけスプレーも売っていますので、そちらをトイレシートに含ませてもいいですね。 飼い主さんがワンちゃんをしっかり世話ができる時はサークルの外に出してあげても大丈夫ですが、外出の時、またお休み際は特に、サークル内に入れて安全を確保してあげて下さい。 すでにトイレシートを使っている時...

猫のサインから選ぶ理想のトイレ
皆様は、どのようなトイレをお使いですか?市場ではさまざまなペット用品が販売されていますが、オーエフティーでもトレー型・システムトイレ・自動猫トイレと豊富なラインナップを取り揃えております。種類が多くなると、どれを買えばよいのか迷いますよね。今回は、猫ちゃん目線でどんなトイレが望ましいのかをお話させていただきます。 野生猫のトイレ事情 本来、野生の猫は柔らかい土の上でトイレをします。排泄後に砂をかけて隠そうとするのは、・猫は嗅覚が敏感で、縄張り意識が強いので、他の猫に自分の居場所がバレないようにするため・草陰で待ち伏せして狩りを行う際に、獲物である小動物たちに自分のニオイがバレて逃げられることがないようにするためと言われています。 室内猫のトイレ事情 室内猫は、自分でトイレを決めることができないので、代わりに飼い主が決めることになります。では、飼い猫は用意されたトイレで満足しているのでしょうか?飼い主の状況や家庭内状況において利用するべき形はそれぞれですが、飼い猫が今のトイレに満足しているかをしっかり観察してみてください。“決められた砂上で排泄する→砂をかけて出ていく”これがきちんとされていれば問題はありません。 猫がトイレに満足しているかを知る方法 満足してもらえているかを知るポイントとして猫のボディランゲージを観察する方法があります。・トイレのフチに足をかけてトイレをする・トイレの壁を引っ掻く・トイレ後砂をかけずに慌てて出ていくこのような動作をしていたら、トイレに不満を持っているかもしれません。原因としては、・トイレが汚い・砂粒が大きい・砂の種類やニオイ・触感が気に入らない・猫に対してトイレのサイズが小さい・砂の量が少ないので十分に砂がかけない等があります。 猫が好むトイレを知る 猫は、綺麗で十分砂かきができるスペースと、落ち着いた空間にある細かい砂粒のトイレが好きです。ただ、猫が好きなトイレの条件を満たしていても、人通りが多い騒がしい場所に設置してしまうと、落ち着いてトイレができずストレスを溜めてしまいます。壁際・人通りが少ない・騒がしくない場所に設置してあげることがポイントです。 理想のトイレを探し求めて 一般的に飼育するにあたり、猫の頭数+1つのトイレが必要と言われており、2頭飼いであれば3つ、3頭飼いであれば4つトイレが必要です。トイレの予備があることは緊急時にも役立ちますし、猫が好きなトイレを知るきっかけにもなります。1つのトイレに絞るのではなく、さまざまなトイレを用意し、いろんな場所に配置してみてください。それぞれ飼っている猫ちゃんが好むトイレが見つかるかもしれません。 ▼ この記事を書いたのは ▼
猫のサインから選ぶ理想のトイレ
皆様は、どのようなトイレをお使いですか?市場ではさまざまなペット用品が販売されていますが、オーエフティーでもトレー型・システムトイレ・自動猫トイレと豊富なラインナップを取り揃えております。種類が多くなると、どれを買えばよいのか迷いますよね。今回は、猫ちゃん目線でどんなトイレが望ましいのかをお話させていただきます。 野生猫のトイレ事情 本来、野生の猫は柔らかい土の上でトイレをします。排泄後に砂をかけて隠そうとするのは、・猫は嗅覚が敏感で、縄張り意識が強いので、他の猫に自分の居場所がバレないようにするため・草陰で待ち伏せして狩りを行う際に、獲物である小動物たちに自分のニオイがバレて逃げられることがないようにするためと言われています。 室内猫のトイレ事情 室内猫は、自分でトイレを決めることができないので、代わりに飼い主が決めることになります。では、飼い猫は用意されたトイレで満足しているのでしょうか?飼い主の状況や家庭内状況において利用するべき形はそれぞれですが、飼い猫が今のトイレに満足しているかをしっかり観察してみてください。“決められた砂上で排泄する→砂をかけて出ていく”これがきちんとされていれば問題はありません。 猫がトイレに満足しているかを知る方法 満足してもらえているかを知るポイントとして猫のボディランゲージを観察する方法があります。・トイレのフチに足をかけてトイレをする・トイレの壁を引っ掻く・トイレ後砂をかけずに慌てて出ていくこのような動作をしていたら、トイレに不満を持っているかもしれません。原因としては、・トイレが汚い・砂粒が大きい・砂の種類やニオイ・触感が気に入らない・猫に対してトイレのサイズが小さい・砂の量が少ないので十分に砂がかけない等があります。 猫が好むトイレを知る 猫は、綺麗で十分砂かきができるスペースと、落ち着いた空間にある細かい砂粒のトイレが好きです。ただ、猫が好きなトイレの条件を満たしていても、人通りが多い騒がしい場所に設置してしまうと、落ち着いてトイレができずストレスを溜めてしまいます。壁際・人通りが少ない・騒がしくない場所に設置してあげることがポイントです。 理想のトイレを探し求めて 一般的に飼育するにあたり、猫の頭数+1つのトイレが必要と言われており、2頭飼いであれば3つ、3頭飼いであれば4つトイレが必要です。トイレの予備があることは緊急時にも役立ちますし、猫が好きなトイレを知るきっかけにもなります。1つのトイレに絞るのではなく、さまざまなトイレを用意し、いろんな場所に配置してみてください。それぞれ飼っている猫ちゃんが好むトイレが見つかるかもしれません。 ▼ この記事を書いたのは ▼

犬の介護について知っておくべきワード
突然ワンちゃんに介護が必要になったとしたら・・・皆様はそのような事を想像したことはありますか?私たちは毎日さまざまなお問合せを頂く中で、実際にそういった場面に出くわすことがあります。そんな時お客様は、「誰に何を相談したらいいのかわからない」「ネットで調べようにもどういう言葉で検索すればいいのかすらわからない」という状況に陥ってしまっているように見えます。そこでまずは今回、犬の介護についてどのような言葉を知っておくべきなのかを取り上げてみました。 ターミナルケア/緩和ケア/ホスピスケア <ターミナルケア>病気や寿命によって余命が残りわずかになったペットに対して行うケアのこと。医療行為を施しても治る見込みがほとんどない場合に、精神面も含めたケアが必要となります。<緩和ケア>ターミナルケアとほぼ同じ意味合いを持ちますが、平行して治療を行いながらケアする場合も含みます。<ホスピスケア>ペットだけでなく家族(飼い主)の苦痛も最小限にすることなどを含めた総合的ケア。人と同様に、ペットの介護でも使用される場合があります。いずれの言葉も同義ではありますが、それぞれ検索することで、より多くの情報が得られる場合があります。 動物病院などで見られるようになった言葉 <ペインコントロール/ペインマネジメント/疼痛管理>薬物療法だけでなく、各種の治療法を駆使して痛みを軽減・消失させること。痛みの管理に関しては分からないところが多いため、医師に相談するのがいいでしょう。 <神経ブロック>ペインコントロールの中でも、麻酔を用いた治療法の一種。人の手術の際には必ず行われる方法です。<湿潤療法(モイストヒーリング)>ラップ療法とも言われ、皮膚潰瘍に対して消毒をせずガーゼの代わりに被覆材を使用するといったアプローチで治療します。床ずれ(褥瘡/じょくそう)ができた場合の処置の一つです。 介護に関連するその他の言葉 <ハイドロコロイド(モイストヒーリング)>ハイドロコロイド素材の保護パッドや絆創膏が市販されており、傷を治す体液を吸収するとゼリーのようにゲル化して傷口を覆います。<ダーマケア>ダーマは皮膚・真皮を意味し、関連商品が販売されています。<ペット用担架>ペット用担架などの商品も発売されています。サイズなどは、メーカーにお問い合わせください。<エリザベスカラー>首元に取り付ける円錐台形状の保護具で、傷口を舐めたりさせないためのものです。<シリンジ>注射器の筒の部分。流動食などを与える際に使用します。<ナックリング>なんらかの原因で起こる足の感覚異常で、足裏が地面ではなく反対(上)に向き、足の甲の部分を引きずった状態のことです。 いろんな情報を得ておきましょう 私たちペット業者でさえ、言葉を知らなければ調べものもできません。飼い主の皆様が突然、介護のような特別な状況に陥った時、速やかに情報を収集して対応するためには、関連ワードを知っていることがとても重要なポイントになるのかもしれません。介護といってもペットの状態はさまざまですし、痛みの有無などはたとえ飼い主であっても判断が難しくなります。ペットたちの終末期に起こる、目に見えない不安や痛みまでケアしてあげれるように、今のうちから必要なワードを覚えておくことをお勧めいたします。
犬の介護について知っておくべきワード
突然ワンちゃんに介護が必要になったとしたら・・・皆様はそのような事を想像したことはありますか?私たちは毎日さまざまなお問合せを頂く中で、実際にそういった場面に出くわすことがあります。そんな時お客様は、「誰に何を相談したらいいのかわからない」「ネットで調べようにもどういう言葉で検索すればいいのかすらわからない」という状況に陥ってしまっているように見えます。そこでまずは今回、犬の介護についてどのような言葉を知っておくべきなのかを取り上げてみました。 ターミナルケア/緩和ケア/ホスピスケア <ターミナルケア>病気や寿命によって余命が残りわずかになったペットに対して行うケアのこと。医療行為を施しても治る見込みがほとんどない場合に、精神面も含めたケアが必要となります。<緩和ケア>ターミナルケアとほぼ同じ意味合いを持ちますが、平行して治療を行いながらケアする場合も含みます。<ホスピスケア>ペットだけでなく家族(飼い主)の苦痛も最小限にすることなどを含めた総合的ケア。人と同様に、ペットの介護でも使用される場合があります。いずれの言葉も同義ではありますが、それぞれ検索することで、より多くの情報が得られる場合があります。 動物病院などで見られるようになった言葉 <ペインコントロール/ペインマネジメント/疼痛管理>薬物療法だけでなく、各種の治療法を駆使して痛みを軽減・消失させること。痛みの管理に関しては分からないところが多いため、医師に相談するのがいいでしょう。 <神経ブロック>ペインコントロールの中でも、麻酔を用いた治療法の一種。人の手術の際には必ず行われる方法です。<湿潤療法(モイストヒーリング)>ラップ療法とも言われ、皮膚潰瘍に対して消毒をせずガーゼの代わりに被覆材を使用するといったアプローチで治療します。床ずれ(褥瘡/じょくそう)ができた場合の処置の一つです。 介護に関連するその他の言葉 <ハイドロコロイド(モイストヒーリング)>ハイドロコロイド素材の保護パッドや絆創膏が市販されており、傷を治す体液を吸収するとゼリーのようにゲル化して傷口を覆います。<ダーマケア>ダーマは皮膚・真皮を意味し、関連商品が販売されています。<ペット用担架>ペット用担架などの商品も発売されています。サイズなどは、メーカーにお問い合わせください。<エリザベスカラー>首元に取り付ける円錐台形状の保護具で、傷口を舐めたりさせないためのものです。<シリンジ>注射器の筒の部分。流動食などを与える際に使用します。<ナックリング>なんらかの原因で起こる足の感覚異常で、足裏が地面ではなく反対(上)に向き、足の甲の部分を引きずった状態のことです。 いろんな情報を得ておきましょう 私たちペット業者でさえ、言葉を知らなければ調べものもできません。飼い主の皆様が突然、介護のような特別な状況に陥った時、速やかに情報を収集して対応するためには、関連ワードを知っていることがとても重要なポイントになるのかもしれません。介護といってもペットの状態はさまざまですし、痛みの有無などはたとえ飼い主であっても判断が難しくなります。ペットたちの終末期に起こる、目に見えない不安や痛みまでケアしてあげれるように、今のうちから必要なワードを覚えておくことをお勧めいたします。

ペットと災害対策をしてみましょう
2011年3月11日に発生した東日本大震災から、ちょうど10年。停電のなか、収まることのない余震。家族と連絡が取れない状況で携帯電話のバッテリーは切れ、水や食料の買い置きも無い…。 地震をはじめ、災害大国に住む私たちにとって、日頃の備えは必要不可欠です。そこで今回は「ペットと一緒に避難する」を考えていきます。 事前に避難所の確認をしましょう 非常時、飼い主はペットと共に行動する同伴避難が原則となっていますが、それぞれの自治体によってルールが異なっています。一度お住まいの市区町村の防災マニュアルに目を通して、避難所の中まで連れて入れるのかを確認しておきましょう。 災害対策ができるSOSペットバッグ 避難グッズはペットの分もしっかりと備えて、家族の誰もがすぐわかるよう一つにまとめておくと安心です。「SOSペットバッグ」は、移動用ケージ・ハウス・避難バッグと3つの機能を兼ね備え、さらにリュック・ショルダー・手提げと3WAYで使い勝手よく使用していただけます。十字型の反射板が車のライトを反射して、暗闇でも安心ですね。 移動用ペットキャリーとして 猫ちゃんや小型のペットはキャリーに入れての避難が必要です。両手が自由になるリュックスタイルは女性に特におすすめで、補助ベルトを使い背中にピタッとフィットさせることができるので、安定感があります。また2本のパイプがケースの形状を保ってくれるのでペットが圧迫される心配もありません。天井部分、側面のメッシュ部分から中の様子がすぐに確認できます。 避難所ではそのままハウスとして ハウスはペットの居場所を確保するだけでなく、周囲への配慮や他のペットとの接触を防ぐなど、安全面・衛生面からも重要な避難グッズの一つです。キャリーとしての利用も含め、いずれも、普段からお部屋で慣れさせておけば、いざという時ペットも安心して中で過ごすことができます。同時に飼い主さんの指示をしっかり聞けるよう、日頃のしつけも重要となってきます! 非常用バックとして 大容量のポケットが3つあるので、必要なものをたっぷり収納できます。避難所ではペット用品の配給はあまり期待できませんので、前もっての準備が必要です。例えば…・薬(かかりつけ医に必要な薬などのアドバイスを受けておきましょう)・フード(できれば5日以上)、500mlの軟水・食器や保存袋、ビニール袋・ペットシーツや猫砂・リード・おもちゃ・タオル、ティッシュ類、爪切り、包帯など 大型犬ならペットケンネル・ファーストクラス 大型のワンちゃんにも、災害時に備えて移動用ケージを準備しましょう。「ペットケンネル・ファーストクラス」なら、組み立ても簡単。強化プラスチックがしっかりとペットを守ります!キャスター付きなので移動もスムーズですよ。詳細はコチラ→ペットケンネル・ファーストクラス キャスター付(L80〜L100)ペットケンネル・ファーストクラス キャスター付(L120XXXL) 最後に 避難時のネコちゃんのトイレでは、猫砂の重量がネックとなります。そこで使い慣れた砂を少々、あとは細かくちぎった新聞紙などで代用してみてください。2つをブレンドし、徐々に慣らすことをオススメします。ビニールを敷いた段ボール箱にセットすれば、簡易トイレが完成します。環境の変化に敏感なネコちゃんのために、時々自宅で試してあげるのも良いでしょう。災害への備えは、転ばぬ先の杖。「パッ!と担いで、サッ!と避難」を普段からイメージしておけば、いざというとき、少しでも落ち着いて行動ができ、気持ちにも余裕が生まれます。是非、災害対策を見直してみてくださいね。今回ご紹介したSOSペットバッグの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼
ペットと災害対策をしてみましょう
2011年3月11日に発生した東日本大震災から、ちょうど10年。停電のなか、収まることのない余震。家族と連絡が取れない状況で携帯電話のバッテリーは切れ、水や食料の買い置きも無い…。 地震をはじめ、災害大国に住む私たちにとって、日頃の備えは必要不可欠です。そこで今回は「ペットと一緒に避難する」を考えていきます。 事前に避難所の確認をしましょう 非常時、飼い主はペットと共に行動する同伴避難が原則となっていますが、それぞれの自治体によってルールが異なっています。一度お住まいの市区町村の防災マニュアルに目を通して、避難所の中まで連れて入れるのかを確認しておきましょう。 災害対策ができるSOSペットバッグ 避難グッズはペットの分もしっかりと備えて、家族の誰もがすぐわかるよう一つにまとめておくと安心です。「SOSペットバッグ」は、移動用ケージ・ハウス・避難バッグと3つの機能を兼ね備え、さらにリュック・ショルダー・手提げと3WAYで使い勝手よく使用していただけます。十字型の反射板が車のライトを反射して、暗闇でも安心ですね。 移動用ペットキャリーとして 猫ちゃんや小型のペットはキャリーに入れての避難が必要です。両手が自由になるリュックスタイルは女性に特におすすめで、補助ベルトを使い背中にピタッとフィットさせることができるので、安定感があります。また2本のパイプがケースの形状を保ってくれるのでペットが圧迫される心配もありません。天井部分、側面のメッシュ部分から中の様子がすぐに確認できます。 避難所ではそのままハウスとして ハウスはペットの居場所を確保するだけでなく、周囲への配慮や他のペットとの接触を防ぐなど、安全面・衛生面からも重要な避難グッズの一つです。キャリーとしての利用も含め、いずれも、普段からお部屋で慣れさせておけば、いざという時ペットも安心して中で過ごすことができます。同時に飼い主さんの指示をしっかり聞けるよう、日頃のしつけも重要となってきます! 非常用バックとして 大容量のポケットが3つあるので、必要なものをたっぷり収納できます。避難所ではペット用品の配給はあまり期待できませんので、前もっての準備が必要です。例えば…・薬(かかりつけ医に必要な薬などのアドバイスを受けておきましょう)・フード(できれば5日以上)、500mlの軟水・食器や保存袋、ビニール袋・ペットシーツや猫砂・リード・おもちゃ・タオル、ティッシュ類、爪切り、包帯など 大型犬ならペットケンネル・ファーストクラス 大型のワンちゃんにも、災害時に備えて移動用ケージを準備しましょう。「ペットケンネル・ファーストクラス」なら、組み立ても簡単。強化プラスチックがしっかりとペットを守ります!キャスター付きなので移動もスムーズですよ。詳細はコチラ→ペットケンネル・ファーストクラス キャスター付(L80〜L100)ペットケンネル・ファーストクラス キャスター付(L120XXXL) 最後に 避難時のネコちゃんのトイレでは、猫砂の重量がネックとなります。そこで使い慣れた砂を少々、あとは細かくちぎった新聞紙などで代用してみてください。2つをブレンドし、徐々に慣らすことをオススメします。ビニールを敷いた段ボール箱にセットすれば、簡易トイレが完成します。環境の変化に敏感なネコちゃんのために、時々自宅で試してあげるのも良いでしょう。災害への備えは、転ばぬ先の杖。「パッ!と担いで、サッ!と避難」を普段からイメージしておけば、いざというとき、少しでも落ち着いて行動ができ、気持ちにも余裕が生まれます。是非、災害対策を見直してみてくださいね。今回ご紹介したSOSペットバッグの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

仔猫の時から自動猫トイレに慣れさせるには
自動猫トイレの認知度が高まってきている中、最近では「仔猫の時期から慣らしておきたい」という方が増えつつあります。今回は、その方法をご紹介いたします。ペットショップやブリーダーから向かい入れた仔猫のほとんどは、小さなトレー型のトイレでしつけられていることが多いため、自動猫トイレを設置しても、すぐにそこで排泄してくれるわけではありません。簡易的に小さな猫トイレも用意しておく必要があります。 特に臆病な性格の仔猫の場合は、自動猫トイレのような大きな物体を目にしたことがありませんので、まずはその存在に慣れさせてあげましょう。 どんな自動猫トイレを選ぶべきか 自動猫トイレは、入り口が少し高い位置にあるものと、低い位置にあるものに分かれます。仔猫は視界が低く、高い場所に上るのも得意とは言えないため、入り口が高い位置にあるトイレを選ぶ場合は、別売の専用ステップを準備してあげることをお勧めします。また、自動猫トイレには、猫ちゃんがトイレに入ったことを感知するセンサーがあります。その種類は、重量(体重)を感知するタイプと赤外線などでトイレに入ったことを感知するタイプがありますが、重量(体重)を感知して作動するタイプの場合、仔猫の軽い体重では、まず反応してくれません。赤外線を使用したものであれば反応しますが、どちらにしても、ある程度の年齢・体重に達するまで、電源は入れずに自動猫トイレの存在自体に慣れさせることを優先していただくほうがいいでしょう。 仔猫の行動と注意点(成猫との比較) ▲センサーが反応することによって排泄物の処理がスタート 猫はもともとよく寝る動物ですが、仔猫はさらに睡眠時間が長くなります。自動猫トイレをトイレとして認識する前なら、薄暗くて居心地良い場所だと感じて寝てしまう子もいます。 また、仔猫の間は非常に多感な時期でもありますので、多くはためらうことなく自動猫トイレに近づき、入っていこうとします。小さな隙間に入ろうとしたり、動くものにも興味を示したりしますので、事故などにつながらないよう、電源を入れずに慣れさせましょう。 どのように慣れさせていくのか 電源を入れていない自動猫トイレの中で排泄してくれるようになれば、作動中に仔猫が入らないように監視しながら、電源を入れ排泄物の処理を行います。ただし、まだウンチも細く、オシッコの塊もとても小さいため、うまく処理されない場合がありますので、トイレ用スコップも用意しておくべきです。 猫は音に敏感な動物なので、自動猫トイレ自体や砂の流れる音も同時に聞かせておいたほうがいいでしょう。 また、仔猫が作動中の自動猫トイレを見ている場合はトイレ全体の動きよりも、排泄物の塊が下にゴロンと落ちる瞬間などに反応を示すはずですので、処理中のトイレの中に入らせないように注意してください。 自動猫トイレのある生活を始めるにあたって 見方を変えると、仔猫にとって自動猫トイレは魅力的なポイントだらけです。 ・穴が開いていて隠れ家構造になっている ・動きがある ・音が出る ・登れる(入り口に高さがあるもの)仔猫がつい興味を惹かれて、自動猫トイレで排泄以外の欲求を満たそうとすれば、トイレのしつけがスムーズにいかないこともあります。自動猫トイレ以外に仔猫が興味を持つおもちゃや、簡単に上り下りの練習になるようなもの、隠れ家的な場所を用意しておいてあげましょう。 そして、仔猫の時期は自動猫トイレに慣らす期間だと思って、飼い主様が不在の時には電源を切っておき、排泄物を処理する時にだけ電源を入れるようにします。猫ちゃんの体重が増えて排泄物のサイズも大きくなり、自動猫トイレをトイレとして認識するようになれば、飼い主様の生活は劇的に変わるでしょう。それまでは、段階的に慣れさせていってください。
仔猫の時から自動猫トイレに慣れさせるには
自動猫トイレの認知度が高まってきている中、最近では「仔猫の時期から慣らしておきたい」という方が増えつつあります。今回は、その方法をご紹介いたします。ペットショップやブリーダーから向かい入れた仔猫のほとんどは、小さなトレー型のトイレでしつけられていることが多いため、自動猫トイレを設置しても、すぐにそこで排泄してくれるわけではありません。簡易的に小さな猫トイレも用意しておく必要があります。 特に臆病な性格の仔猫の場合は、自動猫トイレのような大きな物体を目にしたことがありませんので、まずはその存在に慣れさせてあげましょう。 どんな自動猫トイレを選ぶべきか 自動猫トイレは、入り口が少し高い位置にあるものと、低い位置にあるものに分かれます。仔猫は視界が低く、高い場所に上るのも得意とは言えないため、入り口が高い位置にあるトイレを選ぶ場合は、別売の専用ステップを準備してあげることをお勧めします。また、自動猫トイレには、猫ちゃんがトイレに入ったことを感知するセンサーがあります。その種類は、重量(体重)を感知するタイプと赤外線などでトイレに入ったことを感知するタイプがありますが、重量(体重)を感知して作動するタイプの場合、仔猫の軽い体重では、まず反応してくれません。赤外線を使用したものであれば反応しますが、どちらにしても、ある程度の年齢・体重に達するまで、電源は入れずに自動猫トイレの存在自体に慣れさせることを優先していただくほうがいいでしょう。 仔猫の行動と注意点(成猫との比較) ▲センサーが反応することによって排泄物の処理がスタート 猫はもともとよく寝る動物ですが、仔猫はさらに睡眠時間が長くなります。自動猫トイレをトイレとして認識する前なら、薄暗くて居心地良い場所だと感じて寝てしまう子もいます。 また、仔猫の間は非常に多感な時期でもありますので、多くはためらうことなく自動猫トイレに近づき、入っていこうとします。小さな隙間に入ろうとしたり、動くものにも興味を示したりしますので、事故などにつながらないよう、電源を入れずに慣れさせましょう。 どのように慣れさせていくのか 電源を入れていない自動猫トイレの中で排泄してくれるようになれば、作動中に仔猫が入らないように監視しながら、電源を入れ排泄物の処理を行います。ただし、まだウンチも細く、オシッコの塊もとても小さいため、うまく処理されない場合がありますので、トイレ用スコップも用意しておくべきです。 猫は音に敏感な動物なので、自動猫トイレ自体や砂の流れる音も同時に聞かせておいたほうがいいでしょう。 また、仔猫が作動中の自動猫トイレを見ている場合はトイレ全体の動きよりも、排泄物の塊が下にゴロンと落ちる瞬間などに反応を示すはずですので、処理中のトイレの中に入らせないように注意してください。 自動猫トイレのある生活を始めるにあたって 見方を変えると、仔猫にとって自動猫トイレは魅力的なポイントだらけです。 ・穴が開いていて隠れ家構造になっている ・動きがある ・音が出る ・登れる(入り口に高さがあるもの)仔猫がつい興味を惹かれて、自動猫トイレで排泄以外の欲求を満たそうとすれば、トイレのしつけがスムーズにいかないこともあります。自動猫トイレ以外に仔猫が興味を持つおもちゃや、簡単に上り下りの練習になるようなもの、隠れ家的な場所を用意しておいてあげましょう。 そして、仔猫の時期は自動猫トイレに慣らす期間だと思って、飼い主様が不在の時には電源を切っておき、排泄物を処理する時にだけ電源を入れるようにします。猫ちゃんの体重が増えて排泄物のサイズも大きくなり、自動猫トイレをトイレとして認識するようになれば、飼い主様の生活は劇的に変わるでしょう。それまでは、段階的に慣れさせていってください。

ワンちゃんと掃除機の付き合い方《前編》
今や、私たちの生活において必要不可欠なものとなった家電製品。ほぼ毎日ご使用になられているというご家庭も多いのではないでしょうか。 OFTでも自動猫トイレをはじめ、自動給水器や自動給餌器など、さまざまなペット家電を販売しております。これらの家電製品をワンちゃんは一体どのようにとらえているのでしょうか? 今回はなかでも、ワンちゃんが「危険な生き物なんじゃないか?」と感じてしまいやすい、“ある家電”についてお話しいたします。 犬は家電をどのようにとらえているのか? ▲不規則な動きをする掃除機のホースがワンちゃんの警戒の対象に!? ガコンガコン…と音を鳴らし、たまに揺れる洗濯機。いろいろな音を出しながら光を放つテレビ。 ワンちゃんは人間の何倍もの聴覚を持っていますが、これらに対して怖がって逃げようとしたり、緊張して吠えるという状況はほとんどありません。なぜなら、飼い主が普段からテレビに注目し喋ったり笑ったりする様子や、洗濯機に近づきボタンを操作している様子を観察しているからです。なおかつ、それらの製品はワンちゃんや飼い主に向かって来ることもなく、いつも同じ場所にあります。 ワンちゃんはテレビや洗濯機が何者であるか分からないまでも、それらの音も含めて、毎日を過ごす生活空間の一部と考えているのかもしれません。 掃除機に吠える犬がなぜ多いのか? では、掃除機はどう見えているのでしょうか?大きな吸引音とともに、多くの掃除機はキャスターが付いた稼働式になっており、不規則な動きをします。このような得体の知れない物体が急に現れたら、ビックリしてしまうのは無理もありません。 私たちにとって掃除機はどの家庭にでもある当たり前の存在だとしても、ワンちゃんにとって他の家電とは明らかに違う存在だということです。掃除機をお使いになるときには、ぜひこのようなことを想像してみてください。 クリーナーで犬も住まいも衛生的に OFT DOG CLEANERは、基本機能こそ一般の掃除機と同様ですが、ブラッシング後の毛やホコリ等を取ったり、衛生面においても、あるとたいへん便利な商品です。しかし、ワンちゃんがクリーナー(掃除機)に慣れるまで苦労したという飼い主様も少なくないと聞きます。 次回「ワンちゃんと掃除機の付き合い方《後編》」では、ワンちゃんにDOG CLEANERを慣れさせる方法をお伝えしたいと思います。 ▼ この記事を書いたのは ▼
ワンちゃんと掃除機の付き合い方《前編》
今や、私たちの生活において必要不可欠なものとなった家電製品。ほぼ毎日ご使用になられているというご家庭も多いのではないでしょうか。 OFTでも自動猫トイレをはじめ、自動給水器や自動給餌器など、さまざまなペット家電を販売しております。これらの家電製品をワンちゃんは一体どのようにとらえているのでしょうか? 今回はなかでも、ワンちゃんが「危険な生き物なんじゃないか?」と感じてしまいやすい、“ある家電”についてお話しいたします。 犬は家電をどのようにとらえているのか? ▲不規則な動きをする掃除機のホースがワンちゃんの警戒の対象に!? ガコンガコン…と音を鳴らし、たまに揺れる洗濯機。いろいろな音を出しながら光を放つテレビ。 ワンちゃんは人間の何倍もの聴覚を持っていますが、これらに対して怖がって逃げようとしたり、緊張して吠えるという状況はほとんどありません。なぜなら、飼い主が普段からテレビに注目し喋ったり笑ったりする様子や、洗濯機に近づきボタンを操作している様子を観察しているからです。なおかつ、それらの製品はワンちゃんや飼い主に向かって来ることもなく、いつも同じ場所にあります。 ワンちゃんはテレビや洗濯機が何者であるか分からないまでも、それらの音も含めて、毎日を過ごす生活空間の一部と考えているのかもしれません。 掃除機に吠える犬がなぜ多いのか? では、掃除機はどう見えているのでしょうか?大きな吸引音とともに、多くの掃除機はキャスターが付いた稼働式になっており、不規則な動きをします。このような得体の知れない物体が急に現れたら、ビックリしてしまうのは無理もありません。 私たちにとって掃除機はどの家庭にでもある当たり前の存在だとしても、ワンちゃんにとって他の家電とは明らかに違う存在だということです。掃除機をお使いになるときには、ぜひこのようなことを想像してみてください。 クリーナーで犬も住まいも衛生的に OFT DOG CLEANERは、基本機能こそ一般の掃除機と同様ですが、ブラッシング後の毛やホコリ等を取ったり、衛生面においても、あるとたいへん便利な商品です。しかし、ワンちゃんがクリーナー(掃除機)に慣れるまで苦労したという飼い主様も少なくないと聞きます。 次回「ワンちゃんと掃除機の付き合い方《後編》」では、ワンちゃんにDOG CLEANERを慣れさせる方法をお伝えしたいと思います。 ▼ この記事を書いたのは ▼

新しいトイレに変えるときに試してほしいこと
皆さま、こんにちわ!OFTカスタマーサポート(サポ魂+)の黒猫くんです。 今回のテーマは、「新しいトイレに変えるときに試してほしいこと」。猫ちゃんのトイレの切り替えにお困りの方がいれば、参考にしていただけると嬉しい限りです。 ぜひ知っておきたい猫の特質とは? そもそも猫ちゃんの性質として、自分が暮らしている住環境に重きを置いているため、環境の変化を極端に嫌います。非常にデリケートなので、不安になってしまうのです。そこで、トイレを使ってもらうにあたって前提となるのが絶対に無理やり使わせようとしないこと!環境の変化に対して不安になっている中、その対象であるトイレを無理やり使わせようとすると、より警戒心が強くなり、二度と使ってくれなくなってしまいます。私たちでも、不安が大きい場所に無理やり連れて行かれたりすると、ストレスがかかりますよね…それと同じなのです。 トイレ切替時に試してほしい3つのこと ここからが本題です。もし猫ちゃんがなかなか新しいトイレを使ってくれないときには、次の3つを試してみてください。 1.前回と同じ場所に置く猫ちゃんのストレスを最小限にするため、古いトイレがあった場所に新しいトイレを置いてください。場所が変わると、その変化を嫌がり粗相をしてしまうかもしれません。2.古いトイレの横に、新しいトイレを置く1の方法でも、猫ちゃんが我慢してしまう素振りがあれば、古いトイレと新しいトイレを並べて置いてみてください。そうすることで、少しずつ新しいトイレに慣れてくるかと思います。3.使用済みの猫砂を入れてみる猫ちゃんはニオイで環境の判断をします。使用済みの猫砂を入れることで、「ここはトイレなんだ!」と覚えてもらいましょう。 猫が慣れるのを焦らず、気長に待つ ▲お気に入りのハンモックに乗ってくつろぐ、我が家のかい君です! 以前、お客様からお問い合わせがあったもので、切り替えに約2週間ほど要した事例もあります。猫ちゃんの性格はさまざまですし、臆病な子はもっと時間がかかってしまうかもしれません。ぜひ長い目で猫ちゃんを見守ってあげてくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼
新しいトイレに変えるときに試してほしいこと
皆さま、こんにちわ!OFTカスタマーサポート(サポ魂+)の黒猫くんです。 今回のテーマは、「新しいトイレに変えるときに試してほしいこと」。猫ちゃんのトイレの切り替えにお困りの方がいれば、参考にしていただけると嬉しい限りです。 ぜひ知っておきたい猫の特質とは? そもそも猫ちゃんの性質として、自分が暮らしている住環境に重きを置いているため、環境の変化を極端に嫌います。非常にデリケートなので、不安になってしまうのです。そこで、トイレを使ってもらうにあたって前提となるのが絶対に無理やり使わせようとしないこと!環境の変化に対して不安になっている中、その対象であるトイレを無理やり使わせようとすると、より警戒心が強くなり、二度と使ってくれなくなってしまいます。私たちでも、不安が大きい場所に無理やり連れて行かれたりすると、ストレスがかかりますよね…それと同じなのです。 トイレ切替時に試してほしい3つのこと ここからが本題です。もし猫ちゃんがなかなか新しいトイレを使ってくれないときには、次の3つを試してみてください。 1.前回と同じ場所に置く猫ちゃんのストレスを最小限にするため、古いトイレがあった場所に新しいトイレを置いてください。場所が変わると、その変化を嫌がり粗相をしてしまうかもしれません。2.古いトイレの横に、新しいトイレを置く1の方法でも、猫ちゃんが我慢してしまう素振りがあれば、古いトイレと新しいトイレを並べて置いてみてください。そうすることで、少しずつ新しいトイレに慣れてくるかと思います。3.使用済みの猫砂を入れてみる猫ちゃんはニオイで環境の判断をします。使用済みの猫砂を入れることで、「ここはトイレなんだ!」と覚えてもらいましょう。 猫が慣れるのを焦らず、気長に待つ ▲お気に入りのハンモックに乗ってくつろぐ、我が家のかい君です! 以前、お客様からお問い合わせがあったもので、切り替えに約2週間ほど要した事例もあります。猫ちゃんの性格はさまざまですし、臆病な子はもっと時間がかかってしまうかもしれません。ぜひ長い目で猫ちゃんを見守ってあげてくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼

ペットたちの同居がうまくいく秘訣とは?
ある日、お客様からお問合せをいただきました。『初めて猫を飼おうと思っていますが、後ろ足の悪い保護した子で、御社の自動猫トイレは使えますか?』このような初めて猫と暮らすお客様に対して、私たちがまずすることは、猫のことをどの程度ご存じなのかという確認です。 猫のことを知ることで、必要な用品選びやお部屋の状況がそのままでもよいのかなどを考えるきっかけとなります。交通事故で片足を失った猫ちゃんということであれば、さらに配慮が必要です。 やっぱり気になるニオイ問題 ▲例えば木製のペレットを使うシステムトイレ お客様はもう一つの問題についても相談してこられました。それは、ニオイの問題です。もともとニオイが苦手だそうで、猫の排泄物のニオイは非常にきつく感じるかもしれません。お部屋の空調関係の設備も含め、自動猫トイレの種類、使用する砂の種類、消臭剤選びなどもポイントになってきます。 お客様の家には先住者がいた!? さらに、猫の話をしている中で、新たな問題も発覚しました。よくよく伺ってみると、すでにウサギと暮らしていらっしゃるというのです。 猫ちゃんのほうは足の治療のため1か月以上病院で暮らし、犬や猫など自分以外の動物、そしてスタッフに対しても、まったく緊張せず暮らしていることから社会性が出来ているようです。 ウサギのほうはどうでしょうか? ウサギは人になつくのか? 種類にもよるかもしれませんが、ウサギは非常に人になつきます。 特に今回のお客様のように、一人になついている場合、飼い主以外には威嚇行動をとります。それは、まだ見ぬ猫に対しても同じかもしれません。 ふたり(ウサギと猫)が、同じ空間で生活できるようになるまでは、時間と距離感が必要なようです。その役割は、お客様に託されています。 ウサギと猫を一緒に飼うときの注意点 ウサギは夜行性の草食動物。逆に猫は代表的な肉食動物で、最近では薄明性(明け方や夕方に活発に活動する)との見解が正しいとも言われています。 猫の耳が良いのは、獲物を探し出すためです。一方、ウサギのあの大きな耳は、捕食者である肉食動物から自身を守るために進化した結果なので、自分の住処にネコちゃんが入ってきた場合、今まで休んでいたはずの時間も音に敏感になるかもしれません。 ただし、家の中は自然下ではありませんので、無理せず時間をかけて慣れさせていくことで、仲良く暮らせるようになるのではないかと思います。いつの日か、良いご連絡をいただきたいと感じるお客様との会話でした。 ▼ この記事を書いたのは ▼
ペットたちの同居がうまくいく秘訣とは?
ある日、お客様からお問合せをいただきました。『初めて猫を飼おうと思っていますが、後ろ足の悪い保護した子で、御社の自動猫トイレは使えますか?』このような初めて猫と暮らすお客様に対して、私たちがまずすることは、猫のことをどの程度ご存じなのかという確認です。 猫のことを知ることで、必要な用品選びやお部屋の状況がそのままでもよいのかなどを考えるきっかけとなります。交通事故で片足を失った猫ちゃんということであれば、さらに配慮が必要です。 やっぱり気になるニオイ問題 ▲例えば木製のペレットを使うシステムトイレ お客様はもう一つの問題についても相談してこられました。それは、ニオイの問題です。もともとニオイが苦手だそうで、猫の排泄物のニオイは非常にきつく感じるかもしれません。お部屋の空調関係の設備も含め、自動猫トイレの種類、使用する砂の種類、消臭剤選びなどもポイントになってきます。 お客様の家には先住者がいた!? さらに、猫の話をしている中で、新たな問題も発覚しました。よくよく伺ってみると、すでにウサギと暮らしていらっしゃるというのです。 猫ちゃんのほうは足の治療のため1か月以上病院で暮らし、犬や猫など自分以外の動物、そしてスタッフに対しても、まったく緊張せず暮らしていることから社会性が出来ているようです。 ウサギのほうはどうでしょうか? ウサギは人になつくのか? 種類にもよるかもしれませんが、ウサギは非常に人になつきます。 特に今回のお客様のように、一人になついている場合、飼い主以外には威嚇行動をとります。それは、まだ見ぬ猫に対しても同じかもしれません。 ふたり(ウサギと猫)が、同じ空間で生活できるようになるまでは、時間と距離感が必要なようです。その役割は、お客様に託されています。 ウサギと猫を一緒に飼うときの注意点 ウサギは夜行性の草食動物。逆に猫は代表的な肉食動物で、最近では薄明性(明け方や夕方に活発に活動する)との見解が正しいとも言われています。 猫の耳が良いのは、獲物を探し出すためです。一方、ウサギのあの大きな耳は、捕食者である肉食動物から自身を守るために進化した結果なので、自分の住処にネコちゃんが入ってきた場合、今まで休んでいたはずの時間も音に敏感になるかもしれません。 ただし、家の中は自然下ではありませんので、無理せず時間をかけて慣れさせていくことで、仲良く暮らせるようになるのではないかと思います。いつの日か、良いご連絡をいただきたいと感じるお客様との会話でした。 ▼ この記事を書いたのは ▼

ワンちゃんのお散歩と花粉症対策
春らしい日が続き、本格的に花粉の季節が到来。温かくなるとお出かけしたくなりますが、逆に「花粉症」のためにお出かけが憂鬱になる方もいやっしゃるこの時期。日本独自と言える花粉症は、お悩みを抱える方が年々増加傾向にあります。ワンちゃんとのお散歩も、ちょっと気が重いという飼い主様に、簡単にできる花粉対策がありますのでご紹介いたします。 花粉症の原因となる植物の種類 スギのほかに花粉症を引き起こす原因(アレルゲン)となる主な植物には、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、カナムグラなどがあり、花粉の種類や飛散時期は地域によって異なります。肝心な花粉の飛散開始時期や飛散状況が分からなければ、対策も取れません。花粉の飛散開始時期をなどは、花粉情報サイトを活用して情報収集しましょう。 地域別の花粉飛散 ▲スギ花粉の飛散 全国的に患者さんが増え続けているスギ花粉によるアレルギー。しかし、北海道ではスギ花粉飛散量は非常に少なく、沖縄では植林されていないのでスギ花粉の飛散はありません。スギ花粉の飛散量が比較的多いのは関東・東海地方です。また、関東・東海地方ではヒノキ花粉も飛んでいるため、症状が重い方はシーズン中は体調を崩すことも・・・。関西ではスギとヒノキの花粉飛散量はほぼ同等ですが、天候などの条件によってはヒノキ花粉のほうが多くなることもあります。 花粉が飛散しやすい条件 花粉飛散量は、その日の天候や温度などによって変わり、飛散しやすい日や時間帯があります。花粉が多く飛びやすい日 晴れまたはくもりの日 雨が降った翌日 最高気温が高い日 湿度が低い日 やや強い風が吹き、その後北風に変化した日 からりと晴れて湿度が低く風が強い・・・花粉が飛ぶには最高の条件だそうです。お出かけの時のマスクやメガネは必須ですね。逆に花粉が少ないと予想される日 雨の日 湿気が高い日 風が弱い日 花粉の飛散には湿度が大きく影響しています。湿度が高ければ、花粉の飛散は少なくなります。そして湿度は気温に左右されます。 気温と湿度と花粉の関係は 気温が上がる→湿度が下がる→花粉が多い 気温が下がる→湿度が上がる→花粉が少ない 雨の日で湿度が高く風も少ない・・・花粉の飛散が少ないと言えます。 花粉が飛びやすい時間帯 地域や天候によっても異なりますが、花粉が飛びやすい時間帯は午後1時~3時頃と言われています。これは午後1時~3時頃が1日のうちで最も気温が高くなるためです。早朝、スギやヒノキ林周辺から飛散し始めた花粉は、午前中に郊外、住宅地、都市部へと飛散が広がっていきます。飛散量は昼ごろまで続き、午後に一旦落ち着いて、夕方は気温の低下による空気の対流で花粉の飛散が増加します。花粉の少ない時間帯は夜21時~朝8時になります。午前中や夕方はちょうど一般的に、ワンちゃんのお散歩の時間帯と重なりますので、春先の花粉症シーズンには、通常の午前中や夕方のお散歩の時間帯を早めに夏のお散歩の時間帯(早朝や夜遅め)に切り替えることで、飛散のピークを避けることができます。 コースの変更とブラッシング ▲被毛にも花粉が付着しますので丁寧にブラッシングを。 お散歩中やお散歩から帰った後に花粉症の症状がひどく感じられる場合は、コースの近くにスギ・ヒノキがある可能性があります。飛散が酷い時期は、少しお散歩コースを変えてみるのも一つの手かもしれません。また、人が玄関先で花粉を払うのと同じように、ワンちゃんの被毛にも花粉は付着しますので、お散歩から帰宅した際、家に入る前に念入りにブラッシングすることで、花粉を家の中に持ち込まないための対策になります。 簡単・花粉対策まとめ 夏のお散歩の時間帯(早朝や夜遅め)に切り替える お散歩コースを変えてみる...
ワンちゃんのお散歩と花粉症対策
春らしい日が続き、本格的に花粉の季節が到来。温かくなるとお出かけしたくなりますが、逆に「花粉症」のためにお出かけが憂鬱になる方もいやっしゃるこの時期。日本独自と言える花粉症は、お悩みを抱える方が年々増加傾向にあります。ワンちゃんとのお散歩も、ちょっと気が重いという飼い主様に、簡単にできる花粉対策がありますのでご紹介いたします。 花粉症の原因となる植物の種類 スギのほかに花粉症を引き起こす原因(アレルゲン)となる主な植物には、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、カナムグラなどがあり、花粉の種類や飛散時期は地域によって異なります。肝心な花粉の飛散開始時期や飛散状況が分からなければ、対策も取れません。花粉の飛散開始時期をなどは、花粉情報サイトを活用して情報収集しましょう。 地域別の花粉飛散 ▲スギ花粉の飛散 全国的に患者さんが増え続けているスギ花粉によるアレルギー。しかし、北海道ではスギ花粉飛散量は非常に少なく、沖縄では植林されていないのでスギ花粉の飛散はありません。スギ花粉の飛散量が比較的多いのは関東・東海地方です。また、関東・東海地方ではヒノキ花粉も飛んでいるため、症状が重い方はシーズン中は体調を崩すことも・・・。関西ではスギとヒノキの花粉飛散量はほぼ同等ですが、天候などの条件によってはヒノキ花粉のほうが多くなることもあります。 花粉が飛散しやすい条件 花粉飛散量は、その日の天候や温度などによって変わり、飛散しやすい日や時間帯があります。花粉が多く飛びやすい日 晴れまたはくもりの日 雨が降った翌日 最高気温が高い日 湿度が低い日 やや強い風が吹き、その後北風に変化した日 からりと晴れて湿度が低く風が強い・・・花粉が飛ぶには最高の条件だそうです。お出かけの時のマスクやメガネは必須ですね。逆に花粉が少ないと予想される日 雨の日 湿気が高い日 風が弱い日 花粉の飛散には湿度が大きく影響しています。湿度が高ければ、花粉の飛散は少なくなります。そして湿度は気温に左右されます。 気温と湿度と花粉の関係は 気温が上がる→湿度が下がる→花粉が多い 気温が下がる→湿度が上がる→花粉が少ない 雨の日で湿度が高く風も少ない・・・花粉の飛散が少ないと言えます。 花粉が飛びやすい時間帯 地域や天候によっても異なりますが、花粉が飛びやすい時間帯は午後1時~3時頃と言われています。これは午後1時~3時頃が1日のうちで最も気温が高くなるためです。早朝、スギやヒノキ林周辺から飛散し始めた花粉は、午前中に郊外、住宅地、都市部へと飛散が広がっていきます。飛散量は昼ごろまで続き、午後に一旦落ち着いて、夕方は気温の低下による空気の対流で花粉の飛散が増加します。花粉の少ない時間帯は夜21時~朝8時になります。午前中や夕方はちょうど一般的に、ワンちゃんのお散歩の時間帯と重なりますので、春先の花粉症シーズンには、通常の午前中や夕方のお散歩の時間帯を早めに夏のお散歩の時間帯(早朝や夜遅め)に切り替えることで、飛散のピークを避けることができます。 コースの変更とブラッシング ▲被毛にも花粉が付着しますので丁寧にブラッシングを。 お散歩中やお散歩から帰った後に花粉症の症状がひどく感じられる場合は、コースの近くにスギ・ヒノキがある可能性があります。飛散が酷い時期は、少しお散歩コースを変えてみるのも一つの手かもしれません。また、人が玄関先で花粉を払うのと同じように、ワンちゃんの被毛にも花粉は付着しますので、お散歩から帰宅した際、家に入る前に念入りにブラッシングすることで、花粉を家の中に持ち込まないための対策になります。 簡単・花粉対策まとめ 夏のお散歩の時間帯(早朝や夜遅め)に切り替える お散歩コースを変えてみる...

冬場のお出かけに要注意!クーラント(不凍液)の危険性
冬の季節のペットの散歩の注意点があります。本格的に寒くなってきたこの季節、寒さや雪以外にもペットが外を歩く際に気を付けるべき大切なことがあります。 知っていますか?道端に潜む危険 ▲寒くてもやっぱりお散歩は欠かせません 冬場、冷却水や暖房ヒーターの内部が凍結してしまうことを防ぐため、車や一部のヒーターの内部にはクーラントと呼ばれる不凍液が装備されています。不凍液には凍結を防ぐエチレングリコールという成分が含まれており、これが万が一ペットの体内に摂取されてしまった場合は非常に危険です。エチレングリコールは不凍液以外の溶剤等にも使用されますが、不凍液は特に舐めると甘い味がするため、甘味を好む犬は舐めてしまいやすいのです。濃度が薄かったり、劣化したクーラントが交換されないまま気温が低くなると、凍結し内部で膨張するため部品が破損し、クーラントは外に漏れ出してしまいます。アイルランドではエチレングリコールによる中毒症状が出て病院に運ばれてくる猫も多く、その原因は外で活動する猫たちが車の下に入ったり、ボンネットに乗ったりするため、車から漏れ出た不凍液が体に付着し、それを舐めて体内に摂取してしまうことです。 命に係わる強い毒性のある不凍液 ▲メンテナンスを怠ると道に漏れだすことが… 例えば、不凍液を摂取してしまった猫の生存率はわずか5パーセントと言われています。30分~1時間の間に嗜眠、嘔吐、低体温や発作などが起き、呼吸や心拍数の上昇によって脱水症状になります。これが重度の腎臓障害を引き起こし、24~48時間後には腎不全の症状が現れ、最終的に死に至ります。犬にとっても毒性が強く、早期に中毒症状に気づくことができれば解毒できる可能性はありますが、必ず助かるという保証はありません。濃度にもよりますが、犬も猫もほんのわずかな量のエチレングリコールで命に危険が及ぶため、十分に注意が必要です。特に猫は1ml以下でも致死量となります。 飼い主が気を付ければ防げる誤飲 ▲目の届かないところで摂取してしまうかも エチレングリコールが含まれる不凍液はペットの命を脅かす大変危険な物質ですが、もちろん飼い主が気を付ければ体内への摂取を防ぐことができます。外飼いの猫の場合はなるべく外に出さないようにしてあげれば、不凍液との接触のリスクが下がります。犬の場合は散歩の際に必ずリードを着用し、目を離さないように注意しましょう。不凍液は赤や緑などの蛍光色が付いている場合が多いですが、中には無色透明のものもありますので十分な注意が必要です。そしてもし万が一、不凍液を誤って舐めさせてしまったり、中毒の症状が見られる場合はすぐに獣医に連絡してください。
冬場のお出かけに要注意!クーラント(不凍液)の危険性
冬の季節のペットの散歩の注意点があります。本格的に寒くなってきたこの季節、寒さや雪以外にもペットが外を歩く際に気を付けるべき大切なことがあります。 知っていますか?道端に潜む危険 ▲寒くてもやっぱりお散歩は欠かせません 冬場、冷却水や暖房ヒーターの内部が凍結してしまうことを防ぐため、車や一部のヒーターの内部にはクーラントと呼ばれる不凍液が装備されています。不凍液には凍結を防ぐエチレングリコールという成分が含まれており、これが万が一ペットの体内に摂取されてしまった場合は非常に危険です。エチレングリコールは不凍液以外の溶剤等にも使用されますが、不凍液は特に舐めると甘い味がするため、甘味を好む犬は舐めてしまいやすいのです。濃度が薄かったり、劣化したクーラントが交換されないまま気温が低くなると、凍結し内部で膨張するため部品が破損し、クーラントは外に漏れ出してしまいます。アイルランドではエチレングリコールによる中毒症状が出て病院に運ばれてくる猫も多く、その原因は外で活動する猫たちが車の下に入ったり、ボンネットに乗ったりするため、車から漏れ出た不凍液が体に付着し、それを舐めて体内に摂取してしまうことです。 命に係わる強い毒性のある不凍液 ▲メンテナンスを怠ると道に漏れだすことが… 例えば、不凍液を摂取してしまった猫の生存率はわずか5パーセントと言われています。30分~1時間の間に嗜眠、嘔吐、低体温や発作などが起き、呼吸や心拍数の上昇によって脱水症状になります。これが重度の腎臓障害を引き起こし、24~48時間後には腎不全の症状が現れ、最終的に死に至ります。犬にとっても毒性が強く、早期に中毒症状に気づくことができれば解毒できる可能性はありますが、必ず助かるという保証はありません。濃度にもよりますが、犬も猫もほんのわずかな量のエチレングリコールで命に危険が及ぶため、十分に注意が必要です。特に猫は1ml以下でも致死量となります。 飼い主が気を付ければ防げる誤飲 ▲目の届かないところで摂取してしまうかも エチレングリコールが含まれる不凍液はペットの命を脅かす大変危険な物質ですが、もちろん飼い主が気を付ければ体内への摂取を防ぐことができます。外飼いの猫の場合はなるべく外に出さないようにしてあげれば、不凍液との接触のリスクが下がります。犬の場合は散歩の際に必ずリードを着用し、目を離さないように注意しましょう。不凍液は赤や緑などの蛍光色が付いている場合が多いですが、中には無色透明のものもありますので十分な注意が必要です。そしてもし万が一、不凍液を誤って舐めさせてしまったり、中毒の症状が見られる場合はすぐに獣医に連絡してください。

新商品のイメージ撮影の様子をレポート!
OFT STOREがお店として重要視していること、それは商品のイメージをわかりやすくお伝えすることです。やはりネットショップは実店舗と違い、お客様が実際に商品を手に取ることはできません。だからこそ、商品ページだけでサイズや使用感がわかり、購入後の生活が想像しやすいように…。そんな思いを胸に、商品ページを制作するまで様々な方が撮影に関わっています。今回は、そんなオーエフティーの撮影ロケに同行し、現場の様子をレポートしていきます。― 2018年10月。秋晴れの朝の河川敷はカラッと心地の良い風が吹いていて、絶好の撮影日和でした。カメラマンさん、モデルさん、モデル犬のオラフ君(フレンチブルドッグ・1歳2か月の男の子)が集まり、ロケ撮影のスタートです。今回撮影する商品は実に7種類!WEBページの専属デザイナーとエディターが、事前に何度も打ち合わせて作成したデザインラフをもとに、ページを構成する写真を撮影していきます。 ▲カメラマンの川本さん。レンズを覗く眼差しは真剣そのもの。 スタートを盛り上げてくれたフレブル・オラフ君 まずは全天候型ドッグブーツ、”マットトラッカーズ”。撮影クルーに囲まれて緊張気味だったオラフ君も、モデルさんと遊べばあっという間にリラックス。楽しそうに野原を駆け回ってくれました。ブーツはあまり履きなれていないとのことで不安もあったのですが、実際に装着してみると特に違和感もない様子。夢中になりすぎて顔面からズッコケた瞬間の、奇跡の一枚も撮れちゃいました(笑) ▲マットトラッカーズを履いて元気に飛行犬するオラフ君 ▲痛っ!ころんだ後も元気に走り回って私たちを安心させてくれました。 ワンちゃんはあまり集中力が続かない子が多く、撮影はまさに時間との勝負。手早くロケ撮影を終わらせた後は、屋内でのスタジオ撮影に移ります。今回は、リビング・キッチン・廊下の3つのスタジオを用意。撮影の流れを読んで、同行していたスタッフがテキパキと商品や演出小物を組み立て、設置していきます。ただ見ているだけだった私は、タイムロスのない完璧な流れに舌を巻くばかりでした。 ▲終始てきぱきと指示が飛んでいましたが、時折笑い声も混じる穏やかな雰囲気。 ペット用のサークルやゲート、靴下、肉球クリーム。目まぐるしく商品が取り替えられては次々とシャッターが切られていきます。撮影の合間には、オラフ君が退屈しないように遊んだりおやつをあげることも欠かせません。印象深かった商品が、ペット用の”ハンズフリードライヤー”。オシャレなデザインで、両手を使ってペットを乾かすことができるという画期的なアイテムです。ドライヤーの温かい風とモデルさんの心地よいマッサージで、普段はやんちゃなオラフ君もリラックスした表情でとっても気持ちよさそうでした。 決して簡単ではないモデル犬との付き合い方 ▲撮影の合間のお昼寝タイム 朝から始まった撮影も、終わる頃にはとっぷりと日が暮れかかる時間になっていました。これは十分に大変な作業だなと感じていたのですが、撮影スタッフによると「今回はワンちゃん1匹の撮影だったからスムーズだった」とのこと。確かに、猫ちゃんや小型犬~大型犬など数匹が出演する商品ページになると、コントロールが一層大変になりそうです。ページを構成するラフ画や文章を作成するところから始まって、今回のように撮影が終わった後は、専任のデザイナーが選りすぐりの画像を使って商品ページを制作する作業に入ります。商品ページが出来上がるまでに、たくさんの人たちの思いやこだわりが詰まっているんですね。そんな背景をちょっと想像しながら、当店のページを覗いてみて頂けると嬉しいです。■今回写真で登場した商品はこちら マットトラッカーズ(こちらの製品は廃盤となりました)Alizee ハンズフリードライヤー
新商品のイメージ撮影の様子をレポート!
OFT STOREがお店として重要視していること、それは商品のイメージをわかりやすくお伝えすることです。やはりネットショップは実店舗と違い、お客様が実際に商品を手に取ることはできません。だからこそ、商品ページだけでサイズや使用感がわかり、購入後の生活が想像しやすいように…。そんな思いを胸に、商品ページを制作するまで様々な方が撮影に関わっています。今回は、そんなオーエフティーの撮影ロケに同行し、現場の様子をレポートしていきます。― 2018年10月。秋晴れの朝の河川敷はカラッと心地の良い風が吹いていて、絶好の撮影日和でした。カメラマンさん、モデルさん、モデル犬のオラフ君(フレンチブルドッグ・1歳2か月の男の子)が集まり、ロケ撮影のスタートです。今回撮影する商品は実に7種類!WEBページの専属デザイナーとエディターが、事前に何度も打ち合わせて作成したデザインラフをもとに、ページを構成する写真を撮影していきます。 ▲カメラマンの川本さん。レンズを覗く眼差しは真剣そのもの。 スタートを盛り上げてくれたフレブル・オラフ君 まずは全天候型ドッグブーツ、”マットトラッカーズ”。撮影クルーに囲まれて緊張気味だったオラフ君も、モデルさんと遊べばあっという間にリラックス。楽しそうに野原を駆け回ってくれました。ブーツはあまり履きなれていないとのことで不安もあったのですが、実際に装着してみると特に違和感もない様子。夢中になりすぎて顔面からズッコケた瞬間の、奇跡の一枚も撮れちゃいました(笑) ▲マットトラッカーズを履いて元気に飛行犬するオラフ君 ▲痛っ!ころんだ後も元気に走り回って私たちを安心させてくれました。 ワンちゃんはあまり集中力が続かない子が多く、撮影はまさに時間との勝負。手早くロケ撮影を終わらせた後は、屋内でのスタジオ撮影に移ります。今回は、リビング・キッチン・廊下の3つのスタジオを用意。撮影の流れを読んで、同行していたスタッフがテキパキと商品や演出小物を組み立て、設置していきます。ただ見ているだけだった私は、タイムロスのない完璧な流れに舌を巻くばかりでした。 ▲終始てきぱきと指示が飛んでいましたが、時折笑い声も混じる穏やかな雰囲気。 ペット用のサークルやゲート、靴下、肉球クリーム。目まぐるしく商品が取り替えられては次々とシャッターが切られていきます。撮影の合間には、オラフ君が退屈しないように遊んだりおやつをあげることも欠かせません。印象深かった商品が、ペット用の”ハンズフリードライヤー”。オシャレなデザインで、両手を使ってペットを乾かすことができるという画期的なアイテムです。ドライヤーの温かい風とモデルさんの心地よいマッサージで、普段はやんちゃなオラフ君もリラックスした表情でとっても気持ちよさそうでした。 決して簡単ではないモデル犬との付き合い方 ▲撮影の合間のお昼寝タイム 朝から始まった撮影も、終わる頃にはとっぷりと日が暮れかかる時間になっていました。これは十分に大変な作業だなと感じていたのですが、撮影スタッフによると「今回はワンちゃん1匹の撮影だったからスムーズだった」とのこと。確かに、猫ちゃんや小型犬~大型犬など数匹が出演する商品ページになると、コントロールが一層大変になりそうです。ページを構成するラフ画や文章を作成するところから始まって、今回のように撮影が終わった後は、専任のデザイナーが選りすぐりの画像を使って商品ページを制作する作業に入ります。商品ページが出来上がるまでに、たくさんの人たちの思いやこだわりが詰まっているんですね。そんな背景をちょっと想像しながら、当店のページを覗いてみて頂けると嬉しいです。■今回写真で登場した商品はこちら マットトラッカーズ(こちらの製品は廃盤となりました)Alizee ハンズフリードライヤー

米アマゾンが行っているペット同伴出勤はペット先進国ならではの取り組み!?
現在ネット通販大手の米アマゾンでは、6000匹の犬が社員と共に出社しているという記事がありました。米国では犬にも社員証が発行されるというグーグルなども含め、犬やその他のペットとの同伴出勤を推進する風潮がありますが、当然そこには社員のストレスを軽減させ、社員同士のコミュニケーションを活性化してくれるなどの理由があるようです。またペット自身にとっても、飼い主と別れる必要もなくなり、長時間帰宅を待つ日々から解放もされるため、大変良い環境であると言えそうです。ということで今回は、私たちのいる日本で犬との同伴出勤をした場合、何に配慮し、どんな事を確認しなければならないのか?を考察します。 ペットとの同伴出勤の多くの課題 ▲毎日長時間ひとりで飼い主の帰りを待っているのは寂しくて辛い 社員や会社、ペット自身にとっても、メリットがあるのであれば、『わが社もやってみようじゃないか!』と声を上げる方もいるかもしれません。もし実際に、多くの社員が毎日ペットを連れて会社に出勤してくるような状況になれば、きっと安易にそんなことを口走れなくなるでしょう。そう考えると、6000匹という規模で同伴出勤の取り組みを行っているアマゾンは、まさに『あっぱれ!』と言いたい気持ちになります。では一体、どのような条件が必要で、どのようなことに気を配るべきなのか、猫の情報も少し交えながら紹介していきましょう。 日本でのペット同伴出勤は6つの課題のクリアが必要 1:通勤 同伴出勤するには、まずは彼ら(ペット)を会社に連れて行かなければなりません。車での通勤の場合は問題ありませんが、電車通勤のケースを見てみましょう。犬や猫などのペットを、電車に乗せる時の条件には鉄道会社ごとの違いがあります。持ち込めるペットキャリーのサイズや重さの制限、料金の違いのほか、キャリーではなくカートは大丈夫なのかダメなのか?という部分にも違いがあります。また通勤ラッシュでの出勤や、追加の交通費が支給されるかなど、会社側の補助も大きな問題ですね。2:居住空間会社に到着したら、つぎに彼らの居住空間の確保が必要です。飼い主=社員との十分な共有スペースがある会社なら問題はありませんが、なかなかスペースの確保が難しい場合もあります。当然猫の場合になると、登り下りできる場所の確保も必要ですし、万が一脱走などすれば、大変なことになってしまいますので細心の注意も必要です。3:抜け毛など約10万本あると言われている人間の頭髪は、人により差はありますが、1日数十本から200本ほど抜けると言われています。一方、全身を毛で覆われている犬や猫は、種類にもよりますが、100万本~200万本ほどの毛が生えていると言われていますので、それだけをとってみても今までよりもマメな掃除は必須です。4:アレルギーやニオイ犬や猫アレルギーは、犬や猫のフケや皮脂などに含まれるたんぱく質が原因となりますので、もし問題が発生した場合には、やはり会社の対応が必要です。また犬や猫が会社に来るということは、ニオイの問題に気を配るべきでしょう。体臭については、シャンプーすることで解決できます。トイレについても正しいしつけとマメな処理で、問題になることはないでしょう。他には、強いフレーバーのペットフードなどもあります。ペットの嗜好性の問題もありますので、飼い主がうまく管理することも必要です。5:塗料や芳香剤・植物など地面から顔が近く床に寝そべることも多い犬の場合、床材の塗料、そして清掃時に使う洗剤やワックスにも、一応気を配っておくべきかもしれません。特に猫は、観葉植物を食べて死亡もしくは重篤な症状になることがあるため、気をつけなければなりません。アロマなどもペットに合わせて適切に使用する必要があり、猫の環境整理は重要です。6:社会化さて、最後に当たり前ですが、飼い主以外の人や他の犬にも抵抗なく接することのできるような子でなければ、ペット自身が会社の環境が苦痛になってしまいます。猫は、特に環境変化に敏感ですので、子猫のころから環境に慣れさせなければならないかもしれません。 ▲仕事中もペットと一緒に入れることが理想ですが… アマゾンの場合、6000匹の犬たちが毎日社内でドッグフードを食べ、水を飲み、トイレをして、そして何万本もの抜け毛を落としていくはずなのです。 そんなことを感じさせないニュースの記事を読んでいると、環境整理が行き届いていて素晴らしい!という言葉しか出てきません。ぜひお手本にしたいものです。
米アマゾンが行っているペット同伴出勤はペット先進国ならではの取り組み!?
現在ネット通販大手の米アマゾンでは、6000匹の犬が社員と共に出社しているという記事がありました。米国では犬にも社員証が発行されるというグーグルなども含め、犬やその他のペットとの同伴出勤を推進する風潮がありますが、当然そこには社員のストレスを軽減させ、社員同士のコミュニケーションを活性化してくれるなどの理由があるようです。またペット自身にとっても、飼い主と別れる必要もなくなり、長時間帰宅を待つ日々から解放もされるため、大変良い環境であると言えそうです。ということで今回は、私たちのいる日本で犬との同伴出勤をした場合、何に配慮し、どんな事を確認しなければならないのか?を考察します。 ペットとの同伴出勤の多くの課題 ▲毎日長時間ひとりで飼い主の帰りを待っているのは寂しくて辛い 社員や会社、ペット自身にとっても、メリットがあるのであれば、『わが社もやってみようじゃないか!』と声を上げる方もいるかもしれません。もし実際に、多くの社員が毎日ペットを連れて会社に出勤してくるような状況になれば、きっと安易にそんなことを口走れなくなるでしょう。そう考えると、6000匹という規模で同伴出勤の取り組みを行っているアマゾンは、まさに『あっぱれ!』と言いたい気持ちになります。では一体、どのような条件が必要で、どのようなことに気を配るべきなのか、猫の情報も少し交えながら紹介していきましょう。 日本でのペット同伴出勤は6つの課題のクリアが必要 1:通勤 同伴出勤するには、まずは彼ら(ペット)を会社に連れて行かなければなりません。車での通勤の場合は問題ありませんが、電車通勤のケースを見てみましょう。犬や猫などのペットを、電車に乗せる時の条件には鉄道会社ごとの違いがあります。持ち込めるペットキャリーのサイズや重さの制限、料金の違いのほか、キャリーではなくカートは大丈夫なのかダメなのか?という部分にも違いがあります。また通勤ラッシュでの出勤や、追加の交通費が支給されるかなど、会社側の補助も大きな問題ですね。2:居住空間会社に到着したら、つぎに彼らの居住空間の確保が必要です。飼い主=社員との十分な共有スペースがある会社なら問題はありませんが、なかなかスペースの確保が難しい場合もあります。当然猫の場合になると、登り下りできる場所の確保も必要ですし、万が一脱走などすれば、大変なことになってしまいますので細心の注意も必要です。3:抜け毛など約10万本あると言われている人間の頭髪は、人により差はありますが、1日数十本から200本ほど抜けると言われています。一方、全身を毛で覆われている犬や猫は、種類にもよりますが、100万本~200万本ほどの毛が生えていると言われていますので、それだけをとってみても今までよりもマメな掃除は必須です。4:アレルギーやニオイ犬や猫アレルギーは、犬や猫のフケや皮脂などに含まれるたんぱく質が原因となりますので、もし問題が発生した場合には、やはり会社の対応が必要です。また犬や猫が会社に来るということは、ニオイの問題に気を配るべきでしょう。体臭については、シャンプーすることで解決できます。トイレについても正しいしつけとマメな処理で、問題になることはないでしょう。他には、強いフレーバーのペットフードなどもあります。ペットの嗜好性の問題もありますので、飼い主がうまく管理することも必要です。5:塗料や芳香剤・植物など地面から顔が近く床に寝そべることも多い犬の場合、床材の塗料、そして清掃時に使う洗剤やワックスにも、一応気を配っておくべきかもしれません。特に猫は、観葉植物を食べて死亡もしくは重篤な症状になることがあるため、気をつけなければなりません。アロマなどもペットに合わせて適切に使用する必要があり、猫の環境整理は重要です。6:社会化さて、最後に当たり前ですが、飼い主以外の人や他の犬にも抵抗なく接することのできるような子でなければ、ペット自身が会社の環境が苦痛になってしまいます。猫は、特に環境変化に敏感ですので、子猫のころから環境に慣れさせなければならないかもしれません。 ▲仕事中もペットと一緒に入れることが理想ですが… アマゾンの場合、6000匹の犬たちが毎日社内でドッグフードを食べ、水を飲み、トイレをして、そして何万本もの抜け毛を落としていくはずなのです。 そんなことを感じさせないニュースの記事を読んでいると、環境整理が行き届いていて素晴らしい!という言葉しか出てきません。ぜひお手本にしたいものです。

ペットと楽しむハロウィン!《 アメリカ ボストンのハロウィンペットパレード 》
秋も本番!ハロウィンが近づいてくるこの時期はなんだかワクワクしますよね。ハロウィンといえば仮装してみんなでパーティをするようなイメージがありませんか?本場と言えるアメリカやヨーロッパでは、ペットも飼い主さんと一緒に仮装してハロウィンを楽しむようです。 ▲3匹のワンちゃんがお化けに変身! 日本ではペット用のハロウィンコスチュームはあまりメジャーではありませんが、アメリカではペット用コスチュームがペット用品店の店頭でも数多く販売されており、気軽に仮装ができるのです。中には飼い主と合わせた衣装を自作する人も!映画のキャラクターやアメコミヒーローに扮するペットもいれば、ホットドッグや寿司などの食べ物の仮装をするペットも(笑)その子にぴったりの衣装を合わせる飼い主さんたちのセンスが光ります。こだわりのコスチュームに着替えたら、やっぱりみんなで集まって交流したいですよね。アメリカやヨーロッパなどでは毎年ハロウィンの時期になると各地で大小さまざまな、ペットと一緒に楽しめるイベントが開催されます。 アメリカで開催されているペットのハロウィンイベント ▲賑やかな街並み!ボストン市の中心部(ファニエル・ホール) 今年で6回目を迎えるハロウィンイベントHALLOWEEN PET PARADE & COSTUME CONTESTの主催の方にお話を伺いました。このイベントは、マサチューセッツ州ボストン市の中心に位置するファニエル・ホール・マーケットプレイスという大きなショッピングセンターで開催されているようです。参加者は仮装したペットと一緒にマーケットプレイスの周りをパレードし、審査員の前を歩いてコスチュームをアピールします。1番のショーを繰り広げたペット、飼い主とペットのベストコンビなど様々な賞が用意されており、見事受賞者に選ばれた方々には賞品が贈られます。イベントは正午にスタート。昨年は400人もの参加者が集ったそうです。 ペットがパレードに登場?様々な仮装で大盛り上がり! ▲衣装が凝っていてとてもよく似合っています!(提供:FANEUIL HALL MARKETPLACE) ペットたちがそれぞれに合った衣装を着て登場するパレードは見ているだけでもワクワクします。犬、猫だけでなく爬虫類を連れて参加されている方もいらっしゃるようで驚きました。■昨年度のイベントの様子はこちら 飼い主さんも一緒になって仮装を楽しんでいて、こちらも思わず笑顔になってしまいます♪参加者だけでなく観客の方々もニコニコしながら見ていらっしゃるのがなんだか素敵ですよね。STAR WARSファンである私はSTAR WARSの仮装をしている方が多くて見ていてとても楽しいです(笑)大きな町の中心地のショッピングセンターでこれだけのペットが集まってイベントが開催できるのは海外ならではかもしれませんね。HALLOWEEN PET PARADE & COSTUME CONTESTは毎年開催されており、今年は10月27日に行われるそうです。アメリカということですぐに行ける距離ではありませんが、私も1度は実際に見に行きたいです。日本でもこのようにペットと一緒に参加できる楽しいイベントが増えるといいですね。さて、今後も海外のペットにまつわる情報、イベントなどをどんどんお届けしますのでどうぞお楽しみに!
ペットと楽しむハロウィン!《 アメリカ ボストンのハロウィンペットパレード 》
秋も本番!ハロウィンが近づいてくるこの時期はなんだかワクワクしますよね。ハロウィンといえば仮装してみんなでパーティをするようなイメージがありませんか?本場と言えるアメリカやヨーロッパでは、ペットも飼い主さんと一緒に仮装してハロウィンを楽しむようです。 ▲3匹のワンちゃんがお化けに変身! 日本ではペット用のハロウィンコスチュームはあまりメジャーではありませんが、アメリカではペット用コスチュームがペット用品店の店頭でも数多く販売されており、気軽に仮装ができるのです。中には飼い主と合わせた衣装を自作する人も!映画のキャラクターやアメコミヒーローに扮するペットもいれば、ホットドッグや寿司などの食べ物の仮装をするペットも(笑)その子にぴったりの衣装を合わせる飼い主さんたちのセンスが光ります。こだわりのコスチュームに着替えたら、やっぱりみんなで集まって交流したいですよね。アメリカやヨーロッパなどでは毎年ハロウィンの時期になると各地で大小さまざまな、ペットと一緒に楽しめるイベントが開催されます。 アメリカで開催されているペットのハロウィンイベント ▲賑やかな街並み!ボストン市の中心部(ファニエル・ホール) 今年で6回目を迎えるハロウィンイベントHALLOWEEN PET PARADE & COSTUME CONTESTの主催の方にお話を伺いました。このイベントは、マサチューセッツ州ボストン市の中心に位置するファニエル・ホール・マーケットプレイスという大きなショッピングセンターで開催されているようです。参加者は仮装したペットと一緒にマーケットプレイスの周りをパレードし、審査員の前を歩いてコスチュームをアピールします。1番のショーを繰り広げたペット、飼い主とペットのベストコンビなど様々な賞が用意されており、見事受賞者に選ばれた方々には賞品が贈られます。イベントは正午にスタート。昨年は400人もの参加者が集ったそうです。 ペットがパレードに登場?様々な仮装で大盛り上がり! ▲衣装が凝っていてとてもよく似合っています!(提供:FANEUIL HALL MARKETPLACE) ペットたちがそれぞれに合った衣装を着て登場するパレードは見ているだけでもワクワクします。犬、猫だけでなく爬虫類を連れて参加されている方もいらっしゃるようで驚きました。■昨年度のイベントの様子はこちら 飼い主さんも一緒になって仮装を楽しんでいて、こちらも思わず笑顔になってしまいます♪参加者だけでなく観客の方々もニコニコしながら見ていらっしゃるのがなんだか素敵ですよね。STAR WARSファンである私はSTAR WARSの仮装をしている方が多くて見ていてとても楽しいです(笑)大きな町の中心地のショッピングセンターでこれだけのペットが集まってイベントが開催できるのは海外ならではかもしれませんね。HALLOWEEN PET PARADE & COSTUME CONTESTは毎年開催されており、今年は10月27日に行われるそうです。アメリカということですぐに行ける距離ではありませんが、私も1度は実際に見に行きたいです。日本でもこのようにペットと一緒に参加できる楽しいイベントが増えるといいですね。さて、今後も海外のペットにまつわる情報、イベントなどをどんどんお届けしますのでどうぞお楽しみに!

人とペットの防災対策を考える(4)《 ペットのために普段から行っておく事 》
予知が出来なくなっている地震 平成21年にイタリア・ラクイラで発生した地震をきっかけに、国際的に「予知」についての議論が行われました。地震予知に成功した確実な事例がない、また、地震の発生を警告できるほどの確実性の高い前兆現象は見つかっていない事から、地震発生の時期を特定するのは困難だという認識が示されています。日本も公式に「地震予知はできない」と認めたことになり、警戒宣言も発表できなくなる見通しです。つまり、明日は我が身に起こるかも知れません。そのためにも、日頃から万が一に備えておくことが大切です。 家族であるペットを守るために、普段から行っておくべき事 ●飼主の元に帰れるように飼主情報を明確にし、個体識別をしておく。万が一、ペットが迷子や離ればなれになって何処かで保護されても、すぐに飼主に連絡が出来るように、首輪に鑑札や注射済票、住所・電話番号を記載した迷子札を付けておきましょう。マイクロチップの装着も有効です。また、犬の場合は必ず畜犬登録を行っておきましょう。●普段からマナーを守り、躾をしっかりとする。災害時は、現場が混乱する上、ペットも異常な事態を察知しおびえたり動揺してしまいます。おとなしいペットも、状況次第では、あばれたりする事も起こるかも知れません。普段から、犬や人とふれあわせ社会化をきちんと行ない友好的に育て、人の多い場所やケージに慣れさせておく事は、日常だけでなく非常時にも役立ちます。●大切なトイレの躾お散歩中、外でしか排泄をしない子は、長い時間ケージ等に隔離された場合、排泄を我慢してしまい可哀想な思いをさせてしまいます。トイレシートでも出来るようにしておく事も必要です。糞尿や抜け毛の始末をしたり、臭い等で近隣に迷惑をかけない配慮もしましょう。また、無駄吠えをさせない、待て、ハウスが出来るように躾ておく事も大事です。避難所でも受入がしてもらいやすくするために、飼主としての責任を意識し、回りへの充分な配慮をしましょう。●日々の健康管理も大切日常から、ペットの健康状態に注意し、ノミ・ダニ・フィラリアなど寄生虫の駆除を行いましょう。多数のペットが一緒に保護される場合、1頭でも病気を持っていると、あっという間に感染して広がってしまう事もあります。狂犬病予防接種、各種ワクチン接種も必ず行っておきましょう。また、気になる症状などがある場合は、早めに獣医師の診断を受けて治療をしましょう。被災時に、避難所生活や仮設住宅など、慣れない環境下で体調を崩してしまうのは人間だけでなく、ペットも同様です。飼い主さんが日頃から、ペットの健康管理をしっかり行っておきましよう。●ペットの居場所の確認をするペットの居場所が安全かどうか、点検をしておきましょう。・屋外飼育の場合地震が起きた際、ブロック壁の側や、ガラス窓の下など、建物が倒壊した際、ペットが被害を受けない場所にペットハウスは設置されていますか?水害が多い地域の場合、増水してもペットが溺れないような対策が取られていますか?・屋内飼育の場合地震対策として、倒れやすい家具の固定は必須です。小型のペットの場合、倒れてきた家具などによる怪我や圧死が起こる可能性があります。ガラスケースなど特殊な環境で飼育している場合、ケースが落ちて割れたりしないようにケースを固定し、ガラス飛散防止フィルムを貼るなどの対策をしましょう。次回vol.5につづく人とペットの防災対策を考える(1)《 ペットを守れるのは飼主だけ 》はこちら人とペットの防災対策を考える(2)《 人の安全確保のための防災 》はこちら人とペットの防災対策を考える(3)《 ペットのための備蓄 》はこちら人とペットの防災対策を考える(5)《 飼主が普段から準備しておく事 》はこちらby OFTスタッフ「あーちゃん」
人とペットの防災対策を考える(4)《 ペットのために普段から行っておく事 》
予知が出来なくなっている地震 平成21年にイタリア・ラクイラで発生した地震をきっかけに、国際的に「予知」についての議論が行われました。地震予知に成功した確実な事例がない、また、地震の発生を警告できるほどの確実性の高い前兆現象は見つかっていない事から、地震発生の時期を特定するのは困難だという認識が示されています。日本も公式に「地震予知はできない」と認めたことになり、警戒宣言も発表できなくなる見通しです。つまり、明日は我が身に起こるかも知れません。そのためにも、日頃から万が一に備えておくことが大切です。 家族であるペットを守るために、普段から行っておくべき事 ●飼主の元に帰れるように飼主情報を明確にし、個体識別をしておく。万が一、ペットが迷子や離ればなれになって何処かで保護されても、すぐに飼主に連絡が出来るように、首輪に鑑札や注射済票、住所・電話番号を記載した迷子札を付けておきましょう。マイクロチップの装着も有効です。また、犬の場合は必ず畜犬登録を行っておきましょう。●普段からマナーを守り、躾をしっかりとする。災害時は、現場が混乱する上、ペットも異常な事態を察知しおびえたり動揺してしまいます。おとなしいペットも、状況次第では、あばれたりする事も起こるかも知れません。普段から、犬や人とふれあわせ社会化をきちんと行ない友好的に育て、人の多い場所やケージに慣れさせておく事は、日常だけでなく非常時にも役立ちます。●大切なトイレの躾お散歩中、外でしか排泄をしない子は、長い時間ケージ等に隔離された場合、排泄を我慢してしまい可哀想な思いをさせてしまいます。トイレシートでも出来るようにしておく事も必要です。糞尿や抜け毛の始末をしたり、臭い等で近隣に迷惑をかけない配慮もしましょう。また、無駄吠えをさせない、待て、ハウスが出来るように躾ておく事も大事です。避難所でも受入がしてもらいやすくするために、飼主としての責任を意識し、回りへの充分な配慮をしましょう。●日々の健康管理も大切日常から、ペットの健康状態に注意し、ノミ・ダニ・フィラリアなど寄生虫の駆除を行いましょう。多数のペットが一緒に保護される場合、1頭でも病気を持っていると、あっという間に感染して広がってしまう事もあります。狂犬病予防接種、各種ワクチン接種も必ず行っておきましょう。また、気になる症状などがある場合は、早めに獣医師の診断を受けて治療をしましょう。被災時に、避難所生活や仮設住宅など、慣れない環境下で体調を崩してしまうのは人間だけでなく、ペットも同様です。飼い主さんが日頃から、ペットの健康管理をしっかり行っておきましよう。●ペットの居場所の確認をするペットの居場所が安全かどうか、点検をしておきましょう。・屋外飼育の場合地震が起きた際、ブロック壁の側や、ガラス窓の下など、建物が倒壊した際、ペットが被害を受けない場所にペットハウスは設置されていますか?水害が多い地域の場合、増水してもペットが溺れないような対策が取られていますか?・屋内飼育の場合地震対策として、倒れやすい家具の固定は必須です。小型のペットの場合、倒れてきた家具などによる怪我や圧死が起こる可能性があります。ガラスケースなど特殊な環境で飼育している場合、ケースが落ちて割れたりしないようにケースを固定し、ガラス飛散防止フィルムを貼るなどの対策をしましょう。次回vol.5につづく人とペットの防災対策を考える(1)《 ペットを守れるのは飼主だけ 》はこちら人とペットの防災対策を考える(2)《 人の安全確保のための防災 》はこちら人とペットの防災対策を考える(3)《 ペットのための備蓄 》はこちら人とペットの防災対策を考える(5)《 飼主が普段から準備しておく事 》はこちらby OFTスタッフ「あーちゃん」

猫がキャットタワーから落ちる理由と飼い主が出来ること
得意なはずのキャットタワーから猫が落下する理由・猫の体型との関係 ▲キャットタワーの上で気持ちよく寝てしまう猫ちゃん。かわいいですね。 猫ちゃんと暮らす上での必須アイテムの一つに、みなさんご存知のキャットタワーがあります。 都会暮らしで室内飼育が急増中の猫ちゃんたちにとっては、運動不足解消にもなり、なおかつ爪とぎや遊び場にもなるのですから、猫にとっての最高のグッズと言っても過言では無いでしょう。ただ、その得意なはずのキャットタワーから落下する猫ちゃんがたまにいるという情報を得て、今回、体型というちょっと変わった視点から、猫のバランス感覚についての考察をしてみましょう。 体型が様々なタイプの猫(イエネコ)達。本当に猫はバランス感覚に優れているのか? ▲イエネコに比べて大きな足、爪を持つ南米生息の”マーゲイ” 一般的に、『猫=バランス感覚に優れ、高所好き』というのは間違ってはいないでしょう。しかし、猫(イエネコ)は人によって選択的に作られたものも多いため、その体型もすべて同じではありません。たとえ本能的に高所が好きでも、不安定なところでちゃんとバランスを保てるのだろうかと、少し疑ってしまうような体の特徴を持った猫もいるわけです。では、猫の体型について、理想的な体型というものはあるのでしょうか? 樹上生活をする野生猫たちの体は特徴的 そこで、樹上生活をしている野生のネコ科動物の代表としてマーゲイやウンピョウを取り上げてみます。彼らは森で樹上生活するのに適した体を持っています。共に筋肉質な体と木に上り下りするための強靭な四肢、木にしがみつくためのしっかりした爪と大きな手のひら、樹上でバランスを維持するための大きくて太い尾などを持っているのです。 多様だった猫の体型 一方、猫(イエネコ)に目を移してみましょう。マンクスや他のボブテイル系の尾の無い種類、マンチカンなどの脚の短い種類、そしてコビータイプと言われるペルシャなどのどっしりとした体形の種類の猫は、明らかにマーゲイなどとは異なる体型をしています。マンクスやマンチカンはバランスを維持するための体の特徴を一部分欠いていると言えるかもしれませんし、ペルシャなどは、運動やバランス感覚がネコの中でも良い方ではないようにも思えてきます。つまり体型を比べてみることで、キャットタワーの上り下りなどが得意なタイプとそうでないタイプに分けることができるのかもしれません。 キャットタワーから落ちるもう一つの理由 ▲木の上を専門に生きる猫たちに比べるとやっぱり心配な手足… そもそも樹上生活をする野生の猫たちにとって、子孫を残し、生き抜くためには不安定な木の上での生活を選ぶしかなかったのかもしれません。つまり木から落下することは、死につながる事態であることを本能的に知っているのではないかという事です。逆に、避妊/去勢され、天敵も存在しない室内で一生を終える猫たちは、キャットタワーから落下することが死に直結しない事を学んでいます。人との暮らしが安全であることを理解し、ある意味平和ボケしてしまった猫たちに対し、キャットタワーなど次々とカタチを変えて市場に出てくる猫製品を与えてみても、その安全性を彼らが判定することはできません。 それは猫と暮らす人間の役目であり、それを放棄し商品だけを与え続けていれば、いつしか落ちることもあるのです。 その他に気を配ってあげるべき点 1:年齢まだ筋肉の発達も十分とはいえず、高い場所への飛び移りなどもほとんど経験したことのない幼猫や、高齢になり、筋力も衰えがちな猫ちゃんたちには、あまり高さがなく、飛び移りやすくてステップの広々としたものを選んであげることで、落下を防いであげましょう。2:おもちゃなどの興味をそそられるものたまにキャットタワーに吊り下げ式のおもちゃなどが付属で設置してあるものもありますが、遊びに集中しすぎてキャットタワーから落下することもあります。おもちゃは、低い場所で遊ばせるようにしましょう。3: 遊び相手幼い猫ちゃんを含む複数の猫ちゃんがキャットタワーの上にいる場合も、じゃれ合いなどから落下することがあります。4:引っ掛からない爪日本では禁止されていますが、抜爪している子やソフトクローと呼ばれる爪用キャップをしている子には、爪の引っ掛かりを利用して体を支えられないため、キャットタワーなどの上で素早く移動しようとした際には、失敗してしまうことも考えられます。5:キャットタワーの材質キャットタワーに使用されているステップ表面の材質が、しっかり爪に引っかかる素材かどうか、もしくはそうでなくとも滑りにくい素材でできてきるかどうかを確認しておきましょう。6:タワー周辺落下した場合に、ケガにつながるのは着地した瞬間です。着地した先に危険なものがあれば、たとえ身軽な猫でさえケガをすることもありますので、キャットタワー周辺の安全を確認しておきましょう。筆者:イノヨシ
猫がキャットタワーから落ちる理由と飼い主が出来ること
得意なはずのキャットタワーから猫が落下する理由・猫の体型との関係 ▲キャットタワーの上で気持ちよく寝てしまう猫ちゃん。かわいいですね。 猫ちゃんと暮らす上での必須アイテムの一つに、みなさんご存知のキャットタワーがあります。 都会暮らしで室内飼育が急増中の猫ちゃんたちにとっては、運動不足解消にもなり、なおかつ爪とぎや遊び場にもなるのですから、猫にとっての最高のグッズと言っても過言では無いでしょう。ただ、その得意なはずのキャットタワーから落下する猫ちゃんがたまにいるという情報を得て、今回、体型というちょっと変わった視点から、猫のバランス感覚についての考察をしてみましょう。 体型が様々なタイプの猫(イエネコ)達。本当に猫はバランス感覚に優れているのか? ▲イエネコに比べて大きな足、爪を持つ南米生息の”マーゲイ” 一般的に、『猫=バランス感覚に優れ、高所好き』というのは間違ってはいないでしょう。しかし、猫(イエネコ)は人によって選択的に作られたものも多いため、その体型もすべて同じではありません。たとえ本能的に高所が好きでも、不安定なところでちゃんとバランスを保てるのだろうかと、少し疑ってしまうような体の特徴を持った猫もいるわけです。では、猫の体型について、理想的な体型というものはあるのでしょうか? 樹上生活をする野生猫たちの体は特徴的 そこで、樹上生活をしている野生のネコ科動物の代表としてマーゲイやウンピョウを取り上げてみます。彼らは森で樹上生活するのに適した体を持っています。共に筋肉質な体と木に上り下りするための強靭な四肢、木にしがみつくためのしっかりした爪と大きな手のひら、樹上でバランスを維持するための大きくて太い尾などを持っているのです。 多様だった猫の体型 一方、猫(イエネコ)に目を移してみましょう。マンクスや他のボブテイル系の尾の無い種類、マンチカンなどの脚の短い種類、そしてコビータイプと言われるペルシャなどのどっしりとした体形の種類の猫は、明らかにマーゲイなどとは異なる体型をしています。マンクスやマンチカンはバランスを維持するための体の特徴を一部分欠いていると言えるかもしれませんし、ペルシャなどは、運動やバランス感覚がネコの中でも良い方ではないようにも思えてきます。つまり体型を比べてみることで、キャットタワーの上り下りなどが得意なタイプとそうでないタイプに分けることができるのかもしれません。 キャットタワーから落ちるもう一つの理由 ▲木の上を専門に生きる猫たちに比べるとやっぱり心配な手足… そもそも樹上生活をする野生の猫たちにとって、子孫を残し、生き抜くためには不安定な木の上での生活を選ぶしかなかったのかもしれません。つまり木から落下することは、死につながる事態であることを本能的に知っているのではないかという事です。逆に、避妊/去勢され、天敵も存在しない室内で一生を終える猫たちは、キャットタワーから落下することが死に直結しない事を学んでいます。人との暮らしが安全であることを理解し、ある意味平和ボケしてしまった猫たちに対し、キャットタワーなど次々とカタチを変えて市場に出てくる猫製品を与えてみても、その安全性を彼らが判定することはできません。 それは猫と暮らす人間の役目であり、それを放棄し商品だけを与え続けていれば、いつしか落ちることもあるのです。 その他に気を配ってあげるべき点 1:年齢まだ筋肉の発達も十分とはいえず、高い場所への飛び移りなどもほとんど経験したことのない幼猫や、高齢になり、筋力も衰えがちな猫ちゃんたちには、あまり高さがなく、飛び移りやすくてステップの広々としたものを選んであげることで、落下を防いであげましょう。2:おもちゃなどの興味をそそられるものたまにキャットタワーに吊り下げ式のおもちゃなどが付属で設置してあるものもありますが、遊びに集中しすぎてキャットタワーから落下することもあります。おもちゃは、低い場所で遊ばせるようにしましょう。3: 遊び相手幼い猫ちゃんを含む複数の猫ちゃんがキャットタワーの上にいる場合も、じゃれ合いなどから落下することがあります。4:引っ掛からない爪日本では禁止されていますが、抜爪している子やソフトクローと呼ばれる爪用キャップをしている子には、爪の引っ掛かりを利用して体を支えられないため、キャットタワーなどの上で素早く移動しようとした際には、失敗してしまうことも考えられます。5:キャットタワーの材質キャットタワーに使用されているステップ表面の材質が、しっかり爪に引っかかる素材かどうか、もしくはそうでなくとも滑りにくい素材でできてきるかどうかを確認しておきましょう。6:タワー周辺落下した場合に、ケガにつながるのは着地した瞬間です。着地した先に危険なものがあれば、たとえ身軽な猫でさえケガをすることもありますので、キャットタワー周辺の安全を確認しておきましょう。筆者:イノヨシ

人とペットの防災対策を考える(1)《 ペットを守れるのは飼主だけ 》
いつ起こるかわからない自然災害 ▲日本は地震が起こりやすいプレート上に位置しています。 今年も、西日本に豪雨、そして大阪の地震と災害が立て続けに起り、甚大な被害をもたらしました。災害は身近にあり、決して他人ごとではなく、いつ何処で起こるか解りません。予測されている大地震・南海トラフは明日、起こるかもしれないのです。大きな災害が起きる度に、ペットの防災や防災グッズへの注目が高まります。しかし、災害から日が経つと徐々に関心は薄れていきます・・・大切なペットを守れるのは飼い主さんだけなのです。 日本は地震大国 日本は、地震が起こりやすいプレート上に位置しており地震大国です。そのため、平成7年の阪神淡路大震災、平成23年の東日本大震災等の大きな地震に、幾度となくこれまで見舞われてきました。また、近年では平成28年に熊本県を震源地とする熊本地震が起こり、甚大な被害が出て、沢山の人や動物たちが被災しています。 大切なペットを守れるのは飼い主さんだけ どんなに災害に備えていても、大規模な災害が発生してしまうと、その被害を完全に防ぐ事は無理です。災害が起きても、被害を軽減し、焦らずに速やかに避難するためには、普段から情報収集をし、いざというときに備えて、心(気持ち)と必要なモノの準備を整える事が大切になります。飼い主が無事でいる事が、ペットにとって何より大事な事なのです。ペットは大切な家族の一員です。その防災対策について、国でも取り組みを始めていますが、残念ながらその内容が飼い主までに十分に浸透していないのが現状なのです。飼い主とペットが安全に避難するために、どのような準備が必要か、災害時の備えについて防災のポイントをいくつかの項目に分けて、お伝えしていきます。次回vol.2につづく人とペットの防災対策を考える(2)《 人の安全確保のための防災 》はこちら人とペットの防災対策を考える(3)《 ペットのための備蓄 》はこちら人とペットの防災対策を考える(4)《 ペットのために普段から行っておく事 》はこちら人とペットの防災対策を考える(5)《 飼主が普段から準備しておく事 》はこちらby OFTスタッフ「あーちゃん」
人とペットの防災対策を考える(1)《 ペットを守れるのは飼主だけ 》
いつ起こるかわからない自然災害 ▲日本は地震が起こりやすいプレート上に位置しています。 今年も、西日本に豪雨、そして大阪の地震と災害が立て続けに起り、甚大な被害をもたらしました。災害は身近にあり、決して他人ごとではなく、いつ何処で起こるか解りません。予測されている大地震・南海トラフは明日、起こるかもしれないのです。大きな災害が起きる度に、ペットの防災や防災グッズへの注目が高まります。しかし、災害から日が経つと徐々に関心は薄れていきます・・・大切なペットを守れるのは飼い主さんだけなのです。 日本は地震大国 日本は、地震が起こりやすいプレート上に位置しており地震大国です。そのため、平成7年の阪神淡路大震災、平成23年の東日本大震災等の大きな地震に、幾度となくこれまで見舞われてきました。また、近年では平成28年に熊本県を震源地とする熊本地震が起こり、甚大な被害が出て、沢山の人や動物たちが被災しています。 大切なペットを守れるのは飼い主さんだけ どんなに災害に備えていても、大規模な災害が発生してしまうと、その被害を完全に防ぐ事は無理です。災害が起きても、被害を軽減し、焦らずに速やかに避難するためには、普段から情報収集をし、いざというときに備えて、心(気持ち)と必要なモノの準備を整える事が大切になります。飼い主が無事でいる事が、ペットにとって何より大事な事なのです。ペットは大切な家族の一員です。その防災対策について、国でも取り組みを始めていますが、残念ながらその内容が飼い主までに十分に浸透していないのが現状なのです。飼い主とペットが安全に避難するために、どのような準備が必要か、災害時の備えについて防災のポイントをいくつかの項目に分けて、お伝えしていきます。次回vol.2につづく人とペットの防災対策を考える(2)《 人の安全確保のための防災 》はこちら人とペットの防災対策を考える(3)《 ペットのための備蓄 》はこちら人とペットの防災対策を考える(4)《 ペットのために普段から行っておく事 》はこちら人とペットの防災対策を考える(5)《 飼主が普段から準備しておく事 》はこちらby OFTスタッフ「あーちゃん」

ペットフードと添加物(vol.3)「キャリーオーバー」と「加工助剤」
前回のVol.2では、ペットフードのうちドライフードについては、添加物を避けることがとても難しいということを書かせていただきました。お読みいただいた人の中には、反対のご意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、ドライフードはれっきとした保存食品です。食べ物を一定期間保存するうえで、何の対策もしない事は、とても危険なことなんです。今回は、添加物にまつわるほかのお話をさせていただきます。それは「キャリーオーバー」、そして「加工助剤」というものです。【今回までの記事】ペットフードと添加物(vol.1)ペットフードに含まれる添加物とは?ペットフードと添加物(vol.2)ペットフードに含まれる添加物とは? 原材料に表示義務のない添加物類(キャリーオーバー) 人の食品も同様ですが、ペットフードについても、加工する前の段階で原材料に含まれていた添加物類は、パッケージに表示する必要はありません。例えば、赤色の色素が添加物として使用された「かにかま」を、ペットフードの原材料として加えた場合、色素の記載は不要で、「かにかま」だけでの表記で大丈夫ということになります。この場合、色素はキャリーオーバーという表示義務のない添加物という扱いになります。以前にも書きましたが、例えば外国産の肉粉には、エトキシキンという防腐剤が使用されることがあります。原材料にはエトキシキンと書かれていないペットフードがあり、これもキャリーオーバーの添加物ということになります。 原材料に表示義務のない添加物類 (加工助剤) 加工助剤とは最終製品の原材料を製造する際に、添加物が加えられてはいるものの、製品完成時には添加物は取り除かれているか、もしくは微量になっていたり、問題の無い成分に変えられていたりするものです。まずペットフードでは、酸化を抑えるために加えられているローズマリー抽出物などがあげられます。ローズマリーの葉や花を、エタノール、ヘキサン、メタノールなどに漬け込んで有効成分を抽出し、溶媒を除去するのですが、その溶媒がペットフードに残留していないかという心配の声が、時々聞かれます。他に心配されるものとしては、ワンちゃんが噛んで喜ぶおやつである牛皮性のガムがあります。毛の生えた状態の牛の皮(原皮)が、表面がつるつるのあの白いガムに変化するまでの間に、様々な薬品などに漬け込まれていることから、その残留が懸念され続けているのです。米国のオンラインマガジン 「dogsnaturally」には、次のような記事が多く見受けられます。 「The Most Dangerous Pet Chew Ever: Rawhide!」”最も危険なローハイドガム”「A rawhide stick is not the by-product of the beef industry nor is it made of dehydrated...
ペットフードと添加物(vol.3)「キャリーオーバー」と「加工助剤」
前回のVol.2では、ペットフードのうちドライフードについては、添加物を避けることがとても難しいということを書かせていただきました。お読みいただいた人の中には、反対のご意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、ドライフードはれっきとした保存食品です。食べ物を一定期間保存するうえで、何の対策もしない事は、とても危険なことなんです。今回は、添加物にまつわるほかのお話をさせていただきます。それは「キャリーオーバー」、そして「加工助剤」というものです。【今回までの記事】ペットフードと添加物(vol.1)ペットフードに含まれる添加物とは?ペットフードと添加物(vol.2)ペットフードに含まれる添加物とは? 原材料に表示義務のない添加物類(キャリーオーバー) 人の食品も同様ですが、ペットフードについても、加工する前の段階で原材料に含まれていた添加物類は、パッケージに表示する必要はありません。例えば、赤色の色素が添加物として使用された「かにかま」を、ペットフードの原材料として加えた場合、色素の記載は不要で、「かにかま」だけでの表記で大丈夫ということになります。この場合、色素はキャリーオーバーという表示義務のない添加物という扱いになります。以前にも書きましたが、例えば外国産の肉粉には、エトキシキンという防腐剤が使用されることがあります。原材料にはエトキシキンと書かれていないペットフードがあり、これもキャリーオーバーの添加物ということになります。 原材料に表示義務のない添加物類 (加工助剤) 加工助剤とは最終製品の原材料を製造する際に、添加物が加えられてはいるものの、製品完成時には添加物は取り除かれているか、もしくは微量になっていたり、問題の無い成分に変えられていたりするものです。まずペットフードでは、酸化を抑えるために加えられているローズマリー抽出物などがあげられます。ローズマリーの葉や花を、エタノール、ヘキサン、メタノールなどに漬け込んで有効成分を抽出し、溶媒を除去するのですが、その溶媒がペットフードに残留していないかという心配の声が、時々聞かれます。他に心配されるものとしては、ワンちゃんが噛んで喜ぶおやつである牛皮性のガムがあります。毛の生えた状態の牛の皮(原皮)が、表面がつるつるのあの白いガムに変化するまでの間に、様々な薬品などに漬け込まれていることから、その残留が懸念され続けているのです。米国のオンラインマガジン 「dogsnaturally」には、次のような記事が多く見受けられます。 「The Most Dangerous Pet Chew Ever: Rawhide!」”最も危険なローハイドガム”「A rawhide stick is not the by-product of the beef industry nor is it made of dehydrated...

ペットフードと添加物(vol.2)ペットフードに含まれる添加物とは?
Vol.1では、添加物の基本的な種類とその使用基準などを挙げ、ペットの添加物規制が人と比べてたいへん緩いこと、そして実際にペットで取り決めのある添加物について、どのくらいの量まで許されているのかを、わかりやすい数字を出して比べてみました。今回は見方を変えて、ペットフードに使用されている原材料や成分と添加物との関係を例に出し、ペットフードの実情をお伝えいたします。【今回までの記事】ペットフードと添加物(vol.1)ペットフードに含まれる添加物とは? ドライフードに添加物は避けられない(1) "Canned pet foods are protected from spoilage by their airtight storage in the can, but dry foods, even with modern packaging, must include preservatives to maintain the...
ペットフードと添加物(vol.2)ペットフードに含まれる添加物とは?
Vol.1では、添加物の基本的な種類とその使用基準などを挙げ、ペットの添加物規制が人と比べてたいへん緩いこと、そして実際にペットで取り決めのある添加物について、どのくらいの量まで許されているのかを、わかりやすい数字を出して比べてみました。今回は見方を変えて、ペットフードに使用されている原材料や成分と添加物との関係を例に出し、ペットフードの実情をお伝えいたします。【今回までの記事】ペットフードと添加物(vol.1)ペットフードに含まれる添加物とは? ドライフードに添加物は避けられない(1) "Canned pet foods are protected from spoilage by their airtight storage in the can, but dry foods, even with modern packaging, must include preservatives to maintain the...