OFT STORE BLOG

犬の膀胱結石は溶かせる?症状や治療の方法とは
愛犬の膀胱内に石ができてしまう病気をご存知でしょうか?名前は聞いたことはあるけれど膀胱炎と何が違うの?と疑問に思う方もいらっしゃいますよね。実はこの病気、命をも脅かすことがあるんです。治療の方法はいくつかありますが食事の管理や予防がとても重要。今回は膀胱結石について掘り下げてご説明していきます! 目次■膀胱結石とは■膀胱結石の種類■代表的な症状■治療の方法■膀胱結石後の生活や予防方法■症状の重さによって獣医師と相談を 膀胱結石とは 膀胱結石はその名の通り、膀胱の中にできてしまう石の事です。砂利のように小さなものから小石のような数センチ程度のものまで大きさはさまざま。尿に含まれるミネラル成分や老廃物、化学物質が結晶化して結合したものが結石です。膀胱内ではなく尿道にある石は尿道結石、腎臓にできてしまったときは腎結石と呼び、その全ての総称が尿路結石です。 膀胱結石の種類 膀胱結石にはいくつかの種類があるのですがワンちゃんに見られる結石の9割は以下の2つに分類されます。結石そのものがどちらなのかは取り出してみないとわかりませんが、尿中に結晶成分が出ていたり、尿検査でのph値にかたよりがあれば目星をつけて治療を進めていくことが可能です。 ■ストルバイト結石 細菌感染による感染性と他に要因がある非感染性があります。多くは感染が原因で、菌から出る成分によって尿がアルカリ性になり石ができやすくなることで発症します。ストルバイト結石は療法食で溶かすことができる点が特徴。ですが石が大きい、症状が強い、尿道に詰まっているという時は、ゆっくり石を溶かしている時間はなく、手術が推奨されるでしょう。■シュウ酸カルシウム結石 シュウ酸カルシウム結石はストルバイトとは異なり、感染の有無は関係なく発症します。尿が酸性に傾くとできやすくなる結石で、残念ながら溶かすことはできません。治療は外科的に取り除く手術が第一選択となるでしょう。 代表的な症状 結石の種類に関わらず、発症時は以下のような症状が見られます。 ・頻尿・少量尿・血尿・排尿痛・陰部を気にする・落ち着きがない・食欲元気の低下・尿臭がきつい・排尿体勢を取るが出せない(尿しぶり)結石がどこかに詰まってしまうと強い痛みを感じ食欲や元気もなくなります。全くおしっこが出せない状態が続くと、排出されるべき毒素が体を回り、さまざまな臓器に影響が出てしまうため要注意!様子見はせず、すぐに病院へ連れて行きましょう。 治療の方法 治療方法は大きくわけて3つ。ワンちゃんの状態や症状の重さ、結石の種類によって判断されます。 ■内科治療 感染を起こしている時は抗生剤を服用した治療が必要です。血尿時は止血剤、炎症が強い時は抗炎症薬、症状に合わせた内容で処方されます。■フード管理 ストルバイトの場合はご飯を療法食へ切り替え、膀胱内のph値を整えつつマグネシウムを制限して石を溶かしていきます。原則おやつやその他の食事は禁止。定期的にエコーを見て石の状態をチェックし、溶けないときや症状が強くなったときは、外科治療へステップアップするか相談となります。■外科治療 閉塞があり一刻も早く石を取り除かなくてはいけないときや、溶かすことができないシュウ酸カルシウム結石だったときは、手術での治療が第一選択です。緊急的に尿道カテーテルを通して閉塞を解除する方法もありますが、再度閉塞してしまう可能性が高いため、最終的には手術に踏み切ることを勧められるでしょう。 膀胱結石後の生活や予防方法 結石が溶けた、手術で取り出した、でもそれでおしまい...というわけにはいきません。尿路結石を発症した子はその後も再び結石が見られることが珍しくないからです。普段の食事や生活の中で予防対策を行い、再発を防止しなくてはなりません。療法食を食べ続ける、サプリメントを飲む、水分をしっかり取らせる、などがポイント。かかりつけの獣医師と相談しながら対策を行いましょう。 症状の重さによって獣医師と相談を 尿道閉塞を起こしてしまうと本人はとても辛い上に、症状が長引けば命にも関わります。異変をいち早く察知するためにも、1日の排尿回数や1回量は把握しておきましょう。また症状の度合いによって第一選択となる治療がかわるケースも少なくありません。全く出ていないのか頻回少量でも出せているのか、愛犬の様子を正確に伝え、よく相談してくださいね。
犬の膀胱結石は溶かせる?症状や治療の方法とは
愛犬の膀胱内に石ができてしまう病気をご存知でしょうか?名前は聞いたことはあるけれど膀胱炎と何が違うの?と疑問に思う方もいらっしゃいますよね。実はこの病気、命をも脅かすことがあるんです。治療の方法はいくつかありますが食事の管理や予防がとても重要。今回は膀胱結石について掘り下げてご説明していきます! 目次■膀胱結石とは■膀胱結石の種類■代表的な症状■治療の方法■膀胱結石後の生活や予防方法■症状の重さによって獣医師と相談を 膀胱結石とは 膀胱結石はその名の通り、膀胱の中にできてしまう石の事です。砂利のように小さなものから小石のような数センチ程度のものまで大きさはさまざま。尿に含まれるミネラル成分や老廃物、化学物質が結晶化して結合したものが結石です。膀胱内ではなく尿道にある石は尿道結石、腎臓にできてしまったときは腎結石と呼び、その全ての総称が尿路結石です。 膀胱結石の種類 膀胱結石にはいくつかの種類があるのですがワンちゃんに見られる結石の9割は以下の2つに分類されます。結石そのものがどちらなのかは取り出してみないとわかりませんが、尿中に結晶成分が出ていたり、尿検査でのph値にかたよりがあれば目星をつけて治療を進めていくことが可能です。 ■ストルバイト結石 細菌感染による感染性と他に要因がある非感染性があります。多くは感染が原因で、菌から出る成分によって尿がアルカリ性になり石ができやすくなることで発症します。ストルバイト結石は療法食で溶かすことができる点が特徴。ですが石が大きい、症状が強い、尿道に詰まっているという時は、ゆっくり石を溶かしている時間はなく、手術が推奨されるでしょう。■シュウ酸カルシウム結石 シュウ酸カルシウム結石はストルバイトとは異なり、感染の有無は関係なく発症します。尿が酸性に傾くとできやすくなる結石で、残念ながら溶かすことはできません。治療は外科的に取り除く手術が第一選択となるでしょう。 代表的な症状 結石の種類に関わらず、発症時は以下のような症状が見られます。 ・頻尿・少量尿・血尿・排尿痛・陰部を気にする・落ち着きがない・食欲元気の低下・尿臭がきつい・排尿体勢を取るが出せない(尿しぶり)結石がどこかに詰まってしまうと強い痛みを感じ食欲や元気もなくなります。全くおしっこが出せない状態が続くと、排出されるべき毒素が体を回り、さまざまな臓器に影響が出てしまうため要注意!様子見はせず、すぐに病院へ連れて行きましょう。 治療の方法 治療方法は大きくわけて3つ。ワンちゃんの状態や症状の重さ、結石の種類によって判断されます。 ■内科治療 感染を起こしている時は抗生剤を服用した治療が必要です。血尿時は止血剤、炎症が強い時は抗炎症薬、症状に合わせた内容で処方されます。■フード管理 ストルバイトの場合はご飯を療法食へ切り替え、膀胱内のph値を整えつつマグネシウムを制限して石を溶かしていきます。原則おやつやその他の食事は禁止。定期的にエコーを見て石の状態をチェックし、溶けないときや症状が強くなったときは、外科治療へステップアップするか相談となります。■外科治療 閉塞があり一刻も早く石を取り除かなくてはいけないときや、溶かすことができないシュウ酸カルシウム結石だったときは、手術での治療が第一選択です。緊急的に尿道カテーテルを通して閉塞を解除する方法もありますが、再度閉塞してしまう可能性が高いため、最終的には手術に踏み切ることを勧められるでしょう。 膀胱結石後の生活や予防方法 結石が溶けた、手術で取り出した、でもそれでおしまい...というわけにはいきません。尿路結石を発症した子はその後も再び結石が見られることが珍しくないからです。普段の食事や生活の中で予防対策を行い、再発を防止しなくてはなりません。療法食を食べ続ける、サプリメントを飲む、水分をしっかり取らせる、などがポイント。かかりつけの獣医師と相談しながら対策を行いましょう。 症状の重さによって獣医師と相談を 尿道閉塞を起こしてしまうと本人はとても辛い上に、症状が長引けば命にも関わります。異変をいち早く察知するためにも、1日の排尿回数や1回量は把握しておきましょう。また症状の度合いによって第一選択となる治療がかわるケースも少なくありません。全く出ていないのか頻回少量でも出せているのか、愛犬の様子を正確に伝え、よく相談してくださいね。

みんな笑顔に!動物病院で見られるほっこりシーンとは
動物病院は注射や手術をする場所。スタッフはもちろん動物が大好きですが、悲しいことにペット達には嫌われてしまう事もしばしば…。体調不良で訪れる子も多いので時に緊迫した空気になりますが、同じように感情豊かなペット達が集うとその場の全員が笑顔になるような出来事も起こるんです。今回はそんなお話をご紹介していきます! 目次■問診表から見えてくる家族の形■同じ種類、同じ名前は待合室が盛り上がる■病院断固拒否!必死の抵抗■病院好きさんは大興奮■出会いの場としても活用しよう 問診表から見えてくる家族の形 動物病院に行くと最初に問診表を記入します。ペットのお名前や生年月日、性格など診療する上で重要な情報を書くのですが、その際お子さんが記入されていることがあります。これはペットを飼いたいならば責任を持つ、とお約束になっているご家庭で見られるシーン。少したどたどしい文字で書かれた問診票はスタッフの心も温かくしてくれます。また初めての来院は飼い主さんも緊張するもの。ペットのお名前欄や生年月日欄に誤って飼い主さんの情報が記入されているパターンも! 同じ種類、同じ名前は待合室が盛り上がる 待合室が盛り上がりを見せるのが、同じ種類や名前のペットが重なっている時。ゴールデンレトリバーなどの大型犬種が3頭も集まるとそれはそれは賑やかです。珍しい犬種や猫種だとその偶然に感動される方も少なくありません。また〇〇ちゃーんとお呼びした時にうちの子も同じ名前!!となると飼い主さん同士のお話にも花が咲きますね。最近は可愛らしいお名前の子が多く「みたらし団子ちゃん」や「まんまるまるこちゃん」など、お呼びすると待合室の皆さんが笑顔になる光景も。 病院断固拒否!必死の抵抗 病院嫌いのワンちゃんが必死に座り込んで動かないぞ!と強い意思を見せてくれるのも病院ならではです。大きな体を必死に丸め椅子の下に隠れる様はまさに【頭隠して尻隠さず】の状態。丸見えですよ~と声をかけると絶望の表情…!時に診察室に入らないワンちゃんと飼い主さんの激しい攻防戦が繰り広げられることも。また爪切りなどでお預かりしたものの、病院中に響き渡るような断末魔をあげる子も実は多いんです。そしてそのほとんどが「まだ触ってもいない」状態のとき。私の勤務先の病院では、飼い主さんから見える位置で処置を行っているため、そんな愛犬の様子に頭を抱えながら動画におさめている方も少なくありません。 病院好きさんは大興奮 なかには病院をとっても好いてくれている子もいます。病院に走って来院しそのまま受付にダイブ!自分で受付を済ませ診察をいまかいまかと待ち構え、扉が開こうものなら呼ばれる前に診察室へ駈け込んでいく…なんて猛者も。動物たちに嫌われがちなスタッフは、内心とても嬉しいと思っています!採血や注射の時も尻尾ブンブンが止まらず帰る時は座り込みを開始し、帰ってなるものかと言わんばかり。また猫ちゃんでもケージから出たとたん、へそ天で撫でて~とアピールしてくれる子やスタッフの膝に飛び乗ってくれる子がいます。お帰りの時は、このまま病院好きでいてねと祈りながら見送っています。 出会いの場としても活用しよう いかがでしたか?人間の病院では見られない光景ばかりで、少しドタバタな待合室ですが、そこにはいつも一生懸命に頑張るペット達の姿があります。うちの子は鳴いてしまう、怒ってしまう、と気にされる飼い主さんも多いのですがスタッフはそんな一面もひっくるめてペット達のことが大好きです!そして動物病院に訪れた者同士、お悩みを理解しあえることも多いでしょう。飼い主さん同士が仲良くなる場所として活用していただいてもOKです。ペットの体調が安定している時であれば、ぜひ周りの子達にも注目してみてくださいね!
みんな笑顔に!動物病院で見られるほっこりシーンとは
動物病院は注射や手術をする場所。スタッフはもちろん動物が大好きですが、悲しいことにペット達には嫌われてしまう事もしばしば…。体調不良で訪れる子も多いので時に緊迫した空気になりますが、同じように感情豊かなペット達が集うとその場の全員が笑顔になるような出来事も起こるんです。今回はそんなお話をご紹介していきます! 目次■問診表から見えてくる家族の形■同じ種類、同じ名前は待合室が盛り上がる■病院断固拒否!必死の抵抗■病院好きさんは大興奮■出会いの場としても活用しよう 問診表から見えてくる家族の形 動物病院に行くと最初に問診表を記入します。ペットのお名前や生年月日、性格など診療する上で重要な情報を書くのですが、その際お子さんが記入されていることがあります。これはペットを飼いたいならば責任を持つ、とお約束になっているご家庭で見られるシーン。少したどたどしい文字で書かれた問診票はスタッフの心も温かくしてくれます。また初めての来院は飼い主さんも緊張するもの。ペットのお名前欄や生年月日欄に誤って飼い主さんの情報が記入されているパターンも! 同じ種類、同じ名前は待合室が盛り上がる 待合室が盛り上がりを見せるのが、同じ種類や名前のペットが重なっている時。ゴールデンレトリバーなどの大型犬種が3頭も集まるとそれはそれは賑やかです。珍しい犬種や猫種だとその偶然に感動される方も少なくありません。また〇〇ちゃーんとお呼びした時にうちの子も同じ名前!!となると飼い主さん同士のお話にも花が咲きますね。最近は可愛らしいお名前の子が多く「みたらし団子ちゃん」や「まんまるまるこちゃん」など、お呼びすると待合室の皆さんが笑顔になる光景も。 病院断固拒否!必死の抵抗 病院嫌いのワンちゃんが必死に座り込んで動かないぞ!と強い意思を見せてくれるのも病院ならではです。大きな体を必死に丸め椅子の下に隠れる様はまさに【頭隠して尻隠さず】の状態。丸見えですよ~と声をかけると絶望の表情…!時に診察室に入らないワンちゃんと飼い主さんの激しい攻防戦が繰り広げられることも。また爪切りなどでお預かりしたものの、病院中に響き渡るような断末魔をあげる子も実は多いんです。そしてそのほとんどが「まだ触ってもいない」状態のとき。私の勤務先の病院では、飼い主さんから見える位置で処置を行っているため、そんな愛犬の様子に頭を抱えながら動画におさめている方も少なくありません。 病院好きさんは大興奮 なかには病院をとっても好いてくれている子もいます。病院に走って来院しそのまま受付にダイブ!自分で受付を済ませ診察をいまかいまかと待ち構え、扉が開こうものなら呼ばれる前に診察室へ駈け込んでいく…なんて猛者も。動物たちに嫌われがちなスタッフは、内心とても嬉しいと思っています!採血や注射の時も尻尾ブンブンが止まらず帰る時は座り込みを開始し、帰ってなるものかと言わんばかり。また猫ちゃんでもケージから出たとたん、へそ天で撫でて~とアピールしてくれる子やスタッフの膝に飛び乗ってくれる子がいます。お帰りの時は、このまま病院好きでいてねと祈りながら見送っています。 出会いの場としても活用しよう いかがでしたか?人間の病院では見られない光景ばかりで、少しドタバタな待合室ですが、そこにはいつも一生懸命に頑張るペット達の姿があります。うちの子は鳴いてしまう、怒ってしまう、と気にされる飼い主さんも多いのですがスタッフはそんな一面もひっくるめてペット達のことが大好きです!そして動物病院に訪れた者同士、お悩みを理解しあえることも多いでしょう。飼い主さん同士が仲良くなる場所として活用していただいてもOKです。ペットの体調が安定している時であれば、ぜひ周りの子達にも注目してみてくださいね!

ワンちゃんの断尾や断耳はなんのためにするの?していなくても問題ありません!
皆さんの愛犬はどんな耳の形をしていますか?尻尾の長さはどうでしょう?実は、ワンちゃん達は耳や尻尾を故意的にカットして形を整える事があります。ドーベルマンのシュッと尖った耳やコーギーの短い尻尾はその代表格。しかし、本来あるべきものを人為的にカットするする処置は、当然痛みを伴うものです。そこまでして行う理由は何なのでしょうか?今回は病気が理由となるケースは除き、断耳や断尾の目的などをご紹介していきます。 目次■断尾とはなんのためにするの?■断耳の目的とは?■現代で断尾や断耳のメリットはあるの?■断尾や断耳を行うタイミング、痛みは感じない?■近年ではしていない子も増加中 断尾とはなんのためにするの? 断尾はその名の通り尻尾をカットする処置です。その目的はワンちゃん達が使役犬だった頃にさかのぼります。当時は猟犬や番犬として働いていたため、敵と対峙するような場面も多く、咬みつかれる場所を少しでも少なくするために断尾が行われていました。また狭い場所に入り込まなくてはいけないシーンも多く、ケガを未然に防ぐという理由もあったようです。その後、愛玩犬となっていってもこの風習は受け継がれ、いつしか各犬種のスタンダードな姿が断尾をしている形と認定されるようになっていきました。現在では、動物愛護の観点から断尾を禁止、あるいは必須ではないとしている国もありますが、それまでは犬種のスタンダードな形であることが血統書発行の条件でもあったため、断尾は生活面でその必要性がなくなっても見た目のためだけに続けられてきたのです。 日本では今なお断尾が血統書発行の条件になっている犬種もあります。ドッグショーでも断尾している事が求められてきましたが、現在は断尾している犬は動物愛護に反するとして出場を認めないなど、各国で対応は異なっています。 断耳の目的とは? 断耳も断尾と同様、本来は攻撃を受けにくくし、ケガをしないようにすることが本来の目的でした。また軍用犬として働く犬達は、より遠くの微細な音まで聞こえるように断耳をしていたようです。断尾に比べワンちゃんにかかる負担が大きいためか、現代では断耳されていない子も増えてきましたが、やはりいまだに美容のために行われるケースもあり、賛否両論が絶えません。 現代で断尾や断耳のメリットはあるの? 断尾や断耳を行うメリットはほとんどありません。強いて言えば断耳をすると、耳の通気性がよくなり外耳炎になりにくくなる事、断尾をすれば排せつ物で尻尾が汚れにくいことぐらいです。ドイツやイギリスなど動物愛護先進国では、既に断尾や断耳は禁止行為とされており、愛玩犬として生活していくうえで全く必要がないと言っても過言ではありません。 断尾や断耳を行うタイミング、痛みは感じない? 断尾と断耳では処置を行う時期が異なります。断尾は生後数日以内に無麻酔で行われ、その理由は痛覚が未成熟なため痛みを感じないから...というもの。ただ私自身何回か立ち会ったことがあるのですが、とても痛みを感じていないとは思えませんでした。生まれて間もない子犬が大きな声で鳴き叫ぶ様子は、見ていてとても胸が締め付けられるものでした。 そんな断尾に対し、断耳は生後数か月経過してから麻酔をかけて行うのが一般的です。耳のカット後は綺麗な立ち耳にするための器具を装着して数ヵ月過ごさなくてはいけません。理想的な耳の形にカットする技術が必要で、術後の管理も難しいため近年では行う獣医師も少なくなってきました。当然麻酔から覚めた後の痛みはありますし、器具装着のストレスもかかります。細菌感染を起こすと耳が壊死してしまう事もあるため、術後は慎重に経過を見ていく必要があるでしょう。 近年ではしていない子も増加中 日本では断尾も断耳も禁止されておらず、今もなお処置は行われています。それでも反対の声は年々大きくなっており、最近ではどちらも施されていない子が増えてきました。コーギーやプードルのフサフサと長い尻尾、ピンシャーやドーベルマン、シュナウザーの垂れ耳、これらは処置を受けなかった本来あるべき姿。それはそれは可愛らしいものです。同じ犬種でも見た目に少し差があるのはこういった背景があることを知っていただければ嬉しいです。そしてどのような姿をしていても大切な家族には変わりません。ありのままの愛犬を、たっぷり愛してあげてくださいね!
ワンちゃんの断尾や断耳はなんのためにするの?していなくても問題ありません!
皆さんの愛犬はどんな耳の形をしていますか?尻尾の長さはどうでしょう?実は、ワンちゃん達は耳や尻尾を故意的にカットして形を整える事があります。ドーベルマンのシュッと尖った耳やコーギーの短い尻尾はその代表格。しかし、本来あるべきものを人為的にカットするする処置は、当然痛みを伴うものです。そこまでして行う理由は何なのでしょうか?今回は病気が理由となるケースは除き、断耳や断尾の目的などをご紹介していきます。 目次■断尾とはなんのためにするの?■断耳の目的とは?■現代で断尾や断耳のメリットはあるの?■断尾や断耳を行うタイミング、痛みは感じない?■近年ではしていない子も増加中 断尾とはなんのためにするの? 断尾はその名の通り尻尾をカットする処置です。その目的はワンちゃん達が使役犬だった頃にさかのぼります。当時は猟犬や番犬として働いていたため、敵と対峙するような場面も多く、咬みつかれる場所を少しでも少なくするために断尾が行われていました。また狭い場所に入り込まなくてはいけないシーンも多く、ケガを未然に防ぐという理由もあったようです。その後、愛玩犬となっていってもこの風習は受け継がれ、いつしか各犬種のスタンダードな姿が断尾をしている形と認定されるようになっていきました。現在では、動物愛護の観点から断尾を禁止、あるいは必須ではないとしている国もありますが、それまでは犬種のスタンダードな形であることが血統書発行の条件でもあったため、断尾は生活面でその必要性がなくなっても見た目のためだけに続けられてきたのです。 日本では今なお断尾が血統書発行の条件になっている犬種もあります。ドッグショーでも断尾している事が求められてきましたが、現在は断尾している犬は動物愛護に反するとして出場を認めないなど、各国で対応は異なっています。 断耳の目的とは? 断耳も断尾と同様、本来は攻撃を受けにくくし、ケガをしないようにすることが本来の目的でした。また軍用犬として働く犬達は、より遠くの微細な音まで聞こえるように断耳をしていたようです。断尾に比べワンちゃんにかかる負担が大きいためか、現代では断耳されていない子も増えてきましたが、やはりいまだに美容のために行われるケースもあり、賛否両論が絶えません。 現代で断尾や断耳のメリットはあるの? 断尾や断耳を行うメリットはほとんどありません。強いて言えば断耳をすると、耳の通気性がよくなり外耳炎になりにくくなる事、断尾をすれば排せつ物で尻尾が汚れにくいことぐらいです。ドイツやイギリスなど動物愛護先進国では、既に断尾や断耳は禁止行為とされており、愛玩犬として生活していくうえで全く必要がないと言っても過言ではありません。 断尾や断耳を行うタイミング、痛みは感じない? 断尾と断耳では処置を行う時期が異なります。断尾は生後数日以内に無麻酔で行われ、その理由は痛覚が未成熟なため痛みを感じないから...というもの。ただ私自身何回か立ち会ったことがあるのですが、とても痛みを感じていないとは思えませんでした。生まれて間もない子犬が大きな声で鳴き叫ぶ様子は、見ていてとても胸が締め付けられるものでした。 そんな断尾に対し、断耳は生後数か月経過してから麻酔をかけて行うのが一般的です。耳のカット後は綺麗な立ち耳にするための器具を装着して数ヵ月過ごさなくてはいけません。理想的な耳の形にカットする技術が必要で、術後の管理も難しいため近年では行う獣医師も少なくなってきました。当然麻酔から覚めた後の痛みはありますし、器具装着のストレスもかかります。細菌感染を起こすと耳が壊死してしまう事もあるため、術後は慎重に経過を見ていく必要があるでしょう。 近年ではしていない子も増加中 日本では断尾も断耳も禁止されておらず、今もなお処置は行われています。それでも反対の声は年々大きくなっており、最近ではどちらも施されていない子が増えてきました。コーギーやプードルのフサフサと長い尻尾、ピンシャーやドーベルマン、シュナウザーの垂れ耳、これらは処置を受けなかった本来あるべき姿。それはそれは可愛らしいものです。同じ犬種でも見た目に少し差があるのはこういった背景があることを知っていただければ嬉しいです。そしてどのような姿をしていても大切な家族には変わりません。ありのままの愛犬を、たっぷり愛してあげてくださいね!

犬の自傷行為はなぜ起こる?暇つぶし?原因と今すぐできる対策を解説
愛犬が手足をひっきりなしに舐める、爪を噛む、尻尾を追いかけまわして噛みつく、そんな光景を見た事ありませんか?実はこれ愛犬の退屈サインかもしれません。ひどくなると出血するまで自分を傷つけてしまうこともあるんです。ではどのように対処してあげればいいのでしょうか?今回はワンちゃんの退屈サインや自傷行為についてまとめてみました! 目次■ワンちゃんだって暇をする!■愛犬が退屈な時に見せる行動■実はストレスサインかも■自宅での対策方法■症状に合わせて動物病院の受診を ワンちゃんだって暇をする! 人間はテレビや携帯、当然出かける事もできるので時間を持てますことはあまりありません。しかし、ワンちゃん達はどうでしょう…?限られたスペースの中でお留守番時間が長く、刺激が少ない生活だと【退屈】を強く感じるようになっていきます。体力がある成犬期のワンちゃんは顕著かもしれません。飼い主さんもお仕事やおうちのご予定を一生懸命こなしていますが、その間ワンちゃんも一生懸命お留守番をしてくれています。退屈しない生活環境やお留守番時の対策を取り入れてお互いの負担を減らしていきましょう! 愛犬が退屈な時に見せる行動 ・手足を舐める・爪をかじる・被毛を抜いてしまう・尻尾を追いかける、噛んでしまうこれらはワンちゃんが退屈しのぎに見せる代表的な行動です。動物病院での勤務中、パッと見ただけでもかじっていることがわかるほど爪がボロボロになっているワンちゃんをよくお見かけします。それほどポピュラーな行動であり退屈を感じているワンちゃんが多いともいえますね。自分の体を使って時間をつぶそうとする行為そのものは異常なわけではありません。ただし、これが上限なく続いてしまうと出血やひどい皮膚炎に繋がってしまうので要注意!しっかり様子を見てあげてくださいね。 実はストレスサインかも 前述した行動は時として【分離不安症状】とも呼ばれます。退屈しのぎとの明確な線引きはありませんが傷になるまで、出血するまで、もしくはその段階に達していてもやめずに続けてしまう時は分離不安と考えた方がいいかもしれません。不安やストレスが強くなったときに見られるもので、愛犬のメンタルフォローが必要です。飼い主さんがいない事自体に不安があるのか、お留守番中の物音や環境にストレスがあるのか、まずは原因を探り解決策を模索してみましょう。 自宅での対策方法 お留守番時間を減らし愛犬との時間を増やすことがベストですが難しい方も多いですよね。そこでポイントになるのは【刺激】や【変化】を意識する事。・おもちゃは箱にしまい昨日とは違うものを出す・自宅内におやつを複数隠し、宝探しをしてもらう・コングにおやつを入れ出発直前に渡す・お出かけ前に少し長めの散歩へ行く・自動給餌器を活用し頻回少量の食事を出す・ペット用オンラインカメラで声掛けやおやつをあげる・外が見える場所を作ってあげるおもちゃが出しっぱなしだとワンちゃんも飽きてしまうので、毎日見えない場所にしまいましょう。飼い主さんが出かけた直後に宝探しやおやつ入りコングがもらえると時間を潰せるだけでなく、お留守番=嬉しいことが起こるといいイメージと紐づけることができます。防犯的に大丈夫であればお外が見える場所を一つ作ってあげると、移り変わる景色が刺激になってくれますよ!出来ることから一つずつトライしてみてくださいね。 症状に合わせて動物病院の受診を あまりに症状がひどい時は迷わず動物病院へ。皮膚の赤みや傷はワンちゃんが舐めると悪化しやすく、最初は暇つぶしでしていたものが途中から本当に痒みや痛みが気になっていじっている時もあります。症状に合わせた治療と生活環境の見直し、メンタル面のサポート、複合的に進め改善を目指していきましょう。
犬の自傷行為はなぜ起こる?暇つぶし?原因と今すぐできる対策を解説
愛犬が手足をひっきりなしに舐める、爪を噛む、尻尾を追いかけまわして噛みつく、そんな光景を見た事ありませんか?実はこれ愛犬の退屈サインかもしれません。ひどくなると出血するまで自分を傷つけてしまうこともあるんです。ではどのように対処してあげればいいのでしょうか?今回はワンちゃんの退屈サインや自傷行為についてまとめてみました! 目次■ワンちゃんだって暇をする!■愛犬が退屈な時に見せる行動■実はストレスサインかも■自宅での対策方法■症状に合わせて動物病院の受診を ワンちゃんだって暇をする! 人間はテレビや携帯、当然出かける事もできるので時間を持てますことはあまりありません。しかし、ワンちゃん達はどうでしょう…?限られたスペースの中でお留守番時間が長く、刺激が少ない生活だと【退屈】を強く感じるようになっていきます。体力がある成犬期のワンちゃんは顕著かもしれません。飼い主さんもお仕事やおうちのご予定を一生懸命こなしていますが、その間ワンちゃんも一生懸命お留守番をしてくれています。退屈しない生活環境やお留守番時の対策を取り入れてお互いの負担を減らしていきましょう! 愛犬が退屈な時に見せる行動 ・手足を舐める・爪をかじる・被毛を抜いてしまう・尻尾を追いかける、噛んでしまうこれらはワンちゃんが退屈しのぎに見せる代表的な行動です。動物病院での勤務中、パッと見ただけでもかじっていることがわかるほど爪がボロボロになっているワンちゃんをよくお見かけします。それほどポピュラーな行動であり退屈を感じているワンちゃんが多いともいえますね。自分の体を使って時間をつぶそうとする行為そのものは異常なわけではありません。ただし、これが上限なく続いてしまうと出血やひどい皮膚炎に繋がってしまうので要注意!しっかり様子を見てあげてくださいね。 実はストレスサインかも 前述した行動は時として【分離不安症状】とも呼ばれます。退屈しのぎとの明確な線引きはありませんが傷になるまで、出血するまで、もしくはその段階に達していてもやめずに続けてしまう時は分離不安と考えた方がいいかもしれません。不安やストレスが強くなったときに見られるもので、愛犬のメンタルフォローが必要です。飼い主さんがいない事自体に不安があるのか、お留守番中の物音や環境にストレスがあるのか、まずは原因を探り解決策を模索してみましょう。 自宅での対策方法 お留守番時間を減らし愛犬との時間を増やすことがベストですが難しい方も多いですよね。そこでポイントになるのは【刺激】や【変化】を意識する事。・おもちゃは箱にしまい昨日とは違うものを出す・自宅内におやつを複数隠し、宝探しをしてもらう・コングにおやつを入れ出発直前に渡す・お出かけ前に少し長めの散歩へ行く・自動給餌器を活用し頻回少量の食事を出す・ペット用オンラインカメラで声掛けやおやつをあげる・外が見える場所を作ってあげるおもちゃが出しっぱなしだとワンちゃんも飽きてしまうので、毎日見えない場所にしまいましょう。飼い主さんが出かけた直後に宝探しやおやつ入りコングがもらえると時間を潰せるだけでなく、お留守番=嬉しいことが起こるといいイメージと紐づけることができます。防犯的に大丈夫であればお外が見える場所を一つ作ってあげると、移り変わる景色が刺激になってくれますよ!出来ることから一つずつトライしてみてくださいね。 症状に合わせて動物病院の受診を あまりに症状がひどい時は迷わず動物病院へ。皮膚の赤みや傷はワンちゃんが舐めると悪化しやすく、最初は暇つぶしでしていたものが途中から本当に痒みや痛みが気になっていじっている時もあります。症状に合わせた治療と生活環境の見直し、メンタル面のサポート、複合的に進め改善を目指していきましょう。

愛犬と過ごす冬がやって来る!ケージやクレートの寒さ対策とおススメの寝床♪
最近までなかなか涼しくならないと思っていたのに、急に寒さが厳しくなってきましたね。筆者と暮らす生後6か月の愛犬も、散歩中にブルブル震えるようになったため、今はフリースベストでしっかり防寒対策をしています。この時期は寒暖差が激しく、人もワンちゃんも体調を崩しやすい季節です。そこで今回は、愛犬が快適に過ごせるよう“お部屋での寒さ対策”に焦点を当ててご紹介していきます。 目次■うちの子、寒がってる?■お部屋の空気を暖めよう■ケージ・クレートの寒さ対策■冬でも快適なクレートといえば…■お留守番時も気を付けて! うちの子寒がってる? 体を丸めている、震えている、毛布やタオルに顔を埋めている…体調は悪くないのに、そんな仕草をしているワンちゃんはまさしく今、寒がっています!基本的に寒さには強いワンちゃんですが、冬は10℃以下になると寒さを感じると言われ、室内では20~25℃が適温です。・シニアや子犬・換毛期が無く抜け毛の少ないシングルコートの犬種・毛が短い子・暖かい国をルーツにもつ子・運動量が少なく筋肉量が少ない子は特に寒がりなので、設定温度を少し高めにしましょう。ちなみに顔を隠しているのは、周りの空気に敏感な鼻を隠して暖を取ろうしている仕草です。思わず写真に収めたくなる可愛らしさですが、早めに暖かくなるよう調節してあげてくださいね。関連ブログ・愛犬の寒さ対策!冬場のお洋服やお散歩のポイントは?・冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意! お部屋の空気を暖めよう 寒い日はお部屋全体を暖めることからスタートです。ワンちゃんも人と同じで冷たい空気を吸うとくしゃみや咳が出てしまいます。心臓や呼吸器など持病がある子は悪化させてしまう恐れもあるため、いつも以上に注意してあげてくださいね。ペットのいるお部屋にはエアコンなど火を使わない暖房器具がやっぱり安心です。一緒にサーキュレーターを使えばお部屋が万遍なく暖まるので電気代の節約にもなりますよ。人気のオイルヒーターはお部屋を乾燥させないので皮膚トラブルや呼吸器疾患、ドライアイによる角膜炎などを防いでくれるというメリットがあります。ちなみに人間用のホットカーペットは、ペットにとって熱すぎる傾向があり、脱水症状や低温火傷のリスクが高まります。使用の際は低めの温度設定にし、クッションなどを置いてワンちゃん自ら涼めるよう対策を取ってくださいね。 ケージ・クレートの寒さ対策 ケージやクレートはタオルや毛布で覆うことで冷気が入るのを防ぎ、保温性が高まります。クレートの場合は新聞紙でも効果がありますよ。中に入れるタオルもあたたかい冬素材に衣替え♪毛布、モコモコのクッション、起毛素材の犬用ベッドなどは見た目もあたたかですね。もしフローリングなどに直接クレートを置いているなら、段ボールやアルミシートを敷くだけでも寒さ対策になります。そして体をしっかり暖めてくれる湯たんぽは特にオススメ!お湯を入れるタイプのほかにレンジで温めるタイプもあり手軽に取り入れられるのも嬉しいですね。人間用でも代用できますが、ワンちゃんがイタズラしたくなるような突起が無いものを選び、火傷しないよう厚手のカバーをかけるなど安全対策を行って使用してください。 冬でも快適なクレートといえば… モコモコの毛布に湯たんぽ、ついでにお気に入りのおもちゃまで入る少しゆとりのある寝床をお探しなら、OFTで販売中の人気ハードキャリー『ペットケンネル・ファーストクラス』がおススメです。人が乗っても歪まない頑丈さと豊富なサイズバリエーションが魅力!移動メインのピッタリサイズから、お部屋メインのちょっと大きめサイズまで「うちの子」に合ったちょうどいいクレートが必ず見つかります♪災害時はそのまま抱えて避難できるのも心強いですよ。 お留守番時も気を付けて! 夏と違い冬は暖房器具のスイッチを切って出かける人も多いのではないでしょうか。うっかり帰りが遅くなってしまうと、すっかり室内が冷え込んでいたなんてことも…外出時には暖房器具のタイマーをセットするなど、お留守番時の寒さ対策も忘れないようにしてくださいね。今回はワンちゃんのための寒さ対策をご紹介しました。天気のいい日はぜひ日光浴もさせてあげてくださいね。免疫力が高まり、体の調子を整えてくれますよ♪イベント盛りだくさんの冬、愛犬と元気に楽しく過ごしましょう!
愛犬と過ごす冬がやって来る!ケージやクレートの寒さ対策とおススメの寝床♪
最近までなかなか涼しくならないと思っていたのに、急に寒さが厳しくなってきましたね。筆者と暮らす生後6か月の愛犬も、散歩中にブルブル震えるようになったため、今はフリースベストでしっかり防寒対策をしています。この時期は寒暖差が激しく、人もワンちゃんも体調を崩しやすい季節です。そこで今回は、愛犬が快適に過ごせるよう“お部屋での寒さ対策”に焦点を当ててご紹介していきます。 目次■うちの子、寒がってる?■お部屋の空気を暖めよう■ケージ・クレートの寒さ対策■冬でも快適なクレートといえば…■お留守番時も気を付けて! うちの子寒がってる? 体を丸めている、震えている、毛布やタオルに顔を埋めている…体調は悪くないのに、そんな仕草をしているワンちゃんはまさしく今、寒がっています!基本的に寒さには強いワンちゃんですが、冬は10℃以下になると寒さを感じると言われ、室内では20~25℃が適温です。・シニアや子犬・換毛期が無く抜け毛の少ないシングルコートの犬種・毛が短い子・暖かい国をルーツにもつ子・運動量が少なく筋肉量が少ない子は特に寒がりなので、設定温度を少し高めにしましょう。ちなみに顔を隠しているのは、周りの空気に敏感な鼻を隠して暖を取ろうしている仕草です。思わず写真に収めたくなる可愛らしさですが、早めに暖かくなるよう調節してあげてくださいね。関連ブログ・愛犬の寒さ対策!冬場のお洋服やお散歩のポイントは?・冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意! お部屋の空気を暖めよう 寒い日はお部屋全体を暖めることからスタートです。ワンちゃんも人と同じで冷たい空気を吸うとくしゃみや咳が出てしまいます。心臓や呼吸器など持病がある子は悪化させてしまう恐れもあるため、いつも以上に注意してあげてくださいね。ペットのいるお部屋にはエアコンなど火を使わない暖房器具がやっぱり安心です。一緒にサーキュレーターを使えばお部屋が万遍なく暖まるので電気代の節約にもなりますよ。人気のオイルヒーターはお部屋を乾燥させないので皮膚トラブルや呼吸器疾患、ドライアイによる角膜炎などを防いでくれるというメリットがあります。ちなみに人間用のホットカーペットは、ペットにとって熱すぎる傾向があり、脱水症状や低温火傷のリスクが高まります。使用の際は低めの温度設定にし、クッションなどを置いてワンちゃん自ら涼めるよう対策を取ってくださいね。 ケージ・クレートの寒さ対策 ケージやクレートはタオルや毛布で覆うことで冷気が入るのを防ぎ、保温性が高まります。クレートの場合は新聞紙でも効果がありますよ。中に入れるタオルもあたたかい冬素材に衣替え♪毛布、モコモコのクッション、起毛素材の犬用ベッドなどは見た目もあたたかですね。もしフローリングなどに直接クレートを置いているなら、段ボールやアルミシートを敷くだけでも寒さ対策になります。そして体をしっかり暖めてくれる湯たんぽは特にオススメ!お湯を入れるタイプのほかにレンジで温めるタイプもあり手軽に取り入れられるのも嬉しいですね。人間用でも代用できますが、ワンちゃんがイタズラしたくなるような突起が無いものを選び、火傷しないよう厚手のカバーをかけるなど安全対策を行って使用してください。 冬でも快適なクレートといえば… モコモコの毛布に湯たんぽ、ついでにお気に入りのおもちゃまで入る少しゆとりのある寝床をお探しなら、OFTで販売中の人気ハードキャリー『ペットケンネル・ファーストクラス』がおススメです。人が乗っても歪まない頑丈さと豊富なサイズバリエーションが魅力!移動メインのピッタリサイズから、お部屋メインのちょっと大きめサイズまで「うちの子」に合ったちょうどいいクレートが必ず見つかります♪災害時はそのまま抱えて避難できるのも心強いですよ。 お留守番時も気を付けて! 夏と違い冬は暖房器具のスイッチを切って出かける人も多いのではないでしょうか。うっかり帰りが遅くなってしまうと、すっかり室内が冷え込んでいたなんてことも…外出時には暖房器具のタイマーをセットするなど、お留守番時の寒さ対策も忘れないようにしてくださいね。今回はワンちゃんのための寒さ対策をご紹介しました。天気のいい日はぜひ日光浴もさせてあげてくださいね。免疫力が高まり、体の調子を整えてくれますよ♪イベント盛りだくさんの冬、愛犬と元気に楽しく過ごしましょう!

犬が食べてもいい果物とは?効果や適切な量を知っておこう
愛犬に手作りのご飯をあげている方もいらっしゃいますよね。お肉や野菜に加え、ぜひ取り入れたいのが果物です。水分や甘みもあり、旬であれば栄養も豊富!食が細いワンちゃんでも好んで口にしてくれる子が多い印象です。トッピングやおやつとしても大活躍♪今回は果物別の効能や、適切な与え方についてご説明していきます。 目次■果物をあげる前に注意したいポイント■りんご■バナナ■柿■梨■愛犬の好みと体調を見ながらあげましょう 果物をあげる前に注意したいポイント 愛犬に果物をあげるときは ・用量を守る・アレルギーに注意する・消化しやすい形状、調理方法を選択・持病がある子は獣医師に確認してからこのポイントを忘れないように気を付けましょう。果物は果糖を多く含んでいるため、あげすぎは肥満につながってしまいます。また水分も多く含まれるので、下痢や嘔吐にも注意が必要です。肉や穀類に比べればアレルギーは出にくいですが、こればかりは体質によるもの。初めて食べさせる食材は、ティースプーン程度の少量を与え、皮膚の異常や顔の腫れ、嘔吐や下痢がでないかよく様子を見ましょう。どの果物も皮や種は消化されにくいので避けたほうが安心です。果肉はみじん切りやすりおろし、小さな角切りにすると消化吸収がスムーズですし、加熱してあげるとよりお腹に優しい状態で食べさせてあげることができます。なお持病があるワンちゃんには要注意成分が含まれていることも!まずは獣医師に確認してからスタートしましょう。 りんご りんごにはビタミンC、食物繊維、カリウムを始めとし強い抗酸化作用があるポリフェノールが含まれます。甘みも強く食感もいいため気に入ってくれるワンちゃんも多いでしょう。すりおろしてドライフードに和えてもいいですね。生のままですと消化されにくいこともあるので茹でてもOK。あまり大きなサイズであげてしまうと飲み込めない可能性があるので、体格に合わせたサイズにカットすると安心です。 バナナ バナナは豊富な炭水化物に加えミネラルやビタミンが含まれた食材。1年中暖かい地域で栽培されるため、特に旬はなく、いつでも品質が変わらず安定した供給があります。エネルギー量が高いため、与える量には注意が必要です。ただし消化が良く、適切な大きさにすれば年齢を問わず与えやすいおやつです。一方で、アレルギーを起こしやすい犬もいるため、持病やアレルギーのある子には使用を控えるか、事前に獣医師へ相談すると安心です。 柿 柿には抗酸化作用のあるビタミンC、βカロテン、お腹の調子を整える食物繊維などが含まれます。実はビタミンCはみかんの2倍ほどの含有量なのです。旬を迎えた柿は柔らかく甘み、香り共に芳醇で愛犬の食欲スイッチを押してくれるかもしれません。生のまま与えるときは細かく刻んであげましょう。添加物やお砂糖が入っていなければ干し柿もOK!渋柿や青い柿には中毒を起こす成分が含まれるため、口にしないよう注意しましょう。 梨 夏から秋に旬を迎える梨はその9割が水分。水溶性食物繊維やカリウムといった栄養素を含みます。糖度が高く、シャクシャクとした食感を好むワンちゃんも多いため、水をあまり飲まない子の水分補給食材としても役立ちます。ただし、食べ過ぎるとお腹を冷やしてしまうことがあるため、与える量には注意が必要です。 愛犬の好みと体調を見ながらあげましょう いかがでしたか?既製品のおやつもいいですが旬の果物を活用すれば、美味しく栄養もたっぷり取れて一石二鳥ですよね!ぜひお気に入りの果物を見つけてあげてください。食欲がない時に食べやすい果物をあげてもOK。ただしその際は初めての食材は避け、体調を見ながら、適量の果物を食べさせてあげましょう。
犬が食べてもいい果物とは?効果や適切な量を知っておこう
愛犬に手作りのご飯をあげている方もいらっしゃいますよね。お肉や野菜に加え、ぜひ取り入れたいのが果物です。水分や甘みもあり、旬であれば栄養も豊富!食が細いワンちゃんでも好んで口にしてくれる子が多い印象です。トッピングやおやつとしても大活躍♪今回は果物別の効能や、適切な与え方についてご説明していきます。 目次■果物をあげる前に注意したいポイント■りんご■バナナ■柿■梨■愛犬の好みと体調を見ながらあげましょう 果物をあげる前に注意したいポイント 愛犬に果物をあげるときは ・用量を守る・アレルギーに注意する・消化しやすい形状、調理方法を選択・持病がある子は獣医師に確認してからこのポイントを忘れないように気を付けましょう。果物は果糖を多く含んでいるため、あげすぎは肥満につながってしまいます。また水分も多く含まれるので、下痢や嘔吐にも注意が必要です。肉や穀類に比べればアレルギーは出にくいですが、こればかりは体質によるもの。初めて食べさせる食材は、ティースプーン程度の少量を与え、皮膚の異常や顔の腫れ、嘔吐や下痢がでないかよく様子を見ましょう。どの果物も皮や種は消化されにくいので避けたほうが安心です。果肉はみじん切りやすりおろし、小さな角切りにすると消化吸収がスムーズですし、加熱してあげるとよりお腹に優しい状態で食べさせてあげることができます。なお持病があるワンちゃんには要注意成分が含まれていることも!まずは獣医師に確認してからスタートしましょう。 りんご りんごにはビタミンC、食物繊維、カリウムを始めとし強い抗酸化作用があるポリフェノールが含まれます。甘みも強く食感もいいため気に入ってくれるワンちゃんも多いでしょう。すりおろしてドライフードに和えてもいいですね。生のままですと消化されにくいこともあるので茹でてもOK。あまり大きなサイズであげてしまうと飲み込めない可能性があるので、体格に合わせたサイズにカットすると安心です。 バナナ バナナは豊富な炭水化物に加えミネラルやビタミンが含まれた食材。1年中暖かい地域で栽培されるため、特に旬はなく、いつでも品質が変わらず安定した供給があります。エネルギー量が高いため、与える量には注意が必要です。ただし消化が良く、適切な大きさにすれば年齢を問わず与えやすいおやつです。一方で、アレルギーを起こしやすい犬もいるため、持病やアレルギーのある子には使用を控えるか、事前に獣医師へ相談すると安心です。 柿 柿には抗酸化作用のあるビタミンC、βカロテン、お腹の調子を整える食物繊維などが含まれます。実はビタミンCはみかんの2倍ほどの含有量なのです。旬を迎えた柿は柔らかく甘み、香り共に芳醇で愛犬の食欲スイッチを押してくれるかもしれません。生のまま与えるときは細かく刻んであげましょう。添加物やお砂糖が入っていなければ干し柿もOK!渋柿や青い柿には中毒を起こす成分が含まれるため、口にしないよう注意しましょう。 梨 夏から秋に旬を迎える梨はその9割が水分。水溶性食物繊維やカリウムといった栄養素を含みます。糖度が高く、シャクシャクとした食感を好むワンちゃんも多いため、水をあまり飲まない子の水分補給食材としても役立ちます。ただし、食べ過ぎるとお腹を冷やしてしまうことがあるため、与える量には注意が必要です。 愛犬の好みと体調を見ながらあげましょう いかがでしたか?既製品のおやつもいいですが旬の果物を活用すれば、美味しく栄養もたっぷり取れて一石二鳥ですよね!ぜひお気に入りの果物を見つけてあげてください。食欲がない時に食べやすい果物をあげてもOK。ただしその際は初めての食材は避け、体調を見ながら、適量の果物を食べさせてあげましょう。

『FUDGE -ファッジ- 2025年12月号 Vol.269』にペットケンネルファーストクラ...
FUDGE -ファッジ- 2025年12月号 Vol.269『All About Cats ネコがすき』特集・ BLACK CAT あの娘は黒ネコ・CATS LOVE WARMTH And So Do I !! ネコもわたしも、あったかいのが好きだから・Nyanderful colors ネコのパレット・PARIS LONDON CAT’S SNAP パリっ子とロンドナーのネコとの暮らし・FOR CATS ME ネコのもの、わたしのもの・ Look at the cute kitties....
『FUDGE -ファッジ- 2025年12月号 Vol.269』にペットケンネルファーストクラ...
FUDGE -ファッジ- 2025年12月号 Vol.269『All About Cats ネコがすき』特集・ BLACK CAT あの娘は黒ネコ・CATS LOVE WARMTH And So Do I !! ネコもわたしも、あったかいのが好きだから・Nyanderful colors ネコのパレット・PARIS LONDON CAT’S SNAP パリっ子とロンドナーのネコとの暮らし・FOR CATS ME ネコのもの、わたしのもの・ Look at the cute kitties....

犬の分離不安は治せる病気?対策や治療の方法とは
私たちヒトでも、心の不調というのは体にさまざまな症状をきたしてしまうものです。そして、当然ワンちゃん達にもそういった現象が見られます。嘔吐や下痢、トイレの失敗や自傷行為、その子その子によって症状は色々ですが、その中で代表的な疾患として【分離不安症】というものがあげられます。どのような犬種、年齢でも発症する可能性があるこの病気。治療には飼い主さんの力が必要です。そこで今回は分離不安症について詳しくご説明していきます。 目次■分離不安症とはどういう病気?原因は?■分離不安症の症状■自宅でできる対策や対応方法■病院でできる治療■愛犬の心を守ってあげよう 分離不安症とはどういう病気?原因は? 分離不安症は、飼い主さんの姿が見えなくなったときや、お留守番のときにワンちゃんに色々な症状が現れる不安障害の1つです。もともと群れで生活するワンちゃん達は、ひとりぼっちが得意ではありません。それでも、日々の生活の中で飼い主さんは必ず帰ってくると学習し、お留守番もできるようになり、自宅内では安心して過ごしています。ところが、何かのきっかけで不安が爆発し、気持ちのコントロールができなくなったときに、分離不安症としての症状が見られるようになります。 発症する原因はさまざまで、引っ越しなどによって生活環境が大きく変わったり、お留守番が長すぎた、虐待によるトラウマがある、産まれてすぐに母犬や兄弟犬から引き離された、などがあげられます。 分離不安症の症状 分離不安症の症状は個体差があり、複数の症状が出る子も。代表的な症状は以下になります。・トイレの失敗・飼い主さんが見えるまで鳴き続ける・自傷行為・ひっきりなしに体を舐める・嘔吐や下痢・パニック・家具を傷つける 自宅でできる対策や対応方法 分離不安症の治療には、飼い主さんの協力が必須です。なぜなら不安を打ち消し、安心感を与えてあげられる最大の存在が、大好きな飼い主さんだけだからです。生活環境に分離不安を発症させるような引き金があるケースは、まず原因の排除を優先します。生後間もなく母犬から引き離された、虐待を受けていた経験があるなど、過去の生育問題がきっかけになっているような子には、「今の環境は安心して大丈夫なんだよ」と根気よく伝え、理解してもらうほかありません。 自宅では分離不安症の根源治療がメインになります。常に一緒にいてあげるのは難しいため、まずは短時間のお留守番が目標です。ファーストステップとして、まずは数十秒間、愛犬の前から姿を消してみましょう。この時声をかけたり、テンションを上げないよう注意してください。これはワンちゃんが飼い主さんがいなくなることに気構えしすぎないようにするためです。慣れてきたら少しずつ時間をのばしていきます。姿が見えなくなっても大丈夫なんだと、実体験を通して学習してもらう事が大切なのです。また、散歩の時間や食事の内容の見直しが症状改善に役立つこともあります。愛犬と向き合いながら、ゆっくりその子その子に見合った方法を積み重ねながら進めていきましょう。 病院でできる治療 病院では分離不安症によって出てしまう下痢や嘔吐、膀胱炎などの症状に対して対症療法を行います。さらに心を落ち着かせるサプリメントの処方、そして生活に支障が出るほど症状がひどい子のためには安定剤の処方も可能です。行動療法に詳しい獣医師が在籍する病院を選ぶのもいいでしょう。 愛犬の心を守ってあげよう 愛犬が分離不安症とわかるまで、時間がかかることもあります。理由はわからないけれど体調をよく壊す、普段は大人しいのにお留守番中だけ人が変わったように泣き叫ぶ、断片的な症状から段々と分離不安症がわかるケースも。 実際、私が一緒に暮らしていた愛犬も分離不安症になり、自傷行為やパニックの症状がみられました。突然スイッチが入り、昼夜問わず泣き叫びながら自身を攻撃してしまうのです。うっかり手を出してしまい、手の平が貫通するほどの咬み傷を負った経験もあります。愛犬を怖いと感じた日もありました。それでもやっぱり可愛い家族の一員である事にはかわりありません!我が子の場合は運動量を増やし、自宅内での過ごし方を意識したことでかなり症状は緩和されました。それでも改善を実感するまで数年の時間を要しました。時には出口が見えず、接し方がわからなくなってしまうかもしれません...。しかし、ぜひ長い目でみて、1つずつ出来ることから試していただきたいと思います。
犬の分離不安は治せる病気?対策や治療の方法とは
私たちヒトでも、心の不調というのは体にさまざまな症状をきたしてしまうものです。そして、当然ワンちゃん達にもそういった現象が見られます。嘔吐や下痢、トイレの失敗や自傷行為、その子その子によって症状は色々ですが、その中で代表的な疾患として【分離不安症】というものがあげられます。どのような犬種、年齢でも発症する可能性があるこの病気。治療には飼い主さんの力が必要です。そこで今回は分離不安症について詳しくご説明していきます。 目次■分離不安症とはどういう病気?原因は?■分離不安症の症状■自宅でできる対策や対応方法■病院でできる治療■愛犬の心を守ってあげよう 分離不安症とはどういう病気?原因は? 分離不安症は、飼い主さんの姿が見えなくなったときや、お留守番のときにワンちゃんに色々な症状が現れる不安障害の1つです。もともと群れで生活するワンちゃん達は、ひとりぼっちが得意ではありません。それでも、日々の生活の中で飼い主さんは必ず帰ってくると学習し、お留守番もできるようになり、自宅内では安心して過ごしています。ところが、何かのきっかけで不安が爆発し、気持ちのコントロールができなくなったときに、分離不安症としての症状が見られるようになります。 発症する原因はさまざまで、引っ越しなどによって生活環境が大きく変わったり、お留守番が長すぎた、虐待によるトラウマがある、産まれてすぐに母犬や兄弟犬から引き離された、などがあげられます。 分離不安症の症状 分離不安症の症状は個体差があり、複数の症状が出る子も。代表的な症状は以下になります。・トイレの失敗・飼い主さんが見えるまで鳴き続ける・自傷行為・ひっきりなしに体を舐める・嘔吐や下痢・パニック・家具を傷つける 自宅でできる対策や対応方法 分離不安症の治療には、飼い主さんの協力が必須です。なぜなら不安を打ち消し、安心感を与えてあげられる最大の存在が、大好きな飼い主さんだけだからです。生活環境に分離不安を発症させるような引き金があるケースは、まず原因の排除を優先します。生後間もなく母犬から引き離された、虐待を受けていた経験があるなど、過去の生育問題がきっかけになっているような子には、「今の環境は安心して大丈夫なんだよ」と根気よく伝え、理解してもらうほかありません。 自宅では分離不安症の根源治療がメインになります。常に一緒にいてあげるのは難しいため、まずは短時間のお留守番が目標です。ファーストステップとして、まずは数十秒間、愛犬の前から姿を消してみましょう。この時声をかけたり、テンションを上げないよう注意してください。これはワンちゃんが飼い主さんがいなくなることに気構えしすぎないようにするためです。慣れてきたら少しずつ時間をのばしていきます。姿が見えなくなっても大丈夫なんだと、実体験を通して学習してもらう事が大切なのです。また、散歩の時間や食事の内容の見直しが症状改善に役立つこともあります。愛犬と向き合いながら、ゆっくりその子その子に見合った方法を積み重ねながら進めていきましょう。 病院でできる治療 病院では分離不安症によって出てしまう下痢や嘔吐、膀胱炎などの症状に対して対症療法を行います。さらに心を落ち着かせるサプリメントの処方、そして生活に支障が出るほど症状がひどい子のためには安定剤の処方も可能です。行動療法に詳しい獣医師が在籍する病院を選ぶのもいいでしょう。 愛犬の心を守ってあげよう 愛犬が分離不安症とわかるまで、時間がかかることもあります。理由はわからないけれど体調をよく壊す、普段は大人しいのにお留守番中だけ人が変わったように泣き叫ぶ、断片的な症状から段々と分離不安症がわかるケースも。 実際、私が一緒に暮らしていた愛犬も分離不安症になり、自傷行為やパニックの症状がみられました。突然スイッチが入り、昼夜問わず泣き叫びながら自身を攻撃してしまうのです。うっかり手を出してしまい、手の平が貫通するほどの咬み傷を負った経験もあります。愛犬を怖いと感じた日もありました。それでもやっぱり可愛い家族の一員である事にはかわりありません!我が子の場合は運動量を増やし、自宅内での過ごし方を意識したことでかなり症状は緩和されました。それでも改善を実感するまで数年の時間を要しました。時には出口が見えず、接し方がわからなくなってしまうかもしれません...。しかし、ぜひ長い目でみて、1つずつ出来ることから試していただきたいと思います。
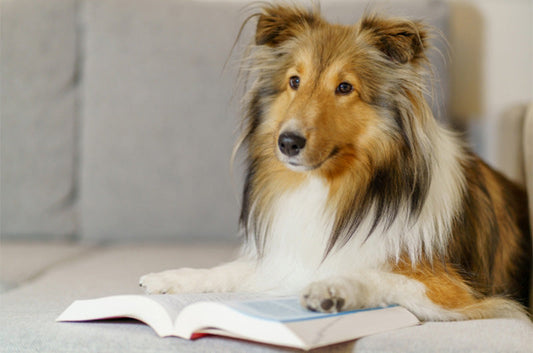
心震える、犬が活躍するおすすめ小説3選
私たち人間にとって最も古くからの友であるワンちゃん。長い歴史の中で紡がれた絆は、時に感動的に、ときに面白おかしくさまざまな作品で描かれてきました。そこで今回は、ワンちゃんを主題にしたおすすめの小説をピックアップ!読書家の飼い主さんもそうでない飼い主さんも、この機会にぜひ本の世界に浸ってみてくださいね。 目次■ワンちゃん×SF超大作!手に汗握る展開が見逃せない『ウォッチャーズ』■ペットロスを小さなときめきで描く『デューク』■一匹の犬が寄り添った群像劇『少年と犬』■犬と人とのつながりを見つめなおすきっかけに ワンちゃん×SF超大作!手に汗握る展開が見逃せない『ウォッチャーズ』 モンスターパニックもののSFホラーでありながら、普段そういったジャンルを読まない方にもぜひおすすめしたい一冊です。完ぺきに言葉を理解する天才ゴールデンレトリーバーのアインシュタインと主人公たちとの掛け合いがとてもかわいらしく、孤独を分け合うような絆はまさに人と人間のかかわりあいの本質だなと思わされます。そして読後にもっとも強烈な印象を残すのが敵役のアウトサイダーの存在です。愛される犬を横目に見ながら、愛を求めて与えられなかった犬が抱く憎しみ、ただひとつの小さな思い出をいつまでも忘れられない哀れさ……何度読んでも同じところで胸が締め付けられて涙してしまいます。発売から30年以上愛される不朽の名作ですが、じつは2021年、本作の続編にあたる『ミステリアム』が刊行されました。こちらも『ウォッチャーズ』とおなじく作者の犬愛があふれており、ワンちゃん好きは必読ですよ。 ペットロスを小さなときめきで描く『デューク』 江國香織さんの短編集『つめたいよるに』は、読みやすい短文で心をあたためてくれる作品ばかりで、慣れていない方の読書や寝る前のリラックスタイムにもおすすめできる一冊です。『つめたいよるに』のなかでもひときわ人気の高い『デューク』は、愛犬を喪ったことで深い悲しみに浸る主人公のもとに不思議な青年が現れ、1日だけのデートをするという、切なくもあたたかいストーリーが展開されます。ペットロスを経験した飼い主さんにとっては、「あの子もこうだったらよかったのにな」と思わずにはいられず、作中の青年があの日傷ついた読者の心をも癒してくれるような気がするのです。 一匹の犬が寄り添った人々をめぐる群像劇『少年と犬』 第163回直木賞を受賞した本作は、東日本大震災の影響が色濃く残る仙台からはじまる、傷ついた人々と一匹の犬をめぐる群像劇です。さまざまな人生に寄り添いながら、迷い犬「多聞」は何を目指して走るのか……読み進めるほどに結末が気になってページをめくる手が止まりません。セーフティーネットからこぼれおちてしまったような、絶望のさなかにいる登場人物たちも、やせこけた多聞に語り掛け、ドッグフードを買い与え、ともに生きたいと願います。根本的な解決にはならないながらも、与えること救いにつながるという、人間が真に必要としているものを浮き彫りにした作品だと感じました。ワンちゃんが大好きな人であれば、健気で聡明な多聞に心惹かれることでしょう。日本中を駆け巡ってただ一人を探し求める多聞。「そんなことできるはずない」とは言い切れないところが、ワンちゃんの不思議な魅力のひとつです。 犬と人とのつながりを見つめなおすきっかけに 気になる小説はありましたか?どの作品も、ワンちゃんが私たちに何をもたらしてくれるのか、筆者の哲学を感じることができる名著ばかりです。読めばいっそう愛犬が愛おしくなることでしょう。
心震える、犬が活躍するおすすめ小説3選
私たち人間にとって最も古くからの友であるワンちゃん。長い歴史の中で紡がれた絆は、時に感動的に、ときに面白おかしくさまざまな作品で描かれてきました。そこで今回は、ワンちゃんを主題にしたおすすめの小説をピックアップ!読書家の飼い主さんもそうでない飼い主さんも、この機会にぜひ本の世界に浸ってみてくださいね。 目次■ワンちゃん×SF超大作!手に汗握る展開が見逃せない『ウォッチャーズ』■ペットロスを小さなときめきで描く『デューク』■一匹の犬が寄り添った群像劇『少年と犬』■犬と人とのつながりを見つめなおすきっかけに ワンちゃん×SF超大作!手に汗握る展開が見逃せない『ウォッチャーズ』 モンスターパニックもののSFホラーでありながら、普段そういったジャンルを読まない方にもぜひおすすめしたい一冊です。完ぺきに言葉を理解する天才ゴールデンレトリーバーのアインシュタインと主人公たちとの掛け合いがとてもかわいらしく、孤独を分け合うような絆はまさに人と人間のかかわりあいの本質だなと思わされます。そして読後にもっとも強烈な印象を残すのが敵役のアウトサイダーの存在です。愛される犬を横目に見ながら、愛を求めて与えられなかった犬が抱く憎しみ、ただひとつの小さな思い出をいつまでも忘れられない哀れさ……何度読んでも同じところで胸が締め付けられて涙してしまいます。発売から30年以上愛される不朽の名作ですが、じつは2021年、本作の続編にあたる『ミステリアム』が刊行されました。こちらも『ウォッチャーズ』とおなじく作者の犬愛があふれており、ワンちゃん好きは必読ですよ。 ペットロスを小さなときめきで描く『デューク』 江國香織さんの短編集『つめたいよるに』は、読みやすい短文で心をあたためてくれる作品ばかりで、慣れていない方の読書や寝る前のリラックスタイムにもおすすめできる一冊です。『つめたいよるに』のなかでもひときわ人気の高い『デューク』は、愛犬を喪ったことで深い悲しみに浸る主人公のもとに不思議な青年が現れ、1日だけのデートをするという、切なくもあたたかいストーリーが展開されます。ペットロスを経験した飼い主さんにとっては、「あの子もこうだったらよかったのにな」と思わずにはいられず、作中の青年があの日傷ついた読者の心をも癒してくれるような気がするのです。 一匹の犬が寄り添った人々をめぐる群像劇『少年と犬』 第163回直木賞を受賞した本作は、東日本大震災の影響が色濃く残る仙台からはじまる、傷ついた人々と一匹の犬をめぐる群像劇です。さまざまな人生に寄り添いながら、迷い犬「多聞」は何を目指して走るのか……読み進めるほどに結末が気になってページをめくる手が止まりません。セーフティーネットからこぼれおちてしまったような、絶望のさなかにいる登場人物たちも、やせこけた多聞に語り掛け、ドッグフードを買い与え、ともに生きたいと願います。根本的な解決にはならないながらも、与えること救いにつながるという、人間が真に必要としているものを浮き彫りにした作品だと感じました。ワンちゃんが大好きな人であれば、健気で聡明な多聞に心惹かれることでしょう。日本中を駆け巡ってただ一人を探し求める多聞。「そんなことできるはずない」とは言い切れないところが、ワンちゃんの不思議な魅力のひとつです。 犬と人とのつながりを見つめなおすきっかけに 気になる小説はありましたか?どの作品も、ワンちゃんが私たちに何をもたらしてくれるのか、筆者の哲学を感じることができる名著ばかりです。読めばいっそう愛犬が愛おしくなることでしょう。

ワンちゃんの糖尿病の原因はなに?症状や治療の方法とは
皆さんは【糖尿病】と聞くとどのようなものをイメージしますか?名前は聞いたことがあっても具体的にどのような病気で、どういった治療が必要なのかはわからない方も多いのではないでしょうか。人間の病気と思われがちな糖尿病ですが、実は罹患するワンちゃんも多くいます。そして治療には飼い主さんの協力が必須となるでしょう。そこで今回はワンちゃんの糖尿病についてご紹介していきます。 目次■犬の糖尿病とは■好発犬種■糖尿病の代表的な症状■糖尿病の治療方法や予後■愛犬が糖尿病になったら 犬の糖尿病とは 糖尿病とは体内でインスリンという物質が作れない、もしくはうまく使えないために血糖値が安定せず、高血糖状態が続く病気です。ワンちゃんの糖尿病は大きく分けて以下の2つ。1.インスリン欠乏性糖尿病膵臓でインスリンが十分量作られず、インスリン注射が必須となる【一型糖尿病】。先天的に病気を持っている子や膵炎、免疫異常が原因で発症することが多いです。なかには原因が不明というケースも。2.インスリン抵抗性糖尿病インスリンは分泌されているが体が反応せずうまく使えない【二型糖尿病】。妊娠や発情時のホルモン変動、クッシングなどのホルモン疾患、そしてステロイドの長期服用が原因で発症する子が多く、原因を除去すると血糖値が安定するパターンもあります。そのためインスリンの使用はケースバイケースとなるでしょう。なおワンちゃんの糖尿病は、インスリン欠乏性が多くを占めています。 好発犬種 糖尿病はどのようなワンちゃんでも発症する可能性があります。しかし、そのなかでも・ミニチュアシュナウザー・トイプードル・ダックスフンドなどが罹りやすい好発犬種です。実際に私が今までに出会った糖尿病のワンちゃん達も、圧倒的にシュナウザーとプードルが多数を占めていました。更に発症しやすい年齢は7歳以降のシニア世代のワンちゃん達。そして男の子より女の子、更に女の子の中でも未避妊のワンちゃん達の発症リスクが最も高くなっています。 糖尿病の代表的な症状 ・多飲多尿・食べているのに痩せていくこの2つが糖尿病の代表的な症状です。なかには無症状、もしくは症状が軽く、春の健康診断などの定期検査で初めて病気に気が付いた!という方も。なお糖尿病が進行すると血液中に有害物質「ケトン」が出始め、一刻を争う「ケトアシドーシス」という状態になってしまうことがあります。こうなると嘔吐や下痢、元気低下といった深刻な症状が見られるようになるため要注意です。 糖尿病の治療方法や予後 ・インスリン治療不足しているインスリンを注射で補う治療方法です。打つ量や回数はワンちゃんの血糖値を細かくチェックし、獣医師が都度調整していきます。自宅での血糖測定やインスリン注射が必要なため飼い主さんの協力が必要不可欠といえるでしょう。・食事療法糖尿病専用の療法食を使って血糖値が急激に上がるのを防ぎ、血糖値コントロールを行う方法です。人間では糖質制限が代表的ですが、ワンちゃんは必要な栄養素の緻密な計算が必要になるため、独断で手作り食に切り替えるなどはやめておきましょう。・生活習慣改善食事はもちろん、おやつや運動も含め生活全体を見直し、改善していく方法です。家族みんなで情報を共有しておくことがポイントとなります。 ・避妊手術女の子のワンちゃんはホルモンが血糖値に大きく影響するため、避妊手術が治療として有効なケースがあります。・入院治療ケトアシドーシス状態まで進行している時は命に関わる緊急事態です。即日で入院して数時間おきの血糖値測定、点滴、食事療法、全てを並行した治療が施されるでしょう。上記のような治療を行いつつ、血糖値が安定してくれば病気と付き合いながら穏やかな余生を過ごすことも可能です。実際に糖尿病でありながらハイシニアで元気に暮らすワンちゃんはたくさんいます。ただし、治療は必須。早期発見、早期治療がポイントで治療開始後も変動する血糖値に適宜対応していく必要があるので定期診察は欠かせません。 愛犬が糖尿病になったら ワンちゃんの糖尿病は、飼い主さんがどれほど治療に参戦できるかが重要です。インスリン注射や血糖値の測定に抵抗を感じたり不安に思う方が多いかと思いますが、どのような方でも必ずできるようになるので安心してくださいね。まずは動物病院でスタッフと練習を重ねてから自宅での治療が開始になるでしょう。この病気は血糖値の変動をしっかり把握しておくと、動物病院との連携が取りやすく治療がスムーズに進められるので、愛犬専用ノートを作り血糖値やインスリン量、食事量や運動時間を記録しておくと安心です。上手にコントロールできるようになるまで少し時間がかかることもありますが、愛犬の様子を見ながら治療を進めていきましょう。
ワンちゃんの糖尿病の原因はなに?症状や治療の方法とは
皆さんは【糖尿病】と聞くとどのようなものをイメージしますか?名前は聞いたことがあっても具体的にどのような病気で、どういった治療が必要なのかはわからない方も多いのではないでしょうか。人間の病気と思われがちな糖尿病ですが、実は罹患するワンちゃんも多くいます。そして治療には飼い主さんの協力が必須となるでしょう。そこで今回はワンちゃんの糖尿病についてご紹介していきます。 目次■犬の糖尿病とは■好発犬種■糖尿病の代表的な症状■糖尿病の治療方法や予後■愛犬が糖尿病になったら 犬の糖尿病とは 糖尿病とは体内でインスリンという物質が作れない、もしくはうまく使えないために血糖値が安定せず、高血糖状態が続く病気です。ワンちゃんの糖尿病は大きく分けて以下の2つ。1.インスリン欠乏性糖尿病膵臓でインスリンが十分量作られず、インスリン注射が必須となる【一型糖尿病】。先天的に病気を持っている子や膵炎、免疫異常が原因で発症することが多いです。なかには原因が不明というケースも。2.インスリン抵抗性糖尿病インスリンは分泌されているが体が反応せずうまく使えない【二型糖尿病】。妊娠や発情時のホルモン変動、クッシングなどのホルモン疾患、そしてステロイドの長期服用が原因で発症する子が多く、原因を除去すると血糖値が安定するパターンもあります。そのためインスリンの使用はケースバイケースとなるでしょう。なおワンちゃんの糖尿病は、インスリン欠乏性が多くを占めています。 好発犬種 糖尿病はどのようなワンちゃんでも発症する可能性があります。しかし、そのなかでも・ミニチュアシュナウザー・トイプードル・ダックスフンドなどが罹りやすい好発犬種です。実際に私が今までに出会った糖尿病のワンちゃん達も、圧倒的にシュナウザーとプードルが多数を占めていました。更に発症しやすい年齢は7歳以降のシニア世代のワンちゃん達。そして男の子より女の子、更に女の子の中でも未避妊のワンちゃん達の発症リスクが最も高くなっています。 糖尿病の代表的な症状 ・多飲多尿・食べているのに痩せていくこの2つが糖尿病の代表的な症状です。なかには無症状、もしくは症状が軽く、春の健康診断などの定期検査で初めて病気に気が付いた!という方も。なお糖尿病が進行すると血液中に有害物質「ケトン」が出始め、一刻を争う「ケトアシドーシス」という状態になってしまうことがあります。こうなると嘔吐や下痢、元気低下といった深刻な症状が見られるようになるため要注意です。 糖尿病の治療方法や予後 ・インスリン治療不足しているインスリンを注射で補う治療方法です。打つ量や回数はワンちゃんの血糖値を細かくチェックし、獣医師が都度調整していきます。自宅での血糖測定やインスリン注射が必要なため飼い主さんの協力が必要不可欠といえるでしょう。・食事療法糖尿病専用の療法食を使って血糖値が急激に上がるのを防ぎ、血糖値コントロールを行う方法です。人間では糖質制限が代表的ですが、ワンちゃんは必要な栄養素の緻密な計算が必要になるため、独断で手作り食に切り替えるなどはやめておきましょう。・生活習慣改善食事はもちろん、おやつや運動も含め生活全体を見直し、改善していく方法です。家族みんなで情報を共有しておくことがポイントとなります。 ・避妊手術女の子のワンちゃんはホルモンが血糖値に大きく影響するため、避妊手術が治療として有効なケースがあります。・入院治療ケトアシドーシス状態まで進行している時は命に関わる緊急事態です。即日で入院して数時間おきの血糖値測定、点滴、食事療法、全てを並行した治療が施されるでしょう。上記のような治療を行いつつ、血糖値が安定してくれば病気と付き合いながら穏やかな余生を過ごすことも可能です。実際に糖尿病でありながらハイシニアで元気に暮らすワンちゃんはたくさんいます。ただし、治療は必須。早期発見、早期治療がポイントで治療開始後も変動する血糖値に適宜対応していく必要があるので定期診察は欠かせません。 愛犬が糖尿病になったら ワンちゃんの糖尿病は、飼い主さんがどれほど治療に参戦できるかが重要です。インスリン注射や血糖値の測定に抵抗を感じたり不安に思う方が多いかと思いますが、どのような方でも必ずできるようになるので安心してくださいね。まずは動物病院でスタッフと練習を重ねてから自宅での治療が開始になるでしょう。この病気は血糖値の変動をしっかり把握しておくと、動物病院との連携が取りやすく治療がスムーズに進められるので、愛犬専用ノートを作り血糖値やインスリン量、食事量や運動時間を記録しておくと安心です。上手にコントロールできるようになるまで少し時間がかかることもありますが、愛犬の様子を見ながら治療を進めていきましょう。

犬臭いなんて言わせない!夏こそ向き合いたい愛犬のニオイ対策と厳選アイテム♪
「愛犬の匂いが大好き♪」という飼い主さんは多いのではないでしょうか。しかしそんな愛犬を溺愛する私たちですら、ほんの少し困惑してしまうのが、夏のニオイ...。 そこで今回は、ワンちゃんに特化したニオイ対策をご紹介させていただきます。 目次■犬が体質的に臭くなりやすいのはなぜ?■散歩するから臭くなる?その理由とは■ニオイが強くなりやすい犬種・特徴■今日からできる!愛犬のニオイ対策4ステップ■愛犬のニオイ対策に効果的なOFT厳選アイテム 犬が体質的に臭くなりやすいのはなぜ? ワンちゃんは、体質的にニオイが出やすい動物です。その理由のひとつが、全身に分布する「アポクリン腺」。この汗腺は強いニオイを発し、人間では脇や陰部、肛門まわりなどに集中しています。ワンちゃんの体がニオイやすいのも納得ですね。 さらに、よだれが多いことも原因のひとつ。口まわりやグルーミングで体についたよだれが酸化し、雑菌が繁殖します。 つまり、汗をかきやすく菌が活発になる夏は、ワンちゃんにとってまさに「ニオイが気になる季節」といえるのです。 散歩するから臭くなる?その理由とは 加えて、高温多湿な夏のお散歩は、ニオイのリスクがぐんと高まるタイミングです。湿度が高いとワンちゃんの被毛は湿っぽくなり、空気中のホコリや汚れ、ニオイの原因物質がまとわりつきやすくなります。皮膚は蒸れて雑菌が繁殖し、ニオイはいっそう強まることに…。さらにほかの動物の排せつ物の痕跡に鼻を近づけたり、ときには体に付いてしまうこともあって、汚れやにおいの原因が増えていきます。こうしたさまざまな条件が重なるなかで、ワンちゃんが楽しく歩くたびに体温は上昇し、汗や皮脂の分泌も活発になり、その結果としてニオイがグッと強まってしまうのです。 ニオイが強くなりやすい犬種・特徴 すべてのワンちゃんが等しく臭うのかといえば、そうではなく、犬種によってニオイの強さには違いがあります。 【体が大きい犬種】体の大きさに比例して汗腺が多く、ニオイが出やすいです。例:ゴールデンレトリーバー【モフモフで毛量が多い、長毛種】熱がこもりやすく、毛が乾きにくいため雑菌が繁殖しやすいです。例:ポメラニアン【鼻ぺちゃ、たれ耳、しわが多い犬種】顔周りや耳のなかが蒸れやすく、汚れがたまりやすいです。例:パグ【皮脂が多い、または猟犬タイプの犬種】皮脂分泌が活発な子や獣臭が強くなるよう進化した猟犬タイプはニオイやすいです。例:シーズー(皮脂多め)、ビーグル(猟犬) 今日からできる!愛犬のニオイ対策4ステップ やっぱり、ワンちゃんも飼い主さんも、ニオイの気にならない毎日を過ごしたいですよね。今すぐできる対策を、以下にまとめました。■ワンちゃんへのアプローチ1.ブラッシング汚れを落とし、皮膚の通気性もキープできます。2,定期的なシャンプー夏でも月1~2回が目安。弱酸性・地肌用など愛犬に合ったシャンプー選びも重要です。3.体を丁寧に拭く散歩後はその都度丁寧に拭いてあげましょう。足裏や口回りも忘れずに。4.耳掃除週に一度はニオイ・汚れを確認しましょう。■身の回りでのアプローチ1.おもちゃ・タオルを洗う唾液がついたものは洗って清潔に保ちましょう。2.ベッドなどは干す洗えないものは陰干し・天日干し。水分が飛び殺菌作用にも期待できます。3.消臭アイテムの活用ペット専用アイテムは悪臭や雑菌対策に効果的です。4. こまめにトイレのお世話ウンチはすぐ処理、定期的な水洗いで清潔を保てます。 お散歩時には服を着せるのもオススメです。筆者の愛犬は現在タンクトップを着ていますが、電信柱に体がこすれても直接体に汚れが付かないので安心感がありますよ。 愛犬のニオイ対策に効果的なOFT厳選アイテム ニオイ対策はペット専用アイテムが効果的です。そこでOFTで取り扱っているおすすめ商品をご紹介します♪ 『洗えるペットマット クッションエアー』水洗いでき、乾きが早いファイバー製クッション。釣り糸が絡まりあった構造で通気性がよく雑菌が繁殖する隙を与えません。『ドギーペール』お部屋にニオイを漂わせない!二重蓋構造でしっかり閉じ込める、ペット専用のごみ箱です。『 SUNSTAR QAIS -clear-』次亜塩素酸水でニオイの元から消臭・除菌するスプレーです。「予想以上の消臭力!」と効果を実感されるお声多数。『SUNSTAR QAIS -air- 04A1J』排せつ臭をピンポイントで除去する、壁掛けタイプの脱臭機です。「閉め切ったお部屋でも悪臭がこもらなくなった」と大好評です。『QAIS-clear- for FABRIC』サッと乾いてべたつかない、ファブリック製品向けの消臭スプレーです。ソファなどに付着した抜け毛が取れやすくなるという効果も。 ニオイ対策は飼い主として重要なマナーのひとつです。しかしながら、ワンちゃんは自分のニオイで安心感を得るため、完璧な消臭は求めていません。 上手にバランスをとりながら夏を味方につけて、今年も愛犬と楽しい思い出をつくってくださいね♪ 【関連ブログ】・ペットのうんち。ゴミ箱1つで臭わない!?臭いが気になるこの季節の対処法♪・ペット用品の正しいお手入れ方法!清潔に長持ちさせるためには?・丸ごと洗えてすぐに乾く!ペット専用ベッド「洗えるペットベッド...
犬臭いなんて言わせない!夏こそ向き合いたい愛犬のニオイ対策と厳選アイテム♪
「愛犬の匂いが大好き♪」という飼い主さんは多いのではないでしょうか。しかしそんな愛犬を溺愛する私たちですら、ほんの少し困惑してしまうのが、夏のニオイ...。 そこで今回は、ワンちゃんに特化したニオイ対策をご紹介させていただきます。 目次■犬が体質的に臭くなりやすいのはなぜ?■散歩するから臭くなる?その理由とは■ニオイが強くなりやすい犬種・特徴■今日からできる!愛犬のニオイ対策4ステップ■愛犬のニオイ対策に効果的なOFT厳選アイテム 犬が体質的に臭くなりやすいのはなぜ? ワンちゃんは、体質的にニオイが出やすい動物です。その理由のひとつが、全身に分布する「アポクリン腺」。この汗腺は強いニオイを発し、人間では脇や陰部、肛門まわりなどに集中しています。ワンちゃんの体がニオイやすいのも納得ですね。 さらに、よだれが多いことも原因のひとつ。口まわりやグルーミングで体についたよだれが酸化し、雑菌が繁殖します。 つまり、汗をかきやすく菌が活発になる夏は、ワンちゃんにとってまさに「ニオイが気になる季節」といえるのです。 散歩するから臭くなる?その理由とは 加えて、高温多湿な夏のお散歩は、ニオイのリスクがぐんと高まるタイミングです。湿度が高いとワンちゃんの被毛は湿っぽくなり、空気中のホコリや汚れ、ニオイの原因物質がまとわりつきやすくなります。皮膚は蒸れて雑菌が繁殖し、ニオイはいっそう強まることに…。さらにほかの動物の排せつ物の痕跡に鼻を近づけたり、ときには体に付いてしまうこともあって、汚れやにおいの原因が増えていきます。こうしたさまざまな条件が重なるなかで、ワンちゃんが楽しく歩くたびに体温は上昇し、汗や皮脂の分泌も活発になり、その結果としてニオイがグッと強まってしまうのです。 ニオイが強くなりやすい犬種・特徴 すべてのワンちゃんが等しく臭うのかといえば、そうではなく、犬種によってニオイの強さには違いがあります。 【体が大きい犬種】体の大きさに比例して汗腺が多く、ニオイが出やすいです。例:ゴールデンレトリーバー【モフモフで毛量が多い、長毛種】熱がこもりやすく、毛が乾きにくいため雑菌が繁殖しやすいです。例:ポメラニアン【鼻ぺちゃ、たれ耳、しわが多い犬種】顔周りや耳のなかが蒸れやすく、汚れがたまりやすいです。例:パグ【皮脂が多い、または猟犬タイプの犬種】皮脂分泌が活発な子や獣臭が強くなるよう進化した猟犬タイプはニオイやすいです。例:シーズー(皮脂多め)、ビーグル(猟犬) 今日からできる!愛犬のニオイ対策4ステップ やっぱり、ワンちゃんも飼い主さんも、ニオイの気にならない毎日を過ごしたいですよね。今すぐできる対策を、以下にまとめました。■ワンちゃんへのアプローチ1.ブラッシング汚れを落とし、皮膚の通気性もキープできます。2,定期的なシャンプー夏でも月1~2回が目安。弱酸性・地肌用など愛犬に合ったシャンプー選びも重要です。3.体を丁寧に拭く散歩後はその都度丁寧に拭いてあげましょう。足裏や口回りも忘れずに。4.耳掃除週に一度はニオイ・汚れを確認しましょう。■身の回りでのアプローチ1.おもちゃ・タオルを洗う唾液がついたものは洗って清潔に保ちましょう。2.ベッドなどは干す洗えないものは陰干し・天日干し。水分が飛び殺菌作用にも期待できます。3.消臭アイテムの活用ペット専用アイテムは悪臭や雑菌対策に効果的です。4. こまめにトイレのお世話ウンチはすぐ処理、定期的な水洗いで清潔を保てます。 お散歩時には服を着せるのもオススメです。筆者の愛犬は現在タンクトップを着ていますが、電信柱に体がこすれても直接体に汚れが付かないので安心感がありますよ。 愛犬のニオイ対策に効果的なOFT厳選アイテム ニオイ対策はペット専用アイテムが効果的です。そこでOFTで取り扱っているおすすめ商品をご紹介します♪ 『洗えるペットマット クッションエアー』水洗いでき、乾きが早いファイバー製クッション。釣り糸が絡まりあった構造で通気性がよく雑菌が繁殖する隙を与えません。『ドギーペール』お部屋にニオイを漂わせない!二重蓋構造でしっかり閉じ込める、ペット専用のごみ箱です。『 SUNSTAR QAIS -clear-』次亜塩素酸水でニオイの元から消臭・除菌するスプレーです。「予想以上の消臭力!」と効果を実感されるお声多数。『SUNSTAR QAIS -air- 04A1J』排せつ臭をピンポイントで除去する、壁掛けタイプの脱臭機です。「閉め切ったお部屋でも悪臭がこもらなくなった」と大好評です。『QAIS-clear- for FABRIC』サッと乾いてべたつかない、ファブリック製品向けの消臭スプレーです。ソファなどに付着した抜け毛が取れやすくなるという効果も。 ニオイ対策は飼い主として重要なマナーのひとつです。しかしながら、ワンちゃんは自分のニオイで安心感を得るため、完璧な消臭は求めていません。 上手にバランスをとりながら夏を味方につけて、今年も愛犬と楽しい思い出をつくってくださいね♪ 【関連ブログ】・ペットのうんち。ゴミ箱1つで臭わない!?臭いが気になるこの季節の対処法♪・ペット用品の正しいお手入れ方法!清潔に長持ちさせるためには?・丸ごと洗えてすぐに乾く!ペット専用ベッド「洗えるペットベッド...

1年じゅう小春日和の心地よさ。コロンとかわいい猫ベッド『キャットベッドCOHALU』新発売
吸湿性・保温性に優れ、季節を問わず快適に使えることで人気の猫ベッド。このたび当社のラインナップに、おしゃれなカラーで寝心地よく、型崩れしにくい理想のアイテムが加わりました。それがこちら!小春日和の心地よさをイメージして名付けられた『キャットベッド COHALU』です。丸まって眠る猫ちゃんの体に沿うコロンとしたフォルムとふかふかの程よい厚みが猫ちゃんを安らぎのまどろみタイムへと誘いますよ。 今回は、そんな『キャットベッド COHALU』の魅力を徹底的にご紹介してきたいと思います。 目次■リッチな肌触り、型崩れも防ぐ1cmの厚み■あたたかく、さらりと心地よい。次世代の不織布素材■おしゃれなデザインと選べるカラー■水洗いも可能■大型猫種や小型犬にも■日常に小春日和のあたたかさを リッチな肌触り、型崩れも防ぐ1cmの厚み ウール製などのキャットベッドはコロンと丸いフォルムが魅力のひとつですが、しばらく使うとヘタってつぶれてしまうことが多いですよね。その点、『キャットベッド COHALU』は1cmのしっかりとした厚みで型崩れが起きにくく、届いたときのキレイなかたちをずっとキープしてくれます。厚手だからこそ叶う、もちもちふわふわのリッチな肌触りに猫ちゃんが夢中になること間違いなしですよ。 あたたかく、さらりと心地よい。次世代の不織布素材 ウールに匹敵する優れた保温性と、合成繊維ならではの通気性・耐久性を兼ね備えたLIFEAPP独自開発の不織布素材。冬はあたたかく、夏はさらりと快適。季節を問わず愛猫がくつろげる“理想のねどこ”を実現しました。また高い耐久性により、猫の本能である爪とぎにも安心。長く使えるだけでなく、形崩れしにくく、お手入れも簡単です。そんな革新的な素材を使った『キャットベッド COHALU』は、あなたの愛猫にとって一年中快適な特等席になるはずです。 おしゃれなデザインと選べるカラー 空間がパッと華やぐマカロンカラーから落ち着いたグレートーンまで、バラエティ豊富な6カラー展開。どれにしようか迷ってしまいますね。ピクニックバスケットのようなあたたかみのあるデザインが特徴的で、持ち手やロゴの差し色がオシャレさを惹き立てています。持ち運びしやすいので、時間帯に合わせて日当たりのいい場所に移動させてあげるのもいいですね。また、上部が覆われたドーム型のデザインではないので、中でくつろぐ猫ちゃんを外から見守ることができるのも嬉しいポイントです。COHALUにつつまれてリラックスした愛猫の寝姿は写真映えもバツグンですよ。 水洗いも可能 汚れが気になってきたら、30℃前後のぬるま湯で手洗いすることも可能です。粗相や吐き戻しの多い猫ちゃんにも安心して使うことができますよね。 大型猫種や小型犬にも 幅約43cmと大きめサイズで、ノルウェージャンフォレストなどの大型猫種や小型犬にもおすすめです。両脚を思いっきり伸ばしたり仰向けに寝転んだりと、自由な体勢でのびのびとくつろぐことができますよ。 日常に小春日和のあたたかさを 夏は涼しく、冬は温かい、厚手な肌触りが気持ちいい『キャットベッド COHALU』。猫ちゃんの毎日に小春日和のような小さな幸せを届けてくれるアイテムです。この機会にぜひチェックしてみてくださいね。
1年じゅう小春日和の心地よさ。コロンとかわいい猫ベッド『キャットベッドCOHALU』新発売
吸湿性・保温性に優れ、季節を問わず快適に使えることで人気の猫ベッド。このたび当社のラインナップに、おしゃれなカラーで寝心地よく、型崩れしにくい理想のアイテムが加わりました。それがこちら!小春日和の心地よさをイメージして名付けられた『キャットベッド COHALU』です。丸まって眠る猫ちゃんの体に沿うコロンとしたフォルムとふかふかの程よい厚みが猫ちゃんを安らぎのまどろみタイムへと誘いますよ。 今回は、そんな『キャットベッド COHALU』の魅力を徹底的にご紹介してきたいと思います。 目次■リッチな肌触り、型崩れも防ぐ1cmの厚み■あたたかく、さらりと心地よい。次世代の不織布素材■おしゃれなデザインと選べるカラー■水洗いも可能■大型猫種や小型犬にも■日常に小春日和のあたたかさを リッチな肌触り、型崩れも防ぐ1cmの厚み ウール製などのキャットベッドはコロンと丸いフォルムが魅力のひとつですが、しばらく使うとヘタってつぶれてしまうことが多いですよね。その点、『キャットベッド COHALU』は1cmのしっかりとした厚みで型崩れが起きにくく、届いたときのキレイなかたちをずっとキープしてくれます。厚手だからこそ叶う、もちもちふわふわのリッチな肌触りに猫ちゃんが夢中になること間違いなしですよ。 あたたかく、さらりと心地よい。次世代の不織布素材 ウールに匹敵する優れた保温性と、合成繊維ならではの通気性・耐久性を兼ね備えたLIFEAPP独自開発の不織布素材。冬はあたたかく、夏はさらりと快適。季節を問わず愛猫がくつろげる“理想のねどこ”を実現しました。また高い耐久性により、猫の本能である爪とぎにも安心。長く使えるだけでなく、形崩れしにくく、お手入れも簡単です。そんな革新的な素材を使った『キャットベッド COHALU』は、あなたの愛猫にとって一年中快適な特等席になるはずです。 おしゃれなデザインと選べるカラー 空間がパッと華やぐマカロンカラーから落ち着いたグレートーンまで、バラエティ豊富な6カラー展開。どれにしようか迷ってしまいますね。ピクニックバスケットのようなあたたかみのあるデザインが特徴的で、持ち手やロゴの差し色がオシャレさを惹き立てています。持ち運びしやすいので、時間帯に合わせて日当たりのいい場所に移動させてあげるのもいいですね。また、上部が覆われたドーム型のデザインではないので、中でくつろぐ猫ちゃんを外から見守ることができるのも嬉しいポイントです。COHALUにつつまれてリラックスした愛猫の寝姿は写真映えもバツグンですよ。 水洗いも可能 汚れが気になってきたら、30℃前後のぬるま湯で手洗いすることも可能です。粗相や吐き戻しの多い猫ちゃんにも安心して使うことができますよね。 大型猫種や小型犬にも 幅約43cmと大きめサイズで、ノルウェージャンフォレストなどの大型猫種や小型犬にもおすすめです。両脚を思いっきり伸ばしたり仰向けに寝転んだりと、自由な体勢でのびのびとくつろぐことができますよ。 日常に小春日和のあたたかさを 夏は涼しく、冬は温かい、厚手な肌触りが気持ちいい『キャットベッド COHALU』。猫ちゃんの毎日に小春日和のような小さな幸せを届けてくれるアイテムです。この機会にぜひチェックしてみてくださいね。

夏のニオイ問題はペットのせい!?今やるべき対策まとめ
愛するペットの匂いを嗅いで癒される…多くの飼い主さんが経験されていることではないでしょうか。でも最近、ちょっとクサイような気がしませんか?それは気のせいではありません。今年もムワッとした湿気とともに、ニオイが気になる季節がやって来たのです!今回は、我が家だけではなく周囲にも影響を与えてしまう、夏のペットのニオイ対策についてご紹介させていただきます。 目次■夏にペットが臭う主な3つの理由■こまめなブラッシングが効果的!■お部屋のニオイ対策は換気と掃除が基本■ニオイ知らずでペットも人も快適な夏を過ごそう! 夏にペットが臭う主な3つの理由 日本の夏は高温多湿で、菌やカビが活発に増えやすいシーズンです。さらに湿気により、私たち人間の鼻の粘膜も潤って、ニオイに敏感になっているともいわれています。このほか、夏にペットが臭う具体的な原因としては、以下の3つが挙げられます。 1.汗ニオイの原因、不動の1位!特にワンちゃんは脂肪分を含む汗を分泌させる「アポクリン腺」が全身にあり、特に臭くなりがちです。2.トイレ雑菌の繁殖とアンモニアの刺激臭が主な原因です。高温・多湿の環境によりニオイが立ちやすく、部屋中に広がりやすいうえにこもりがちになるため、いっそう強く感じるようになります。特に猫ちゃんのオシッコには「フェリニン」という独特のニオイを放つ成分が含まれているのも要因となっています。3.フードの食べ残しお皿に残ったごはんの酸化・腐敗するだけでなく、唾液が混ざることで悪臭が発生しやすくなります。 こまめなブラッシングが効果的! ニオイ対策はまず、ペット自身のケアがカギとなります。なかでも重要なのはこまめなブラッシングとシャンプー! ブラッシングは体についた汚れを落としてニオイの元を除去できます。加えて皮膚の血行がよくなるというプラスの効果が得られるのも嬉しいポイントですね。シャンプーは月に1~2回が目安です。夏だからと言って回数を増やしすぎるのはおススメできません。洗いすぎは皮膚の乾燥を招き、かえってトラブルの原因となってしまいます。シャンプーの際は細かい泡で優しく洗い、しっかりすすぎ、隅々まで乾かしてあげましょう。また夏場はペットの口臭も気になるところ。水分不足やエアコンによるお口の乾燥が原因です。自然に水分をとってもらえるよう、水の中にお気に入りのおやつを入れる、薄めたスポーツドリンクを与えるなどの工夫をしてあげると熱中症予防にもなって安心ですよ♪ お部屋のニオイ対策は換気と掃除が基本 さらに気を配りたいのがお部屋のニオイ。飼い主さんと一緒に過ごすソファやラグには、ペットの皮脂や涎が付着しており、悪臭の原因になります。基本は"こまめな掃除"と"こまめな換気"を心掛けつつ、特に以下のポイントを意識すれば快適さを実感できるでしょう。 ・窓を開ける、換気扇やサーキュレーターの使用・エアコンのフィルター掃除・トイレ掃除と猫砂の交換・密閉タイプのごみ箱を使用・ペット愛用のタオルやおもちゃはまめに洗濯・カーテン・ラグ・クッションカバーの洗濯・洗濯できないものは日干しあわせて、消臭スプレーや消臭剤、脱臭機や空気清浄機を併用すれば、かなりの確率でニオイを防げます。 とはいえ、ペットにとって自分のニオイは安心感を得られるものです。完全に消しすぎない、ちょうどいいラインを意識して行ってくださいね。強い香りでのごまかしはかえって逆効果ですよ。【関連ブログ】・猫トイレの洗いすぎ!?ニオイがないのは猫にとって死活問題! ニオイ知らずでペットも人も快適な夏を過ごそう! 夏のニオイ対策は、わが家だけでなく周囲への配慮にもなります。そして健康維持や心地よいお部屋環境づくりにもつながって、まさにいいことづくし♪ペットと過ごす夏をもっと快適で心地よいものにするためにも、無理なくできることから始めてみてくださいね。【関連ブログ】・ペットのうんち。ゴミ箱1つで臭わない!?臭いが気になるこの季節の対処法♪・口コミで高評価!OFT No.1猫砂『セリームバイオサンド』シリーズのススメ・ペット用品の正しいお手入れ方法!清潔に長持ちさせるためには?・犬用自動トイレを推奨する3つの理由・購入時の参考に:自動猫トイレのニオイ対策!便利な消臭機能5つ
夏のニオイ問題はペットのせい!?今やるべき対策まとめ
愛するペットの匂いを嗅いで癒される…多くの飼い主さんが経験されていることではないでしょうか。でも最近、ちょっとクサイような気がしませんか?それは気のせいではありません。今年もムワッとした湿気とともに、ニオイが気になる季節がやって来たのです!今回は、我が家だけではなく周囲にも影響を与えてしまう、夏のペットのニオイ対策についてご紹介させていただきます。 目次■夏にペットが臭う主な3つの理由■こまめなブラッシングが効果的!■お部屋のニオイ対策は換気と掃除が基本■ニオイ知らずでペットも人も快適な夏を過ごそう! 夏にペットが臭う主な3つの理由 日本の夏は高温多湿で、菌やカビが活発に増えやすいシーズンです。さらに湿気により、私たち人間の鼻の粘膜も潤って、ニオイに敏感になっているともいわれています。このほか、夏にペットが臭う具体的な原因としては、以下の3つが挙げられます。 1.汗ニオイの原因、不動の1位!特にワンちゃんは脂肪分を含む汗を分泌させる「アポクリン腺」が全身にあり、特に臭くなりがちです。2.トイレ雑菌の繁殖とアンモニアの刺激臭が主な原因です。高温・多湿の環境によりニオイが立ちやすく、部屋中に広がりやすいうえにこもりがちになるため、いっそう強く感じるようになります。特に猫ちゃんのオシッコには「フェリニン」という独特のニオイを放つ成分が含まれているのも要因となっています。3.フードの食べ残しお皿に残ったごはんの酸化・腐敗するだけでなく、唾液が混ざることで悪臭が発生しやすくなります。 こまめなブラッシングが効果的! ニオイ対策はまず、ペット自身のケアがカギとなります。なかでも重要なのはこまめなブラッシングとシャンプー! ブラッシングは体についた汚れを落としてニオイの元を除去できます。加えて皮膚の血行がよくなるというプラスの効果が得られるのも嬉しいポイントですね。シャンプーは月に1~2回が目安です。夏だからと言って回数を増やしすぎるのはおススメできません。洗いすぎは皮膚の乾燥を招き、かえってトラブルの原因となってしまいます。シャンプーの際は細かい泡で優しく洗い、しっかりすすぎ、隅々まで乾かしてあげましょう。また夏場はペットの口臭も気になるところ。水分不足やエアコンによるお口の乾燥が原因です。自然に水分をとってもらえるよう、水の中にお気に入りのおやつを入れる、薄めたスポーツドリンクを与えるなどの工夫をしてあげると熱中症予防にもなって安心ですよ♪ お部屋のニオイ対策は換気と掃除が基本 さらに気を配りたいのがお部屋のニオイ。飼い主さんと一緒に過ごすソファやラグには、ペットの皮脂や涎が付着しており、悪臭の原因になります。基本は"こまめな掃除"と"こまめな換気"を心掛けつつ、特に以下のポイントを意識すれば快適さを実感できるでしょう。 ・窓を開ける、換気扇やサーキュレーターの使用・エアコンのフィルター掃除・トイレ掃除と猫砂の交換・密閉タイプのごみ箱を使用・ペット愛用のタオルやおもちゃはまめに洗濯・カーテン・ラグ・クッションカバーの洗濯・洗濯できないものは日干しあわせて、消臭スプレーや消臭剤、脱臭機や空気清浄機を併用すれば、かなりの確率でニオイを防げます。 とはいえ、ペットにとって自分のニオイは安心感を得られるものです。完全に消しすぎない、ちょうどいいラインを意識して行ってくださいね。強い香りでのごまかしはかえって逆効果ですよ。【関連ブログ】・猫トイレの洗いすぎ!?ニオイがないのは猫にとって死活問題! ニオイ知らずでペットも人も快適な夏を過ごそう! 夏のニオイ対策は、わが家だけでなく周囲への配慮にもなります。そして健康維持や心地よいお部屋環境づくりにもつながって、まさにいいことづくし♪ペットと過ごす夏をもっと快適で心地よいものにするためにも、無理なくできることから始めてみてくださいね。【関連ブログ】・ペットのうんち。ゴミ箱1つで臭わない!?臭いが気になるこの季節の対処法♪・口コミで高評価!OFT No.1猫砂『セリームバイオサンド』シリーズのススメ・ペット用品の正しいお手入れ方法!清潔に長持ちさせるためには?・犬用自動トイレを推奨する3つの理由・購入時の参考に:自動猫トイレのニオイ対策!便利な消臭機能5つ

愛犬を置いて旅行へ…安心してお留守番してもらう5つのコツと便利グッズ
もう夏休みはすぐそこ!!絆が深まり思い出も増える愛犬との旅行♪を検討されている方も多いのではないでしょうか?しかし時にはさまざまな事情からどうしても一緒に行くのが難しく、お留守番をしてもらわなくてはならない場面も出てきますよね。でも長時間の留守番は不安…そこで今回はワンちゃんに安心してお留守番してもらう方法をご紹介します。 目次■愛犬を置いて旅行に行ってもいい?■長時間の留守番のカギは快適な環境づくり■ペットホテル・ペットシッターの活用法と注意点■旅行中も安心!OFTおすすめアイテム 愛犬を置いて旅行に行ってもいい? 1歳以上の健康な成犬やシニアで、お留守番に慣れている子なら、1日のほとんどを寝て過ごすため、1泊2日程度のお留守番は無理なく過ごせることが多いでしょう。しかし、1歳に満たない幼犬(パピー)や持病のある子、いたずら好き、過去にトラウマがある子は要注意。一人ぼっちの不安から問題行動を起こしてしまう、体調の急変や事故が起きやすいといったリスクが高いためおススメできません。また、条件を満たしているワンちゃんでも、「うちの子は大丈夫」と過信せず、4~6時間の普段のお留守番の様子から可能かどうかをまずは見極めるのが重要です。 長時間の留守番のカギは“快適な環境づくり” ワンちゃんの長時間のお留守番を成功させるカギは、快適な環境づくり。確認したい点は大きく分けて以下の6つです。1.お水お水が無くなるのは絶対に避けたい事態です。器を複数設置する、もしくは自動給水器を設置すると安心ですね。2.ごはんワンちゃんは器にあるだけ全部食べてしまいがち。そこで決まった時間に決まった量のフードが出てくる自動給餌器の利用をおススメします。3.トイレ吸収量の高いシーツを使用し、可能であればトイレを複数個所用意します。OFTではなんと、世界初!ワンちゃん専用自動トイレ『ブリリアントパッド』も販売中!外出先からでも、トイレ周辺の様子をリアルタイムで写真で確認できるのは嬉しいですね。4.室温エアコンは24時間運転で。人感センサーに注意し、途中でOFFにならないようにします。5.照明電気は、愛犬が落ち着く方に合わせてあげてください。つけたままでも真っ暗でも大丈夫です。6.安全対策おもちゃは誤飲しない大きさのものを。また、電気コードや観葉植物を隠す・片付ける・届かない場所へ移動させるなどの対策も忘れないでくださいね。普段は興味を示さなくても、長時間のお留守番では普段と違う行動をしてしまう子も多いため、注意が必要です! ペットホテル・ペットシッターの活用法と注意点 ワンちゃんだけでのお留守番に不安がある場合は「ペットホテル」「ペットシッター」「家族・友人を頼る」の3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて検討してみてください。■ペットホテル【メリット】・専門スタッフが常駐しているので安心・体調の変化にすぐに対応してもらえる・長期のお預かりにも対応してくれる 【デメリット】・他のペットと接することで感染症やストレスのリスクがある・吠え癖がある子は断られることも ■ペットシッター【メリット】・自宅で過ごせるため、愛犬のストレスが少ない・ライフスタイルに合わせた柔軟な対応が可能 【デメリット】・知らない人に鍵を預けるため、防犯面の不安がある・体調不良時の対応が遅れる可能性がある ■家族・知人に頼む【メリット】・慣れた相手なら気軽に頼めて、愛犬もリラックスできる・柔軟に対応してもらえる・費用がかからない 【デメリット】・相手に気を遣う・犬があまり懐いていない場合、不安が大きい・トラブルが起きたとき、人間関係にヒビが入る可能性も 愛犬が懐いている人、普段から利用する施設であればワンちゃんのストレスもぐっと軽減します。かかりつけの動物病院に預けられる場合もあるので、事前に確認しておくといいですね。 旅行中も安心!OFTおすすめアイテム OFTではワンちゃんの快適なお留守番に役立つ便利なアイテムをご用意しています。『BrilliantPad SMART』自動で排せつ物を巻き取る、犬専用自動トイレです。Wi-Fiに接続して外出先からのお掃除も可能。トイレに来たタイミングで静止画を自動で撮影してくれる、嬉しい機能つきです。『FACELINK FEEDER』カメラでいつでも給餌器周辺を見守ることができるだけでなく、 双方向の音声通話機能も搭載されているので、お留守番の機会が多いさみしがりなワンちゃんにもおすすめです。『ブリングウォーター』最大容量2.5Lとお留守番にうってつけのタンク型給水器。こぼれにくく、暴れてひっくり返りにくいフォルムで安心です。入荷するとあっという間に売り切れてしまう人気商品!愛犬と一晩離れるのは飼い主さんも寂しいものですよね。しかし便利なアイテムを使って快適なお部屋を整えれば、ワンちゃんも安心してお留守番ができます。大事なのは帰宅後のスキンシップ!お留守番を頑張ったワンちゃんをたっぷり褒めて、たくさん甘えさせてあげてくださいね♪ 【関連ブログ】■ワンちゃんのお留守番を快適にする自動犬トイレ『BrilliantPad SMART』の専用ロールがリニューアルしました♪■自動給餌器はここまで進化した!顔認証で猫ちゃんの健康管理をパーソナライズ化できる『FACELINK』発売■水がこぼれにくい設計!持ち運びできる給水器。イタズラ好きのワンちゃんに♪
愛犬を置いて旅行へ…安心してお留守番してもらう5つのコツと便利グッズ
もう夏休みはすぐそこ!!絆が深まり思い出も増える愛犬との旅行♪を検討されている方も多いのではないでしょうか?しかし時にはさまざまな事情からどうしても一緒に行くのが難しく、お留守番をしてもらわなくてはならない場面も出てきますよね。でも長時間の留守番は不安…そこで今回はワンちゃんに安心してお留守番してもらう方法をご紹介します。 目次■愛犬を置いて旅行に行ってもいい?■長時間の留守番のカギは快適な環境づくり■ペットホテル・ペットシッターの活用法と注意点■旅行中も安心!OFTおすすめアイテム 愛犬を置いて旅行に行ってもいい? 1歳以上の健康な成犬やシニアで、お留守番に慣れている子なら、1日のほとんどを寝て過ごすため、1泊2日程度のお留守番は無理なく過ごせることが多いでしょう。しかし、1歳に満たない幼犬(パピー)や持病のある子、いたずら好き、過去にトラウマがある子は要注意。一人ぼっちの不安から問題行動を起こしてしまう、体調の急変や事故が起きやすいといったリスクが高いためおススメできません。また、条件を満たしているワンちゃんでも、「うちの子は大丈夫」と過信せず、4~6時間の普段のお留守番の様子から可能かどうかをまずは見極めるのが重要です。 長時間の留守番のカギは“快適な環境づくり” ワンちゃんの長時間のお留守番を成功させるカギは、快適な環境づくり。確認したい点は大きく分けて以下の6つです。1.お水お水が無くなるのは絶対に避けたい事態です。器を複数設置する、もしくは自動給水器を設置すると安心ですね。2.ごはんワンちゃんは器にあるだけ全部食べてしまいがち。そこで決まった時間に決まった量のフードが出てくる自動給餌器の利用をおススメします。3.トイレ吸収量の高いシーツを使用し、可能であればトイレを複数個所用意します。OFTではなんと、世界初!ワンちゃん専用自動トイレ『ブリリアントパッド』も販売中!外出先からでも、トイレ周辺の様子をリアルタイムで写真で確認できるのは嬉しいですね。4.室温エアコンは24時間運転で。人感センサーに注意し、途中でOFFにならないようにします。5.照明電気は、愛犬が落ち着く方に合わせてあげてください。つけたままでも真っ暗でも大丈夫です。6.安全対策おもちゃは誤飲しない大きさのものを。また、電気コードや観葉植物を隠す・片付ける・届かない場所へ移動させるなどの対策も忘れないでくださいね。普段は興味を示さなくても、長時間のお留守番では普段と違う行動をしてしまう子も多いため、注意が必要です! ペットホテル・ペットシッターの活用法と注意点 ワンちゃんだけでのお留守番に不安がある場合は「ペットホテル」「ペットシッター」「家族・友人を頼る」の3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて検討してみてください。■ペットホテル【メリット】・専門スタッフが常駐しているので安心・体調の変化にすぐに対応してもらえる・長期のお預かりにも対応してくれる 【デメリット】・他のペットと接することで感染症やストレスのリスクがある・吠え癖がある子は断られることも ■ペットシッター【メリット】・自宅で過ごせるため、愛犬のストレスが少ない・ライフスタイルに合わせた柔軟な対応が可能 【デメリット】・知らない人に鍵を預けるため、防犯面の不安がある・体調不良時の対応が遅れる可能性がある ■家族・知人に頼む【メリット】・慣れた相手なら気軽に頼めて、愛犬もリラックスできる・柔軟に対応してもらえる・費用がかからない 【デメリット】・相手に気を遣う・犬があまり懐いていない場合、不安が大きい・トラブルが起きたとき、人間関係にヒビが入る可能性も 愛犬が懐いている人、普段から利用する施設であればワンちゃんのストレスもぐっと軽減します。かかりつけの動物病院に預けられる場合もあるので、事前に確認しておくといいですね。 旅行中も安心!OFTおすすめアイテム OFTではワンちゃんの快適なお留守番に役立つ便利なアイテムをご用意しています。『BrilliantPad SMART』自動で排せつ物を巻き取る、犬専用自動トイレです。Wi-Fiに接続して外出先からのお掃除も可能。トイレに来たタイミングで静止画を自動で撮影してくれる、嬉しい機能つきです。『FACELINK FEEDER』カメラでいつでも給餌器周辺を見守ることができるだけでなく、 双方向の音声通話機能も搭載されているので、お留守番の機会が多いさみしがりなワンちゃんにもおすすめです。『ブリングウォーター』最大容量2.5Lとお留守番にうってつけのタンク型給水器。こぼれにくく、暴れてひっくり返りにくいフォルムで安心です。入荷するとあっという間に売り切れてしまう人気商品!愛犬と一晩離れるのは飼い主さんも寂しいものですよね。しかし便利なアイテムを使って快適なお部屋を整えれば、ワンちゃんも安心してお留守番ができます。大事なのは帰宅後のスキンシップ!お留守番を頑張ったワンちゃんをたっぷり褒めて、たくさん甘えさせてあげてくださいね♪ 【関連ブログ】■ワンちゃんのお留守番を快適にする自動犬トイレ『BrilliantPad SMART』の専用ロールがリニューアルしました♪■自動給餌器はここまで進化した!顔認証で猫ちゃんの健康管理をパーソナライズ化できる『FACELINK』発売■水がこぼれにくい設計!持ち運びできる給水器。イタズラ好きのワンちゃんに♪

地震が怖い…その気持ちを安心に変える。ペットと備える防災対策と避難グッズ
7月5日に何かが起こる…そんな予言が、いまSNSで話題になっています。隕石や地震などあくまで噂とわかっていても不安になるものですよね。でも、その気持ちが芽生えたときこそ備えを始める絶好のタイミング!今回は不安な気持ちを少しでも安心に変えるために、ペットと一緒にできる防災対策をご紹介します。 目次■ペットは地震を予知する?■ペットとの在宅避難に必要な3つの備え■ペットと同行避難をする際にも焦らない3つの事前準備■OFTで揃う!防災・避難グッズおすすめ3選 ペットは地震を予知する? 7月5日の予言が当たるかどうかはわかりませんが...自然災害については洪水や落雷のように予測できるものと、地震のように予測できないものがあります。 そんななか、地震をペットたちが予知しているという話を聞いたことはないでしょうか。 例えば、過去には・愛犬が理由なく遠吠えを始めた・そわそわ落ち着かなかった・猫ちゃんがしきりに外へ出たがった・鳴き続けたなど、普段と違う行動をしたという話も多く耳にします。実際、東北大学の統計ではワンちゃん・猫ちゃんが異常行動を示したという結果も明らかにされていて、もはや言い伝えや気のせいで片付けるのが難しくなってきているのです。 これからはペットの様子を見守るのも、防災対策のひとつに加えたいところですね。 ペットとの在宅避難するために必要な備え3つ 災害への不安は普段の備えで気持ちを軽くすることができます。在宅避難時は「備蓄」と「快適に過ごせる環境づくり」がポイントです。1.備蓄(フード・水・薬)・フードは食なれたものを準備・水は体重1キロ当たり一日100mlが目安・常備薬・ペットシーツや猫砂また、器類も忘れずにしましょう。※災害時はペットの支援物資は後回しにされがちです。特に療養食やお薬などは1ヵ月月分の備えがあると安心ですね。2.お部屋の安全対策・ケージやサークルの置き場所を確認し、家具の下敷き・飛散したガラスによる怪我を防ぐ・強い揺れで窓が開いて脱走する事故も。外出時は窓の施錠も忘れずに※事前に家具の転倒防止やガラスシートで飛散防止を行っておくといいですよ。 3.迷子防止の対策・迷子札・鑑札・マイクロチップ装着で身元がわかるようにしておく・迷子対策のためのペット写真を撮っておく・「うちの子メモ」を作っておく(接種歴・持病・かかりつけ医など)※しっかり対策をしておけば再会する確率が格段に上がり、保護された際も適切な対応をしてもらえます。 ペットと同行避難をするときに必要な3つの準備 避難所に行く場合はペットを連れての同行避難を行います。素早く行動するためには日ごろの下準備がカギとなるでしょう。1.事前に避難所の確認・自分が住む自治体の避難所がペットを受け入れてくれるか確認しておく・避難所の次の手段として「一時預け先」を決めておく。親戚・かかりつけ医・サロンなど 2.定められたワクチンの接種・ワクチンは定められた通り接種しておく※未接種の場合、受け入れを断られる場合があります。 3.最低限のトレーニング・キャリーバッグに慣らしておく・ペットシーツで排せつできるようにしておく・他の犬や人に慣らしておく※特にキャリーに慣れていると災害時でのストレスが大幅に軽減されます。 OFTで揃う!防災・避難グッズおすすめ3選 OFTでは普段から無理なく防災対策が行えるアイテムを多数ご用意しています。『ペットケンネルファーストクラス』人が乗っても歪まない強度で、中のペットを圧迫や落下物からしっかり守ります。『ECO CAT TRAY』使い捨てのトイレトレー。災害時に重要な衛生対策に最適です。『CATLINK FACELINK FEEDER』2025年6月に登場した顔認証システム搭載の自動給餌器!フードが3.5リットル入り、停電時も対応します。“バックアップ電源”で停電時でも最大14日間作動して安心ですね。災害など天変地異についての予言は昔からあり、実は毎日どこかでささやかれているとも言います。信じすぎず、でも、いざというときに慌てないよう意識をしておくことが最も重要です。備蓄などは政府も推奨している“ローリングストック”がおススメですよ。ぜひ、参考にしてくださいね。
地震が怖い…その気持ちを安心に変える。ペットと備える防災対策と避難グッズ
7月5日に何かが起こる…そんな予言が、いまSNSで話題になっています。隕石や地震などあくまで噂とわかっていても不安になるものですよね。でも、その気持ちが芽生えたときこそ備えを始める絶好のタイミング!今回は不安な気持ちを少しでも安心に変えるために、ペットと一緒にできる防災対策をご紹介します。 目次■ペットは地震を予知する?■ペットとの在宅避難に必要な3つの備え■ペットと同行避難をする際にも焦らない3つの事前準備■OFTで揃う!防災・避難グッズおすすめ3選 ペットは地震を予知する? 7月5日の予言が当たるかどうかはわかりませんが...自然災害については洪水や落雷のように予測できるものと、地震のように予測できないものがあります。 そんななか、地震をペットたちが予知しているという話を聞いたことはないでしょうか。 例えば、過去には・愛犬が理由なく遠吠えを始めた・そわそわ落ち着かなかった・猫ちゃんがしきりに外へ出たがった・鳴き続けたなど、普段と違う行動をしたという話も多く耳にします。実際、東北大学の統計ではワンちゃん・猫ちゃんが異常行動を示したという結果も明らかにされていて、もはや言い伝えや気のせいで片付けるのが難しくなってきているのです。 これからはペットの様子を見守るのも、防災対策のひとつに加えたいところですね。 ペットとの在宅避難するために必要な備え3つ 災害への不安は普段の備えで気持ちを軽くすることができます。在宅避難時は「備蓄」と「快適に過ごせる環境づくり」がポイントです。1.備蓄(フード・水・薬)・フードは食なれたものを準備・水は体重1キロ当たり一日100mlが目安・常備薬・ペットシーツや猫砂また、器類も忘れずにしましょう。※災害時はペットの支援物資は後回しにされがちです。特に療養食やお薬などは1ヵ月月分の備えがあると安心ですね。2.お部屋の安全対策・ケージやサークルの置き場所を確認し、家具の下敷き・飛散したガラスによる怪我を防ぐ・強い揺れで窓が開いて脱走する事故も。外出時は窓の施錠も忘れずに※事前に家具の転倒防止やガラスシートで飛散防止を行っておくといいですよ。 3.迷子防止の対策・迷子札・鑑札・マイクロチップ装着で身元がわかるようにしておく・迷子対策のためのペット写真を撮っておく・「うちの子メモ」を作っておく(接種歴・持病・かかりつけ医など)※しっかり対策をしておけば再会する確率が格段に上がり、保護された際も適切な対応をしてもらえます。 ペットと同行避難をするときに必要な3つの準備 避難所に行く場合はペットを連れての同行避難を行います。素早く行動するためには日ごろの下準備がカギとなるでしょう。1.事前に避難所の確認・自分が住む自治体の避難所がペットを受け入れてくれるか確認しておく・避難所の次の手段として「一時預け先」を決めておく。親戚・かかりつけ医・サロンなど 2.定められたワクチンの接種・ワクチンは定められた通り接種しておく※未接種の場合、受け入れを断られる場合があります。 3.最低限のトレーニング・キャリーバッグに慣らしておく・ペットシーツで排せつできるようにしておく・他の犬や人に慣らしておく※特にキャリーに慣れていると災害時でのストレスが大幅に軽減されます。 OFTで揃う!防災・避難グッズおすすめ3選 OFTでは普段から無理なく防災対策が行えるアイテムを多数ご用意しています。『ペットケンネルファーストクラス』人が乗っても歪まない強度で、中のペットを圧迫や落下物からしっかり守ります。『ECO CAT TRAY』使い捨てのトイレトレー。災害時に重要な衛生対策に最適です。『CATLINK FACELINK FEEDER』2025年6月に登場した顔認証システム搭載の自動給餌器!フードが3.5リットル入り、停電時も対応します。“バックアップ電源”で停電時でも最大14日間作動して安心ですね。災害など天変地異についての予言は昔からあり、実は毎日どこかでささやかれているとも言います。信じすぎず、でも、いざというときに慌てないよう意識をしておくことが最も重要です。備蓄などは政府も推奨している“ローリングストック”がおススメですよ。ぜひ、参考にしてくださいね。

保護犬との暮らし。接し方や注意したいポイントとは?
既にワンちゃんを飼っている方も、これから迎えようと考えている方も、保護ぜひ犬のことを知っていただきたいと思います。どのような過去を持ったワンちゃん達で、一緒に暮らしていくうえで注意すべきポイントはどんなことか...。私自身動物病院で勤務し、たくさんの保護犬達に出会ってきました。新しいおうちにきたばかりで、まだまだ緊張が見える彼ら。そんな彼らがゆっくり時間をかけ愛情を注がれていくうちに笑顔が溢れるワンちゃんになっていく様は、胸が温かくなると同時にそれまでの壮絶な生い立ちが垣間見えるようで切なくもなります。今回は保護犬を迎えるためにはどういった手順を踏めばいいか、整えるべき環境はどういったものか?などをご説明していきましょう! 目次■保護犬達の生い立ち■保護犬の性格は?■保護犬の迎え方■整えておきたい生活環境■ゆっくり時間をかけて特別な関係作りを 保護犬達の生い立ち ひと言で保護犬といっても、その生い立ちはさまざまです。例えば繁殖犬として酷使されていた、飼育放棄された、保健所に入っていて殺処分手前だった、虐待通報があった、飼育崩壊が起きたなど。こういった子たちが保護団体の手によって救出され、【保護犬】としてシェルターやボランティアさんのお宅で過ごしながら新しい飼い主さんのお迎えを待っています。なかには狭いケージに何頭も押し込められ、十分な世話もされず、糞尿にまみれながら飢えに耐えていたという子も。 保護犬の性格は? 保護犬達の性格はそれまでにどのような経験をしてきているかに大きく左右されます。上記のような辛い環境下にいた子であれば人間に対し恐怖心を持っていても当然ですよね。多く見られるのは・臆病・警戒心が強い・環境変化にデリケート・初めましての場所や人が苦手・大きな音や声、金属音が苦手・抱っこなど触れられることが嫌いといった性格。最初は心を閉ざしていても、それは自然な事なのです。ぜひそのまま受け入れてあげて欲しいと思います。もちろん人間大好き!甘えたくて仕方がない!という子もいます。まずは保護主さんに、本人の性格を聞いてみるのもいいでしょう。 保護犬の迎え方 保護犬の引き取り方法はいくつかあります。・保護団体を通して行う・保健所から引き取る・譲渡会に行く・SNSでの里親募集など。注目したいポイントは、トライアル期間が設けられているかどうかです。実際に一緒に暮らし、ワンちゃんの様子や家族との相性を見ることは保護犬を迎え入れるうえでとても大切。できれば数日間のトライアルができると安心ですね。また里親になる方に対し、家族構成や居住環境に条件が付いていることもあるため、事前に確認しましょう。 整えておきたい生活環境 保護犬をおうちに迎えるときは、できるだけリラックスできる環境を作ってあげてください。広々した空間で自由に過ごさせてあげたくなりますが、最初はワンちゃん専用のスペースを作り、少しずつ慣れてもらう方がスムーズです。クレートでも、サークルでも構いません。まずは安心して過ごせるワンちゃんだけのテリトリーを作ってあげましょう。また恐怖心や緊張から飛び出すように逃げだしてしまう子もいます。安全を確保するためにも脱走防止策は必ず行っておいてくださいね。食器や排せつ場所、使用するリードやハーネス類は保護主さんに確認し、今までと同じものを使ってあげるとワンちゃんが混乱しなくてすみます。 ゆっくり時間をかけて特別な関係作りを 保護犬は慣れるまで数ヵ月以上の時間がかかります。抱っこはおろか触る事さえできず、部屋の隅っこで丸くなり少しも動かない…そんな姿に焦りを感じる事もあるかもしれません。ですが彼らにとってそれまでの長く苦しい時間は=人生そのものでもあったのです。環境の変化に戸惑いや不安、緊張が生まれるのは当然のこと。どうかゆっくり時間をかけ、信頼関係を築いていただければと思います。 私の勤務先に毎月通ってくれる元保護犬ちゃんがいます。初めて会ったときは飼い主さんにも心を開くことができず、爪切りをしようとするものなら大パニックを起こし、お漏らしをしていました。それでも飼い主さんは一心に愛情を注ぎ、月に1度の通院を習慣にしながらワンちゃんとの関係作りを頑張ってこられました。病院の入り口で抵抗していた子が、数年たった今では、飼い主さんにピタッとしがみつくように来院し、爪切りも頑張って我慢できるようになったのです。初めてその姿を見たときは、飼い主さんと一緒に目頭を熱くした記憶があります。たとえ時間はかかっても、心から安らげるよう愛情をたっぷり注いであげたいですね。
保護犬との暮らし。接し方や注意したいポイントとは?
既にワンちゃんを飼っている方も、これから迎えようと考えている方も、保護ぜひ犬のことを知っていただきたいと思います。どのような過去を持ったワンちゃん達で、一緒に暮らしていくうえで注意すべきポイントはどんなことか...。私自身動物病院で勤務し、たくさんの保護犬達に出会ってきました。新しいおうちにきたばかりで、まだまだ緊張が見える彼ら。そんな彼らがゆっくり時間をかけ愛情を注がれていくうちに笑顔が溢れるワンちゃんになっていく様は、胸が温かくなると同時にそれまでの壮絶な生い立ちが垣間見えるようで切なくもなります。今回は保護犬を迎えるためにはどういった手順を踏めばいいか、整えるべき環境はどういったものか?などをご説明していきましょう! 目次■保護犬達の生い立ち■保護犬の性格は?■保護犬の迎え方■整えておきたい生活環境■ゆっくり時間をかけて特別な関係作りを 保護犬達の生い立ち ひと言で保護犬といっても、その生い立ちはさまざまです。例えば繁殖犬として酷使されていた、飼育放棄された、保健所に入っていて殺処分手前だった、虐待通報があった、飼育崩壊が起きたなど。こういった子たちが保護団体の手によって救出され、【保護犬】としてシェルターやボランティアさんのお宅で過ごしながら新しい飼い主さんのお迎えを待っています。なかには狭いケージに何頭も押し込められ、十分な世話もされず、糞尿にまみれながら飢えに耐えていたという子も。 保護犬の性格は? 保護犬達の性格はそれまでにどのような経験をしてきているかに大きく左右されます。上記のような辛い環境下にいた子であれば人間に対し恐怖心を持っていても当然ですよね。多く見られるのは・臆病・警戒心が強い・環境変化にデリケート・初めましての場所や人が苦手・大きな音や声、金属音が苦手・抱っこなど触れられることが嫌いといった性格。最初は心を閉ざしていても、それは自然な事なのです。ぜひそのまま受け入れてあげて欲しいと思います。もちろん人間大好き!甘えたくて仕方がない!という子もいます。まずは保護主さんに、本人の性格を聞いてみるのもいいでしょう。 保護犬の迎え方 保護犬の引き取り方法はいくつかあります。・保護団体を通して行う・保健所から引き取る・譲渡会に行く・SNSでの里親募集など。注目したいポイントは、トライアル期間が設けられているかどうかです。実際に一緒に暮らし、ワンちゃんの様子や家族との相性を見ることは保護犬を迎え入れるうえでとても大切。できれば数日間のトライアルができると安心ですね。また里親になる方に対し、家族構成や居住環境に条件が付いていることもあるため、事前に確認しましょう。 整えておきたい生活環境 保護犬をおうちに迎えるときは、できるだけリラックスできる環境を作ってあげてください。広々した空間で自由に過ごさせてあげたくなりますが、最初はワンちゃん専用のスペースを作り、少しずつ慣れてもらう方がスムーズです。クレートでも、サークルでも構いません。まずは安心して過ごせるワンちゃんだけのテリトリーを作ってあげましょう。また恐怖心や緊張から飛び出すように逃げだしてしまう子もいます。安全を確保するためにも脱走防止策は必ず行っておいてくださいね。食器や排せつ場所、使用するリードやハーネス類は保護主さんに確認し、今までと同じものを使ってあげるとワンちゃんが混乱しなくてすみます。 ゆっくり時間をかけて特別な関係作りを 保護犬は慣れるまで数ヵ月以上の時間がかかります。抱っこはおろか触る事さえできず、部屋の隅っこで丸くなり少しも動かない…そんな姿に焦りを感じる事もあるかもしれません。ですが彼らにとってそれまでの長く苦しい時間は=人生そのものでもあったのです。環境の変化に戸惑いや不安、緊張が生まれるのは当然のこと。どうかゆっくり時間をかけ、信頼関係を築いていただければと思います。 私の勤務先に毎月通ってくれる元保護犬ちゃんがいます。初めて会ったときは飼い主さんにも心を開くことができず、爪切りをしようとするものなら大パニックを起こし、お漏らしをしていました。それでも飼い主さんは一心に愛情を注ぎ、月に1度の通院を習慣にしながらワンちゃんとの関係作りを頑張ってこられました。病院の入り口で抵抗していた子が、数年たった今では、飼い主さんにピタッとしがみつくように来院し、爪切りも頑張って我慢できるようになったのです。初めてその姿を見たときは、飼い主さんと一緒に目頭を熱くした記憶があります。たとえ時間はかかっても、心から安らげるよう愛情をたっぷり注いであげたいですね。

ペットの熱中症対策は早めが肝心!令和の夏に備えるポイントをご紹介
日陰は涼しいけれど、日差しは強烈…!突然やって来る夏日に、早くも熱中症対策が気になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。ここ最近の夏の暑さは人間にも、ペットにとっても過酷な環境ですよね。そこで今回は、今すぐ準備できる熱中症対策と、気を付けたいポイントをわかりやすくご紹介いたします。 目次■これまでとは違う熱中症事情■令和の暑さ対策と新常識!■上手な水分補給のコツ■OFTおすすめ!高機能でオシャレな水飲みアイテム これまでとは違う熱中症事情 昭和~平成の初めごろに子ども時代を過ごした大人たちにとっては「夏は梅雨明けから」が当たり前の感覚でしたが、年々、いつの間にか真夏に突入してしまっていたと感じることが増えてきました。実際に気温や天候パターンが異常に変化する「気候変動」が進んでいて、日本はジメジメして暑い高温多湿気候になりつつあると言われています。まさにこれこそが、「昔より暑くなった」と感じる一因です。こうした気候の変化により、ペットを取り巻く環境にも少しずつ影響が現れ始めています。たとえば、蚊の活動時期が早まったことで、フィラリア予防を例年より1ヵ月前倒しして始める動物病院が増えてきました。熱中症対策も例外ではなく、早め早めから始めてもちょうどいいといえる時代になってきているのです。 令和の暑さ対策と新常識! 昔より暑いとはいえ、熱中症対策の基本は変わりません。ただし、今の気候に合わせてアップデートしたいポイントがあるので以下を参考に準備してみてくださいね。 ■室内での対策 【エアコンは基本24時間運転!】室温はワンちゃんが20~25度、猫ちゃんが21〜28度、湿度はどちらも40〜60%が目安。計測時はペットの目線が理想です。サーキュレーターで空気を循環させるとより効果的ですよ。【日差しを遮る】屋内でも直射日光が入ると温度・湿度が急激に上昇し危険です。カーテンで日差しを遮るほか、すだれなどで家の外側から防ぐのもおススメです。【クールマットを活用する】お腹や脇をマットに乗せるだけで効果的に体温を下げることができます。■屋外での対策 【短時間でもお水を持参!】短時間のお散歩でも、気温が高い日はこまめに水分補給を行いましょう。【涼しい時間帯を選んでの散歩】暑い時間を避け夏は6~8時までに、夕方は17~19時ごろのお散歩が安心です。地面の熱さ確認も忘れないでくださいね。【クール素材の服・アイスリング・靴を活用】首やわきの下など体を冷やす部分に冷感素材のアイテムを着用することで体温の上昇を抑えます。また、靴はアスファルトの熱から肉球を守ってくれますよ。 上手な水分補給のコツ 熱中症対策に重要な水分補給ですが、なかにはもともと積極的にお水を飲んでくれない子もいますよね。そういう子にぜひ試して欲しい“つい飲みたくなっちゃう”コツを、いくつかご紹介します♪■ウェットフードを与える日々のごはんから水分が摂れます摂取できます。■水の中にお気に入りのおやつを入れるおやつにつられて水に興味を持ってくれることも。■犬には氷、猫にはぬるめのお水ワンちゃんは氷、猫ちゃんは冷たすぎないお水を好む傾向があります。■フレーバー水を活用ペット用ミルクや薄めたスポーツドリンク、お肉やお魚の煮汁をお水に少し加えると飲んでくれる場合もあります。また、旬の野菜…スイカやキュウリ、トマトなどをおやつ代わりにするのも有効です。ただし、どれも水分たっぷりで体を冷やしやすいため、あげ過ぎは禁物。体質や体調に合わせて与えてくださいね。 OFTおすすめ!高機能でオシャレな水飲みアイテム OFTではペットも飼い主さんも嬉しい、便利でオシャレな水飲みアイテムを取り揃えています! 『ワイヤレスファウンテン』動く水が好きな猫ちゃん向けに設計された自動給水器です。高性能フィルターで常に新鮮なお水を供給し、アプリとの連携でお水をどれくらい飲んだか外出先からも確認できます。もちろんワンちゃんにもおススメですよ。 『ブリングウォーター』取っ手付きで持ち運びラクラクの水飲み器です。飲み口の水位が低い位置で保たれており、豪快にこぼして空っぽになるのを防ぎます。お出掛けや車移動にもピッタリ。『ピダン ペット用携帯給水器』人間用の水筒と言っても違和感のないオシャレすぎる携帯給水器です。活性炭フィルター付きで、お散歩中も、美味しいお水を飲ませてあげられます。 ワンちゃん猫ちゃんは、人間のように汗をかけないため、熱中症になるリスクが非常に高い生き物です。だからこそ最新の情報を取り入れ、適切な暑さ対策を行うことが重要です。とはいえ、楽しいことも多い季節。しっかり準備をして、思い出に残る夏を過ごしましょう♪ ...
ペットの熱中症対策は早めが肝心!令和の夏に備えるポイントをご紹介
日陰は涼しいけれど、日差しは強烈…!突然やって来る夏日に、早くも熱中症対策が気になる飼い主さんも多いのではないでしょうか。ここ最近の夏の暑さは人間にも、ペットにとっても過酷な環境ですよね。そこで今回は、今すぐ準備できる熱中症対策と、気を付けたいポイントをわかりやすくご紹介いたします。 目次■これまでとは違う熱中症事情■令和の暑さ対策と新常識!■上手な水分補給のコツ■OFTおすすめ!高機能でオシャレな水飲みアイテム これまでとは違う熱中症事情 昭和~平成の初めごろに子ども時代を過ごした大人たちにとっては「夏は梅雨明けから」が当たり前の感覚でしたが、年々、いつの間にか真夏に突入してしまっていたと感じることが増えてきました。実際に気温や天候パターンが異常に変化する「気候変動」が進んでいて、日本はジメジメして暑い高温多湿気候になりつつあると言われています。まさにこれこそが、「昔より暑くなった」と感じる一因です。こうした気候の変化により、ペットを取り巻く環境にも少しずつ影響が現れ始めています。たとえば、蚊の活動時期が早まったことで、フィラリア予防を例年より1ヵ月前倒しして始める動物病院が増えてきました。熱中症対策も例外ではなく、早め早めから始めてもちょうどいいといえる時代になってきているのです。 令和の暑さ対策と新常識! 昔より暑いとはいえ、熱中症対策の基本は変わりません。ただし、今の気候に合わせてアップデートしたいポイントがあるので以下を参考に準備してみてくださいね。 ■室内での対策 【エアコンは基本24時間運転!】室温はワンちゃんが20~25度、猫ちゃんが21〜28度、湿度はどちらも40〜60%が目安。計測時はペットの目線が理想です。サーキュレーターで空気を循環させるとより効果的ですよ。【日差しを遮る】屋内でも直射日光が入ると温度・湿度が急激に上昇し危険です。カーテンで日差しを遮るほか、すだれなどで家の外側から防ぐのもおススメです。【クールマットを活用する】お腹や脇をマットに乗せるだけで効果的に体温を下げることができます。■屋外での対策 【短時間でもお水を持参!】短時間のお散歩でも、気温が高い日はこまめに水分補給を行いましょう。【涼しい時間帯を選んでの散歩】暑い時間を避け夏は6~8時までに、夕方は17~19時ごろのお散歩が安心です。地面の熱さ確認も忘れないでくださいね。【クール素材の服・アイスリング・靴を活用】首やわきの下など体を冷やす部分に冷感素材のアイテムを着用することで体温の上昇を抑えます。また、靴はアスファルトの熱から肉球を守ってくれますよ。 上手な水分補給のコツ 熱中症対策に重要な水分補給ですが、なかにはもともと積極的にお水を飲んでくれない子もいますよね。そういう子にぜひ試して欲しい“つい飲みたくなっちゃう”コツを、いくつかご紹介します♪■ウェットフードを与える日々のごはんから水分が摂れます摂取できます。■水の中にお気に入りのおやつを入れるおやつにつられて水に興味を持ってくれることも。■犬には氷、猫にはぬるめのお水ワンちゃんは氷、猫ちゃんは冷たすぎないお水を好む傾向があります。■フレーバー水を活用ペット用ミルクや薄めたスポーツドリンク、お肉やお魚の煮汁をお水に少し加えると飲んでくれる場合もあります。また、旬の野菜…スイカやキュウリ、トマトなどをおやつ代わりにするのも有効です。ただし、どれも水分たっぷりで体を冷やしやすいため、あげ過ぎは禁物。体質や体調に合わせて与えてくださいね。 OFTおすすめ!高機能でオシャレな水飲みアイテム OFTではペットも飼い主さんも嬉しい、便利でオシャレな水飲みアイテムを取り揃えています! 『ワイヤレスファウンテン』動く水が好きな猫ちゃん向けに設計された自動給水器です。高性能フィルターで常に新鮮なお水を供給し、アプリとの連携でお水をどれくらい飲んだか外出先からも確認できます。もちろんワンちゃんにもおススメですよ。 『ブリングウォーター』取っ手付きで持ち運びラクラクの水飲み器です。飲み口の水位が低い位置で保たれており、豪快にこぼして空っぽになるのを防ぎます。お出掛けや車移動にもピッタリ。『ピダン ペット用携帯給水器』人間用の水筒と言っても違和感のないオシャレすぎる携帯給水器です。活性炭フィルター付きで、お散歩中も、美味しいお水を飲ませてあげられます。 ワンちゃん猫ちゃんは、人間のように汗をかけないため、熱中症になるリスクが非常に高い生き物です。だからこそ最新の情報を取り入れ、適切な暑さ対策を行うことが重要です。とはいえ、楽しいことも多い季節。しっかり準備をして、思い出に残る夏を過ごしましょう♪ ...

犬が全抜歯手術を受ける理由とは?費用やその後の生活の注意点
愛犬の歯石や口臭、気になりますよね。人間の様に毎食後歯磨きができればいいのですが、させてくれるワンちゃんはほんの一握り。お口を触られることを本能的に嫌う動物ですから、無理はありません。アメリカでは3歳以上のワンちゃんの80%が何らかのお口トラブルを抱えている、なんてデータも報告されています。でもこのお口トラブル、放置しすぎると【全抜歯】を避けられない状態まで進行してしまう事も…!そこで今回は全抜歯をしなくてはいけない理由や、治療にかかる費用、抜歯後の生活にスポットをあてご紹介していきましょう! 目次■全抜歯手術とは?■手術を受けないといけない理由■かかる費用や入院日数■全抜歯後の生活■セカンドオピニオンの視野に入れよう 全抜歯手術とは? その名の通り、生えている歯を全て抜いてしまう手術です。お腹を切る手術ではないので、簡単で短時間で終わると思われがちですが顎の骨が折れるリスクや大量出血の可能性があり、とても大掛かりな処置となります。太い歯を抜いた部分は穴が開いて出血しますので、その都度止血し、歯肉の縫合を行っていくため当然時間がかかるうえ、年齢を重ねている子であれば麻酔のリスクも避けられません。個人的には獣医師、看護師が特に緊張する手術の一つだと思っています。通常の動物病院でも行う事はできますが、最近では専用設備を整えた歯科専門の動物病院も多く、セカンドオピニオンを勧められるケースも多いでしょう。 手術を受けないといけない理由 飼い主さんの中には全抜歯の処置を行うことに抵抗を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?実際勤務しているとそういったお声を耳にします。そして、動物病院スタッフとしてもできるだけ残せる歯は残してあげたいと思っているのです。ではどういった場合に全抜歯が必要になるのでしょうか?それは歯周病が重度まで進行し生活の質を大きく落としてしまっている時。たかが歯周病とあなどってはいけません。歯石の沈着が進むと歯肉はやせ衰え、顎の骨は溶け、出血、痛み、蓄膿、鼻汁とさまざまな症状が出てきます。食事を取るにも痛みが伴い、ヨダレが止まらず悪臭を放つ、そんな状態になってしまう事も。この状態まできてしまうと、できるだけ早い処置が理想的。愛犬の状態を考慮し、獣医師と相談しながら処置の内容やタイミングを決めていきましょう。 かかる費用や入院日数 抜歯する歯の本数、手術にかかった時間、ワンちゃんの体格、などで料金は変動します。一概にはいえませんが、おおよそ10万円~15万円、入院は1泊~3泊前後が平均的です。歯科専門の動物病院ですと、専用の施設が整っているためもう少し金額はかかるかもしれません。通常乳歯の抜歯などは保険適応外ですが、重度歯肉炎による抜歯はペット保険の対象となる事もあります。事前にご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。手術前に見積もりを出してもらう事もできますので、スタッフに確認してみてくださいね。 全抜歯後の生活 歯がなくてご飯は食べられるのか、顔の形が変わってしまうのではないかなど、不安に感じる点は多いかと思います。まず食事ですが、基本的にワンちゃん達は前歯で食いちぎり、そのまま丸呑みする動物ですから歯がなくても問題はありません。ただ食べにくさは少なからず出てきますので・ドライフードをふやかす・ウェットフードに切り替えるなど、今までよりも食べやすい食事に切り替えてあげるといいでしょう。またお顔の形に関しては、舌が出っぱなしになってしまうことや、マズルが細く見える事もあります。これは抜歯だけではなく顎の骨が溶けてしまっていることも原因です。それ自体が生活に大きな支障をきたすことはありませんが、そういった可能性があることは処置する前に頭に入れておきましょう。 セカンドオピニオンの視野に入れよう 歯周病はとてもポピュラーな病気です。重度まで進行し全抜歯が必要になったワンちゃん達もたくさん見てきました。全抜歯をしたあと痛みが消え、食欲が戻ってきた、若返った気がする、なんて子もいます。ただ最近では専門的な検査や再生医療など、全抜歯以外の選択肢を選ぶことができる歯科専門の動物病院も増えてきています。もし治療に迷いがある時は、セカンドオピニオンを検討してみてください。愛犬と飼い主さんが納得できる形でケアしてあげましょう!
犬が全抜歯手術を受ける理由とは?費用やその後の生活の注意点
愛犬の歯石や口臭、気になりますよね。人間の様に毎食後歯磨きができればいいのですが、させてくれるワンちゃんはほんの一握り。お口を触られることを本能的に嫌う動物ですから、無理はありません。アメリカでは3歳以上のワンちゃんの80%が何らかのお口トラブルを抱えている、なんてデータも報告されています。でもこのお口トラブル、放置しすぎると【全抜歯】を避けられない状態まで進行してしまう事も…!そこで今回は全抜歯をしなくてはいけない理由や、治療にかかる費用、抜歯後の生活にスポットをあてご紹介していきましょう! 目次■全抜歯手術とは?■手術を受けないといけない理由■かかる費用や入院日数■全抜歯後の生活■セカンドオピニオンの視野に入れよう 全抜歯手術とは? その名の通り、生えている歯を全て抜いてしまう手術です。お腹を切る手術ではないので、簡単で短時間で終わると思われがちですが顎の骨が折れるリスクや大量出血の可能性があり、とても大掛かりな処置となります。太い歯を抜いた部分は穴が開いて出血しますので、その都度止血し、歯肉の縫合を行っていくため当然時間がかかるうえ、年齢を重ねている子であれば麻酔のリスクも避けられません。個人的には獣医師、看護師が特に緊張する手術の一つだと思っています。通常の動物病院でも行う事はできますが、最近では専用設備を整えた歯科専門の動物病院も多く、セカンドオピニオンを勧められるケースも多いでしょう。 手術を受けないといけない理由 飼い主さんの中には全抜歯の処置を行うことに抵抗を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?実際勤務しているとそういったお声を耳にします。そして、動物病院スタッフとしてもできるだけ残せる歯は残してあげたいと思っているのです。ではどういった場合に全抜歯が必要になるのでしょうか?それは歯周病が重度まで進行し生活の質を大きく落としてしまっている時。たかが歯周病とあなどってはいけません。歯石の沈着が進むと歯肉はやせ衰え、顎の骨は溶け、出血、痛み、蓄膿、鼻汁とさまざまな症状が出てきます。食事を取るにも痛みが伴い、ヨダレが止まらず悪臭を放つ、そんな状態になってしまう事も。この状態まできてしまうと、できるだけ早い処置が理想的。愛犬の状態を考慮し、獣医師と相談しながら処置の内容やタイミングを決めていきましょう。 かかる費用や入院日数 抜歯する歯の本数、手術にかかった時間、ワンちゃんの体格、などで料金は変動します。一概にはいえませんが、おおよそ10万円~15万円、入院は1泊~3泊前後が平均的です。歯科専門の動物病院ですと、専用の施設が整っているためもう少し金額はかかるかもしれません。通常乳歯の抜歯などは保険適応外ですが、重度歯肉炎による抜歯はペット保険の対象となる事もあります。事前にご加入の保険会社に問い合わせてみましょう。手術前に見積もりを出してもらう事もできますので、スタッフに確認してみてくださいね。 全抜歯後の生活 歯がなくてご飯は食べられるのか、顔の形が変わってしまうのではないかなど、不安に感じる点は多いかと思います。まず食事ですが、基本的にワンちゃん達は前歯で食いちぎり、そのまま丸呑みする動物ですから歯がなくても問題はありません。ただ食べにくさは少なからず出てきますので・ドライフードをふやかす・ウェットフードに切り替えるなど、今までよりも食べやすい食事に切り替えてあげるといいでしょう。またお顔の形に関しては、舌が出っぱなしになってしまうことや、マズルが細く見える事もあります。これは抜歯だけではなく顎の骨が溶けてしまっていることも原因です。それ自体が生活に大きな支障をきたすことはありませんが、そういった可能性があることは処置する前に頭に入れておきましょう。 セカンドオピニオンの視野に入れよう 歯周病はとてもポピュラーな病気です。重度まで進行し全抜歯が必要になったワンちゃん達もたくさん見てきました。全抜歯をしたあと痛みが消え、食欲が戻ってきた、若返った気がする、なんて子もいます。ただ最近では専門的な検査や再生医療など、全抜歯以外の選択肢を選ぶことができる歯科専門の動物病院も増えてきています。もし治療に迷いがある時は、セカンドオピニオンを検討してみてください。愛犬と飼い主さんが納得できる形でケアしてあげましょう!

愛犬の一生にかかる総額は?ワンちゃんを迎える前に知っておきたいこと
ワンちゃんとの暮らし、幼いころから憧れていた…!という方も多いのではないでしょうか?かく言う私もその一人。お散歩やドッグラン、旅行など愛犬と過ごす時間はきっと楽しくて素敵なものなのだろうと想像したものです。ですが当時学生だった私は犬との暮らしにどれほどのお金がかかるのかをしっかり把握していませんでした。家族が1人増え、その生涯を見届けるのが飼い主さんの責任。そこにかかる金額を事前に知っておくことはとても大切な事です。では実際、何に、いくらかかるものなのでしょうか?今回はワンちゃんの生涯にかかる金額を算出してみました。 目次■生体販売の矛盾■最低限かかるお金とは?■予想外に起こる出費■お金がない、は飼えないとイコール? 生体販売の矛盾 最近になりペットショップやブリーダーなど生体販売を行うものに対しての法整備が進んできました。代表的なものはマイクロチップの装着義務や販売する月齢の縛りでしょうか。生体販売価格はピンキリで15万円~100万円前後。月齢が浅いワンちゃんや体が小さいワンちゃん、純血のワンちゃんが高値で売買される傾向にあります。新しい家族とのご縁をつなぐ場所。疑問を感じるのは【分割払い可能】と明示している店舗があまりに多いことです。中には24回、36回と月額1万円以内に収まるような分割プランも用意されており、分割にすればなんとか…という状態でもお迎えできてしまうのが現状です。厳しいようですが金銭的な面でも責任を持てなければワンちゃんを飼ってはいけません。お迎えからがスタート!どうか先々のことを試算して検討してほしいなと思います。 最低限かかるお金とは? ワンちゃんが健康に一生を過ごした場合、最低限必要な費用はどのくらいかかるのでしょうか。平均寿命が14歳で、日本で最も飼育頭数の多い犬種であるプードルを例に試算してみます。・フード 3000円/月×12か月×14年・混合ワクチン(年1回接種として) 7000円/回×14年・狂犬病予防接種(年1回接種として) 3600円×14年・フィラリア予防(5~12月)1500円×8か月×14年・ノミやマダニの予防(5~10月)1500円×6か月×14年・シャンプーカット8000円×12か月×14年・消耗品(シーツやお散歩用品)5000円×12か月×14年総計317万円程。ここに体調不良時の医療費、療法食代、ペット保険に加入するのであれば保険料、お留守番時の空調費などが加わります。予防薬は地域によって通年投与が必要ですし中型、大型犬であれば更に数百万円がプラスされると考えましょう。 予想外に起こる出費 動物には人間のような健康保険はなく、任意で加入するペット保険があるのみです。動物病院は自由診療のため価格設定もまちまち。特に大学病院や専門病院、二次診療施設は医療費も高額になってきます。『若いうちはペット保険に入っていたものの病気をしないから』と新規加入困難なシニア期に入ってから保険を解約し、その直後に大病を患ってしまうケースも少なくありません。手術や抗がん剤治療は場合によって100万円以上の費用がかかります。私自身金銭的な負担が大きく治療を諦めざるを得ない飼い主さんを多く見てきました。これは人間と異なる医療費算出方法のため、そこまでの大きな費用がかかること自体想定外だったのでしょう。また、動物病院の関係者でなければ金額の目途をつけるのは難しいと思います。突然大きな金額が必要になることもあると知っておきましょう。 お金がない人は飼ってはいけない? 過去に、迷子の犬を保護し、当院へ連れてきてくださった方がいらっしゃいました。 そのワンちゃんは外を徘徊していたため、診察だけでなく各種検査も必要でした。しかし、保護主の方は「金銭的に厳しい。せっかく命を救い、一緒に暮らそうとしているのに、金銭を要求するのか」とおっしゃいました。私たち動物病院のスタッフは、もちろん動物が好きでこの仕事をしています。しかし、どんなにお気持ちは理解できても、無償で医療を提供することはできません。さらに、「お金がない人間は犬を飼うべきではないのか?」という質問に対し、対応した獣医師は 「その通りです」 とお答えしました。命を助け、受診されたことは素晴らしい行動ですが、ワンちゃんの一生を受け入れるには、それ相応の費用がかかるのも事実です。 その後、保護主の方と相談し、病院で里親を探すことになりました。そのワンちゃんは、最終的に素晴らしい里親さんと出会い、幸せな生活を送ることができました。ペットを迎える際には、十分な準備と責任が伴います。もし、周囲に勢いだけで飼おうとしている方がいたら、ぜひ一度考える機会を作ってあげてくださいね。
愛犬の一生にかかる総額は?ワンちゃんを迎える前に知っておきたいこと
ワンちゃんとの暮らし、幼いころから憧れていた…!という方も多いのではないでしょうか?かく言う私もその一人。お散歩やドッグラン、旅行など愛犬と過ごす時間はきっと楽しくて素敵なものなのだろうと想像したものです。ですが当時学生だった私は犬との暮らしにどれほどのお金がかかるのかをしっかり把握していませんでした。家族が1人増え、その生涯を見届けるのが飼い主さんの責任。そこにかかる金額を事前に知っておくことはとても大切な事です。では実際、何に、いくらかかるものなのでしょうか?今回はワンちゃんの生涯にかかる金額を算出してみました。 目次■生体販売の矛盾■最低限かかるお金とは?■予想外に起こる出費■お金がない、は飼えないとイコール? 生体販売の矛盾 最近になりペットショップやブリーダーなど生体販売を行うものに対しての法整備が進んできました。代表的なものはマイクロチップの装着義務や販売する月齢の縛りでしょうか。生体販売価格はピンキリで15万円~100万円前後。月齢が浅いワンちゃんや体が小さいワンちゃん、純血のワンちゃんが高値で売買される傾向にあります。新しい家族とのご縁をつなぐ場所。疑問を感じるのは【分割払い可能】と明示している店舗があまりに多いことです。中には24回、36回と月額1万円以内に収まるような分割プランも用意されており、分割にすればなんとか…という状態でもお迎えできてしまうのが現状です。厳しいようですが金銭的な面でも責任を持てなければワンちゃんを飼ってはいけません。お迎えからがスタート!どうか先々のことを試算して検討してほしいなと思います。 最低限かかるお金とは? ワンちゃんが健康に一生を過ごした場合、最低限必要な費用はどのくらいかかるのでしょうか。平均寿命が14歳で、日本で最も飼育頭数の多い犬種であるプードルを例に試算してみます。・フード 3000円/月×12か月×14年・混合ワクチン(年1回接種として) 7000円/回×14年・狂犬病予防接種(年1回接種として) 3600円×14年・フィラリア予防(5~12月)1500円×8か月×14年・ノミやマダニの予防(5~10月)1500円×6か月×14年・シャンプーカット8000円×12か月×14年・消耗品(シーツやお散歩用品)5000円×12か月×14年総計317万円程。ここに体調不良時の医療費、療法食代、ペット保険に加入するのであれば保険料、お留守番時の空調費などが加わります。予防薬は地域によって通年投与が必要ですし中型、大型犬であれば更に数百万円がプラスされると考えましょう。 予想外に起こる出費 動物には人間のような健康保険はなく、任意で加入するペット保険があるのみです。動物病院は自由診療のため価格設定もまちまち。特に大学病院や専門病院、二次診療施設は医療費も高額になってきます。『若いうちはペット保険に入っていたものの病気をしないから』と新規加入困難なシニア期に入ってから保険を解約し、その直後に大病を患ってしまうケースも少なくありません。手術や抗がん剤治療は場合によって100万円以上の費用がかかります。私自身金銭的な負担が大きく治療を諦めざるを得ない飼い主さんを多く見てきました。これは人間と異なる医療費算出方法のため、そこまでの大きな費用がかかること自体想定外だったのでしょう。また、動物病院の関係者でなければ金額の目途をつけるのは難しいと思います。突然大きな金額が必要になることもあると知っておきましょう。 お金がない人は飼ってはいけない? 過去に、迷子の犬を保護し、当院へ連れてきてくださった方がいらっしゃいました。 そのワンちゃんは外を徘徊していたため、診察だけでなく各種検査も必要でした。しかし、保護主の方は「金銭的に厳しい。せっかく命を救い、一緒に暮らそうとしているのに、金銭を要求するのか」とおっしゃいました。私たち動物病院のスタッフは、もちろん動物が好きでこの仕事をしています。しかし、どんなにお気持ちは理解できても、無償で医療を提供することはできません。さらに、「お金がない人間は犬を飼うべきではないのか?」という質問に対し、対応した獣医師は 「その通りです」 とお答えしました。命を助け、受診されたことは素晴らしい行動ですが、ワンちゃんの一生を受け入れるには、それ相応の費用がかかるのも事実です。 その後、保護主の方と相談し、病院で里親を探すことになりました。そのワンちゃんは、最終的に素晴らしい里親さんと出会い、幸せな生活を送ることができました。ペットを迎える際には、十分な準備と責任が伴います。もし、周囲に勢いだけで飼おうとしている方がいたら、ぜひ一度考える機会を作ってあげてくださいね。

アウトドアの季節♪キャンプ場でも愛犬の放し飼いは禁止...簡単にリードを固定するには?
ワンちゃんを自然の中でのびのび遊ばせてあげたい!最近ではペット連れOKなキャンプ場も増えてきましたよね♪そんな思いから休日には一緒にアウトドアレジャーへと出掛ける飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、自然豊かなレジャースポットであってもワンちゃんの放し飼いは絶対禁止!レジャースポットだからこそ、必ず繋ぎ留めておくのがマナーです。そこでOFTから、おもりタイプのドッグキーパー『K9アンカー』をご紹介します。 目次■犬連れキャンプではリードの固定が必須事項!■キャンプ場でワンちゃんを固定する方法■おもりタイプの固定器具『K9アンカー』■日常の何気ないシーンでも大活躍! 犬連れキャンプではリードの固定が必須事項! キャンプ場にはそれぞれ利用規約が定められていますが、ペット可能な施設では別途、同伴者に向けてのルールが設けられています。狂犬病や混合ワクチンの接種済であることはもちろん、初めからリードを外して遊べるドッグフリーサイトを除けば「ペットの放し飼い」を禁止している施設がほとんどと言っていいでしょう。一方で、テントの設営や食事の準備などで忙しく、抱っこしたままの状態やリードをずっと持っているわけにもいかないですよね。少し目を離した隙に脱走してしまい、他のワンちゃんとケンカを始めたり、迷子になったり…なんてトラブルも実際に起きています。野外で一緒に楽しい時間を過ごすためには、ワンちゃんを安全な場所に安全な方法で固定することが重要であり、飼い主さんの義務でもあるのです。 キャンプ場でワンちゃんを固定する方法 野外でワンちゃんを繋ぐには、リードを木にくくりつけるほか、テントの杭(ペグ)や屋外用のドッグポールを使用する方法があります。特にドッグポールはワンちゃん専用に設計されているため使いやすく安全・安心ですね。地面に打ち込むのでしっかり固定はできますが、土がある場所でしか使えない、打ち込みが甘いと地面から浮き上がって来てしまうというデメリットもあり、注意が必要です。そこでキャンプ初心者さんや、ペグの打ち込み方に不安がある人、もっと気軽にワンちゃんを繋ぎたい人は置くだけでいい「おもりタイプ」の固定器具をオススメします。※キャンプ場内の木やフェンスに繋ぐのは破損の原因にもなり、利用規約で禁止されている場合もあるため、ご注意ください。 おもりタイプの固定器具『K9アンカー』 OFTにて販売中の『K9アンカー』は「おもり」タイプのドッグキーパーです。設置方法は付属のワイヤーを取り付けてリードを繋ぐだけ。あとはどこでも好きな場所に置いて設置完了です。テントの中でも使えるので、ずっと一緒に過ごせて嬉しいですね♪コンクリートの上にだって置けちゃいます。表面はレジンでコーティングされており、拭くだけでスルッと汚れが落ちてお手入れもラクラク。丸みのあるフォルムで、ワンちゃんの体も傷つけません。 1つあたりの重さが9㎏、最大4枚まで重ねて使用できます。ワンちゃんの体格やパワーに合わせて選んでくださいね。 日常の何気ないシーンでも大活躍! アウトドアシーンだけでなく、日常生活でも重宝するのがおもりタイプのいいトコロ。お庭で、広い公園で…お家の中でも来客時や掃除機をかける少しの時間待っていてもらうのにも最適です。筆者である私の実家は海沿いの街なのですが、庭の土はサラサラと柔らかくペグを打ち込むことができないため、安定感のある『K9アンカー』が非常に役立っています。同じような地域にお住まいの方には特におオススメです。 実は、おもりタイプのドッグキーパーは意外と市場に少なく、『K9アンカー』は入荷してもすぐに完売してしまう人気商品。薄型で邪魔になりにくく、普段から車に乗せておけば、いざという時にも便利です♪アウトドア好きの方は、ぜひチェックしてみてください!
アウトドアの季節♪キャンプ場でも愛犬の放し飼いは禁止...簡単にリードを固定するには?
ワンちゃんを自然の中でのびのび遊ばせてあげたい!最近ではペット連れOKなキャンプ場も増えてきましたよね♪そんな思いから休日には一緒にアウトドアレジャーへと出掛ける飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、自然豊かなレジャースポットであってもワンちゃんの放し飼いは絶対禁止!レジャースポットだからこそ、必ず繋ぎ留めておくのがマナーです。そこでOFTから、おもりタイプのドッグキーパー『K9アンカー』をご紹介します。 目次■犬連れキャンプではリードの固定が必須事項!■キャンプ場でワンちゃんを固定する方法■おもりタイプの固定器具『K9アンカー』■日常の何気ないシーンでも大活躍! 犬連れキャンプではリードの固定が必須事項! キャンプ場にはそれぞれ利用規約が定められていますが、ペット可能な施設では別途、同伴者に向けてのルールが設けられています。狂犬病や混合ワクチンの接種済であることはもちろん、初めからリードを外して遊べるドッグフリーサイトを除けば「ペットの放し飼い」を禁止している施設がほとんどと言っていいでしょう。一方で、テントの設営や食事の準備などで忙しく、抱っこしたままの状態やリードをずっと持っているわけにもいかないですよね。少し目を離した隙に脱走してしまい、他のワンちゃんとケンカを始めたり、迷子になったり…なんてトラブルも実際に起きています。野外で一緒に楽しい時間を過ごすためには、ワンちゃんを安全な場所に安全な方法で固定することが重要であり、飼い主さんの義務でもあるのです。 キャンプ場でワンちゃんを固定する方法 野外でワンちゃんを繋ぐには、リードを木にくくりつけるほか、テントの杭(ペグ)や屋外用のドッグポールを使用する方法があります。特にドッグポールはワンちゃん専用に設計されているため使いやすく安全・安心ですね。地面に打ち込むのでしっかり固定はできますが、土がある場所でしか使えない、打ち込みが甘いと地面から浮き上がって来てしまうというデメリットもあり、注意が必要です。そこでキャンプ初心者さんや、ペグの打ち込み方に不安がある人、もっと気軽にワンちゃんを繋ぎたい人は置くだけでいい「おもりタイプ」の固定器具をオススメします。※キャンプ場内の木やフェンスに繋ぐのは破損の原因にもなり、利用規約で禁止されている場合もあるため、ご注意ください。 おもりタイプの固定器具『K9アンカー』 OFTにて販売中の『K9アンカー』は「おもり」タイプのドッグキーパーです。設置方法は付属のワイヤーを取り付けてリードを繋ぐだけ。あとはどこでも好きな場所に置いて設置完了です。テントの中でも使えるので、ずっと一緒に過ごせて嬉しいですね♪コンクリートの上にだって置けちゃいます。表面はレジンでコーティングされており、拭くだけでスルッと汚れが落ちてお手入れもラクラク。丸みのあるフォルムで、ワンちゃんの体も傷つけません。 1つあたりの重さが9㎏、最大4枚まで重ねて使用できます。ワンちゃんの体格やパワーに合わせて選んでくださいね。 日常の何気ないシーンでも大活躍! アウトドアシーンだけでなく、日常生活でも重宝するのがおもりタイプのいいトコロ。お庭で、広い公園で…お家の中でも来客時や掃除機をかける少しの時間待っていてもらうのにも最適です。筆者である私の実家は海沿いの街なのですが、庭の土はサラサラと柔らかくペグを打ち込むことができないため、安定感のある『K9アンカー』が非常に役立っています。同じような地域にお住まいの方には特におオススメです。 実は、おもりタイプのドッグキーパーは意外と市場に少なく、『K9アンカー』は入荷してもすぐに完売してしまう人気商品。薄型で邪魔になりにくく、普段から車に乗せておけば、いざという時にも便利です♪アウトドア好きの方は、ぜひチェックしてみてください!

愛犬の適切な睡眠時間!夢を見たりうなされることはある?
愛犬の可愛い寝顔、いつまでも見ていたいですよね。でもなんだかいつ見ても寝てばかり…いくら可愛いとはいえ寝すぎなのでは?と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。ワンちゃん達にとって睡眠は心身の健康に大きく影響するものですが、そのサイクルや時間は人間と異なります。また寝言のように鳴いたり、走っているような動きをしたり、いびきをかいたり…まるで夢でも見ているの?と思う仕草をすることも!そこで今回はワンちゃん達の睡眠事情についてご紹介していきましょう。 目次■犬の適切な睡眠時間■犬の睡眠サイクル■犬は夢を見る?■いびきをかくのは普通の事?■良質な睡眠をとってもらうために 犬の適切な睡眠時間 ワンちゃん達の平均睡眠時間は約12時間。1日の半分は寝ているのが正常です。お留守番の間は寝て過ごすワンちゃんが多いのもうなずけますね。ただし体格や年齢、運動量にも左右されるため、あくまで目安と考えましょう。例えば子犬は15~20時間ほど眠るため1日中寝ている事も珍しくありません。人間の赤ちゃんと同じように月齢が浅いほど眠っている時間が長くなります。また、シニアのワンちゃん達も年齢を重ねるにつれ睡眠時間が長くなり、最終的に18~20時間近く眠るように変化します。これも自然な現象なので大きな心配はありません。ただし突然寝込み始めた、ぐったりしている、食欲がないというときは体調が悪いサインかもしれません。普段と違う点がある場合は、注意して見てあげてくださいね。 犬の睡眠サイクル 睡眠には浅い眠りで脳が覚醒状態の【レム睡眠】と深い眠りで脳も休息状態の【ノンレム睡眠】があります。人間はこの2つの睡眠サイクルを繰り返し、その割合は2:8、ノンレム睡眠の方がずっと長いのが特徴です。これに対しワンちゃん達は、2つの睡眠サイクルを繰り返す点は同じですが、その割合が8:2。なんと人間とは真逆で浅い眠りであるレム睡眠がほとんどを占めているのです。これは野生時代の名残りで、外敵の接近や周囲の異常にいち早く気が付くことができるため。浅い眠りでもしっかり体を回復させるため、その分、長時間の眠りを必要とすると言われています。 犬は夢を見る? それでは、ワンちゃん達は夢を見るのでしょうか?こればかりは聞くことができないので断言はできませんが、筆者が一緒に暮らしていた愛犬も寝言のようにフンフンと鳴いてみたり、ドッグランに行った日の夜は足が泳いでいたりと夢を見ているのかな?と感じるシーンが何回もありました。人間が夢を見るのは眠りが浅いレム睡眠の最中。そう考えるとレム睡眠が大半を占めているワンちゃん達が夢を見ていても何ら不思議ではありませんね。本来、夢というものは脳内にあるさまざまな情報を整理するために見ると言われています。ワンちゃん達も、その日起きた楽しかったことや驚いたことを反芻しながら整理しているのかもしれませんね。時にうなされる事もあるかもしれません...。しかし、四肢が突っ張るような動き、ガクガクと震えるような動きをしているときは痙攣発作の可能性もあります。判断がつかないときは動画に収め、獣医師に見てもらうと安心です。 いびきをかくのは普通の事? ワンちゃんの中には人間に負けず劣らずのいびきをかくような子もいます。いびきは気道や鼻、空気の通り道が狭くなることで起こる現象で、先天的に鼻腔が狭いフレンチブルドックやボストンテリアなどの短頭種のワンちゃん達によく見られます。その他にいびきをかく理由としては以下のような事にがあげられます。・深い眠りにつき筋肉がゆるんだことで気道が一時的に狭くなっている・シニア期に入り筋肉が衰えたことで気道が狭くなっている・肥満により気道が潰されてしまっている・気道周囲に腫瘍がある なかには無呼吸症候群になってしまう子や、チアノーゼを起こしてしまうケースもあります。突然いびきをかくようになった、苦しそうにしている、どんどんひどくなっている場合は、一度動物病院を受診しましょう。 良質な睡眠をとってもらうために ワンちゃん達が好む寝床にはいくつかの条件があります。・薄暗く、囲まれた場所・フカフカした素材で安心する香り・人間の動線から外れた静かで清潔な場所もちろん飼い主さんと一緒が1番!という子もいるので一概にはいえませんが、寝床作りの際はぜひ参考にしてみてください。良質な睡眠は心身の健康につながります。愛犬が安心して眠れるよう、しっかりサポートしてあげましょう。
愛犬の適切な睡眠時間!夢を見たりうなされることはある?
愛犬の可愛い寝顔、いつまでも見ていたいですよね。でもなんだかいつ見ても寝てばかり…いくら可愛いとはいえ寝すぎなのでは?と心配になる方もいらっしゃるかもしれません。ワンちゃん達にとって睡眠は心身の健康に大きく影響するものですが、そのサイクルや時間は人間と異なります。また寝言のように鳴いたり、走っているような動きをしたり、いびきをかいたり…まるで夢でも見ているの?と思う仕草をすることも!そこで今回はワンちゃん達の睡眠事情についてご紹介していきましょう。 目次■犬の適切な睡眠時間■犬の睡眠サイクル■犬は夢を見る?■いびきをかくのは普通の事?■良質な睡眠をとってもらうために 犬の適切な睡眠時間 ワンちゃん達の平均睡眠時間は約12時間。1日の半分は寝ているのが正常です。お留守番の間は寝て過ごすワンちゃんが多いのもうなずけますね。ただし体格や年齢、運動量にも左右されるため、あくまで目安と考えましょう。例えば子犬は15~20時間ほど眠るため1日中寝ている事も珍しくありません。人間の赤ちゃんと同じように月齢が浅いほど眠っている時間が長くなります。また、シニアのワンちゃん達も年齢を重ねるにつれ睡眠時間が長くなり、最終的に18~20時間近く眠るように変化します。これも自然な現象なので大きな心配はありません。ただし突然寝込み始めた、ぐったりしている、食欲がないというときは体調が悪いサインかもしれません。普段と違う点がある場合は、注意して見てあげてくださいね。 犬の睡眠サイクル 睡眠には浅い眠りで脳が覚醒状態の【レム睡眠】と深い眠りで脳も休息状態の【ノンレム睡眠】があります。人間はこの2つの睡眠サイクルを繰り返し、その割合は2:8、ノンレム睡眠の方がずっと長いのが特徴です。これに対しワンちゃん達は、2つの睡眠サイクルを繰り返す点は同じですが、その割合が8:2。なんと人間とは真逆で浅い眠りであるレム睡眠がほとんどを占めているのです。これは野生時代の名残りで、外敵の接近や周囲の異常にいち早く気が付くことができるため。浅い眠りでもしっかり体を回復させるため、その分、長時間の眠りを必要とすると言われています。 犬は夢を見る? それでは、ワンちゃん達は夢を見るのでしょうか?こればかりは聞くことができないので断言はできませんが、筆者が一緒に暮らしていた愛犬も寝言のようにフンフンと鳴いてみたり、ドッグランに行った日の夜は足が泳いでいたりと夢を見ているのかな?と感じるシーンが何回もありました。人間が夢を見るのは眠りが浅いレム睡眠の最中。そう考えるとレム睡眠が大半を占めているワンちゃん達が夢を見ていても何ら不思議ではありませんね。本来、夢というものは脳内にあるさまざまな情報を整理するために見ると言われています。ワンちゃん達も、その日起きた楽しかったことや驚いたことを反芻しながら整理しているのかもしれませんね。時にうなされる事もあるかもしれません...。しかし、四肢が突っ張るような動き、ガクガクと震えるような動きをしているときは痙攣発作の可能性もあります。判断がつかないときは動画に収め、獣医師に見てもらうと安心です。 いびきをかくのは普通の事? ワンちゃんの中には人間に負けず劣らずのいびきをかくような子もいます。いびきは気道や鼻、空気の通り道が狭くなることで起こる現象で、先天的に鼻腔が狭いフレンチブルドックやボストンテリアなどの短頭種のワンちゃん達によく見られます。その他にいびきをかく理由としては以下のような事にがあげられます。・深い眠りにつき筋肉がゆるんだことで気道が一時的に狭くなっている・シニア期に入り筋肉が衰えたことで気道が狭くなっている・肥満により気道が潰されてしまっている・気道周囲に腫瘍がある なかには無呼吸症候群になってしまう子や、チアノーゼを起こしてしまうケースもあります。突然いびきをかくようになった、苦しそうにしている、どんどんひどくなっている場合は、一度動物病院を受診しましょう。 良質な睡眠をとってもらうために ワンちゃん達が好む寝床にはいくつかの条件があります。・薄暗く、囲まれた場所・フカフカした素材で安心する香り・人間の動線から外れた静かで清潔な場所もちろん飼い主さんと一緒が1番!という子もいるので一概にはいえませんが、寝床作りの際はぜひ参考にしてみてください。良質な睡眠は心身の健康につながります。愛犬が安心して眠れるよう、しっかりサポートしてあげましょう。

猫にもマイクロチップは必要?装着後のメリットや手続きとは
2022年以降、販売される犬と猫にはマイクロチップ装着が義務化されました。ワンちゃんは畜犬登録にマイクロチップの識別番号を使うようになり、飼い主さんへの浸透も早かったように感じています。それに対し猫ちゃんは役所で手続きをすることもなく、使うタイミングが少ないため、まだマイクロチップ自体を認知していない飼い主さんも多いようです。そもそも使いどころがよくわからないと、必要なものなのかも判断できませんよね。そこで今回は猫ちゃんのマイクロチップにまつわる情報をまとめてみました! 目次■マイクロチップとは■猫ちゃんがマイクロチップをつける理由■マイクロチップの手続き■装着するか迷ったときは マイクロチップとは マイクロチップは皮膚の下に挿入する電子チップのことです。直径1.2mm、長さ8mm程の小さなもので麻酔を使わず挿入できます。皮膚の上から専用リーダーをかざすとマイクロチップに記憶された識別番号が表示され、その番号と紐付けされた飼い主さんの情報を見られるというシステム。マイクロチップ本体は電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して番号を送り返すことができる仕組みになっており、一度入れると生涯交換の必要はありません。 猫ちゃんがマイクロチップをつける理由 完全室内飼いの猫ちゃんだと、マイクロチップの必要性を感じないかもしれませんが、どのような生活環境であっても装着はしておくべきです。・脱走・迷子・災害時こういった時に1つの安心材料となるのがマイクロチップなのです。玄関が開いた瞬間や、窓の隙間から思わぬタイミングで脱走してしまうケースも少なくありません。勤務先の動物病院にも保護された猫ちゃんが来院しますが、人懐っこく体も綺麗で迷子なんじゃないか…と感じる子もしばしばいます。ほとんどの動物病院がマイクロチップリーダーを持っていますので、マイクロチップさえ入っていればこの段階で飼い主さんにご連絡ができるのです。マイクロチップの義務化は、遺棄や外での繁殖を防止する意味も兼ねていますが、飼い主さんにとっては行方不明時の手がかりの1つとしての意味が大きくなります。 マイクロチップの手続き マイクロチップは、識別番号と飼い主さんの情報を紐付けすることが重要です。以下を参考に手続きをぜひ進めてみましょう!■マイクロチップを挿入している子を迎えたペットショップやブリーダーさんからお迎えした子であれば、既にマイクロチップは装着されているはずです。チップ内には繁殖元、あるいは販売元の情報が記憶されているので、まずは飼い主さんの情報に書き換えましょう。環境省の【犬と猫のマイクロチップ情報登録】のページから登録作業を行ってください。この時、販売元から渡される【登録証明書】が必要となりますので手元に用意しておくとスムーズです。■動物病院でマイクロチップを挿入した動物病院が発行する【装着証明書】を使って登録手続きを行います。■マイクロチップは入っているが、番号がわからないどこの動物病院でもいいので、リーダーを使ってマイクロチップが入っている事を伝え、その番号を確認してもらいましょう。その後【マイクロチップ識別番号証明書】という書類を発行してもらってください。これが装着証明書の代わりになります。■過去にマイクロチップを挿入しているが、環境省のデータベースに未登録こちらは【移行登録申請】の書類を提出します。ただ装着日や装着した獣医師の名前などが必要で、書類作成が難しい場合は上記のマイクロチップ識別番号証明書を発行してもらう手順でも問題ないでしょう。環境省:Q30移行登録手順どこに該当するのかわからない時は、直接問い合わせてみてくださいね。 装着するか迷ったときは マイクロチップを装着するか迷う方も多いと思います。体に電子チップをいれて大丈夫なのか、痛くはないのか、不安も心配もありますよね。個人的には、若く持病がない子にはぜひ積極的に取り入れて欲しいと思いますが、ハイシニアや持病がある子は、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。愛猫がいなくなり、涙を流す飼い主さんをたくさん見てきました。マイクロチップで飼い主さんを見つけたこともあります。ただ17年動物病院で勤務して、マイクロチップのせいで体調が悪くなった子は見たことがありません。いざという時に、飼い主さんと愛猫を繋ぐものは多いに越したことはありませんよね。まずは相談だけでもOKです。悩んだ時は、かかりつけの動物病院で話を聞いてみてくださいね。
猫にもマイクロチップは必要?装着後のメリットや手続きとは
2022年以降、販売される犬と猫にはマイクロチップ装着が義務化されました。ワンちゃんは畜犬登録にマイクロチップの識別番号を使うようになり、飼い主さんへの浸透も早かったように感じています。それに対し猫ちゃんは役所で手続きをすることもなく、使うタイミングが少ないため、まだマイクロチップ自体を認知していない飼い主さんも多いようです。そもそも使いどころがよくわからないと、必要なものなのかも判断できませんよね。そこで今回は猫ちゃんのマイクロチップにまつわる情報をまとめてみました! 目次■マイクロチップとは■猫ちゃんがマイクロチップをつける理由■マイクロチップの手続き■装着するか迷ったときは マイクロチップとは マイクロチップは皮膚の下に挿入する電子チップのことです。直径1.2mm、長さ8mm程の小さなもので麻酔を使わず挿入できます。皮膚の上から専用リーダーをかざすとマイクロチップに記憶された識別番号が表示され、その番号と紐付けされた飼い主さんの情報を見られるというシステム。マイクロチップ本体は電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して番号を送り返すことができる仕組みになっており、一度入れると生涯交換の必要はありません。 猫ちゃんがマイクロチップをつける理由 完全室内飼いの猫ちゃんだと、マイクロチップの必要性を感じないかもしれませんが、どのような生活環境であっても装着はしておくべきです。・脱走・迷子・災害時こういった時に1つの安心材料となるのがマイクロチップなのです。玄関が開いた瞬間や、窓の隙間から思わぬタイミングで脱走してしまうケースも少なくありません。勤務先の動物病院にも保護された猫ちゃんが来院しますが、人懐っこく体も綺麗で迷子なんじゃないか…と感じる子もしばしばいます。ほとんどの動物病院がマイクロチップリーダーを持っていますので、マイクロチップさえ入っていればこの段階で飼い主さんにご連絡ができるのです。マイクロチップの義務化は、遺棄や外での繁殖を防止する意味も兼ねていますが、飼い主さんにとっては行方不明時の手がかりの1つとしての意味が大きくなります。 マイクロチップの手続き マイクロチップは、識別番号と飼い主さんの情報を紐付けすることが重要です。以下を参考に手続きをぜひ進めてみましょう!■マイクロチップを挿入している子を迎えたペットショップやブリーダーさんからお迎えした子であれば、既にマイクロチップは装着されているはずです。チップ内には繁殖元、あるいは販売元の情報が記憶されているので、まずは飼い主さんの情報に書き換えましょう。環境省の【犬と猫のマイクロチップ情報登録】のページから登録作業を行ってください。この時、販売元から渡される【登録証明書】が必要となりますので手元に用意しておくとスムーズです。■動物病院でマイクロチップを挿入した動物病院が発行する【装着証明書】を使って登録手続きを行います。■マイクロチップは入っているが、番号がわからないどこの動物病院でもいいので、リーダーを使ってマイクロチップが入っている事を伝え、その番号を確認してもらいましょう。その後【マイクロチップ識別番号証明書】という書類を発行してもらってください。これが装着証明書の代わりになります。■過去にマイクロチップを挿入しているが、環境省のデータベースに未登録こちらは【移行登録申請】の書類を提出します。ただ装着日や装着した獣医師の名前などが必要で、書類作成が難しい場合は上記のマイクロチップ識別番号証明書を発行してもらう手順でも問題ないでしょう。環境省:Q30移行登録手順どこに該当するのかわからない時は、直接問い合わせてみてくださいね。 装着するか迷ったときは マイクロチップを装着するか迷う方も多いと思います。体に電子チップをいれて大丈夫なのか、痛くはないのか、不安も心配もありますよね。個人的には、若く持病がない子にはぜひ積極的に取り入れて欲しいと思いますが、ハイシニアや持病がある子は、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。愛猫がいなくなり、涙を流す飼い主さんをたくさん見てきました。マイクロチップで飼い主さんを見つけたこともあります。ただ17年動物病院で勤務して、マイクロチップのせいで体調が悪くなった子は見たことがありません。いざという時に、飼い主さんと愛猫を繋ぐものは多いに越したことはありませんよね。まずは相談だけでもOKです。悩んだ時は、かかりつけの動物病院で話を聞いてみてくださいね。

ペット不可の住宅でペットを飼うとどうなる?リスクや対策方法とは
日本は何回かの大きなペットブームがあり、2000年ごろからペットと暮らせるマンションが急増しました。マンション住まいでペットと暮らす方も多くいらっしゃるかと思います。ですが、賃貸物件ではペット不可住宅の割合が圧倒的に多く、仮にペット可であったとしても賃料が割高なケースがほとんどです。既にペットと暮らしている方は住居探しに苦労してしまいますよね。実際のところ、ペット不可住宅でペットと暮らしている方は一定数いらっしゃいます。しかし、本当に発覚せずに過ごせるものなのか、もし見つかった場合どのような対応を求められるのか…。今回はそんな疑問についてまとめました。 目次■ペット連れで住める家とは■ペットがいることは発覚する?■ペット不可住宅でルールを破るリスク■ペットの行き場を無くさないために ペット連れで住める家とは https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/60/02/1000_F_168600257_oE3SFYWoK7YNs6dxaKYZZjWNmEIR1LKg.jpgまずペット可としている住宅にもいくつか種類があります。これは大家さんが入居者募集の際に明記するものなので事前にしっかり確認しておきましょう。・ペット相談可ペットの頭数や犬種、猫種、性格などによってペット連れを許可するかどうかを大家さんが判断します。例え1頭であっても他の入居者への配慮からNGになる可能性も。・ペット可ペット連れをOKとしている物件。ただし頭数やペットの体格にルールを設けている物件も多くあります。防音やペット用設備はなく、近隣トラブルが起きないよう目を配る必要があるでしょう。・ペット共生型住居ペットと暮らすことを前提に作られている住宅です。例えばペット専用の足洗い場や屋上ドッグランが設けられている、防音設備が整っているなど。飼い主さんにもペットにも嬉しい設備が整っている分賃料は割高となります。 ペットがいることは発覚する? ペット不可の住宅でペットを飼ったらバレるのか…これはやはり、見つかってしまう可能性の方がずっと高いです。お散歩に鳴き声、通院やトリミング、業者が自宅内に入ることもあるでしょう。その全てのタイミングでペットの存在を隠し通すのは無理があります。居住期間が長くなるほどボロが出てしまうはず。過去にペット不可のマンションに居住していた経験がありますが、猫ちゃんを飼育されていた方が鳴き声や臭いをきっかけに強制退去させられた現場を見たことがあります。せっかく愛すべきペットと暮らしているのに、余計な我慢をさせてしまったり、精神をすり減らすのは悲しいものですよね。安心した生活を送るためにも、適した住居選びが重要となります。 ペット不可住宅でルールを破るリスク 住宅の掲げたルールを破って暮らす場合、以下のようなリスクがあります。・近隣トラブルの発生・強制退去・賠償金や違約金の支払いアレルギーや苦手意識からあえて動物が入れない物件に入居している方もいますので、当然近隣トラブルは起きやすいでしょう。また契約書に違反時の賠償金発生の旨が記載されている物件も多くあります。強制退去になった場合は、待機期間なしで引っ越しするよう要求されてしまうというリスクがあり、路頭に迷ってしまう可能性も否めません。 ペットの行き場を無くさないために 基本的な事ですが、ペット可の物件を選ぶことが重要です。明記されていない物件でも、大家さんと交渉することで許可が得られる場合があります。大切なペットの存在を隠してしまうと、その後の生活に大きな支障をきたす可能性があるため、正直に相談し、受け入れてもらえる住まいを見つけましょう。また、犬や猫は不可でも、鳥やハムスター、フェレットやうさぎなどの小動物であれば飼育可能な物件もあります。ペット可であっても、近隣への配慮は忘れずに。たとえ静かな子であっても、適切な住環境を整えてあげることが大切です。
ペット不可の住宅でペットを飼うとどうなる?リスクや対策方法とは
日本は何回かの大きなペットブームがあり、2000年ごろからペットと暮らせるマンションが急増しました。マンション住まいでペットと暮らす方も多くいらっしゃるかと思います。ですが、賃貸物件ではペット不可住宅の割合が圧倒的に多く、仮にペット可であったとしても賃料が割高なケースがほとんどです。既にペットと暮らしている方は住居探しに苦労してしまいますよね。実際のところ、ペット不可住宅でペットと暮らしている方は一定数いらっしゃいます。しかし、本当に発覚せずに過ごせるものなのか、もし見つかった場合どのような対応を求められるのか…。今回はそんな疑問についてまとめました。 目次■ペット連れで住める家とは■ペットがいることは発覚する?■ペット不可住宅でルールを破るリスク■ペットの行き場を無くさないために ペット連れで住める家とは https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/60/02/1000_F_168600257_oE3SFYWoK7YNs6dxaKYZZjWNmEIR1LKg.jpgまずペット可としている住宅にもいくつか種類があります。これは大家さんが入居者募集の際に明記するものなので事前にしっかり確認しておきましょう。・ペット相談可ペットの頭数や犬種、猫種、性格などによってペット連れを許可するかどうかを大家さんが判断します。例え1頭であっても他の入居者への配慮からNGになる可能性も。・ペット可ペット連れをOKとしている物件。ただし頭数やペットの体格にルールを設けている物件も多くあります。防音やペット用設備はなく、近隣トラブルが起きないよう目を配る必要があるでしょう。・ペット共生型住居ペットと暮らすことを前提に作られている住宅です。例えばペット専用の足洗い場や屋上ドッグランが設けられている、防音設備が整っているなど。飼い主さんにもペットにも嬉しい設備が整っている分賃料は割高となります。 ペットがいることは発覚する? ペット不可の住宅でペットを飼ったらバレるのか…これはやはり、見つかってしまう可能性の方がずっと高いです。お散歩に鳴き声、通院やトリミング、業者が自宅内に入ることもあるでしょう。その全てのタイミングでペットの存在を隠し通すのは無理があります。居住期間が長くなるほどボロが出てしまうはず。過去にペット不可のマンションに居住していた経験がありますが、猫ちゃんを飼育されていた方が鳴き声や臭いをきっかけに強制退去させられた現場を見たことがあります。せっかく愛すべきペットと暮らしているのに、余計な我慢をさせてしまったり、精神をすり減らすのは悲しいものですよね。安心した生活を送るためにも、適した住居選びが重要となります。 ペット不可住宅でルールを破るリスク 住宅の掲げたルールを破って暮らす場合、以下のようなリスクがあります。・近隣トラブルの発生・強制退去・賠償金や違約金の支払いアレルギーや苦手意識からあえて動物が入れない物件に入居している方もいますので、当然近隣トラブルは起きやすいでしょう。また契約書に違反時の賠償金発生の旨が記載されている物件も多くあります。強制退去になった場合は、待機期間なしで引っ越しするよう要求されてしまうというリスクがあり、路頭に迷ってしまう可能性も否めません。 ペットの行き場を無くさないために 基本的な事ですが、ペット可の物件を選ぶことが重要です。明記されていない物件でも、大家さんと交渉することで許可が得られる場合があります。大切なペットの存在を隠してしまうと、その後の生活に大きな支障をきたす可能性があるため、正直に相談し、受け入れてもらえる住まいを見つけましょう。また、犬や猫は不可でも、鳥やハムスター、フェレットやうさぎなどの小動物であれば飼育可能な物件もあります。ペット可であっても、近隣への配慮は忘れずに。たとえ静かな子であっても、適切な住環境を整えてあげることが大切です。

2025年春目前!愛犬に今年必要な予防をおさらいしましょう
暖かい日が増え、少しずつ春の訪れを感じる季節になりました。春といえば、ワンちゃん達の予防シーズンの到来です。これまでにも記事で取り上げてきましたが、春の予防は種類が多く、混乱してしまう飼い主さんも少なくありません。そこで今回は、春の予防をあらためておさらいし、まとめてしっかり対策できるようにご紹介します! 目次■春の予防とは?■狂犬病予防接種■フィラリア検査と予防薬■健康診断タイミング■ノミマダニ予防■高齢な子や持病がある子は相談を 春の予防とは? 「春の予防」と一言でまとめてしまいがちですが、その内容は狂犬病予防、フィラリア予防、ノミマダニ予防と多岐に渡ります。春が予防シーズンとされるのは、自治体から一斉に狂犬病予防接種のお知らせが届く時期であると同時に、フィラリアやノミマダニ予防が必要となる時期が目前に迫っているためです。今のうちにまとめて対策しておくことで、愛犬に必要な予防を漏れなく済ませることができます。とはいえ「うちの子は混合ワクチンの時期でもある」「我が家は健康診断も一緒に受けている」といったケースもあり、さまざまな予防が重なることで混乱してしまうことも。そこで、1つ1つ整理しながら、今年必要な予防のをしっかり確認していきましょう。 狂犬病予防接種 狂犬病予防接種は、畜犬登録を行っているワンちゃんであれば必ず役所から接種のお知らせが届くシステムです。年に1度の接種が義務とされており、その区切りは【年度】となっています。前年度の接種時期に関わらず、新年度を迎えた4月にお知らせは一律発送され、11月頃までに接種完了の手続きが行われないと督促が届きます。これまで役所の窓口や動物病院で行われていた畜犬登録は、マイクロチップが義務化されて以降はマイクロチップの手続きをすることで自動で行われるようになりました。愛犬をお迎え後、まだ手続きされていないようであれば取り急ぎ済ませてしまいましょう。 関連ブログ[2025年最新版]狂犬病予防注射を打つ時期は?必要な手続きや金額とは フィラリア検査と予防薬 フィラリア予防は、毎月1回のお薬で愛犬をフィラリア症から守る大切な予防医療です。 予防期間は地域によって異なりますが、多くの地域では5月~12月とされ、暖かい地域では通年予防が推奨されています。この違いは、感染源である蚊が活動する時期に影響されるためです。 ただし、すべての蚊が危険なわけではなく、フィラリアの赤ちゃん(ミクロフィラリア)を持った蚊に刺された場合にのみ感染。愛犬の体内に入ったミクロフィラリアは約3か月かけて成長し、成虫のフィラリアへと育ちます。この期間内に予防薬を投与し、体内のフィラリア幼虫を駆除することで、発症を防ぐことがで可能です。そのため、蚊の発生時期に応じて予防開始・終了のタイミングに差が出るのです。 また、シーズン初めに予防薬を使う前には、フィラリア症に感染していないか血液検査が必要です。これは、万が一すでに感染していた場合、予防薬の投与によってショック症状を引き起こすリスクがあるためです。 予防薬にはさまざまなタイプがあるため、愛犬に合ったものを選んで無理なく続けましょう! 関連ブログ犬のフィラリア予防、病気の実態や飲み忘れ時の対応方法とは 健康診断タイミング 前述のフィラリア検査は、血液1滴ほどで済む簡単な検査ですが、せっかく採血をするのであれば少し多めに採血し、全身の健康チェックも行うのが「春の健康診断」です。 動物病院によっては、エコー検査やレントゲン検査など、人間ドックのような詳しい健康診断を受けられる場合もあります。もちろん、健康診断のタイミングは春に限らずいつでも可能ですが、この時期は費用が少し抑えられることも多いため、気になっている方はぜひ動物病院のスタッフに相談してみてください。 ワンちゃんの年齢は、人間の数倍のスピードで進んでいきます。例えば、2歳のワンちゃんは人間でいうと24歳、5歳なら40歳程度に相当します。私たちと同じように、ワンちゃんにも定期的な健康診断が大切です。健康チェックを習慣にすることで、大切な家族の健康を守りましょう! 関連ブログ春の健康診断!メリットや受診すべき愛犬の目安は? ノミマダニ予防 ノミ、マダニといった外部寄生虫も5月頃から予防を行います。フィラリア予防と同時スタートになるので最近は1つで全てが予防できるオールインワンタイプの予防薬が人気です。フィラリア症とは違いノミやマダニが出ない季節になれば予防は終了してもOK。ただし冬時期でもノミやマダニが付いてしまう子がチラホラいますので心配であれば通年予防でもいいですね。一般的には10~12月までと言われています。 関連ブログペットのノミ・マダニ予防、開始時期やお薬選びのポイントとは? 高齢な子や持病がある子は相談を 今年必要な予防について、しっかり把握できたでしょうか?高齢のワンちゃんや持病があるワンちゃんは、どの予防が適切かかかりつけ獣医師と相談することが大切です。高齢だからこそ健康診断が必要だと思うかもしれませんが、採血がストレスやトラウマになってしまう場合もあるため、獣医師がその判断を下すこともあります。もちろん、若くて元気な子であっても心配なことは遠慮せず相談しましょう。みんなが元気にで安心して一年を過ごせるように、春の予防をしっかり行いましょう!
2025年春目前!愛犬に今年必要な予防をおさらいしましょう
暖かい日が増え、少しずつ春の訪れを感じる季節になりました。春といえば、ワンちゃん達の予防シーズンの到来です。これまでにも記事で取り上げてきましたが、春の予防は種類が多く、混乱してしまう飼い主さんも少なくありません。そこで今回は、春の予防をあらためておさらいし、まとめてしっかり対策できるようにご紹介します! 目次■春の予防とは?■狂犬病予防接種■フィラリア検査と予防薬■健康診断タイミング■ノミマダニ予防■高齢な子や持病がある子は相談を 春の予防とは? 「春の予防」と一言でまとめてしまいがちですが、その内容は狂犬病予防、フィラリア予防、ノミマダニ予防と多岐に渡ります。春が予防シーズンとされるのは、自治体から一斉に狂犬病予防接種のお知らせが届く時期であると同時に、フィラリアやノミマダニ予防が必要となる時期が目前に迫っているためです。今のうちにまとめて対策しておくことで、愛犬に必要な予防を漏れなく済ませることができます。とはいえ「うちの子は混合ワクチンの時期でもある」「我が家は健康診断も一緒に受けている」といったケースもあり、さまざまな予防が重なることで混乱してしまうことも。そこで、1つ1つ整理しながら、今年必要な予防のをしっかり確認していきましょう。 狂犬病予防接種 狂犬病予防接種は、畜犬登録を行っているワンちゃんであれば必ず役所から接種のお知らせが届くシステムです。年に1度の接種が義務とされており、その区切りは【年度】となっています。前年度の接種時期に関わらず、新年度を迎えた4月にお知らせは一律発送され、11月頃までに接種完了の手続きが行われないと督促が届きます。これまで役所の窓口や動物病院で行われていた畜犬登録は、マイクロチップが義務化されて以降はマイクロチップの手続きをすることで自動で行われるようになりました。愛犬をお迎え後、まだ手続きされていないようであれば取り急ぎ済ませてしまいましょう。 関連ブログ[2025年最新版]狂犬病予防注射を打つ時期は?必要な手続きや金額とは フィラリア検査と予防薬 フィラリア予防は、毎月1回のお薬で愛犬をフィラリア症から守る大切な予防医療です。 予防期間は地域によって異なりますが、多くの地域では5月~12月とされ、暖かい地域では通年予防が推奨されています。この違いは、感染源である蚊が活動する時期に影響されるためです。 ただし、すべての蚊が危険なわけではなく、フィラリアの赤ちゃん(ミクロフィラリア)を持った蚊に刺された場合にのみ感染。愛犬の体内に入ったミクロフィラリアは約3か月かけて成長し、成虫のフィラリアへと育ちます。この期間内に予防薬を投与し、体内のフィラリア幼虫を駆除することで、発症を防ぐことがで可能です。そのため、蚊の発生時期に応じて予防開始・終了のタイミングに差が出るのです。 また、シーズン初めに予防薬を使う前には、フィラリア症に感染していないか血液検査が必要です。これは、万が一すでに感染していた場合、予防薬の投与によってショック症状を引き起こすリスクがあるためです。 予防薬にはさまざまなタイプがあるため、愛犬に合ったものを選んで無理なく続けましょう! 関連ブログ犬のフィラリア予防、病気の実態や飲み忘れ時の対応方法とは 健康診断タイミング 前述のフィラリア検査は、血液1滴ほどで済む簡単な検査ですが、せっかく採血をするのであれば少し多めに採血し、全身の健康チェックも行うのが「春の健康診断」です。 動物病院によっては、エコー検査やレントゲン検査など、人間ドックのような詳しい健康診断を受けられる場合もあります。もちろん、健康診断のタイミングは春に限らずいつでも可能ですが、この時期は費用が少し抑えられることも多いため、気になっている方はぜひ動物病院のスタッフに相談してみてください。 ワンちゃんの年齢は、人間の数倍のスピードで進んでいきます。例えば、2歳のワンちゃんは人間でいうと24歳、5歳なら40歳程度に相当します。私たちと同じように、ワンちゃんにも定期的な健康診断が大切です。健康チェックを習慣にすることで、大切な家族の健康を守りましょう! 関連ブログ春の健康診断!メリットや受診すべき愛犬の目安は? ノミマダニ予防 ノミ、マダニといった外部寄生虫も5月頃から予防を行います。フィラリア予防と同時スタートになるので最近は1つで全てが予防できるオールインワンタイプの予防薬が人気です。フィラリア症とは違いノミやマダニが出ない季節になれば予防は終了してもOK。ただし冬時期でもノミやマダニが付いてしまう子がチラホラいますので心配であれば通年予防でもいいですね。一般的には10~12月までと言われています。 関連ブログペットのノミ・マダニ予防、開始時期やお薬選びのポイントとは? 高齢な子や持病がある子は相談を 今年必要な予防について、しっかり把握できたでしょうか?高齢のワンちゃんや持病があるワンちゃんは、どの予防が適切かかかりつけ獣医師と相談することが大切です。高齢だからこそ健康診断が必要だと思うかもしれませんが、採血がストレスやトラウマになってしまう場合もあるため、獣医師がその判断を下すこともあります。もちろん、若くて元気な子であっても心配なことは遠慮せず相談しましょう。みんなが元気にで安心して一年を過ごせるように、春の予防をしっかり行いましょう!
