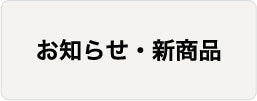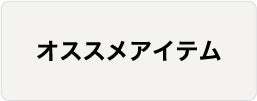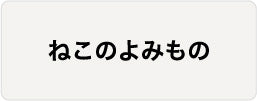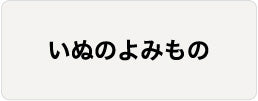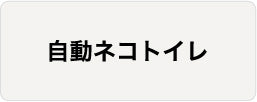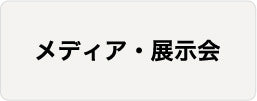OFT STORE BLOG

マンションでペットと快適に過ごすために知っておきたいポイントとは?
ひと昔前までは、番犬として外で過ごしていたワンちゃんや、家の中と外を自由に行き来していた猫ちゃんですが、近年では共に室内で飼育する人が大半を占めるようになりました。マンションでペットを飼育されている方も今は少なくありません。最近では、ペット可マンションだけでなく、人もペットも快適に暮らせるように考えて造られたペットコンセプトマンションが建てられるほど飼育環境は激変しています。需要が高まるペットコンセプトマンションとは?またペットとの共同生活で注意する点について確認していきましょう。 ペット共用設備とは ▲一般的なペット用足洗い場 ペットコンセプトマンションの特徴としては、マンション自体がペットと暮らすことを前提に造られているため設備が充実しているところです。それぞれのマンションによっては異なりますが、一般的には• 足洗い場• グルーミングルーム• ドッグラン• 汚物ダスト• リードフックがあり、まさにペットの飼い主さんにとって痒い所に手が届くような配慮がなされています。また、ドッグランはペットの運動だけでなく、飼い主さん同士の情報交換の場としても利用できるのも嬉しいですよね。共有部だけでなく、各部屋にも足腰に負担がかからない床材を使用していたり、脱臭機能が備わっていたりとペット目線で考えられて設計されているからこそ快適に暮らせるのです。 マンションの管理規約 ペットと共にマンションで生活する場合に必ず確認しておきたいことが、マンションの管理規約です。規約によっては、飼育可能な種類、飼育頭数や大きさの制限など様々です。後々になってトラブルにならないよう、不明な点は必ずオーナーさんや管理会社に事前に確認をしておきましょう。また、規約が変更された場合もしっかり目を通すことが大切です。自己判断は、規約違反になるだけでなく近隣の住人からの信用も失いかねません。災害時の避難経路の確保など、いざという時に必要となるため、あらかじめ正しく申請する義務があります。 ペットでのよくあるトラブル いくらペット可マンションとはいえペットと自由に住んで良いということではなく、住民全員が気持ちよく住めるよう守るべきルールがあります。ペット可マンションには、ペットを飼っている方もいない方も一緒に生活をしているため、お互いの気持ちを理解し合うことが大切です。よくある近隣トラブルとして• 鳴き声などの騒音• 共有部での排泄やノーリード• ニオイ• ペット飼育者の規約違反などです。特に犬を飼育していない方にとっては、長時間に渡る鳴き声には耐えがたいものがあります。ほんの少しの配慮で未然に防ぐことができるトラブルから、ワンちゃんの躾やトレーニングが必要なものまで様々です。ペットも大切な家族、パートナーだからこそ、飼い主さんもモラルやルールを守って、住みやすい環境を作ってあげたいですね。 住まいの工夫 ペットと共にマンションで暮らす方が増えている今、限られた空間でも快適に過ごせるよう室内の工夫が重要になってきます。ペット達や飼い主さんが楽しく暮らせるために、見直したいポイントとはどのようなものでしょうか。■安全対策フローリングの場合、ペットが滑ってケガをしてしまう可能性があるため、床材を滑らない素材にかえてみるのも良いでしょう。カーペットやラグを敷くだけでも随分変わってきます♪また、ベランダの行き来を自由にする子には、脱走防止や落下防止対策も必要になります。ペットが通れそうな隙間をなくし、柵やネットで囲ってあげましょう。ベランダ用の落下防止ネットも、簡単に購入できますので是非活用してみて下さいね。ただし、ジャンプ力のある猫ちゃんやワンちゃんですと、飛び越えてしまう危険もあるため、ベランダ自体に出さないことも考慮しましょう。■ストレス対策犬・猫どちらの場合でも一人で落ち着けるプライベート空間を確保してあげましょう。運動不足にならないよう立体的な動きができるよう工夫し、猫ちゃんの場合は特に上下運動ができるキャットタワーなどの用意も必要です。また、トイレや寝床は出入りが激しいと落ち着かずストレスの原因ともなりますので、設置場所も気にかけてあげて下さいね。■その他悪臭が部屋に充満しないよう、こまめに換気を行いましょう。また、ニオイだけでなく、湿度によって病気になってしまうこともあるため通気・換気は良くしておいてください。ニオイや足音などの騒音によってトラブルが発生する場合もあります。カーペットやラグ、また空気清浄機等を活用してみましょう。 少子化や高齢化、また単身世帯が増えたことに比例してか、東京都を中心に全国でも年々マンション化率も高くなっています。マンションは狭いから...とペットと過ごすのに不便だと感じる方もいるかもしれません。しかし、工夫次第では快適に過ごすことができます。モラルやマナーをしっかり守って、可愛いペット達と素敵な共同生活を楽しみましょう♪ ▼ この記事を書いたのは ▼
マンションでペットと快適に過ごすために知っておきたいポイントとは?
ひと昔前までは、番犬として外で過ごしていたワンちゃんや、家の中と外を自由に行き来していた猫ちゃんですが、近年では共に室内で飼育する人が大半を占めるようになりました。マンションでペットを飼育されている方も今は少なくありません。最近では、ペット可マンションだけでなく、人もペットも快適に暮らせるように考えて造られたペットコンセプトマンションが建てられるほど飼育環境は激変しています。需要が高まるペットコンセプトマンションとは?またペットとの共同生活で注意する点について確認していきましょう。 ペット共用設備とは ▲一般的なペット用足洗い場 ペットコンセプトマンションの特徴としては、マンション自体がペットと暮らすことを前提に造られているため設備が充実しているところです。それぞれのマンションによっては異なりますが、一般的には• 足洗い場• グルーミングルーム• ドッグラン• 汚物ダスト• リードフックがあり、まさにペットの飼い主さんにとって痒い所に手が届くような配慮がなされています。また、ドッグランはペットの運動だけでなく、飼い主さん同士の情報交換の場としても利用できるのも嬉しいですよね。共有部だけでなく、各部屋にも足腰に負担がかからない床材を使用していたり、脱臭機能が備わっていたりとペット目線で考えられて設計されているからこそ快適に暮らせるのです。 マンションの管理規約 ペットと共にマンションで生活する場合に必ず確認しておきたいことが、マンションの管理規約です。規約によっては、飼育可能な種類、飼育頭数や大きさの制限など様々です。後々になってトラブルにならないよう、不明な点は必ずオーナーさんや管理会社に事前に確認をしておきましょう。また、規約が変更された場合もしっかり目を通すことが大切です。自己判断は、規約違反になるだけでなく近隣の住人からの信用も失いかねません。災害時の避難経路の確保など、いざという時に必要となるため、あらかじめ正しく申請する義務があります。 ペットでのよくあるトラブル いくらペット可マンションとはいえペットと自由に住んで良いということではなく、住民全員が気持ちよく住めるよう守るべきルールがあります。ペット可マンションには、ペットを飼っている方もいない方も一緒に生活をしているため、お互いの気持ちを理解し合うことが大切です。よくある近隣トラブルとして• 鳴き声などの騒音• 共有部での排泄やノーリード• ニオイ• ペット飼育者の規約違反などです。特に犬を飼育していない方にとっては、長時間に渡る鳴き声には耐えがたいものがあります。ほんの少しの配慮で未然に防ぐことができるトラブルから、ワンちゃんの躾やトレーニングが必要なものまで様々です。ペットも大切な家族、パートナーだからこそ、飼い主さんもモラルやルールを守って、住みやすい環境を作ってあげたいですね。 住まいの工夫 ペットと共にマンションで暮らす方が増えている今、限られた空間でも快適に過ごせるよう室内の工夫が重要になってきます。ペット達や飼い主さんが楽しく暮らせるために、見直したいポイントとはどのようなものでしょうか。■安全対策フローリングの場合、ペットが滑ってケガをしてしまう可能性があるため、床材を滑らない素材にかえてみるのも良いでしょう。カーペットやラグを敷くだけでも随分変わってきます♪また、ベランダの行き来を自由にする子には、脱走防止や落下防止対策も必要になります。ペットが通れそうな隙間をなくし、柵やネットで囲ってあげましょう。ベランダ用の落下防止ネットも、簡単に購入できますので是非活用してみて下さいね。ただし、ジャンプ力のある猫ちゃんやワンちゃんですと、飛び越えてしまう危険もあるため、ベランダ自体に出さないことも考慮しましょう。■ストレス対策犬・猫どちらの場合でも一人で落ち着けるプライベート空間を確保してあげましょう。運動不足にならないよう立体的な動きができるよう工夫し、猫ちゃんの場合は特に上下運動ができるキャットタワーなどの用意も必要です。また、トイレや寝床は出入りが激しいと落ち着かずストレスの原因ともなりますので、設置場所も気にかけてあげて下さいね。■その他悪臭が部屋に充満しないよう、こまめに換気を行いましょう。また、ニオイだけでなく、湿度によって病気になってしまうこともあるため通気・換気は良くしておいてください。ニオイや足音などの騒音によってトラブルが発生する場合もあります。カーペットやラグ、また空気清浄機等を活用してみましょう。 少子化や高齢化、また単身世帯が増えたことに比例してか、東京都を中心に全国でも年々マンション化率も高くなっています。マンションは狭いから...とペットと過ごすのに不便だと感じる方もいるかもしれません。しかし、工夫次第では快適に過ごすことができます。モラルやマナーをしっかり守って、可愛いペット達と素敵な共同生活を楽しみましょう♪ ▼ この記事を書いたのは ▼

びっくり仰天!動物病院エピソード~生命の不思議編
動物病院にいらっしゃる様々な患者様とお話する時間は、私たちスタッフにとって大変楽しい時間です。新しい家族が増えたとき、心配事があったとき、ご相談頂けることは嬉しいことですし解決した時は一層喜びを感じます。今回はそんなスタッフがつい笑顔になってしまった病院エピソードをご紹介します。 新しい家族を一頭迎えたはずが… 先住犬を老衰で亡くされた飼い主さん。気持ちが落ち着いた頃、ご家族とご相談のうえ新しい家族を迎え入れる事を決心されました。新しく家族となったのは元繁殖犬で、保護された経歴をもつ女の子のワンちゃんです。とても小柄で臆病な性格でしたが、飼い主さんご家族がとても温和で優しい方だったこともあり、少しずつ新しい生活になじんでいけたようです。初日にワンちゃんを連れご挨拶に来ていただき、スタッフも大変嬉しく思っていました。ところが1週間ほどすると打って変わって体調が悪いとご来院されたのです。食欲が落ち、動かない。そしてお腹が腫れているというのです。お腹の腫れは重篤な病気のサインということもあります。早速エコーでお腹の中を確認しようと仰向けの姿勢になってもらいました。すると…エコーをあてた院長が一言『おめでとうございます。赤ちゃんです!!』飼い主さんはびっくり仰天。どうも保護された時点で妊娠していたようで、気が付かれないまま譲渡されたようでした。あれよと言う間に出産の日が訪れ無事に2頭の赤ちゃんを出産。今まで繁殖犬だったため出産した我が子とすぐに離ればなれにされていたワンちゃんでしたが、その後3頭で仲良く一緒に暮らすことができ、すっかりお転婆さんに成長してくれました♪ 5頭妊娠していたはずが… ダックスフンドのカップルを飼われていた飼い主さん。2頭はとても仲が良く、妊娠したようだとご来院いただきました。ダックスフンドは難産になる事も多く、帝王切開になることも少なくありません。飼い主さんはお仕事がお忙しいため予定日前後は出産管理として入院をご希望されていました。小型犬の平均妊娠頭数は3~4頭です。助産につくスタッフも必要ですから出産前にエコーとレントゲンにて頭数の確認が行われました。お腹の中には小さな赤ちゃんが沢山いるようで、重なって写る事もあり正確な頭数はわかりませんでしたが、どうやら5頭、もしくはそれ以上いるようでした。そして予定日前日に入院、予定通りに陣痛が来ました。とても頑張り屋さんでスタッフの手も借りず、出産してはすぐに赤ちゃんの処理を自分でこなしていきます。ところが5頭目が出てきたあとも出産が終わる気配が一向にありません。1頭、また1頭と次々に子犬が誕生します。そして最終的に生まれた頭数はなんと…9頭!みんな元気いっぱいです。お世話で忙しいママと元気いっぱいの9頭の子犬ちゃんは、しばらく病院にお泊りです。すっかりスタッフはメロメロになってしまい出勤時、退勤時、夜勤時にはみんながこぞって大家族のもとへ通うようになりました。その後、みんな仲良く新しいおうちで賑やかに暮らしています!とご報告をいただきました。 お兄ちゃんになったワンちゃん お次はご夫婦にとても可愛がられていた男の子のチワワです。お二人の愛情を一心にうけてスクスク育っていましたが、ある日家族が増えることになりました。そう、お二人のお子さん、人間の赤ちゃんです。実はこのチワワちゃんちょっぴり噛み癖がありヤキモチ焼きな性格で、ご出産前から飼い主さんは心配されているようでした。少しずつ接触させてみてくださいね、とお話していたのですが産後はやはり中々ご来院できず、半年ほどたってようやくお会いすることができました。すると最初はヤキモチを焼いていたチワワちゃんがすっかりお兄ちゃん化しているというではないですか!お布団を運んであげたりおもちゃを貸してあげたりと大変微笑ましい成長を遂げていました。 その後、赤ちゃんが動ける時期になると、おやつを奪われたり、叩かれたり(赤ちゃん本人は撫でているつもりなのでしょうね)とどうやらお兄ちゃん業も大変なよう。ご来院頂くときはチワワちゃんが主役、お母さんを独り占めできることもあり以前よりスタッフにも友好的になってくれた、というオマケが付いてきました。今ではすっかり遊び友達として仲良くしているようです♪ 不測の事態が起きたときはまずご相談ください 今回はどのケースも素敵な結果に終わりましたが出産など新しい家族が増えるときは不測の事態が起こることも想定されます。そんな時は悩むより先に動物病院へご相談くださいね。特に出産は人間同様命がけですから、飼い主さんと病院スタッフが連携しておくことが大切です。どんな些細な事でも不安な時は動物病院を頼ってくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
びっくり仰天!動物病院エピソード~生命の不思議編
動物病院にいらっしゃる様々な患者様とお話する時間は、私たちスタッフにとって大変楽しい時間です。新しい家族が増えたとき、心配事があったとき、ご相談頂けることは嬉しいことですし解決した時は一層喜びを感じます。今回はそんなスタッフがつい笑顔になってしまった病院エピソードをご紹介します。 新しい家族を一頭迎えたはずが… 先住犬を老衰で亡くされた飼い主さん。気持ちが落ち着いた頃、ご家族とご相談のうえ新しい家族を迎え入れる事を決心されました。新しく家族となったのは元繁殖犬で、保護された経歴をもつ女の子のワンちゃんです。とても小柄で臆病な性格でしたが、飼い主さんご家族がとても温和で優しい方だったこともあり、少しずつ新しい生活になじんでいけたようです。初日にワンちゃんを連れご挨拶に来ていただき、スタッフも大変嬉しく思っていました。ところが1週間ほどすると打って変わって体調が悪いとご来院されたのです。食欲が落ち、動かない。そしてお腹が腫れているというのです。お腹の腫れは重篤な病気のサインということもあります。早速エコーでお腹の中を確認しようと仰向けの姿勢になってもらいました。すると…エコーをあてた院長が一言『おめでとうございます。赤ちゃんです!!』飼い主さんはびっくり仰天。どうも保護された時点で妊娠していたようで、気が付かれないまま譲渡されたようでした。あれよと言う間に出産の日が訪れ無事に2頭の赤ちゃんを出産。今まで繁殖犬だったため出産した我が子とすぐに離ればなれにされていたワンちゃんでしたが、その後3頭で仲良く一緒に暮らすことができ、すっかりお転婆さんに成長してくれました♪ 5頭妊娠していたはずが… ダックスフンドのカップルを飼われていた飼い主さん。2頭はとても仲が良く、妊娠したようだとご来院いただきました。ダックスフンドは難産になる事も多く、帝王切開になることも少なくありません。飼い主さんはお仕事がお忙しいため予定日前後は出産管理として入院をご希望されていました。小型犬の平均妊娠頭数は3~4頭です。助産につくスタッフも必要ですから出産前にエコーとレントゲンにて頭数の確認が行われました。お腹の中には小さな赤ちゃんが沢山いるようで、重なって写る事もあり正確な頭数はわかりませんでしたが、どうやら5頭、もしくはそれ以上いるようでした。そして予定日前日に入院、予定通りに陣痛が来ました。とても頑張り屋さんでスタッフの手も借りず、出産してはすぐに赤ちゃんの処理を自分でこなしていきます。ところが5頭目が出てきたあとも出産が終わる気配が一向にありません。1頭、また1頭と次々に子犬が誕生します。そして最終的に生まれた頭数はなんと…9頭!みんな元気いっぱいです。お世話で忙しいママと元気いっぱいの9頭の子犬ちゃんは、しばらく病院にお泊りです。すっかりスタッフはメロメロになってしまい出勤時、退勤時、夜勤時にはみんながこぞって大家族のもとへ通うようになりました。その後、みんな仲良く新しいおうちで賑やかに暮らしています!とご報告をいただきました。 お兄ちゃんになったワンちゃん お次はご夫婦にとても可愛がられていた男の子のチワワです。お二人の愛情を一心にうけてスクスク育っていましたが、ある日家族が増えることになりました。そう、お二人のお子さん、人間の赤ちゃんです。実はこのチワワちゃんちょっぴり噛み癖がありヤキモチ焼きな性格で、ご出産前から飼い主さんは心配されているようでした。少しずつ接触させてみてくださいね、とお話していたのですが産後はやはり中々ご来院できず、半年ほどたってようやくお会いすることができました。すると最初はヤキモチを焼いていたチワワちゃんがすっかりお兄ちゃん化しているというではないですか!お布団を運んであげたりおもちゃを貸してあげたりと大変微笑ましい成長を遂げていました。 その後、赤ちゃんが動ける時期になると、おやつを奪われたり、叩かれたり(赤ちゃん本人は撫でているつもりなのでしょうね)とどうやらお兄ちゃん業も大変なよう。ご来院頂くときはチワワちゃんが主役、お母さんを独り占めできることもあり以前よりスタッフにも友好的になってくれた、というオマケが付いてきました。今ではすっかり遊び友達として仲良くしているようです♪ 不測の事態が起きたときはまずご相談ください 今回はどのケースも素敵な結果に終わりましたが出産など新しい家族が増えるときは不測の事態が起こることも想定されます。そんな時は悩むより先に動物病院へご相談くださいね。特に出産は人間同様命がけですから、飼い主さんと病院スタッフが連携しておくことが大切です。どんな些細な事でも不安な時は動物病院を頼ってくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

愛が溢れる飼い主さん!動物病院での珍エピソード
動物病院に勤めていると、ペット達と飼い主さんの数だけ物語があります。『夫婦は似てくる』とよく言いますが、不思議なことに飼い主さんとペット達も似ている!と感じる事が多くあります。それはきっと家族として堅い絆が結ばれているからこそなのでしょう。病気やケガ、予防接種など動物病院に足を運ぶ理由は様々ですが、愛が溢れているが故のほっこりしてしまう場面や事件も!今回はそんなエピソードをご紹介していきます。 骨折!?足を痛がる本当の理由とは? 可愛らしいチワワちゃんを慌てて連れていらっしゃった奥様。来院主訴を確認すると『後ろ足を地面につけない』とのこと。足を完全にあげ、全く地面に着くことができない時は骨折の可能性も高いためスタッフにも緊張が走ります。診察前に看護師である私が問診を取るために飼い主さんを診察室の中へお呼びしました。チワワちゃんは確かに後ろ足をあげ、全く地面に着くことができないようです。でもその割に痛がる様子もなく、それどころか尻尾を振って大変ご機嫌なご様子。違和感を感じ「足、少し見せてもらってもいいかな?」と声をかけながら後ろ足を確認すると…何やら肉球にべったりとくっついているではありませんか。「お母さん、これのせいかなと思うのですが…お心当たりありますか?」と伺うと、飼い主さんは一瞬絶句したあと「これ…おばあちゃんの…ピップ〇レキバン…!」と絞り出すように答えてくださいました。スタッフの緊張も解け途端に和やかな雰囲気に。その後肉球が傷つかないようピップ〇レキバンを剥がし元気に帰宅していかれました。 まさかガン!?涙目の飼い主さんに告げられたのは… お次にいらしたのは若いお兄さんと女の子の猫ちゃんペアの患者様です。お一人暮らしの大切なパートナーとして猫ちゃんを迎え入れ、健診や予防にも熱心に通っていただいていました。とても可愛がられているご様子がスタッフにも伝わってくるような素敵な飼い主様です。ところがその日は浮かない表情のお兄さん、診察室で事情を聞くと突然お腹にしこりが沢山できてしまったとのこと。来院前にインターネットで検索し悪性腫瘍なのではないかと不安になってしまったそうです。猫ちゃんはまだ若く、避妊手術も若齢で済ませていたので(ガンや乳腺腫瘍の可能性は低そうだけど…)と思いながらもまずは患部を見せてもらうことにしました。キャリーバックから猫ちゃんを出すお兄さんは今にも泣きだしてしまいそうなほど思い詰めたお顔をされています…。「これです…こことここと、あと毛に隠れてるんですけどこっちにも…」とお兄さんに患部を見せて頂き、スタッフ一同失礼ながらもホッと安心しました。それは腫瘍でもなんでもなかったのです。「これは……全部乳首、ですね!!」お伝えするとお兄さんは驚きながら「えっ!?猫にも乳首、あるんですか!?」と言いながらも安心したようで、満面の笑みを見せてくださいました。その後はせっかく来たので…。と検診を受け無事ご帰宅頂きました! 飼い主さんが好きすぎて食べてしまったもの 最後は飼い主が大好きなゴールデンレトリバーちゃんのお話。子犬期から飼い主さんにべったりだったこのワンちゃん。体が大きくなっても飼い主さんへの愛は大きくなる一方のようで来院時はなんと抱っこでいらっしゃるほどラブラブが印象的な患者様でした。ところがこの大きな愛がとんでもない事件を巻き起こしてしまったのです。事件はワンちゃんがお留守番中に起きたようです。寂しくなってしまったワンちゃんは飼い主さんの丸めた靴下をかじって遊び寂しさを紛らわせていました。実は飼い主さんの靴下は特別匂いが強く、遊び道具として好むワンちゃんは沢山います。ところが遊びが過熱したワンちゃんはその靴下をゴクン!と飲み込んでしまったのです。翌日、お腹の中で靴下が詰まったことにより嘔吐症状が始まりました。靴下が見当たらないことに気が付いた飼い主さんは大慌てでご来院。時間が経過していたこともあり即日で麻酔下での摘出処置となってしまいました。処置は無事成功し、靴下も摘出されましたが念のため入院しなくてはいけません。離れるときはお互いに寂しさいっぱいの表情でしたがワンちゃんの回復も早く、その後元気に退院していかれました。 どんなことでも是非動物病院へ 我が子が大切だからこそ、いざという時はパニックになってしまうものですよね。動物病院のスタッフはプロでもありますが、中身は皆さまと同じく動物が大好きな人間ですからそのお気持ちもよくよく理解しています。どんな些細な事でも抱え込まず気軽に受診してみてくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
愛が溢れる飼い主さん!動物病院での珍エピソード
動物病院に勤めていると、ペット達と飼い主さんの数だけ物語があります。『夫婦は似てくる』とよく言いますが、不思議なことに飼い主さんとペット達も似ている!と感じる事が多くあります。それはきっと家族として堅い絆が結ばれているからこそなのでしょう。病気やケガ、予防接種など動物病院に足を運ぶ理由は様々ですが、愛が溢れているが故のほっこりしてしまう場面や事件も!今回はそんなエピソードをご紹介していきます。 骨折!?足を痛がる本当の理由とは? 可愛らしいチワワちゃんを慌てて連れていらっしゃった奥様。来院主訴を確認すると『後ろ足を地面につけない』とのこと。足を完全にあげ、全く地面に着くことができない時は骨折の可能性も高いためスタッフにも緊張が走ります。診察前に看護師である私が問診を取るために飼い主さんを診察室の中へお呼びしました。チワワちゃんは確かに後ろ足をあげ、全く地面に着くことができないようです。でもその割に痛がる様子もなく、それどころか尻尾を振って大変ご機嫌なご様子。違和感を感じ「足、少し見せてもらってもいいかな?」と声をかけながら後ろ足を確認すると…何やら肉球にべったりとくっついているではありませんか。「お母さん、これのせいかなと思うのですが…お心当たりありますか?」と伺うと、飼い主さんは一瞬絶句したあと「これ…おばあちゃんの…ピップ〇レキバン…!」と絞り出すように答えてくださいました。スタッフの緊張も解け途端に和やかな雰囲気に。その後肉球が傷つかないようピップ〇レキバンを剥がし元気に帰宅していかれました。 まさかガン!?涙目の飼い主さんに告げられたのは… お次にいらしたのは若いお兄さんと女の子の猫ちゃんペアの患者様です。お一人暮らしの大切なパートナーとして猫ちゃんを迎え入れ、健診や予防にも熱心に通っていただいていました。とても可愛がられているご様子がスタッフにも伝わってくるような素敵な飼い主様です。ところがその日は浮かない表情のお兄さん、診察室で事情を聞くと突然お腹にしこりが沢山できてしまったとのこと。来院前にインターネットで検索し悪性腫瘍なのではないかと不安になってしまったそうです。猫ちゃんはまだ若く、避妊手術も若齢で済ませていたので(ガンや乳腺腫瘍の可能性は低そうだけど…)と思いながらもまずは患部を見せてもらうことにしました。キャリーバックから猫ちゃんを出すお兄さんは今にも泣きだしてしまいそうなほど思い詰めたお顔をされています…。「これです…こことここと、あと毛に隠れてるんですけどこっちにも…」とお兄さんに患部を見せて頂き、スタッフ一同失礼ながらもホッと安心しました。それは腫瘍でもなんでもなかったのです。「これは……全部乳首、ですね!!」お伝えするとお兄さんは驚きながら「えっ!?猫にも乳首、あるんですか!?」と言いながらも安心したようで、満面の笑みを見せてくださいました。その後はせっかく来たので…。と検診を受け無事ご帰宅頂きました! 飼い主さんが好きすぎて食べてしまったもの 最後は飼い主が大好きなゴールデンレトリバーちゃんのお話。子犬期から飼い主さんにべったりだったこのワンちゃん。体が大きくなっても飼い主さんへの愛は大きくなる一方のようで来院時はなんと抱っこでいらっしゃるほどラブラブが印象的な患者様でした。ところがこの大きな愛がとんでもない事件を巻き起こしてしまったのです。事件はワンちゃんがお留守番中に起きたようです。寂しくなってしまったワンちゃんは飼い主さんの丸めた靴下をかじって遊び寂しさを紛らわせていました。実は飼い主さんの靴下は特別匂いが強く、遊び道具として好むワンちゃんは沢山います。ところが遊びが過熱したワンちゃんはその靴下をゴクン!と飲み込んでしまったのです。翌日、お腹の中で靴下が詰まったことにより嘔吐症状が始まりました。靴下が見当たらないことに気が付いた飼い主さんは大慌てでご来院。時間が経過していたこともあり即日で麻酔下での摘出処置となってしまいました。処置は無事成功し、靴下も摘出されましたが念のため入院しなくてはいけません。離れるときはお互いに寂しさいっぱいの表情でしたがワンちゃんの回復も早く、その後元気に退院していかれました。 どんなことでも是非動物病院へ 我が子が大切だからこそ、いざという時はパニックになってしまうものですよね。動物病院のスタッフはプロでもありますが、中身は皆さまと同じく動物が大好きな人間ですからそのお気持ちもよくよく理解しています。どんな些細な事でも抱え込まず気軽に受診してみてくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

ペット保険は必要?入るタイミングや選び方
皆さんは【ペット保険】に加入されていますか?私が動物看護師になったばかりの14年前は、今ほどペット保険はポピュラーではなく、加入されている方もそこまで多くありませんでした。しかし、年数を重ねるほど加入されている方が増えてきたように思います。今では多くの会社さんがペット保険を売り出しており、いざ加入しようと思っても悩んでしまう方も多いかと思います。そこで今回はペット保険のメリットやデメリット、注意ポイントなどをまとめてみました。 ペット保険とは? 私たち人間は、健康保険が効く保険診療ですが、ペット達はどうでしょうか?動物病院での診療は【自由診療】といわれ公的な保険システムは存在していません。全額飼い主さんがお支払いを行い、診療価格も各動物病院が自由に決める事ができます。ゆえに手術や入院、長期に渡る通院、内服治療となると飼い主さんにかかる金銭的負担が大きくなってしまいます。そこで活躍してくれるのがペット保険。毎月の保険料を支払う事でペット達の通院時に診療費が補償されるものです。様々なプランが用意されていますがペットの年齢や持病によって加入できるプランが制限される場合もあります。なおワクチンや避妊、去勢手術、健康診断など予防医療に該当するものは保険対象外となります。 加入するメリット 最大のメリットは予期せぬ病気や手術でも金額的負担を最小限に抑えられることです。言い換えれば選択できる治療方法の幅が広がる事ともいえます。生涯一度も病院にかからず健康で過ごすことができれば一番良いですが、年齢を重ねていくうちに病気が出てくるのは自然な事です。できる治療は全てしてあげたい飼い主さんにとって、ペット保険は背中を押す強い味方となってくれます。 加入するデメリット デメリットとしては掛け捨てであること、窓口清算ができないことなどがあげられます。貯蓄型保険がある人間とは異なりペットちゃん達は掛け捨て保険が基本となります。病気をしなければ保険を使う機会もありませんから保険料が勿体ない、と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。また窓口清算ができない保険も多く一度飼い主さんが全額支払い、後日保険会社に申請、その後補償額が振り込まれる、というのが一般的な流れになります。現状窓口清算ができる保険会社さんは限られており、取り扱っていない動物病院さんも多いため毎回の申請手続きが面倒であることはデメリットといえるかもしれません。 加入するタイミングやポイント ペット保険はシニアになるほど加入が難しくなっていきます。また加入できても持病は免責事項として補償対象外になってしまうことも。若いうちは不要と思いがちですが、持病などがないうちから加入しておくとシニア期以降も安心です。一番大切なことは飼い主さんに負担がなく加入できる保険であることです。安心代として月にかけられる金額を算出し、そこに合わせて保険プランを探してみましょう。 保険料が年数を重ねるごとにあがっていくケースも多いため将来的にいくらぐらいの保険料になるかも問い合わせておくと確実です。最近ではシニアから加入できるプランを出している保険会社さんもありますので加入希望の方は諦めずにチェックしてみてくださいね。 無理のない保険料を目安にペット保険選びを 動物病院で勤務していると全然病気しないから!と保険を解約した翌月に体調を壊してしまった…なんて子がいたりします。万が一の時にかかる負担を無くすためのペット保険ですから、月々の保険料が負担になってしまっては元も子もありません。ペットの年齢や体調、かけられる金額を考慮してペット保険を検討してみましょう。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
ペット保険は必要?入るタイミングや選び方
皆さんは【ペット保険】に加入されていますか?私が動物看護師になったばかりの14年前は、今ほどペット保険はポピュラーではなく、加入されている方もそこまで多くありませんでした。しかし、年数を重ねるほど加入されている方が増えてきたように思います。今では多くの会社さんがペット保険を売り出しており、いざ加入しようと思っても悩んでしまう方も多いかと思います。そこで今回はペット保険のメリットやデメリット、注意ポイントなどをまとめてみました。 ペット保険とは? 私たち人間は、健康保険が効く保険診療ですが、ペット達はどうでしょうか?動物病院での診療は【自由診療】といわれ公的な保険システムは存在していません。全額飼い主さんがお支払いを行い、診療価格も各動物病院が自由に決める事ができます。ゆえに手術や入院、長期に渡る通院、内服治療となると飼い主さんにかかる金銭的負担が大きくなってしまいます。そこで活躍してくれるのがペット保険。毎月の保険料を支払う事でペット達の通院時に診療費が補償されるものです。様々なプランが用意されていますがペットの年齢や持病によって加入できるプランが制限される場合もあります。なおワクチンや避妊、去勢手術、健康診断など予防医療に該当するものは保険対象外となります。 加入するメリット 最大のメリットは予期せぬ病気や手術でも金額的負担を最小限に抑えられることです。言い換えれば選択できる治療方法の幅が広がる事ともいえます。生涯一度も病院にかからず健康で過ごすことができれば一番良いですが、年齢を重ねていくうちに病気が出てくるのは自然な事です。できる治療は全てしてあげたい飼い主さんにとって、ペット保険は背中を押す強い味方となってくれます。 加入するデメリット デメリットとしては掛け捨てであること、窓口清算ができないことなどがあげられます。貯蓄型保険がある人間とは異なりペットちゃん達は掛け捨て保険が基本となります。病気をしなければ保険を使う機会もありませんから保険料が勿体ない、と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。また窓口清算ができない保険も多く一度飼い主さんが全額支払い、後日保険会社に申請、その後補償額が振り込まれる、というのが一般的な流れになります。現状窓口清算ができる保険会社さんは限られており、取り扱っていない動物病院さんも多いため毎回の申請手続きが面倒であることはデメリットといえるかもしれません。 加入するタイミングやポイント ペット保険はシニアになるほど加入が難しくなっていきます。また加入できても持病は免責事項として補償対象外になってしまうことも。若いうちは不要と思いがちですが、持病などがないうちから加入しておくとシニア期以降も安心です。一番大切なことは飼い主さんに負担がなく加入できる保険であることです。安心代として月にかけられる金額を算出し、そこに合わせて保険プランを探してみましょう。 保険料が年数を重ねるごとにあがっていくケースも多いため将来的にいくらぐらいの保険料になるかも問い合わせておくと確実です。最近ではシニアから加入できるプランを出している保険会社さんもありますので加入希望の方は諦めずにチェックしてみてくださいね。 無理のない保険料を目安にペット保険選びを 動物病院で勤務していると全然病気しないから!と保険を解約した翌月に体調を壊してしまった…なんて子がいたりします。万が一の時にかかる負担を無くすためのペット保険ですから、月々の保険料が負担になってしまっては元も子もありません。ペットの年齢や体調、かけられる金額を考慮してペット保険を検討してみましょう。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意!
寒さが厳しい季節になってきましたね。飼い主さんは勿論、ペット達の冬支度は進んでいますか?人間に比べ、体温が高く毛に覆われている彼らですが、寒さには弱く寒さ対策は欠かせません。実は冬になりやすい病気や悪化してしまう病気も…。今回は冬時期に特に注意したい病気やその対策についてご紹介します。 おしっこ疾患 体感温度が下がることでお水を飲む量が減ってしまうため、膀胱結石や膀胱炎など尿路疾患にかかりやすい時期となります。おしっこに行く回数や色合いをよく観察しておきましょう。対策としては、水分摂取量をあげること。お水を飲みたがらない場合はウェットタイプのフードを使って食事から水分を取ってもらってくださいね。 心臓病 人間同様、心臓病に寒さは大敵です。気温が下がると血管が収縮し血圧があがるため心臓にかかる負担が増えてしまうためです。特に持病があるペット達は病気が進行してしまう可能性もありますので自宅内の温度管理を工夫してあげましょう。暖房をつけていても暖気は上に流れていくため、足元までしっかり循環できていないことがあります。家族の中で生活視点が低いペット達だけが寒さを感じていることも。サーキュレーターやブランケットなどをうまく使って寒さ対策をしてあげてくださいね。 低温火傷 冬場に活躍する暖房器具ですが使い方によっては低温火傷を負ってしまう事もあります。低温火傷とは、体温より少し高めの温度が同じ場所にあたり続けることで引き起こる火傷症状で、ヒーターやホットカーペット、湯たんぽなどは要注意!高温火傷のような瞬間的な熱さや痛みを伴わないので飼い主さんもペット本人も気が付かないうちに症状が進んでしまう事があります。・ヒーターにはガードをつける・ホットカーペットには一枚毛布を重ねておく・湯たんぽはタオルを巻くなど、暖房器具とペットの間にワンクッションいれるよう意識してみてくださいね。 クリスマスは誤食に注意 冬のイベントといえばクリスマスですよね。実はこのクリスマス、動物病院では誤食の要注意デーとして警戒されています…!ケーキや定番のチキンはワンちゃん達の嗅覚をくすぐる特別な食べ物です。少量誤食してしまうだけでも下痢や嘔吐を引き起こす可能性がありますが、特に注意したいのはチキンの骨。鶏肉の骨は加熱すると縦に割れやすくなります。誤食時に割れてしまうと先端が鋭利な状態のまま体内に入り臓器を傷つけたり、突き破るようなことがあり大変危険です。最悪の場合、聖夜に開腹手術をすることになってしまうかも…クリスマスのごちそうは味付けをしていないペット用を別で用意し、人間用の食事はいつも以上に手が届かないよう注意して置きましょう。 ペット達と冬を乗り越えるために ペット達の中にも冬が好きな子、苦手な子と様々かと思います。震えていないか、体調は変わりないかなど本人の様子に合わせて寒さ対策をしてあげましょう。温度計を足元に置いておくと視覚的にもわかりやすいかと思います。暖を取れる場所と、少し涼しい場所を作ってあげると自分で過ごしやすい場所へと動けるのでお留守番時も安心です。今年は冷え込みが厳しい冬になりそうですがしっかり冬支度を整え、元気に乗り越えましょう! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
冬に多いペットの病気。クリスマスにも要注意!
寒さが厳しい季節になってきましたね。飼い主さんは勿論、ペット達の冬支度は進んでいますか?人間に比べ、体温が高く毛に覆われている彼らですが、寒さには弱く寒さ対策は欠かせません。実は冬になりやすい病気や悪化してしまう病気も…。今回は冬時期に特に注意したい病気やその対策についてご紹介します。 おしっこ疾患 体感温度が下がることでお水を飲む量が減ってしまうため、膀胱結石や膀胱炎など尿路疾患にかかりやすい時期となります。おしっこに行く回数や色合いをよく観察しておきましょう。対策としては、水分摂取量をあげること。お水を飲みたがらない場合はウェットタイプのフードを使って食事から水分を取ってもらってくださいね。 心臓病 人間同様、心臓病に寒さは大敵です。気温が下がると血管が収縮し血圧があがるため心臓にかかる負担が増えてしまうためです。特に持病があるペット達は病気が進行してしまう可能性もありますので自宅内の温度管理を工夫してあげましょう。暖房をつけていても暖気は上に流れていくため、足元までしっかり循環できていないことがあります。家族の中で生活視点が低いペット達だけが寒さを感じていることも。サーキュレーターやブランケットなどをうまく使って寒さ対策をしてあげてくださいね。 低温火傷 冬場に活躍する暖房器具ですが使い方によっては低温火傷を負ってしまう事もあります。低温火傷とは、体温より少し高めの温度が同じ場所にあたり続けることで引き起こる火傷症状で、ヒーターやホットカーペット、湯たんぽなどは要注意!高温火傷のような瞬間的な熱さや痛みを伴わないので飼い主さんもペット本人も気が付かないうちに症状が進んでしまう事があります。・ヒーターにはガードをつける・ホットカーペットには一枚毛布を重ねておく・湯たんぽはタオルを巻くなど、暖房器具とペットの間にワンクッションいれるよう意識してみてくださいね。 クリスマスは誤食に注意 冬のイベントといえばクリスマスですよね。実はこのクリスマス、動物病院では誤食の要注意デーとして警戒されています…!ケーキや定番のチキンはワンちゃん達の嗅覚をくすぐる特別な食べ物です。少量誤食してしまうだけでも下痢や嘔吐を引き起こす可能性がありますが、特に注意したいのはチキンの骨。鶏肉の骨は加熱すると縦に割れやすくなります。誤食時に割れてしまうと先端が鋭利な状態のまま体内に入り臓器を傷つけたり、突き破るようなことがあり大変危険です。最悪の場合、聖夜に開腹手術をすることになってしまうかも…クリスマスのごちそうは味付けをしていないペット用を別で用意し、人間用の食事はいつも以上に手が届かないよう注意して置きましょう。 ペット達と冬を乗り越えるために ペット達の中にも冬が好きな子、苦手な子と様々かと思います。震えていないか、体調は変わりないかなど本人の様子に合わせて寒さ対策をしてあげましょう。温度計を足元に置いておくと視覚的にもわかりやすいかと思います。暖を取れる場所と、少し涼しい場所を作ってあげると自分で過ごしやすい場所へと動けるのでお留守番時も安心です。今年は冷え込みが厳しい冬になりそうですがしっかり冬支度を整え、元気に乗り越えましょう! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

ペットだって歯が命!残った歯垢がわずか3日で...
ペットの歯磨きを、皆様毎日されているでしょうか?もし、今ドキッとされた方がいらっしゃれば、是非こちらのブログを読んでいただきたいと思います。 実は、ペット達は人間よりも歯垢がつきやすく、歯石に変わるまでもとても早いため、歯に関する病気が一番多いといわれているのです。意外と知られていない歯磨きや口内チェックの必要性を知って、一緒に病気知らずの健康な歯を目指しましょう! 実は怖い歯の病気 歯くらいで大袈裟!なんて思う方もいるかもしれませんが、歯周病や歯肉炎は口の中だけでなく次第に体へと細菌が感染し、大きな病気になってしまう可能性も…。鼻炎や顎の骨折、心臓病、腎臓病、肝炎、骨髄炎など最悪死に至る場合もあるため軽視はできません。そのためにも、日々のケアとして口や歯茎のチェックが重要となります。· 口臭がないか· 歯茎が赤く腫れていないか· 出血していないか· 歯石が付いていないか· ヨダレの量が以前より増えていないかこれらの項目を確認し、異常や気になることがあれば獣医師に相談し、必要であれば早めに処置してもらいましょう。 歯が抜けるタイミング 犬も猫も生後3ヶ月頃から6ヶ月頃までに乳歯から永久歯へと生え変わります。個体差はありますが、遅くても1歳頃までには全て永久歯になるため、痒そうにしていたら身体の大きさに合った噛みやすいオモチャをあたえて下さい。また、歯が抜けそうな時はご飯も食べにくくなってしまうため、フードを水やお湯でふやかして食べやすくするなど工夫してあげましょう。この時期にで注意してあげたい事は乳歯が残ったままになってしまう「乳歯遺残」がないかどうかです。乳歯が抜けず残ったままの状態でいると二枚歯になってしまい歯並びが悪くなり嚙み合わせも上手くいかなくなってしまいます。歯石も付きやすくなり歯周病などの病気にもなりやすくなってしまうため、生後6,7ヶ月以上経っても抜けそうにないようでしたら獣医師に診察してもらいましょう。病院にもよりますが、避妊や去勢を予定している場合は一緒に診てもらうことで愛犬に負担をかけずチェックすることができ、1回の麻酔で抜歯もしてもらえて安心です。乳歯遺残は飼い主でも気づかないことが多いため、予定していない方はワクチンや診察で通院する際に口の中も診てもらうことをおすすめします。抜歯は生え方をしっかりと確認してから行う必要があるので、無理に自分で抜くことは避けて下さいね。 放置してしまうと 歯周病や歯肉炎をそのままにしてしまうとあっという間に悪化してしまい、治療が困難になってしまいます。レントゲンや麻酔、抜歯などが必要になると、ペットの身体に負担がかかってしまううえ、年齢によっては麻酔ができないために治療が限られてしまうのです。また、飼い主さんも治療方法によっては治療費が高額になってしまい金銭面でも負担が…一度破損してしまった歯の組織は元に戻らないため日々のケアと観察を怠らないようにしましょう。 歯磨きが重要 歯垢から歯石になるまでわずか3日といわれているため、毎日の歯磨きはとても重要です。嫌がらないように子犬、子猫のころから習慣づけてあげると楽しくケアすることができますよ。嫌がってしまう子も多いのですが、健康な歯を保つためにも欠かすことはできません。まず口を触ることから始め、歯磨きは怖くないということを少しずつ教えていき上手にできたらたくさん褒めてあげましょう。どうしても難しいようでしたら、遊びながら歯磨き効果が期待できるロープ状のオモチャやデンタルガムなどを利用してみて下さいね。 人間同様、ペットも歯はとても大切です。悪くなってしまうと思いがけない病気になってしまうだけでなく、高度な治療も必要になってしまいます。散歩やブラッシングのように日々のケアの一つとして歯磨きも習慣づけ、ペットの健康な歯を守ってあげて下さいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼
ペットだって歯が命!残った歯垢がわずか3日で...
ペットの歯磨きを、皆様毎日されているでしょうか?もし、今ドキッとされた方がいらっしゃれば、是非こちらのブログを読んでいただきたいと思います。 実は、ペット達は人間よりも歯垢がつきやすく、歯石に変わるまでもとても早いため、歯に関する病気が一番多いといわれているのです。意外と知られていない歯磨きや口内チェックの必要性を知って、一緒に病気知らずの健康な歯を目指しましょう! 実は怖い歯の病気 歯くらいで大袈裟!なんて思う方もいるかもしれませんが、歯周病や歯肉炎は口の中だけでなく次第に体へと細菌が感染し、大きな病気になってしまう可能性も…。鼻炎や顎の骨折、心臓病、腎臓病、肝炎、骨髄炎など最悪死に至る場合もあるため軽視はできません。そのためにも、日々のケアとして口や歯茎のチェックが重要となります。· 口臭がないか· 歯茎が赤く腫れていないか· 出血していないか· 歯石が付いていないか· ヨダレの量が以前より増えていないかこれらの項目を確認し、異常や気になることがあれば獣医師に相談し、必要であれば早めに処置してもらいましょう。 歯が抜けるタイミング 犬も猫も生後3ヶ月頃から6ヶ月頃までに乳歯から永久歯へと生え変わります。個体差はありますが、遅くても1歳頃までには全て永久歯になるため、痒そうにしていたら身体の大きさに合った噛みやすいオモチャをあたえて下さい。また、歯が抜けそうな時はご飯も食べにくくなってしまうため、フードを水やお湯でふやかして食べやすくするなど工夫してあげましょう。この時期にで注意してあげたい事は乳歯が残ったままになってしまう「乳歯遺残」がないかどうかです。乳歯が抜けず残ったままの状態でいると二枚歯になってしまい歯並びが悪くなり嚙み合わせも上手くいかなくなってしまいます。歯石も付きやすくなり歯周病などの病気にもなりやすくなってしまうため、生後6,7ヶ月以上経っても抜けそうにないようでしたら獣医師に診察してもらいましょう。病院にもよりますが、避妊や去勢を予定している場合は一緒に診てもらうことで愛犬に負担をかけずチェックすることができ、1回の麻酔で抜歯もしてもらえて安心です。乳歯遺残は飼い主でも気づかないことが多いため、予定していない方はワクチンや診察で通院する際に口の中も診てもらうことをおすすめします。抜歯は生え方をしっかりと確認してから行う必要があるので、無理に自分で抜くことは避けて下さいね。 放置してしまうと 歯周病や歯肉炎をそのままにしてしまうとあっという間に悪化してしまい、治療が困難になってしまいます。レントゲンや麻酔、抜歯などが必要になると、ペットの身体に負担がかかってしまううえ、年齢によっては麻酔ができないために治療が限られてしまうのです。また、飼い主さんも治療方法によっては治療費が高額になってしまい金銭面でも負担が…一度破損してしまった歯の組織は元に戻らないため日々のケアと観察を怠らないようにしましょう。 歯磨きが重要 歯垢から歯石になるまでわずか3日といわれているため、毎日の歯磨きはとても重要です。嫌がらないように子犬、子猫のころから習慣づけてあげると楽しくケアすることができますよ。嫌がってしまう子も多いのですが、健康な歯を保つためにも欠かすことはできません。まず口を触ることから始め、歯磨きは怖くないということを少しずつ教えていき上手にできたらたくさん褒めてあげましょう。どうしても難しいようでしたら、遊びながら歯磨き効果が期待できるロープ状のオモチャやデンタルガムなどを利用してみて下さいね。 人間同様、ペットも歯はとても大切です。悪くなってしまうと思いがけない病気になってしまうだけでなく、高度な治療も必要になってしまいます。散歩やブラッシングのように日々のケアの一つとして歯磨きも習慣づけ、ペットの健康な歯を守ってあげて下さいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼

ワンちゃんにオススメ食材と注意したい食材
愛犬のお食事、皆さんはどうされていますか?一般的に流通している総合栄養食は、そのフードだけで体に必要な栄養素全てが取れるというものになっています。そのため無理にプラスαの食事をつける必要はありません。 ですが、おやつやトッピングとして食材をプラスすることでぐっと嗜好性があがり特別感を演出することもできますよね。前回のブログワンちゃんには要注意!その意外な食材とは?では、ワンちゃんにとって危険となる食材について書かせて頂きました。そこで今回は積極的にあげたい食材やあげる前に注意が必要な食材など、ワンちゃんの【食】についてまとめてみました。 積極的にとりたい食材 ■旬の野菜や果物シーズンを迎えた野菜や果物は栄養価が高く、味も濃厚です。なんといってもワンちゃんの嗅覚を刺激する香りが芳醇なことが強みと言えます。春はキャベツ、夏はトマト、秋は梨、冬は大根、などシーズンごとにトッピングを変えることでワンちゃんも喜んでくれるはず♪栄養価が高い反面、太りやすくなる食材もありますのであげすぎには注意しましょう。カロリー計算をして量をコントロールしてあげると安心です。■お芋類お腹がデリケートなワンちゃんにおススメしたい食材はかぼちゃやサツマイモなどのお芋類。満足感もある上、お腹の中のお掃除に役立つ万能食材です。生のままですとデンプン質が分解されにくいため必ず加熱してから与えましょう。ただしお腹の動きを過剰にアップさせてしまうこともありますので、まずは少量ずつ与えお腹を下さないか様子を見てみましょう。愛犬の1日の必要カロリーは【体重×30+70×活動係数】で算出が可能です。活動係数は避妊去勢の有無や年齢、運動量によって異なりますので愛犬にあった数値を検索してみて下さいね。 やや注意したい食材 どのような食材でもアレルギーを起こす可能性はゼロではありません。また調理方法など、与え方によっては危険なものも…。その中でも特に注意したい食材をピックアップしました。■肉類豚、牛、鶏肉にはアレルギーを起こす可能性があります。ラムや鹿肉はアレルギーを起こしにくいと言われていますが初めてあげるときは特に注意してみてあげましょう。最初は症状が出なくても長期的に食べる事で徐々に症状が出始めるケースもあります。牛肉は生でもOKですが加熱用は避け新鮮なものを選ぶことが重要です。その他のお肉は加熱してから与えてくださいね。■魚類肉類と同様に貴重なタンパク源になるお魚ですがこちらもアレルギーの可能性があります。また骨がお口に刺さってしまうようなケースも…。与えるときは加熱し小さく切り分けて使用しましょう。■乳製品ワンちゃん用であってもアレルギー反応を起こしてしまう子がいます。また乳製品はカロリーも高め…少量から始め、あげすぎには注意しましょう。週に1回、などあげる日を限定しておくことをお勧めします。人間用の乳製品はお腹を壊してしまう可能性が高いためワンちゃんにはNGです。アレルギーの代表的な症状には下痢や嘔吐、皮膚の痒み、お顔周りの赤みなどがあげられます。こういった症状が出てきた時は一度気になる食材をストップし、獣医師にご相談なさってくださいね。 与える時のポイント ワンちゃんにフード以外の食材を与えるときは飲み込みやすいサイズにカットし、カロリーオーバーしない適度な量を意識してあげてくださいね。お肉やお野菜をゆがいてあげるときはゆで汁にも栄養成分が含まれています!製氷機で冷凍して保存しておくととっても便利。フードをふやかす時や、食事の風味付けに是非活用してみましょう! さいごに いかがでしたか?冷蔵庫にあるもので明日から活用できるものもあるのではないでしょうか?何よりも大切にしたいポイントは愛犬が喜んでくれる事、そして体に合っているものを選んであげる事です。体質や好みは様々ですから、色々と試しながら愛犬にぴったりの食材見つけてあげてくださいね♪ ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
ワンちゃんにオススメ食材と注意したい食材
愛犬のお食事、皆さんはどうされていますか?一般的に流通している総合栄養食は、そのフードだけで体に必要な栄養素全てが取れるというものになっています。そのため無理にプラスαの食事をつける必要はありません。 ですが、おやつやトッピングとして食材をプラスすることでぐっと嗜好性があがり特別感を演出することもできますよね。前回のブログワンちゃんには要注意!その意外な食材とは?では、ワンちゃんにとって危険となる食材について書かせて頂きました。そこで今回は積極的にあげたい食材やあげる前に注意が必要な食材など、ワンちゃんの【食】についてまとめてみました。 積極的にとりたい食材 ■旬の野菜や果物シーズンを迎えた野菜や果物は栄養価が高く、味も濃厚です。なんといってもワンちゃんの嗅覚を刺激する香りが芳醇なことが強みと言えます。春はキャベツ、夏はトマト、秋は梨、冬は大根、などシーズンごとにトッピングを変えることでワンちゃんも喜んでくれるはず♪栄養価が高い反面、太りやすくなる食材もありますのであげすぎには注意しましょう。カロリー計算をして量をコントロールしてあげると安心です。■お芋類お腹がデリケートなワンちゃんにおススメしたい食材はかぼちゃやサツマイモなどのお芋類。満足感もある上、お腹の中のお掃除に役立つ万能食材です。生のままですとデンプン質が分解されにくいため必ず加熱してから与えましょう。ただしお腹の動きを過剰にアップさせてしまうこともありますので、まずは少量ずつ与えお腹を下さないか様子を見てみましょう。愛犬の1日の必要カロリーは【体重×30+70×活動係数】で算出が可能です。活動係数は避妊去勢の有無や年齢、運動量によって異なりますので愛犬にあった数値を検索してみて下さいね。 やや注意したい食材 どのような食材でもアレルギーを起こす可能性はゼロではありません。また調理方法など、与え方によっては危険なものも…。その中でも特に注意したい食材をピックアップしました。■肉類豚、牛、鶏肉にはアレルギーを起こす可能性があります。ラムや鹿肉はアレルギーを起こしにくいと言われていますが初めてあげるときは特に注意してみてあげましょう。最初は症状が出なくても長期的に食べる事で徐々に症状が出始めるケースもあります。牛肉は生でもOKですが加熱用は避け新鮮なものを選ぶことが重要です。その他のお肉は加熱してから与えてくださいね。■魚類肉類と同様に貴重なタンパク源になるお魚ですがこちらもアレルギーの可能性があります。また骨がお口に刺さってしまうようなケースも…。与えるときは加熱し小さく切り分けて使用しましょう。■乳製品ワンちゃん用であってもアレルギー反応を起こしてしまう子がいます。また乳製品はカロリーも高め…少量から始め、あげすぎには注意しましょう。週に1回、などあげる日を限定しておくことをお勧めします。人間用の乳製品はお腹を壊してしまう可能性が高いためワンちゃんにはNGです。アレルギーの代表的な症状には下痢や嘔吐、皮膚の痒み、お顔周りの赤みなどがあげられます。こういった症状が出てきた時は一度気になる食材をストップし、獣医師にご相談なさってくださいね。 与える時のポイント ワンちゃんにフード以外の食材を与えるときは飲み込みやすいサイズにカットし、カロリーオーバーしない適度な量を意識してあげてくださいね。お肉やお野菜をゆがいてあげるときはゆで汁にも栄養成分が含まれています!製氷機で冷凍して保存しておくととっても便利。フードをふやかす時や、食事の風味付けに是非活用してみましょう! さいごに いかがでしたか?冷蔵庫にあるもので明日から活用できるものもあるのではないでしょうか?何よりも大切にしたいポイントは愛犬が喜んでくれる事、そして体に合っているものを選んであげる事です。体質や好みは様々ですから、色々と試しながら愛犬にぴったりの食材見つけてあげてくださいね♪ ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

ワクチン後はお散歩OK?注意したいポイント
ワンちゃん達が定期的に接種する【混合ワクチン】。様々な感染症から愛犬を守り、より安心して生活を送っていくために必要な予防接種の一つです。ワクチンの接種後は普段より少し注意してあげたいポイントがいくつかあります。子犬ちゃんはいつからお散歩に出ていいのかも気になりますよね!そこで今回は混合ワクチン接種後の過ごし方についてご紹介していきます。 ワクチンの必要性 ワンちゃん達にとって感染症は命を脅かしてしまう恐ろしい病気です。中には生まれつきの病気や、アレルギーがありワクチンを打つことができない子たちもいます。打てる子がしっかりワクチンを打つことで、どんな子でも安心して生活が送れる環境になっていきます。特に免疫力が弱い子犬期のワクチンはスケジュール通り接種することが大切です。 ワクチンの回数やタイミングはバラバラ! ワンちゃん達のワクチン接種時期はその子その子によって異なります。母犬からの移行抗体を持つ子犬期は、より免疫力の高い抗体をつくるため2回または3回続けてワクチン接種を行います。成犬期では生活環境によって接種するワクチンを決め1~3年に1回のペースでワクチン接種を行います。多頭飼いで全員の接種タイミングを統一したい、という場合にはかかりつけの獣医師に相談してみてくださいね。 ワクチン接種後の注意点 ■運動接種後は息が上がるほどの激しい運動は控えましょう。体温が上がることで副反応が出やすくなってしまいます。当日のお散歩はおトイレ出し程度で済ませ、あとはおうちで安静に過ごします。■シャンプーシャンプーも体温が上がってしまうため当日は避けた方が安心です。病院で緊張してしまった子もいると思いますのでストレス面から見てもワクチン当日のグルーミングやトリミングはやめておきましょう。■お出かけ接種直後に遠方へのお出かけはお勧めしません。興奮によって体温があがってしまう可能性、そして万が一副反応が起きてしまった場合再受診に時間がかかってしまうことが考えられるからです。何かあってもすぐに動ける範囲で行動しましょう。 副反応が出てしまったら? ワクチンの副反応には様々なものがあります。嘔吐や下痢、食欲元気の低下は比較的ポピュラーで起こりやすい症状。一回きりですぐ治った、翌日には元気になった、と言う場合には大事に至らないケースがほとんどです。様子を見ても大丈夫かどうかは、自己判断せずかかりつけに電話で確認してみましょう。副反応の中で最も深刻な症状は【アナフィラキシーショック】です。接種から15分~30分前後で呼吸困難、顔の腫れ、ぐったりする、などの症状が見られます。この場合は様子を見ずにかかりつけへ行き再受診なさってくださいね。抗アレルギーのお注射で症状は改善します。アレルギー症状が出ないかご不安な方は接種後30分程度院内で様子を見させてもらいましょう! ワクチン接種後のお散歩デビュー 子犬ちゃんのお散歩デビュー、心待ちにしている方が多いですよね。接種後すぐにでも行きたいところですが、実は抗体が完全に作られるまでは2週間のタイムラグがあります。そのためお散歩は2週間しっかり待ってからデビューさせてあげましょう。この期間の間、抱っこで短時間お外に出るくらいであればOKです。いきなりお外を歩かせるより少しずつお外に慣らすいい機会ですから、是非お外の空気は吸わせてあげてください。 感染症から守りましょう 接種するワクチンの種類は居住地区やライフスタイルによって変わりますので獣医師と相談しましょう。また接種は何時でもできますが、万が一アレルギーが起きた場合を考慮し休診時間ギリギリの時間は避けた方が安心です。愛犬から少しでも感染症から守れるよう、獣医師とワクチン接種のスケジュールを相談しながらしっかり進めてくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
ワクチン後はお散歩OK?注意したいポイント
ワンちゃん達が定期的に接種する【混合ワクチン】。様々な感染症から愛犬を守り、より安心して生活を送っていくために必要な予防接種の一つです。ワクチンの接種後は普段より少し注意してあげたいポイントがいくつかあります。子犬ちゃんはいつからお散歩に出ていいのかも気になりますよね!そこで今回は混合ワクチン接種後の過ごし方についてご紹介していきます。 ワクチンの必要性 ワンちゃん達にとって感染症は命を脅かしてしまう恐ろしい病気です。中には生まれつきの病気や、アレルギーがありワクチンを打つことができない子たちもいます。打てる子がしっかりワクチンを打つことで、どんな子でも安心して生活が送れる環境になっていきます。特に免疫力が弱い子犬期のワクチンはスケジュール通り接種することが大切です。 ワクチンの回数やタイミングはバラバラ! ワンちゃん達のワクチン接種時期はその子その子によって異なります。母犬からの移行抗体を持つ子犬期は、より免疫力の高い抗体をつくるため2回または3回続けてワクチン接種を行います。成犬期では生活環境によって接種するワクチンを決め1~3年に1回のペースでワクチン接種を行います。多頭飼いで全員の接種タイミングを統一したい、という場合にはかかりつけの獣医師に相談してみてくださいね。 ワクチン接種後の注意点 ■運動接種後は息が上がるほどの激しい運動は控えましょう。体温が上がることで副反応が出やすくなってしまいます。当日のお散歩はおトイレ出し程度で済ませ、あとはおうちで安静に過ごします。■シャンプーシャンプーも体温が上がってしまうため当日は避けた方が安心です。病院で緊張してしまった子もいると思いますのでストレス面から見てもワクチン当日のグルーミングやトリミングはやめておきましょう。■お出かけ接種直後に遠方へのお出かけはお勧めしません。興奮によって体温があがってしまう可能性、そして万が一副反応が起きてしまった場合再受診に時間がかかってしまうことが考えられるからです。何かあってもすぐに動ける範囲で行動しましょう。 副反応が出てしまったら? ワクチンの副反応には様々なものがあります。嘔吐や下痢、食欲元気の低下は比較的ポピュラーで起こりやすい症状。一回きりですぐ治った、翌日には元気になった、と言う場合には大事に至らないケースがほとんどです。様子を見ても大丈夫かどうかは、自己判断せずかかりつけに電話で確認してみましょう。副反応の中で最も深刻な症状は【アナフィラキシーショック】です。接種から15分~30分前後で呼吸困難、顔の腫れ、ぐったりする、などの症状が見られます。この場合は様子を見ずにかかりつけへ行き再受診なさってくださいね。抗アレルギーのお注射で症状は改善します。アレルギー症状が出ないかご不安な方は接種後30分程度院内で様子を見させてもらいましょう! ワクチン接種後のお散歩デビュー 子犬ちゃんのお散歩デビュー、心待ちにしている方が多いですよね。接種後すぐにでも行きたいところですが、実は抗体が完全に作られるまでは2週間のタイムラグがあります。そのためお散歩は2週間しっかり待ってからデビューさせてあげましょう。この期間の間、抱っこで短時間お外に出るくらいであればOKです。いきなりお外を歩かせるより少しずつお外に慣らすいい機会ですから、是非お外の空気は吸わせてあげてください。 感染症から守りましょう 接種するワクチンの種類は居住地区やライフスタイルによって変わりますので獣医師と相談しましょう。また接種は何時でもできますが、万が一アレルギーが起きた場合を考慮し休診時間ギリギリの時間は避けた方が安心です。愛犬から少しでも感染症から守れるよう、獣医師とワクチン接種のスケジュールを相談しながらしっかり進めてくださいね。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

多頭飼育について考えよう
「1頭でのお留守番は寂しそう。」「可愛いペットに囲まれて暮らしたい。」「行き場のないペットを保護してあげたい。」このように色々な思いから多頭飼育を考えている方もいるのではないでしょうか。大好きなペットとの暮らしは賑やかで楽しそうですよね。しかし、安易に迎えてしまったことで環境に合わず、飼育放棄をしてしまう飼い主さんが増えていることもまた問題となっています。今回は、様々な角度から多頭飼育のメリットや注意点をふまえて解説したいと思います。 多頭飼育とは 多頭飼育とは、複数のペットを同じ家庭内で飼育することを言います。一頭飼いとの違いは賑やかさ・楽しいさ・癒しなどが挙げられますが、それ以外にも環境・金銭面・相性などがあり、生活がガラリと変わります。散歩やケアも飼っている頭数分行う必要があり、ご飯や予防接種など出費もかさんでしまいます。しかし同時に、多頭飼いにも沢山のメリットがあります。ペット達が、仲間と過ごすことで自然と社会性が身につき、良き遊び相手にもなるので運動不足の解消やコミュニケーションにも繋がるうえに、一緒にいることで孤独感から安心感へと変わり、ストレスが軽減される子もいるのです。仲良く過ごしてくれる姿は飼い主としても嬉しく微笑ましいですよね。 先住ペットとの付き合い方や注意点 多頭飼育で最も注意したいことは先住ペットが多頭飼育に向いているかどうかです。その子の性格や体格を把握し、もう1頭迎えても大丈夫なのか検討していきましょう。お迎えが決まった場合、対面初日でお互いにマイナスイメージがついてしまわないように慎重に顔合わせを行う必要があります。早く仲良くなってほしいと思って、迎えたペットをいきなり部屋に放つのはNGです。先住ペットにストレスがかからないよう、慣れるまでは必ず飼い主が見守ってあげてくださいね。生活が変わったことや今まで愛情を独り占めできていた分、警戒心が強くなったり嫉妬心から飼い主に甘えることが多くなり、問題行動を取りだす子もいます。不安にさせないよう、日々の行動をよく観察し接してあげましょう。慣れてくると徐々にペット同士で上下関係など社会性が身についてくるので、仲良くしていたりじゃれ合っていたりしている場合は干渉せず温かく見守ってみましょう。 多頭飼育に向いている種類 多頭飼育に向いているペットの種類はあるのでしょうか?闘犬や日本犬など多頭飼育に向いていないと言われる種類もいますが、実際はその子自身の性格にもよります。「警戒心が強い」「独占欲が強い」「気が強い」などといった子が先住ペットの場合、後住ペットに慣れるまで時間がかかり、場合によっては警戒心や嫉妬心から後住ペットを攻撃してしまう可能性もあるため注意が必要です。反対に「人懐こい」「社交的」といった子は多頭飼育に向いていて、あっという間に馴染んでしまいます。散歩時に他のペットとの相性や関わりを観察してみましょう。性別に関しては、ホルモンによる縄張り意識等を考え、オス同士やメス同士よりも異性の組み合わせが良いと言われていますが、こちらに関してもやはり元々の先住ペットの性格によります。 多頭向けアイテムを上手に使う 多頭飼育になると、やはりお世話をする飼い主さんの多くの時間と労力を費やすことになります。そこで、少しでも快適に過ごして頂けるように多頭飼育向けのおすすめの商品をご紹介させて頂きます。自動ネコトイレ ▲3匹まで対応『自動ネコトイレ CATLINK SCOOPER PRO(キャットリンク スクーパー プロ)』 猫ちゃんのお世話で1番時間がかかり大変なのがトイレ掃除です。自動ネコトイレは、多頭の猫ちゃん達が排泄するたびに清掃してくれるので、常に清潔なトイレを保ってくれる優れものです。アプリを使用し、それぞれの猫ちゃんの排泄時間や回数を教えてくれる便利機能まで登載されている自動ネコトイレもあるのでぜひチェックしてみて下さいね。シェアフィーダー ▲シュアーフィーダーマイクロチップ 専用のタグかマイクロチップを登録することで蓋が自動的に開閉するので、ペット同志のご飯の奪い合いや横取りの心配がありません。ご飯の種類が違うという場合でも食べ間違いが防げて安心です。湿気やほこりでフードがダメになってしまう心配もなく、新鮮なご飯を食べさせることができるのは嬉しいですね。クレート ▲ペットケンネル・ファーストクラス トップオープン 多頭飼育の場合、それぞれのペットが安心して休める場所はとても重要です。折り畳みもできて持ち運びにも便利なソフトケンネルは自宅でも外出先でも使用できます。安心できるハウスとして日々使用することで、災害時もケンネルの中で落ち着けることがメリットでもあります。ツインカーゴ ▲Sturdi ペットツインカーゴ 一見大きなキャリーに見えるツインカーゴは、中央で仕切ることができます。仕切ることで2部屋になるので、小型犬やネコの場合キャリーを2つ購入しなくてもOK。軽量なので持ち運びも簡単で、車や旅先でも利用できるキャリーです。 ペット好きの方なら一度は憧れる多頭飼育ですが、「可愛いから」「好きだから」という理由だけで安易に迎えるのはかえってペット達を傷つけてしまうこともあります。自分とペットが共に幸せに暮らせるかを一番にじっくり考えてみて下さいね。とはいえ、ペット達に囲まれての賑やかな生活は、何とも言えない至福と癒しがあります。日々のお世話に悩んでいる方はぜひアイテムを上手に利用して快適に過ごしてみましょう。 ▼ この記事を書いたのは ▼...
多頭飼育について考えよう
「1頭でのお留守番は寂しそう。」「可愛いペットに囲まれて暮らしたい。」「行き場のないペットを保護してあげたい。」このように色々な思いから多頭飼育を考えている方もいるのではないでしょうか。大好きなペットとの暮らしは賑やかで楽しそうですよね。しかし、安易に迎えてしまったことで環境に合わず、飼育放棄をしてしまう飼い主さんが増えていることもまた問題となっています。今回は、様々な角度から多頭飼育のメリットや注意点をふまえて解説したいと思います。 多頭飼育とは 多頭飼育とは、複数のペットを同じ家庭内で飼育することを言います。一頭飼いとの違いは賑やかさ・楽しいさ・癒しなどが挙げられますが、それ以外にも環境・金銭面・相性などがあり、生活がガラリと変わります。散歩やケアも飼っている頭数分行う必要があり、ご飯や予防接種など出費もかさんでしまいます。しかし同時に、多頭飼いにも沢山のメリットがあります。ペット達が、仲間と過ごすことで自然と社会性が身につき、良き遊び相手にもなるので運動不足の解消やコミュニケーションにも繋がるうえに、一緒にいることで孤独感から安心感へと変わり、ストレスが軽減される子もいるのです。仲良く過ごしてくれる姿は飼い主としても嬉しく微笑ましいですよね。 先住ペットとの付き合い方や注意点 多頭飼育で最も注意したいことは先住ペットが多頭飼育に向いているかどうかです。その子の性格や体格を把握し、もう1頭迎えても大丈夫なのか検討していきましょう。お迎えが決まった場合、対面初日でお互いにマイナスイメージがついてしまわないように慎重に顔合わせを行う必要があります。早く仲良くなってほしいと思って、迎えたペットをいきなり部屋に放つのはNGです。先住ペットにストレスがかからないよう、慣れるまでは必ず飼い主が見守ってあげてくださいね。生活が変わったことや今まで愛情を独り占めできていた分、警戒心が強くなったり嫉妬心から飼い主に甘えることが多くなり、問題行動を取りだす子もいます。不安にさせないよう、日々の行動をよく観察し接してあげましょう。慣れてくると徐々にペット同士で上下関係など社会性が身についてくるので、仲良くしていたりじゃれ合っていたりしている場合は干渉せず温かく見守ってみましょう。 多頭飼育に向いている種類 多頭飼育に向いているペットの種類はあるのでしょうか?闘犬や日本犬など多頭飼育に向いていないと言われる種類もいますが、実際はその子自身の性格にもよります。「警戒心が強い」「独占欲が強い」「気が強い」などといった子が先住ペットの場合、後住ペットに慣れるまで時間がかかり、場合によっては警戒心や嫉妬心から後住ペットを攻撃してしまう可能性もあるため注意が必要です。反対に「人懐こい」「社交的」といった子は多頭飼育に向いていて、あっという間に馴染んでしまいます。散歩時に他のペットとの相性や関わりを観察してみましょう。性別に関しては、ホルモンによる縄張り意識等を考え、オス同士やメス同士よりも異性の組み合わせが良いと言われていますが、こちらに関してもやはり元々の先住ペットの性格によります。 多頭向けアイテムを上手に使う 多頭飼育になると、やはりお世話をする飼い主さんの多くの時間と労力を費やすことになります。そこで、少しでも快適に過ごして頂けるように多頭飼育向けのおすすめの商品をご紹介させて頂きます。自動ネコトイレ ▲3匹まで対応『自動ネコトイレ CATLINK SCOOPER PRO(キャットリンク スクーパー プロ)』 猫ちゃんのお世話で1番時間がかかり大変なのがトイレ掃除です。自動ネコトイレは、多頭の猫ちゃん達が排泄するたびに清掃してくれるので、常に清潔なトイレを保ってくれる優れものです。アプリを使用し、それぞれの猫ちゃんの排泄時間や回数を教えてくれる便利機能まで登載されている自動ネコトイレもあるのでぜひチェックしてみて下さいね。シェアフィーダー ▲シュアーフィーダーマイクロチップ 専用のタグかマイクロチップを登録することで蓋が自動的に開閉するので、ペット同志のご飯の奪い合いや横取りの心配がありません。ご飯の種類が違うという場合でも食べ間違いが防げて安心です。湿気やほこりでフードがダメになってしまう心配もなく、新鮮なご飯を食べさせることができるのは嬉しいですね。クレート ▲ペットケンネル・ファーストクラス トップオープン 多頭飼育の場合、それぞれのペットが安心して休める場所はとても重要です。折り畳みもできて持ち運びにも便利なソフトケンネルは自宅でも外出先でも使用できます。安心できるハウスとして日々使用することで、災害時もケンネルの中で落ち着けることがメリットでもあります。ツインカーゴ ▲Sturdi ペットツインカーゴ 一見大きなキャリーに見えるツインカーゴは、中央で仕切ることができます。仕切ることで2部屋になるので、小型犬やネコの場合キャリーを2つ購入しなくてもOK。軽量なので持ち運びも簡単で、車や旅先でも利用できるキャリーです。 ペット好きの方なら一度は憧れる多頭飼育ですが、「可愛いから」「好きだから」という理由だけで安易に迎えるのはかえってペット達を傷つけてしまうこともあります。自分とペットが共に幸せに暮らせるかを一番にじっくり考えてみて下さいね。とはいえ、ペット達に囲まれての賑やかな生活は、何とも言えない至福と癒しがあります。日々のお世話に悩んでいる方はぜひアイテムを上手に利用して快適に過ごしてみましょう。 ▼ この記事を書いたのは ▼...

ワンちゃんには要注意!その意外な食材とは?
最近ではワンちゃんのフードも様々な種類が流通しています。愛犬の好みや体質、一体どのフードなら合うのか…迷ってしまいますよね。中には手作りのフードやトッピングをしてアレンジされている方も多いかと思います。旬の野菜や果物は栄養価が高く、味や香りも濃厚なため食が細いワンちゃんも喜んで食べてくれますよね。しかし!ワンちゃん達には口にするだけで命を危機にさらす食材も数多く存在しています。そこで、今回は気を付けて頂きたい食材や、その理由などをピックアップしてご紹介します。 あげてはダメ!中毒を起こしてしまう食べ物とその症状 ■玉ネギをはじめネギ属の食材玉ネギがワンちゃんにとって危険であることは有名ですが、玉ネギに限らずネギ属の食材が全てNGであることをご存知でしょうか?玉ネギ以外ではネギ、ニンニク、ニラ、島ラッキョウなどがあげられます。ネギ属の食材にはワンちゃんの赤血球を破壊する成分が含まれています。この成分は加熱しても破壊されることがないので調理済みであってもその危険性は変わりません。中毒を起こすと【溶血性貧血】を引き起こし命に関わる危険な状態になることも…。嘔吐、下血、血尿、痙攣、などの症状が出ることもあります。体重に対し5g以上摂取してしまうと中毒症状が出始める、と言われていますがその量は個体差があります。基本的に口にすることがないようにしましょう!■チョコレート甘いチョコレートは危険食材でありながらワンちゃんが喜んで食べてしまう厄介な存在!カカオに含まれているテオブロミンという成分、ワンちゃん達はこれを分解する力が弱く中毒症状を引き起こしてしまいます。カカオ濃度が高いチョコレートほど危険で嘔吐や下痢、頻脈、興奮状態、痙攣、などの症状が見られます。多量のテオブロミンを摂取してしまうと勿論命に関わることもあります。■ブドウあまり知られていませんがワンちゃんにブドウは大変危険な食材です。とはいってもブドウに含まれるどの成分が中毒を起こすのかはいまだにはっきりしていません。ブドウを食べる事で引き起こされる症状はその名の通り【ブドウ中毒】といわれ、小型犬であれば一粒であっても命を脅かす危険があります。嘔吐や下痢が見られる他、腎臓の数値が跳ね上がり急性腎不全を引きこしてしまいます。腎臓の数値によってはその日のうちに意識が混濁するほどの状態になってしまうことも…。干しブドウであっても危険性は変わりませんので絶対に与えないようにしましょう。 危険な食材を食べてしまった時は? 落ちた食材を口にしてしまったり、盗み食いをされてしまうケースもあるかと思います。そのようなときは慌てず、まずは電話で動物病院の指示を仰ぎましょう。誤食の場合、ポイントになるのは・食べた量・食べた時間・症状の有無になります。食べてしまった直後であれば嘔吐を促し、誤食したものを吐き出させる処置を行うことができます。もし時間が経過している、既に症状が出ている、といった場合には点滴、入院などの治療を行います。診察の際は誤食してしまったものを持参して確認してもらうとスムーズです。中毒症状が出る量は体重だけでなく、ワンちゃんの体質によっても異なりますので決して様子を見ず、獣医師に確認なさってくださいね。また自宅で嘔吐させる方法は、かえって症状を悪化させてしまうこともありますので絶対にやめましょう! 知る、そして避ける 今回ご紹介したものは危険食材の一部になります。新しい食べ物を与えるときは、必ず安全か調べてからあげる習慣をつけておくと安心です。実際に危険食材与えてしまい、症状を起こしてからご来院頂く患者様も多くいらっしゃいます。お話を聞くと体に良いと思っていた、喜んでくれたから…と飼い主様の愛情が隠れているのがとても切ないところでもあります。危険な食材を知り、避けてあげる事が大切です。安心して楽しく食事を楽しんでもらいましょう♪ ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
ワンちゃんには要注意!その意外な食材とは?
最近ではワンちゃんのフードも様々な種類が流通しています。愛犬の好みや体質、一体どのフードなら合うのか…迷ってしまいますよね。中には手作りのフードやトッピングをしてアレンジされている方も多いかと思います。旬の野菜や果物は栄養価が高く、味や香りも濃厚なため食が細いワンちゃんも喜んで食べてくれますよね。しかし!ワンちゃん達には口にするだけで命を危機にさらす食材も数多く存在しています。そこで、今回は気を付けて頂きたい食材や、その理由などをピックアップしてご紹介します。 あげてはダメ!中毒を起こしてしまう食べ物とその症状 ■玉ネギをはじめネギ属の食材玉ネギがワンちゃんにとって危険であることは有名ですが、玉ネギに限らずネギ属の食材が全てNGであることをご存知でしょうか?玉ネギ以外ではネギ、ニンニク、ニラ、島ラッキョウなどがあげられます。ネギ属の食材にはワンちゃんの赤血球を破壊する成分が含まれています。この成分は加熱しても破壊されることがないので調理済みであってもその危険性は変わりません。中毒を起こすと【溶血性貧血】を引き起こし命に関わる危険な状態になることも…。嘔吐、下血、血尿、痙攣、などの症状が出ることもあります。体重に対し5g以上摂取してしまうと中毒症状が出始める、と言われていますがその量は個体差があります。基本的に口にすることがないようにしましょう!■チョコレート甘いチョコレートは危険食材でありながらワンちゃんが喜んで食べてしまう厄介な存在!カカオに含まれているテオブロミンという成分、ワンちゃん達はこれを分解する力が弱く中毒症状を引き起こしてしまいます。カカオ濃度が高いチョコレートほど危険で嘔吐や下痢、頻脈、興奮状態、痙攣、などの症状が見られます。多量のテオブロミンを摂取してしまうと勿論命に関わることもあります。■ブドウあまり知られていませんがワンちゃんにブドウは大変危険な食材です。とはいってもブドウに含まれるどの成分が中毒を起こすのかはいまだにはっきりしていません。ブドウを食べる事で引き起こされる症状はその名の通り【ブドウ中毒】といわれ、小型犬であれば一粒であっても命を脅かす危険があります。嘔吐や下痢が見られる他、腎臓の数値が跳ね上がり急性腎不全を引きこしてしまいます。腎臓の数値によってはその日のうちに意識が混濁するほどの状態になってしまうことも…。干しブドウであっても危険性は変わりませんので絶対に与えないようにしましょう。 危険な食材を食べてしまった時は? 落ちた食材を口にしてしまったり、盗み食いをされてしまうケースもあるかと思います。そのようなときは慌てず、まずは電話で動物病院の指示を仰ぎましょう。誤食の場合、ポイントになるのは・食べた量・食べた時間・症状の有無になります。食べてしまった直後であれば嘔吐を促し、誤食したものを吐き出させる処置を行うことができます。もし時間が経過している、既に症状が出ている、といった場合には点滴、入院などの治療を行います。診察の際は誤食してしまったものを持参して確認してもらうとスムーズです。中毒症状が出る量は体重だけでなく、ワンちゃんの体質によっても異なりますので決して様子を見ず、獣医師に確認なさってくださいね。また自宅で嘔吐させる方法は、かえって症状を悪化させてしまうこともありますので絶対にやめましょう! 知る、そして避ける 今回ご紹介したものは危険食材の一部になります。新しい食べ物を与えるときは、必ず安全か調べてからあげる習慣をつけておくと安心です。実際に危険食材与えてしまい、症状を起こしてからご来院頂く患者様も多くいらっしゃいます。お話を聞くと体に良いと思っていた、喜んでくれたから…と飼い主様の愛情が隠れているのがとても切ないところでもあります。危険な食材を知り、避けてあげる事が大切です。安心して楽しく食事を楽しんでもらいましょう♪ ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

可愛いけど困ってしまう…野良猫トラブルの解決方法
ご近所でばったり野良猫に出会ったこと、皆様ありますよね。 野良猫、屋外飼育してされている猫ちゃんの数は東京都が推定数を試算しており、その数なんと都内だけで12万頭にも及ぶとされています。(平成29年度)これだけの数がいれば当然、糞尿被害や繁殖問題など様々なトラブルが発生します。そこで今回は野良猫にまつわるトラブルを対策も含めご紹介していきます。 敷地内での糞尿被害 野良猫トラブルで最も耳にするのは住宅の敷地内や公園での糞尿被害です。過去には都内の砂場、その約半数が猫の糞尿からくる寄生虫に汚染されているという調査報告があがった年もありました。それでも公園などの公共施設は管轄している地区が定期的に点検、消毒を行ってくれます。しかし、住宅の周りはご自身でケアするしかありません。猫ちゃんの糞尿はマーキングも兼ねているため元々臭いがきつく、時間が経過することで更に悪臭が強まってしまいます。そしてその臭いを辿ってまた猫ちゃん達がマーキングしにくる、という悪循環が生まれるのです。そこで対策方法として【入らせない】【残さない】【臭いを消す】がポイントです。具体例としては…・敷地に入れないようネットやトゲ付きマットでガードする・排泄物は見つけ次第処理、水で流す・木酢液を希釈し散布する・臭い残りがきつい場所にはハイターの希釈液を散布する・置物や超音波の猫避けグッズを配置するなどがあげられます。木酢液はホームセンターのガーデン用品売り場にありますのでチェックしてみてくださいね。なおハイターは人体にも猫ちゃんにも有害成分ですから、どうしても臭いが取れない場所にのみ使用し、使用後はしばらく立ち入れないよう工夫しておきましょう。 どんどん増えてしまう繁殖問題 猫ちゃん達は1回の出産で5頭前後の子猫を産みます。外猫ちゃん達の一生はとても過酷です。家猫ちゃんの平均寿命が15歳前後なのに対し、外で暮らす猫ちゃん達は5歳前後までしか生きることができません。感染症や飢え、外敵からの攻撃、気温、交通事故、外にある全てがその命を脅かす脅威なのです。野良猫ちゃんにご飯をあげたくなる気持ちもとてもよくわかるのですが、中途半端な優しさはかえって猫ちゃん達を過酷な環境に放り出すことになってしまいます。この繁殖問題に歯止めをかけるには避妊、去勢の手術を行うしかありません。ご自身で保護し、手術を受けさせてからまた外に戻す。という方も多くいらっしゃいます。このような場合は事前に動物病院にその旨を伝えておくと、手術の最後にお耳の端っこをカットし、誰が見ても手術済であることがわかるようにしてくれます。こうすると再び手術のために保護されてしまう事を防ぐことができます。地域によっては猫ちゃんの避妊去勢手術に助成金を出している場所もありますので居住地区の役所で確認してみてくださいね。 野良猫を保護するときの注意点 野良猫ちゃんの保護は並大抵のことではありません。子猫であっても3か月以上の子猫であれば暴れて咬みつく可能性も大いにあります。成猫になると容易に触ることはできないかと思います。このような時は、愛護団体や保護ボランティアさんの手が借りられないか聞いてみましょう。中には猫の捕獲機を貸してくれることもあります。ご自身で保護される場合はケージ、バスタオル、軍手、洗濯ネットを用意し長そで長ズボンで挑みましょう。バスタオルを上からかけ、静かに抱き上げ速やかにケージに入れます。この時に洗濯ネットに入れることができるとその後の動物病院での受診、処置がとってもスムーズに進みます。もちろん無理はせず、暴れたり逃げ出してしまう時は日を改めてください。この時のポイントはとにかく物音を立てず、静かに行う事です。もし引っかかれたり、咬まれてしまった時は細菌感染を起こしてしまう可能性があります。様子を見ず、その日のうちに外科を受診なさってくださいね。 最後に いかがでしたか?野良猫ちゃん達に何も非はないとわかっていても、糞尿被害には頭を抱えてしまいますよね。もし野良猫ちゃんを保護する場合は手術後にリリースするのか、里親を探すのか、などその後のこともしっかり検討してから行動しましょう。全ての猫ちゃん達が幸せな暮らしができるよう、対策を行い共存していけたらいいですね。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
可愛いけど困ってしまう…野良猫トラブルの解決方法
ご近所でばったり野良猫に出会ったこと、皆様ありますよね。 野良猫、屋外飼育してされている猫ちゃんの数は東京都が推定数を試算しており、その数なんと都内だけで12万頭にも及ぶとされています。(平成29年度)これだけの数がいれば当然、糞尿被害や繁殖問題など様々なトラブルが発生します。そこで今回は野良猫にまつわるトラブルを対策も含めご紹介していきます。 敷地内での糞尿被害 野良猫トラブルで最も耳にするのは住宅の敷地内や公園での糞尿被害です。過去には都内の砂場、その約半数が猫の糞尿からくる寄生虫に汚染されているという調査報告があがった年もありました。それでも公園などの公共施設は管轄している地区が定期的に点検、消毒を行ってくれます。しかし、住宅の周りはご自身でケアするしかありません。猫ちゃんの糞尿はマーキングも兼ねているため元々臭いがきつく、時間が経過することで更に悪臭が強まってしまいます。そしてその臭いを辿ってまた猫ちゃん達がマーキングしにくる、という悪循環が生まれるのです。そこで対策方法として【入らせない】【残さない】【臭いを消す】がポイントです。具体例としては…・敷地に入れないようネットやトゲ付きマットでガードする・排泄物は見つけ次第処理、水で流す・木酢液を希釈し散布する・臭い残りがきつい場所にはハイターの希釈液を散布する・置物や超音波の猫避けグッズを配置するなどがあげられます。木酢液はホームセンターのガーデン用品売り場にありますのでチェックしてみてくださいね。なおハイターは人体にも猫ちゃんにも有害成分ですから、どうしても臭いが取れない場所にのみ使用し、使用後はしばらく立ち入れないよう工夫しておきましょう。 どんどん増えてしまう繁殖問題 猫ちゃん達は1回の出産で5頭前後の子猫を産みます。外猫ちゃん達の一生はとても過酷です。家猫ちゃんの平均寿命が15歳前後なのに対し、外で暮らす猫ちゃん達は5歳前後までしか生きることができません。感染症や飢え、外敵からの攻撃、気温、交通事故、外にある全てがその命を脅かす脅威なのです。野良猫ちゃんにご飯をあげたくなる気持ちもとてもよくわかるのですが、中途半端な優しさはかえって猫ちゃん達を過酷な環境に放り出すことになってしまいます。この繁殖問題に歯止めをかけるには避妊、去勢の手術を行うしかありません。ご自身で保護し、手術を受けさせてからまた外に戻す。という方も多くいらっしゃいます。このような場合は事前に動物病院にその旨を伝えておくと、手術の最後にお耳の端っこをカットし、誰が見ても手術済であることがわかるようにしてくれます。こうすると再び手術のために保護されてしまう事を防ぐことができます。地域によっては猫ちゃんの避妊去勢手術に助成金を出している場所もありますので居住地区の役所で確認してみてくださいね。 野良猫を保護するときの注意点 野良猫ちゃんの保護は並大抵のことではありません。子猫であっても3か月以上の子猫であれば暴れて咬みつく可能性も大いにあります。成猫になると容易に触ることはできないかと思います。このような時は、愛護団体や保護ボランティアさんの手が借りられないか聞いてみましょう。中には猫の捕獲機を貸してくれることもあります。ご自身で保護される場合はケージ、バスタオル、軍手、洗濯ネットを用意し長そで長ズボンで挑みましょう。バスタオルを上からかけ、静かに抱き上げ速やかにケージに入れます。この時に洗濯ネットに入れることができるとその後の動物病院での受診、処置がとってもスムーズに進みます。もちろん無理はせず、暴れたり逃げ出してしまう時は日を改めてください。この時のポイントはとにかく物音を立てず、静かに行う事です。もし引っかかれたり、咬まれてしまった時は細菌感染を起こしてしまう可能性があります。様子を見ず、その日のうちに外科を受診なさってくださいね。 最後に いかがでしたか?野良猫ちゃん達に何も非はないとわかっていても、糞尿被害には頭を抱えてしまいますよね。もし野良猫ちゃんを保護する場合は手術後にリリースするのか、里親を探すのか、などその後のこともしっかり検討してから行動しましょう。全ての猫ちゃん達が幸せな暮らしができるよう、対策を行い共存していけたらいいですね。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

犬連れのキャンプを楽しむ最強アイテムが登場しました【ibiyaya アウトドア ペットワゴン】
近年では、第二次キャンプブームも到来し、ひと昔前までは少し敷居の高かったものの今や家族や友達と手軽に楽しめるようになりました。最近では、1人で行くソロキャンや女子キャンという言葉もよく聞くようになりましたね。その中でも特に、ワンちゃんを一緒に連れて行けるキャンプ場が、登場したと同時に瞬く間に全国に広がったのです。愛犬と一緒に自然を楽しめるなんて最高ですよね♪そこでOFTからも、ワンちゃんと一緒にアウトドアを楽しむペットワゴンが登場しました。その名も『ibiyaya アウトドア ペットワゴン』です。従来のペットカートと一味違い、アウトドアを楽しみたい方に自信を持ってオススメできる製品なのです! 多頭での移動が便利 元気いっぱいに自然を走り回るワンちゃん達の姿は微笑ましいですが、多頭での移動は四方八方へ行ってしまい大変ですよね。ibiyaya アウトドア ペットワゴンでは、耐荷重は約50㎏までなら小型犬や中型犬なら複数匹一緒に乗せることができるのでストレスは一切ありません。 ワゴンの中には、大きめの飛び出し防止リードも2本ついているので、なお安心ですよ。 ▲ステップ付きでワンちゃん自身で乗り降りしてくれます。 引いて運ぶペットワゴン ▲ルーフは取り外し可能 大きく持ちやすく設計されたハンドルを引くので、重くても楽に運ぶことができます。直径約27㎝の大きなタイヤで、安定感も抜群!そのうえ、座面もクッション素材でできているので、ワンちゃん達の移動も快適です。 多目的に使用可能 もちろんアウトドア用カートとしての併用も可能です。キャンプ用品を運んだり、荷物置き場としても活用下さいね。折りたためて、車にも乗せることができるので、ちょっとしたお出かけにも使って頂けます。 ▲コンパクトに畳んで車に収納 男心をくすぐってしまうフォルム 新発売前に、インテックス大阪にて『Pet Exposition 2021 Pet博 大阪会場』にて展示させて頂きました。詳細はこちら 『Pet Exposition 2021 Pet博 大阪会場』出展レポート その中でも、キャンプ好きの男性方の注目の的となったのがこちらのペットワゴンです!存在感のある頑丈なフレームなのに、場所を選ばずどこでも軽快に移動できるところが男性陣の心をくすぐったのかもしれませんね♪飼い主さんにも、ワンちゃんにも嬉しい機能満載のこちらのペットワゴンで、思い切りアウトドアを楽しんで下さいね。ibiyaya アウトドア ペットワゴンの詳細はこちら
犬連れのキャンプを楽しむ最強アイテムが登場しました【ibiyaya アウトドア ペットワゴン】
近年では、第二次キャンプブームも到来し、ひと昔前までは少し敷居の高かったものの今や家族や友達と手軽に楽しめるようになりました。最近では、1人で行くソロキャンや女子キャンという言葉もよく聞くようになりましたね。その中でも特に、ワンちゃんを一緒に連れて行けるキャンプ場が、登場したと同時に瞬く間に全国に広がったのです。愛犬と一緒に自然を楽しめるなんて最高ですよね♪そこでOFTからも、ワンちゃんと一緒にアウトドアを楽しむペットワゴンが登場しました。その名も『ibiyaya アウトドア ペットワゴン』です。従来のペットカートと一味違い、アウトドアを楽しみたい方に自信を持ってオススメできる製品なのです! 多頭での移動が便利 元気いっぱいに自然を走り回るワンちゃん達の姿は微笑ましいですが、多頭での移動は四方八方へ行ってしまい大変ですよね。ibiyaya アウトドア ペットワゴンでは、耐荷重は約50㎏までなら小型犬や中型犬なら複数匹一緒に乗せることができるのでストレスは一切ありません。 ワゴンの中には、大きめの飛び出し防止リードも2本ついているので、なお安心ですよ。 ▲ステップ付きでワンちゃん自身で乗り降りしてくれます。 引いて運ぶペットワゴン ▲ルーフは取り外し可能 大きく持ちやすく設計されたハンドルを引くので、重くても楽に運ぶことができます。直径約27㎝の大きなタイヤで、安定感も抜群!そのうえ、座面もクッション素材でできているので、ワンちゃん達の移動も快適です。 多目的に使用可能 もちろんアウトドア用カートとしての併用も可能です。キャンプ用品を運んだり、荷物置き場としても活用下さいね。折りたためて、車にも乗せることができるので、ちょっとしたお出かけにも使って頂けます。 ▲コンパクトに畳んで車に収納 男心をくすぐってしまうフォルム 新発売前に、インテックス大阪にて『Pet Exposition 2021 Pet博 大阪会場』にて展示させて頂きました。詳細はこちら 『Pet Exposition 2021 Pet博 大阪会場』出展レポート その中でも、キャンプ好きの男性方の注目の的となったのがこちらのペットワゴンです!存在感のある頑丈なフレームなのに、場所を選ばずどこでも軽快に移動できるところが男性陣の心をくすぐったのかもしれませんね♪飼い主さんにも、ワンちゃんにも嬉しい機能満載のこちらのペットワゴンで、思い切りアウトドアを楽しんで下さいね。ibiyaya アウトドア ペットワゴンの詳細はこちら

ワンちゃんと素敵なドライブの旅へ
ワンちゃんの通院や一緒にお買い物、また遠出の旅行などで、一緒に車で移動する時はクレートやドライブボックス、犬用のシートベルトなどを利用して安全対策を行います。今回は安全面はもちろんのこと、さらに可愛くて車内が和む「ブースターボックス」をご紹介したいと思います。 運転中のリスク 運転中にあまりのワンちゃんの可愛いさに膝の上へ乗せてしまったり、ついつい助手席の窓から顔を出したまま車を走らせてしまったりすることはありませんか?実は、このような行為は道路交通法に抵触しており、何よりも非常に危険なのです。しっかり気を付けていても、とっさの急ブレーキや他の車からの追突など思わぬ瞬間は起こります。突然の衝撃でパニックになったワンちゃんが運転席へ潜り込んで来たり、窓から投げ出されてしまう可能性があるうえ、安全のためのエアバッグの展開の衝撃で大けがを負わせてしまうことも。飼い主さんはどんな時でもペットの安全を第一に考えて安全措置を講じる義務があり、さらには運転に専念できるような環境作りが必要です。せっかくのワンちゃんとのお出掛け、ぜひ楽しみたいですよね♪ ブースターボックス ▲ブースターボックス ラタン ブースターボックスは車の座席に取り付けるワンちゃん専用指定席です。ボックスをワンちゃんの目線と窓の高さに合わせて設置すれば、座ったまま外の景色を見ることができ、腰の負担が軽減されるのは嬉しいですよね♪ 飛び出し防止用のリードを繋いでおけば転げ落ちることもなく、窓やドアから飛び出してしまう心配もありません。リードは2本付属していますので、小型のワンちゃんであれば2匹一緒に入れてあげることが可能です。 ▲飛び出し防止リード(2本) また、抜け毛の散らかりやお外遊びでの汚れが気になる場合も、直接シートにふれないので車内を綺麗に保てます。もちろん、クッションカバー、本体カバーともに手洗い可能なので清潔に長くお使いいただけます。 フェイクファーをあしらったニット柄と、リラックス感溢れるラタン柄の2種類をご用意しました。ブースターボックスニットは、フワフワで見た目も暖かく、これから寒くなる秋冬に向けてオススメです♪ 簡単組み立て 組み立ては工具も不要で一人で簡単に装着することができます。シートベルトを通すループが付いているので、助手席だけでなく後部座席に取り付けられるのもポイントです♪ワンちゃんが乗らないときはコンパクトに畳んで収納して下さいね。 ワンちゃんの喜ぶ設計 ワンちゃんも景色を楽しみながらリラックス♪車の振動も軽減されるので、車酔いしてしまう子にも優しいですね。フチや底にはクッション性を持たせてあるので、長距離移動でも疲れずゆったり過ごせます。是非ドライブボックスを活用して、車でのお出掛けを楽しんでくださいね!ブースターボックスの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼
ワンちゃんと素敵なドライブの旅へ
ワンちゃんの通院や一緒にお買い物、また遠出の旅行などで、一緒に車で移動する時はクレートやドライブボックス、犬用のシートベルトなどを利用して安全対策を行います。今回は安全面はもちろんのこと、さらに可愛くて車内が和む「ブースターボックス」をご紹介したいと思います。 運転中のリスク 運転中にあまりのワンちゃんの可愛いさに膝の上へ乗せてしまったり、ついつい助手席の窓から顔を出したまま車を走らせてしまったりすることはありませんか?実は、このような行為は道路交通法に抵触しており、何よりも非常に危険なのです。しっかり気を付けていても、とっさの急ブレーキや他の車からの追突など思わぬ瞬間は起こります。突然の衝撃でパニックになったワンちゃんが運転席へ潜り込んで来たり、窓から投げ出されてしまう可能性があるうえ、安全のためのエアバッグの展開の衝撃で大けがを負わせてしまうことも。飼い主さんはどんな時でもペットの安全を第一に考えて安全措置を講じる義務があり、さらには運転に専念できるような環境作りが必要です。せっかくのワンちゃんとのお出掛け、ぜひ楽しみたいですよね♪ ブースターボックス ▲ブースターボックス ラタン ブースターボックスは車の座席に取り付けるワンちゃん専用指定席です。ボックスをワンちゃんの目線と窓の高さに合わせて設置すれば、座ったまま外の景色を見ることができ、腰の負担が軽減されるのは嬉しいですよね♪ 飛び出し防止用のリードを繋いでおけば転げ落ちることもなく、窓やドアから飛び出してしまう心配もありません。リードは2本付属していますので、小型のワンちゃんであれば2匹一緒に入れてあげることが可能です。 ▲飛び出し防止リード(2本) また、抜け毛の散らかりやお外遊びでの汚れが気になる場合も、直接シートにふれないので車内を綺麗に保てます。もちろん、クッションカバー、本体カバーともに手洗い可能なので清潔に長くお使いいただけます。 フェイクファーをあしらったニット柄と、リラックス感溢れるラタン柄の2種類をご用意しました。ブースターボックスニットは、フワフワで見た目も暖かく、これから寒くなる秋冬に向けてオススメです♪ 簡単組み立て 組み立ては工具も不要で一人で簡単に装着することができます。シートベルトを通すループが付いているので、助手席だけでなく後部座席に取り付けられるのもポイントです♪ワンちゃんが乗らないときはコンパクトに畳んで収納して下さいね。 ワンちゃんの喜ぶ設計 ワンちゃんも景色を楽しみながらリラックス♪車の振動も軽減されるので、車酔いしてしまう子にも優しいですね。フチや底にはクッション性を持たせてあるので、長距離移動でも疲れずゆったり過ごせます。是非ドライブボックスを活用して、車でのお出掛けを楽しんでくださいね!ブースターボックスの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

【2022年6月】犬猫のマイクロチップ装着の義務化におけるメリットやデメリットは?
2022年6月より動物愛護保護法のもと、犬猫のマイクロチップ装着が義務化することになりました。義務化するのは生体販売を行うペットショップやブリーダーさんに限定され、既に飼育している方はできるだけ装着といった努力義務となりますが、中には異物を体に入れるようで怖い、と感じている方も多いのではないでしょうか?そこで、この記事ではマイクロチップの必要性やメリット、デメリットをまとめてご紹介していきます。 マイクロチップとは ▲インジェクター(マイクロチップ挿入機) マイクロチップとはその名の通りとても小さい電子標識チップです。大きさは直径2mm、長さは10mm前後で、その中には世界に一つだけの15桁の識別番号が入っています。この番号と飼い主さんの情報を紐付けることで、体の中に絶対紛失する事のない迷子札が入ったことになります。専用の読み込み機をペットの体にかざすことで識別番号を表示させることができ、その番号をインターネットや獣医師会で照会することで、飼い主さんの情報も確認することができます。読み込み機は動物病院や保健所、保護センターなどに置かれており、迷子の猫ちゃんやわんちゃんが保護された場合はまずマイクロチップの有無が確認され、飼い主さんへ連絡がいくという流れになります。 装着方法 マイクロチップの装着は動物病院で行うことができます。在庫がない場合もありますので一度電話で確認してから向かいましょう。注射器より少し太いインジェクターという器具で体内に挿入します。痛そうに見えますが皮下に打ちますので、通常の注射と痛みはほとんど変わらないと言われています。実際挿入に立ち会う機会も多いのですが、ほとんどの子は雰囲気に緊張している間にいつのまにか終わっている…!といった印象です。見ている飼い主さんの方がドキドキしてしまうかもしれませんね。首のうしろ部分に挿入するのが一般的で麻酔や鎮静などは必要ありません。数十秒から1分程度で終了し、その後シャンプーや運動をしても問題ありませんのでご安心くださいね。 装着後の手続き ▲挿入済みのチップをリーダーで確認中 実は動物病院で行うのは『マイクロチップの装着』のみで、飼い主さんの情報登録の手続きはできません。挿入されたマイクロチップの識別番号は空っぽで、まだ飼い主さんの情報は何も入っていませんので注意してくださいね。マイクロチップ装着後はインターネット、もしくは申請用紙にて飼い主さん自身で情報登録の手続きを行います。申請用紙は動物病院でもらえますので装着後は忘れずに申請用紙をもらって帰りましょう。登録先は【動物ID普及推進会議(AIPO)】になります。この団体が飼い主さんの情報を一括して管理していますので、お引越しや電話番号の変更があったときは忘れずに情報変更の手続きをとりましょう。登録内容は飼い主さんの住所や電話番号(2つ)、アドレス、ペットの名前、毛色や種別など様々です。緊急時に使用される連絡先ですので、空欄は作らず全て埋めておくと安心です。 料金 マイクロチップにかかる料金は2種類です。まず、動物病院に支払う装着費用の2千円から5千円程度(支払う金額は病院差があります)、そして環境省によるとAIPOに支払う登録料がWeb申請で300円、書面での申請が1000円です。 メリットとデメリット マイクロチップ最大のメリットは迷子になった時、飼い主さんの元に帰ってこられる確率がグッとあがる事です。普段どんなに注意していても災害時などにはぐれてしまう可能性はあります。事実、東日本大震災時には多くのペット達が飼い主さんと離ればなれになってしまいました。マイクロチップは迷子札や首輪のように外れてしまう事がない点でも安心です。デメリットとしては装着に多少の痛みを感じる、MRI撮影時に画像がゆがむ可能性があるなどがあげられます。ただしMRI撮影は大きな病気や手術をする時にしか撮影せず、撮影自体ができないわけでもありません。また撮影してもペットの体には影響しませんのでご安心くださいね。 マイクロチップを利用した製品 ▲シュアーフィーダーマイクロチップ こちらの給餌器は、マイクロチップを付けた猫ちゃんや、専用タグを付けている猫ちゃんが近づくとセンサーが感知し、自動で蓋の開け閉めをしてくれます。マイクロチップが多頭飼育でのそれぞれの猫ちゃんを識別してくれるので、エサの奪い合いも防止することができます。今後、マイクロチップを装着しているペットが増えると共に、このような便利な商品もどんどん登場していくのではないでしょうか♪シュアーフィーダーマイクロチップの詳細はこちら まとめ いかがでしたか?装着に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、マイクロチップの挿入による健康被害はないと獣医師会も発表しています。実際に、今までに数百頭のマイクロチップ装着に立ち会ってきましたが、それによって体調を壊してしまう子は見ていません。もちろん強制ではありませんから、シニアや持病があるペットちゃん達は無理をする必要はありませんが、シニア期のワンちゃんは痴呆が始まり徘徊しながら行方不明になってしまうことも。迷われる方は是非獣医師にご相談なさってくださいね。愛犬の体調や性格を踏まえ検討してみましょう! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
【2022年6月】犬猫のマイクロチップ装着の義務化におけるメリットやデメリットは?
2022年6月より動物愛護保護法のもと、犬猫のマイクロチップ装着が義務化することになりました。義務化するのは生体販売を行うペットショップやブリーダーさんに限定され、既に飼育している方はできるだけ装着といった努力義務となりますが、中には異物を体に入れるようで怖い、と感じている方も多いのではないでしょうか?そこで、この記事ではマイクロチップの必要性やメリット、デメリットをまとめてご紹介していきます。 マイクロチップとは ▲インジェクター(マイクロチップ挿入機) マイクロチップとはその名の通りとても小さい電子標識チップです。大きさは直径2mm、長さは10mm前後で、その中には世界に一つだけの15桁の識別番号が入っています。この番号と飼い主さんの情報を紐付けることで、体の中に絶対紛失する事のない迷子札が入ったことになります。専用の読み込み機をペットの体にかざすことで識別番号を表示させることができ、その番号をインターネットや獣医師会で照会することで、飼い主さんの情報も確認することができます。読み込み機は動物病院や保健所、保護センターなどに置かれており、迷子の猫ちゃんやわんちゃんが保護された場合はまずマイクロチップの有無が確認され、飼い主さんへ連絡がいくという流れになります。 装着方法 マイクロチップの装着は動物病院で行うことができます。在庫がない場合もありますので一度電話で確認してから向かいましょう。注射器より少し太いインジェクターという器具で体内に挿入します。痛そうに見えますが皮下に打ちますので、通常の注射と痛みはほとんど変わらないと言われています。実際挿入に立ち会う機会も多いのですが、ほとんどの子は雰囲気に緊張している間にいつのまにか終わっている…!といった印象です。見ている飼い主さんの方がドキドキしてしまうかもしれませんね。首のうしろ部分に挿入するのが一般的で麻酔や鎮静などは必要ありません。数十秒から1分程度で終了し、その後シャンプーや運動をしても問題ありませんのでご安心くださいね。 装着後の手続き ▲挿入済みのチップをリーダーで確認中 実は動物病院で行うのは『マイクロチップの装着』のみで、飼い主さんの情報登録の手続きはできません。挿入されたマイクロチップの識別番号は空っぽで、まだ飼い主さんの情報は何も入っていませんので注意してくださいね。マイクロチップ装着後はインターネット、もしくは申請用紙にて飼い主さん自身で情報登録の手続きを行います。申請用紙は動物病院でもらえますので装着後は忘れずに申請用紙をもらって帰りましょう。登録先は【動物ID普及推進会議(AIPO)】になります。この団体が飼い主さんの情報を一括して管理していますので、お引越しや電話番号の変更があったときは忘れずに情報変更の手続きをとりましょう。登録内容は飼い主さんの住所や電話番号(2つ)、アドレス、ペットの名前、毛色や種別など様々です。緊急時に使用される連絡先ですので、空欄は作らず全て埋めておくと安心です。 料金 マイクロチップにかかる料金は2種類です。まず、動物病院に支払う装着費用の2千円から5千円程度(支払う金額は病院差があります)、そして環境省によるとAIPOに支払う登録料がWeb申請で300円、書面での申請が1000円です。 メリットとデメリット マイクロチップ最大のメリットは迷子になった時、飼い主さんの元に帰ってこられる確率がグッとあがる事です。普段どんなに注意していても災害時などにはぐれてしまう可能性はあります。事実、東日本大震災時には多くのペット達が飼い主さんと離ればなれになってしまいました。マイクロチップは迷子札や首輪のように外れてしまう事がない点でも安心です。デメリットとしては装着に多少の痛みを感じる、MRI撮影時に画像がゆがむ可能性があるなどがあげられます。ただしMRI撮影は大きな病気や手術をする時にしか撮影せず、撮影自体ができないわけでもありません。また撮影してもペットの体には影響しませんのでご安心くださいね。 マイクロチップを利用した製品 ▲シュアーフィーダーマイクロチップ こちらの給餌器は、マイクロチップを付けた猫ちゃんや、専用タグを付けている猫ちゃんが近づくとセンサーが感知し、自動で蓋の開け閉めをしてくれます。マイクロチップが多頭飼育でのそれぞれの猫ちゃんを識別してくれるので、エサの奪い合いも防止することができます。今後、マイクロチップを装着しているペットが増えると共に、このような便利な商品もどんどん登場していくのではないでしょうか♪シュアーフィーダーマイクロチップの詳細はこちら まとめ いかがでしたか?装着に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、マイクロチップの挿入による健康被害はないと獣医師会も発表しています。実際に、今までに数百頭のマイクロチップ装着に立ち会ってきましたが、それによって体調を壊してしまう子は見ていません。もちろん強制ではありませんから、シニアや持病があるペットちゃん達は無理をする必要はありませんが、シニア期のワンちゃんは痴呆が始まり徘徊しながら行方不明になってしまうことも。迷われる方は是非獣医師にご相談なさってくださいね。愛犬の体調や性格を踏まえ検討してみましょう! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

多頭でも、猫ちゃんでも使える、便利なペットカート♪
ここ最近では、ペットの多頭飼育をされている飼い主さんが増えています。毎日、賑やかで癒されることも多いかと思いますが、その反面、移動に苦労される方も多いのでないでしょうか?そこで、今回は多頭でも使える分離型ペットカートをご紹介させて頂きます。 多頭で使いやすい機能 PGカート ドライブシステムは、丈夫なスチール製のフレームを使用。なのに軽量でコンパクトにたためるので、ペットの荷物が多い時でも簡単に持ち運びができます。また、耐荷重が約20kgとなっているのでチワワやトイプードルなどの小型犬なら一緒のカートに入ってお散歩を楽しんで頂けます♪コット内には飛び出し防止リードも2本ついているので安心して移動ができますよ。 ▲コット内の飛び出し防止リード2本 猫ちゃんの移動にも 普段、お家にいることが多い猫ちゃん達。通院時や急なお出かけでお困りの方に朗報です。このPGカート ドライブシステムは、ワンちゃんだけでなく、猫ちゃんにも乗って頂けます。また、コット部分を取り外して簡単に車のシートに取り付けが可能なので、猫ちゃんを待たすことなくすぐに出発できちゃいます♪360度全てがメッシュ素材になっているので、景色を見るのが好きな猫ちゃんにはピッタリですね。顔を合わせながら対面式でカートも押せるので、飼い主様のニコニコ笑顔で可愛いペット達も安心してくれますよ。 ▲360度メッシュ素材で周りを見渡せるからこそ、ペット達も安心します♪ ▲飼い主様の笑顔がペット達の安心感につながります。 暑さも和らぎ過ごしやすい気候の今、ペット達まで笑顔になるPGカート ドライブシステムはいかがでしょうか?PGカート ドライブシステムの詳細はこちら 関連ブログはこちら新製品【PGカートドライブシステム】の発売が開始しました ▼ この記事を書いたのは ▼
多頭でも、猫ちゃんでも使える、便利なペットカート♪
ここ最近では、ペットの多頭飼育をされている飼い主さんが増えています。毎日、賑やかで癒されることも多いかと思いますが、その反面、移動に苦労される方も多いのでないでしょうか?そこで、今回は多頭でも使える分離型ペットカートをご紹介させて頂きます。 多頭で使いやすい機能 PGカート ドライブシステムは、丈夫なスチール製のフレームを使用。なのに軽量でコンパクトにたためるので、ペットの荷物が多い時でも簡単に持ち運びができます。また、耐荷重が約20kgとなっているのでチワワやトイプードルなどの小型犬なら一緒のカートに入ってお散歩を楽しんで頂けます♪コット内には飛び出し防止リードも2本ついているので安心して移動ができますよ。 ▲コット内の飛び出し防止リード2本 猫ちゃんの移動にも 普段、お家にいることが多い猫ちゃん達。通院時や急なお出かけでお困りの方に朗報です。このPGカート ドライブシステムは、ワンちゃんだけでなく、猫ちゃんにも乗って頂けます。また、コット部分を取り外して簡単に車のシートに取り付けが可能なので、猫ちゃんを待たすことなくすぐに出発できちゃいます♪360度全てがメッシュ素材になっているので、景色を見るのが好きな猫ちゃんにはピッタリですね。顔を合わせながら対面式でカートも押せるので、飼い主様のニコニコ笑顔で可愛いペット達も安心してくれますよ。 ▲360度メッシュ素材で周りを見渡せるからこそ、ペット達も安心します♪ ▲飼い主様の笑顔がペット達の安心感につながります。 暑さも和らぎ過ごしやすい気候の今、ペット達まで笑顔になるPGカート ドライブシステムはいかがでしょうか?PGカート ドライブシステムの詳細はこちら 関連ブログはこちら新製品【PGカートドライブシステム】の発売が開始しました ▼ この記事を書いたのは ▼

犬の習性を利用してトイレトレーニングを
可愛いワンちゃんと家族になったその日からすぐに始めたいのが「トイレトレーニング」です。迎えた子が子犬でも成犬でも、トイレの場所をなるべく早く覚えてもらいたいですよね。ところが、トレーニング完了した後でも、突然外でしかオシッコをしなくなったり、室内のあらゆる場所にマーキングを始めてしまったりするワンちゃんもいます。そんな飼い主さんへ、置くだけでトイレのマナーが身についてしまう便利なアイテム、『マーキングポール』をご紹介します。ワンちゃん自らポールを狙い撃ちにいくワンダフルな商品ですよ♪ ワンちゃんがトイレで足上げする理由 本能的に自分の縄張りを示す犬の習性の1つで、足を上げて少量のオシッコをかける行為をマーキングといいます。より高い位置にかけることで他の犬のニオイを消したり、自分を大きく見せたりする効果もあり、中には両足をあげ逆立ちになる子もいるほど、ワンちゃんにとっては重要性の高いものなんですね。去勢していない男の子だけの行動と思われがちですが、去勢後でも、さらには発情期や自己主張の強い女の子も同様に行います。また他にも、不安や興奮、ストレスなどもマーキングという形で表れるようです。 マーキングポールとは 条件反射で柱に足を上げてしまうワンちゃんの習性を利用して、そのままトイレの場所を定着させよう!と開発されたのが「マーキングポール」です。見た目はとってもシンプルですが効果は抜群で、ワンちゃんも飼い主さんもストレスなく、設置するだけで自然にトイレトレーニングが行えます。 使用するメリット 土台、ポール、キャップの簡単構造で、いつも使用しているペットシーツを巻き付け、お好きな場所にすぐ設置できます。取り換えもペットシーツを交換するだけで、手を汚すことは無く、汚れを拭きとるだけでお手入れもらくちんです。汚れがひどい時は、丸ごと水洗いが可能なので中性洗剤を使って優しく洗ってくださいね。 マーキングポールを置くことにより、自然とワンちゃんがポールに向かってオシッコをしてくれるので、マーキングを室内のあちらこちらにしてしまう、また広範囲に飛ばしてペットシーツの裏までビショビショ、お掃除が大変!という飼い主様のストレスも軽減できます♪ クリアレット2との併用がオススメ ▲デザイナーズトイレ クリアレット2シリーズ マーキングポールと相性抜群のトイレトレーがこちらの「クリアレット2」です。むれないメッシュトレータイプと、シーツのズレを防ぐストッパータイプの2種類あり、クリアレット2専用「飛散ガード ハイタイプ」を合わせて使用すれば、左右・後方の3方向への飛び散りもしっかりガードできます。透明な本体はインテリアの邪魔をしないので、リビングや寝室などどこにでもとけこみます。こちらも、パーツを外して丸洗いもできて常に清潔に保つことができるのが嬉しいですよね。マーキング癖が付いてしまった子も、これからトレーニングが始まる子も、トイレが上手になるマーキングポールを是非とも活用して下さいね。ワンちゃんとの暮らしがさらに快適なものになりますよ♪マーキングポールホワイトの詳細はこちらクリアレット2シリーズの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼
犬の習性を利用してトイレトレーニングを
可愛いワンちゃんと家族になったその日からすぐに始めたいのが「トイレトレーニング」です。迎えた子が子犬でも成犬でも、トイレの場所をなるべく早く覚えてもらいたいですよね。ところが、トレーニング完了した後でも、突然外でしかオシッコをしなくなったり、室内のあらゆる場所にマーキングを始めてしまったりするワンちゃんもいます。そんな飼い主さんへ、置くだけでトイレのマナーが身についてしまう便利なアイテム、『マーキングポール』をご紹介します。ワンちゃん自らポールを狙い撃ちにいくワンダフルな商品ですよ♪ ワンちゃんがトイレで足上げする理由 本能的に自分の縄張りを示す犬の習性の1つで、足を上げて少量のオシッコをかける行為をマーキングといいます。より高い位置にかけることで他の犬のニオイを消したり、自分を大きく見せたりする効果もあり、中には両足をあげ逆立ちになる子もいるほど、ワンちゃんにとっては重要性の高いものなんですね。去勢していない男の子だけの行動と思われがちですが、去勢後でも、さらには発情期や自己主張の強い女の子も同様に行います。また他にも、不安や興奮、ストレスなどもマーキングという形で表れるようです。 マーキングポールとは 条件反射で柱に足を上げてしまうワンちゃんの習性を利用して、そのままトイレの場所を定着させよう!と開発されたのが「マーキングポール」です。見た目はとってもシンプルですが効果は抜群で、ワンちゃんも飼い主さんもストレスなく、設置するだけで自然にトイレトレーニングが行えます。 使用するメリット 土台、ポール、キャップの簡単構造で、いつも使用しているペットシーツを巻き付け、お好きな場所にすぐ設置できます。取り換えもペットシーツを交換するだけで、手を汚すことは無く、汚れを拭きとるだけでお手入れもらくちんです。汚れがひどい時は、丸ごと水洗いが可能なので中性洗剤を使って優しく洗ってくださいね。 マーキングポールを置くことにより、自然とワンちゃんがポールに向かってオシッコをしてくれるので、マーキングを室内のあちらこちらにしてしまう、また広範囲に飛ばしてペットシーツの裏までビショビショ、お掃除が大変!という飼い主様のストレスも軽減できます♪ クリアレット2との併用がオススメ ▲デザイナーズトイレ クリアレット2シリーズ マーキングポールと相性抜群のトイレトレーがこちらの「クリアレット2」です。むれないメッシュトレータイプと、シーツのズレを防ぐストッパータイプの2種類あり、クリアレット2専用「飛散ガード ハイタイプ」を合わせて使用すれば、左右・後方の3方向への飛び散りもしっかりガードできます。透明な本体はインテリアの邪魔をしないので、リビングや寝室などどこにでもとけこみます。こちらも、パーツを外して丸洗いもできて常に清潔に保つことができるのが嬉しいですよね。マーキング癖が付いてしまった子も、これからトレーニングが始まる子も、トイレが上手になるマーキングポールを是非とも活用して下さいね。ワンちゃんとの暮らしがさらに快適なものになりますよ♪マーキングポールホワイトの詳細はこちらクリアレット2シリーズの詳細はこちら ▼ この記事を書いたのは ▼

リードは愛犬の命を守る。すべての子に着用を!
お散歩に欠かせないリード。色々なデザインやブランドがあり、似合うものを選ぶ時間も楽しいひと時ですよね。そんな当たり前に使っているリードが、どれほどの危険から愛犬を守ってくれているか皆様ご存知でしょうか?そして、リードをつけることで守られるのは愛犬の命だけではありません。今回は改めてリードの大切さやその役割についてご紹介していきます。 こんな危険から愛犬を守ります リードがないことでワンちゃん達がさらされる危険は大きく分けて交通事故、咬傷事故、そして脱走の3つです。そして、どれもリードを正しく装着していれば防ぐことができる事故なのです。実際に動物病院で勤務していると年間で数頭は交通事故に遭ったワンちゃん達に出会います。命を失ってしまう子、後遺症を抱えてしまう子、大きな手術を受ける子、その代償はあまりに大きく悲しいものです。また都内だけを見ても年間で300件ほどの咬傷事故が起きています。咬んでしまった、咬まれてしまった、その後飼い主同士でトラブルになってしまうなど、こちらも事故から解決までに時間を要するケースが多くあります。ワンちゃん達の移動距離はとても広いので脱走したまま、行方不明になってしまうことも。リード1本でこれだけの危険から愛犬を、そして飼い主さん自身を守ることができるのです。 リードをつけなくていい子はいません 中にはリードがなくてもぴったりと飼い主さんの後をついてきてくれるワンちゃんもいますよね。シニア期に入りもう走らない、臆病な性格で動かない、などリードの必要性をあまり感じない方もいらっしゃるかもしれません。ですが、私が勤務中に対応してきたワンちゃん達も皆大人しく、賢く、従順な性格でした。どんなにお利口さんでも、車の運転手からは愛犬の姿は全く見えていないのです。リードがなければ尚更散歩中とは認識してもらえないでしょう。また愛犬自身が飛び出したり、咬みつくことがなかったとしても、他のワンちゃんは飛びかかってきたりするかもしれません。どんなにいい子であっても、リードの着用がいらないワンちゃんは一頭もいないのです。 つける場所、外す場所のメリハリを♪ とはいえ、リードに縛られず思いっきり走らせてあげたいのも親心です。そんな時は是非ドッグランを活用しましょう♪ノーリードOKのドッグランも多くあります。小型、中型、大型と愛犬の体格別にスペースを分けている場所も多いので安心感できますね。近くにドッグランがない方はロングリードを使って広い公園や広場をお散歩しても楽しいですよ。ただし、ワンちゃんが苦手な方もいますのでいざという時はすぐに愛犬を呼び戻せるよう注意はしておきましょう。反対にノーリードOKと明記されていない病院やサロン、ペットショップなどの場所でも必ず装着して下さいね。 リードを付けるときのポイント! 事故に遭ったワンちゃん達の中にはリードをつけていたけれど抜けてしまったという子もいます。これを防ぐために、まずは首輪の大きさが合っているか確認しましょう。首輪は飼い主さんの指が1~2本入るほどのきつさで着用します。つけた後に上に引っ張りあげ、抜けてしまわないかチェックしておくと安心です。また首輪とリードの接続部分も摩擦によって劣化していきます。定期的に新しいものに交換してあげてくださいね。それでもワンちゃん達の引っ張る力は強いので抜けてしまう可能性はゼロではありません。首輪とは別にハーネス(胴輪)を着用し、ダブルリードにしておくことが一番確実で安心な方法です。 多くの動物病院やペットホテルではこのダブルリードを基本としています。またハーネスは心臓や気管が弱いワンちゃん達でも負担なく着用できますので、持病があるワンちゃん達にもおススメです。 アイテムを活用してより快適に♪ ▲置き型の係留器具 K9アンカー お散歩やアウトドアに行った際、リードをつなぐ場所がなく困った方も多いかもしれません。そのような時は場所を選ばずリードフックの役割をしてくれるK9アンカーを活用してみましょう!脱走してしまう心配もなく一緒にお外を楽しむことができます♪色々なアイテムを活用して是非一緒に楽しんでくださいね!動物看護師になってから何頭も事故に遭ったワンちゃん達に出会ってきました。決して放任主義の飼い主様だったわけではなく、とても可愛がっておられた方ばかりです。愛犬を信用していたからこそのノーリードだったのだと思います。ですが事故はワンちゃんに非がなくとも降りかかってきてしまう物です。どうか命綱であるリードは外さず、沢山の危険から愛犬を守ってあげてくださいね! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
リードは愛犬の命を守る。すべての子に着用を!
お散歩に欠かせないリード。色々なデザインやブランドがあり、似合うものを選ぶ時間も楽しいひと時ですよね。そんな当たり前に使っているリードが、どれほどの危険から愛犬を守ってくれているか皆様ご存知でしょうか?そして、リードをつけることで守られるのは愛犬の命だけではありません。今回は改めてリードの大切さやその役割についてご紹介していきます。 こんな危険から愛犬を守ります リードがないことでワンちゃん達がさらされる危険は大きく分けて交通事故、咬傷事故、そして脱走の3つです。そして、どれもリードを正しく装着していれば防ぐことができる事故なのです。実際に動物病院で勤務していると年間で数頭は交通事故に遭ったワンちゃん達に出会います。命を失ってしまう子、後遺症を抱えてしまう子、大きな手術を受ける子、その代償はあまりに大きく悲しいものです。また都内だけを見ても年間で300件ほどの咬傷事故が起きています。咬んでしまった、咬まれてしまった、その後飼い主同士でトラブルになってしまうなど、こちらも事故から解決までに時間を要するケースが多くあります。ワンちゃん達の移動距離はとても広いので脱走したまま、行方不明になってしまうことも。リード1本でこれだけの危険から愛犬を、そして飼い主さん自身を守ることができるのです。 リードをつけなくていい子はいません 中にはリードがなくてもぴったりと飼い主さんの後をついてきてくれるワンちゃんもいますよね。シニア期に入りもう走らない、臆病な性格で動かない、などリードの必要性をあまり感じない方もいらっしゃるかもしれません。ですが、私が勤務中に対応してきたワンちゃん達も皆大人しく、賢く、従順な性格でした。どんなにお利口さんでも、車の運転手からは愛犬の姿は全く見えていないのです。リードがなければ尚更散歩中とは認識してもらえないでしょう。また愛犬自身が飛び出したり、咬みつくことがなかったとしても、他のワンちゃんは飛びかかってきたりするかもしれません。どんなにいい子であっても、リードの着用がいらないワンちゃんは一頭もいないのです。 つける場所、外す場所のメリハリを♪ とはいえ、リードに縛られず思いっきり走らせてあげたいのも親心です。そんな時は是非ドッグランを活用しましょう♪ノーリードOKのドッグランも多くあります。小型、中型、大型と愛犬の体格別にスペースを分けている場所も多いので安心感できますね。近くにドッグランがない方はロングリードを使って広い公園や広場をお散歩しても楽しいですよ。ただし、ワンちゃんが苦手な方もいますのでいざという時はすぐに愛犬を呼び戻せるよう注意はしておきましょう。反対にノーリードOKと明記されていない病院やサロン、ペットショップなどの場所でも必ず装着して下さいね。 リードを付けるときのポイント! 事故に遭ったワンちゃん達の中にはリードをつけていたけれど抜けてしまったという子もいます。これを防ぐために、まずは首輪の大きさが合っているか確認しましょう。首輪は飼い主さんの指が1~2本入るほどのきつさで着用します。つけた後に上に引っ張りあげ、抜けてしまわないかチェックしておくと安心です。また首輪とリードの接続部分も摩擦によって劣化していきます。定期的に新しいものに交換してあげてくださいね。それでもワンちゃん達の引っ張る力は強いので抜けてしまう可能性はゼロではありません。首輪とは別にハーネス(胴輪)を着用し、ダブルリードにしておくことが一番確実で安心な方法です。 多くの動物病院やペットホテルではこのダブルリードを基本としています。またハーネスは心臓や気管が弱いワンちゃん達でも負担なく着用できますので、持病があるワンちゃん達にもおススメです。 アイテムを活用してより快適に♪ ▲置き型の係留器具 K9アンカー お散歩やアウトドアに行った際、リードをつなぐ場所がなく困った方も多いかもしれません。そのような時は場所を選ばずリードフックの役割をしてくれるK9アンカーを活用してみましょう!脱走してしまう心配もなく一緒にお外を楽しむことができます♪色々なアイテムを活用して是非一緒に楽しんでくださいね!動物看護師になってから何頭も事故に遭ったワンちゃん達に出会ってきました。決して放任主義の飼い主様だったわけではなく、とても可愛がっておられた方ばかりです。愛犬を信用していたからこそのノーリードだったのだと思います。ですが事故はワンちゃんに非がなくとも降りかかってきてしまう物です。どうか命綱であるリードは外さず、沢山の危険から愛犬を守ってあげてくださいね! ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

世界のペットとトイレ事情vol.1~スペイン、ロシア編
私たちオーエフティーでは、世界のペット用品を自らの足で探し、その中でもペット用トイレに力を入れて販売しています。アジアやヨーロッパなど様々な国のペットトイレを取り扱っていますが、その輸入している国の背景を知ることもまた大切だと考えています。今回は、色々な国のペット事情、またトイレ事情について数回に分けてご紹介したいと思います。 スペイン スペインの街中では、ペットと一緒に並んで散歩や食事、ショッピングなど楽しまれている飼い主さんを沢山見かけることができます。ペットと共に生活をすることが自然だと考えられているため、賃貸物件や集合住宅でもあえて『ペット可』と表示されることはほどんどないくらいです。 ▲ワンちゃんと共に走るマラソン大会も地方によって多々開催されます。 法律で禁止はされていますが、ノーリードの大型や中型のワンちゃんを連れて散歩を楽しむ飼い主さん達も多くみられます。それは、ペットが小さいうちからしつけやトレーニングに力を入れているため、しっかりと飼い主さんとの信頼関係が築かれているからです。ワンちゃん達も噛みついたり吠えたりすることなく、飼い主さんに寄り添っています。しかし、反対にマナーといえばまだまだ悪い部分も多く、町中にペット達の排泄物が落ちているのも現状です。ドイツなどヨーロッパの多くでは、ペットシーツの認知度も低く販売している店舗もほとんどないため、散歩時にすましていることが多いようです。対策として、マドリード市内ではワンちゃんのうんち専用のゴミ箱や専用のゴミ袋が町の至る所に設置されていたり、また、バルセロナのエル・ベンドレルという小さい町では、2014年になんと公衆の犬専用水洗トイレも登場したそうです! 参照:The Guardian for 200years いつか、わんちゃんと実際に訪れてみたいですね♪ ロシア連邦 世界的な調査会社「GfK(Growth from Knowledge)」が2016年に発表した「グローバルのペット飼育率調査」によると、ロシアでのペット飼育率はなんと73%と、ほとんどの家庭で何かしらの動物を飼育していることになります。ちなみに日本の飼育率は当時で37%です。大体の国で犬が1番多く飼われている中、ロシアでは犬の約2倍の猫ちゃんが飼育されています。ほぼ全土が寒冷気候に属しているため、基本的にペットは室内飼いをしているため、猫が飼いやすいうえに、もともと猫が好きな国民性であることが主な理由だとか。多くの方が生活している集合住宅でも飼育可能であることにも納得です。また、猫砂のラインナップも充実しています。郊外の方ではお金をかけず、往来の砂を箱に入れてトイレにされている飼い主さんも見られますが、都会の方では日本と同じく一般的なトレー型からシステムトイレまで様々です。ただ、雪道を持って歩くのが大変な餌や猫砂などの重いものは、オンラインショップで購入される方が多いようです。 冬の雪道での散歩はワンちゃんには厳しく、フットカバーを履かせるなど、ペット用品も充実しています。ロシアでは狂犬病のワクチンが義務付けられていないので、ワクチン接種をしていない犬が多いうえ、日本と同じく飼育放棄も問題となっているので元ペットの犬も合わせて野犬化となりウロウロしている光景も多くみられます。(外務省)しかしその反面、ロシア国内をペットと一緒に旅行するにはペットパスポート、海外でペットと旅行する場合は、目的国の法的要件と輸送する動物のタイプにより異なった国際ペットパスポートおよび/または関係する獣医師書類が必要です。(詳細はアエロフロート・ロシア航空HP参照)パスポートの中にワクチンの接種歴や治療歴、マイクロチップ情報などが管理されているのには驚きですね!次回も、世界の色々なペット達の生活を覗いてみたいと思います♪お楽しみに。 ▼ この記事を書いたのは ▼
世界のペットとトイレ事情vol.1~スペイン、ロシア編
私たちオーエフティーでは、世界のペット用品を自らの足で探し、その中でもペット用トイレに力を入れて販売しています。アジアやヨーロッパなど様々な国のペットトイレを取り扱っていますが、その輸入している国の背景を知ることもまた大切だと考えています。今回は、色々な国のペット事情、またトイレ事情について数回に分けてご紹介したいと思います。 スペイン スペインの街中では、ペットと一緒に並んで散歩や食事、ショッピングなど楽しまれている飼い主さんを沢山見かけることができます。ペットと共に生活をすることが自然だと考えられているため、賃貸物件や集合住宅でもあえて『ペット可』と表示されることはほどんどないくらいです。 ▲ワンちゃんと共に走るマラソン大会も地方によって多々開催されます。 法律で禁止はされていますが、ノーリードの大型や中型のワンちゃんを連れて散歩を楽しむ飼い主さん達も多くみられます。それは、ペットが小さいうちからしつけやトレーニングに力を入れているため、しっかりと飼い主さんとの信頼関係が築かれているからです。ワンちゃん達も噛みついたり吠えたりすることなく、飼い主さんに寄り添っています。しかし、反対にマナーといえばまだまだ悪い部分も多く、町中にペット達の排泄物が落ちているのも現状です。ドイツなどヨーロッパの多くでは、ペットシーツの認知度も低く販売している店舗もほとんどないため、散歩時にすましていることが多いようです。対策として、マドリード市内ではワンちゃんのうんち専用のゴミ箱や専用のゴミ袋が町の至る所に設置されていたり、また、バルセロナのエル・ベンドレルという小さい町では、2014年になんと公衆の犬専用水洗トイレも登場したそうです! 参照:The Guardian for 200years いつか、わんちゃんと実際に訪れてみたいですね♪ ロシア連邦 世界的な調査会社「GfK(Growth from Knowledge)」が2016年に発表した「グローバルのペット飼育率調査」によると、ロシアでのペット飼育率はなんと73%と、ほとんどの家庭で何かしらの動物を飼育していることになります。ちなみに日本の飼育率は当時で37%です。大体の国で犬が1番多く飼われている中、ロシアでは犬の約2倍の猫ちゃんが飼育されています。ほぼ全土が寒冷気候に属しているため、基本的にペットは室内飼いをしているため、猫が飼いやすいうえに、もともと猫が好きな国民性であることが主な理由だとか。多くの方が生活している集合住宅でも飼育可能であることにも納得です。また、猫砂のラインナップも充実しています。郊外の方ではお金をかけず、往来の砂を箱に入れてトイレにされている飼い主さんも見られますが、都会の方では日本と同じく一般的なトレー型からシステムトイレまで様々です。ただ、雪道を持って歩くのが大変な餌や猫砂などの重いものは、オンラインショップで購入される方が多いようです。 冬の雪道での散歩はワンちゃんには厳しく、フットカバーを履かせるなど、ペット用品も充実しています。ロシアでは狂犬病のワクチンが義務付けられていないので、ワクチン接種をしていない犬が多いうえ、日本と同じく飼育放棄も問題となっているので元ペットの犬も合わせて野犬化となりウロウロしている光景も多くみられます。(外務省)しかしその反面、ロシア国内をペットと一緒に旅行するにはペットパスポート、海外でペットと旅行する場合は、目的国の法的要件と輸送する動物のタイプにより異なった国際ペットパスポートおよび/または関係する獣医師書類が必要です。(詳細はアエロフロート・ロシア航空HP参照)パスポートの中にワクチンの接種歴や治療歴、マイクロチップ情報などが管理されているのには驚きですね!次回も、世界の色々なペット達の生活を覗いてみたいと思います♪お楽しみに。 ▼ この記事を書いたのは ▼

コロナ禍でのwithペット生活、注意点や対策は?
いまだ収まる気配のないコロナウイルス感染症。コロナとの共存は飼い主さんだけでなくペット達にも沢山の我慢やストレスを与えている事かと思います。中にはペットへの感染や自身が感染した時の対応をどうしたらよいかと悩む方も多いのではないでしょうか?そこで今回はコロナ禍でも安心してペット達と暮らす注意点やポイントをご紹介します。 ペットにもうつる? 現時点で罹患した飼い主さんのペットから新型コロナウイルスが検出された、という報告が各国からあがっています。まだ研究も進んでいませんが、ワンちゃんや猫ちゃんに確認されていることからその他のペットちゃん達にも感染するリスクがあると考えた方がいいでしょう。反対にペットから人間に感染した報告は今の所は上がっていません。ただし、コロナは依然未知のウイルスです。ウイルス保持の可能性があるペットちゃんと生活する場合には十分な注意が必要です。 犬コロナウイルス感染症は別物です ワンちゃん達が定期的に接種する混合ワクチンには予防できる疾患の中に【犬コロナウイルス感染症】という名の病気が含まれています。紛らわしいのですが、この病気は新型コロナウイルス感染症とは全くの別物になります。犬コロナウイルスは昔からあるウイルスで、罹患すると下痢や嘔吐などの消化器症状が出てしまいます。感染犬の便中にウイルスが潜んでおり、何らかの形で接触してしまうと感染します。混合ワクチンを接種していても新型コロナウイルスの感染は防ぐことができません。 ペットがコロナになるとどうなる? こちらに関してはまだ情報も少なく正確なことはわかっていません。報告された症状の中には呼吸器症状や、消化器症状があげられているようです。もしご自身の感染が発覚し、数日後からペットに何らかの症状が出てきた場合には感染を疑った方がいいでしょう。特に心臓疾患や呼吸器疾患などの持病があるペットは、飼い主さんとある程度の距離を取り、病状をよく観察してあげる必要があります。 ペットの感染対策 ペット達の感染経路は既に感染している飼い主さんとの接触と考えられます。四足歩行で視点が低く、お外でおしゃべりや飲食もしないため、外気中に浮遊しているウイルスから感染する確率は極めて低いと考えられます。動物用マスクなども販売されていますが効果の真偽はわからない上に、口呼吸の彼らにとっては非常に息苦しく危険なアイテムとなります。こういったものの使用は避けましょう。まずは清潔な生活を心がけ、飼い主さん自身が感染に注意することが感染対策となります。またペットに持病がある場合には普段飲んでいる薬を取りに行けなくなることもあるかもしれません。2週間分ほど多めにストックしておくと安心です。 飼い主が感染した場合 自身が罹患した場合、ペットをどうしたらいいか悩まれる方は多いかと思います。ホテル療養や入院になったとしても愛猫や愛犬を一人残していくわけにはいきませんよね。ただ残念ながらペットもウイルス保持している可能性があるため通常のペットショップや動物病院の利用は断られてしまうかもしれません。このような時のために事前に緊急時に預かってもらえる人を探しておきましょう。また自宅療養になった時に物資が足りなくなってしまわぬようフードやシーツは少し多めにストックを。できればサークルや大きめのケージなど感染者から隔離できるアイテムを揃えておくと万全です。中にはコロナ感染時にペットのお預かり行う保険会社さんもあります。ペット保険に加入されているようであれば一度問い合わせをしておきましょう。 まとめ いかがでしたか?神経を使う事が多く気疲れしてしまいますが、ペット達も飼い主さんの気持ちや世の中の変化を敏感に感じ取っています。気を張りすぎず、できることから行ってくださいね。感染時、誰よりも不安を感じるのは飼い主さん自身ですよね。どんなに対策を取っていても感染を避けられないこともあります。事前にしっかりと準備し、万が一の時には待っているペット達のためにも療養に集中できるようにしましょう。1日も早く、みんなが安心して過ごせるようにコロナウイルス感染症の収束を心から願っております。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
コロナ禍でのwithペット生活、注意点や対策は?
いまだ収まる気配のないコロナウイルス感染症。コロナとの共存は飼い主さんだけでなくペット達にも沢山の我慢やストレスを与えている事かと思います。中にはペットへの感染や自身が感染した時の対応をどうしたらよいかと悩む方も多いのではないでしょうか?そこで今回はコロナ禍でも安心してペット達と暮らす注意点やポイントをご紹介します。 ペットにもうつる? 現時点で罹患した飼い主さんのペットから新型コロナウイルスが検出された、という報告が各国からあがっています。まだ研究も進んでいませんが、ワンちゃんや猫ちゃんに確認されていることからその他のペットちゃん達にも感染するリスクがあると考えた方がいいでしょう。反対にペットから人間に感染した報告は今の所は上がっていません。ただし、コロナは依然未知のウイルスです。ウイルス保持の可能性があるペットちゃんと生活する場合には十分な注意が必要です。 犬コロナウイルス感染症は別物です ワンちゃん達が定期的に接種する混合ワクチンには予防できる疾患の中に【犬コロナウイルス感染症】という名の病気が含まれています。紛らわしいのですが、この病気は新型コロナウイルス感染症とは全くの別物になります。犬コロナウイルスは昔からあるウイルスで、罹患すると下痢や嘔吐などの消化器症状が出てしまいます。感染犬の便中にウイルスが潜んでおり、何らかの形で接触してしまうと感染します。混合ワクチンを接種していても新型コロナウイルスの感染は防ぐことができません。 ペットがコロナになるとどうなる? こちらに関してはまだ情報も少なく正確なことはわかっていません。報告された症状の中には呼吸器症状や、消化器症状があげられているようです。もしご自身の感染が発覚し、数日後からペットに何らかの症状が出てきた場合には感染を疑った方がいいでしょう。特に心臓疾患や呼吸器疾患などの持病があるペットは、飼い主さんとある程度の距離を取り、病状をよく観察してあげる必要があります。 ペットの感染対策 ペット達の感染経路は既に感染している飼い主さんとの接触と考えられます。四足歩行で視点が低く、お外でおしゃべりや飲食もしないため、外気中に浮遊しているウイルスから感染する確率は極めて低いと考えられます。動物用マスクなども販売されていますが効果の真偽はわからない上に、口呼吸の彼らにとっては非常に息苦しく危険なアイテムとなります。こういったものの使用は避けましょう。まずは清潔な生活を心がけ、飼い主さん自身が感染に注意することが感染対策となります。またペットに持病がある場合には普段飲んでいる薬を取りに行けなくなることもあるかもしれません。2週間分ほど多めにストックしておくと安心です。 飼い主が感染した場合 自身が罹患した場合、ペットをどうしたらいいか悩まれる方は多いかと思います。ホテル療養や入院になったとしても愛猫や愛犬を一人残していくわけにはいきませんよね。ただ残念ながらペットもウイルス保持している可能性があるため通常のペットショップや動物病院の利用は断られてしまうかもしれません。このような時のために事前に緊急時に預かってもらえる人を探しておきましょう。また自宅療養になった時に物資が足りなくなってしまわぬようフードやシーツは少し多めにストックを。できればサークルや大きめのケージなど感染者から隔離できるアイテムを揃えておくと万全です。中にはコロナ感染時にペットのお預かり行う保険会社さんもあります。ペット保険に加入されているようであれば一度問い合わせをしておきましょう。 まとめ いかがでしたか?神経を使う事が多く気疲れしてしまいますが、ペット達も飼い主さんの気持ちや世の中の変化を敏感に感じ取っています。気を張りすぎず、できることから行ってくださいね。感染時、誰よりも不安を感じるのは飼い主さん自身ですよね。どんなに対策を取っていても感染を避けられないこともあります。事前にしっかりと準備し、万が一の時には待っているペット達のためにも療養に集中できるようにしましょう。1日も早く、みんなが安心して過ごせるようにコロナウイルス感染症の収束を心から願っております。 ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

猫のかかりやすい病気Vol.2~猫風邪
季節の変わり目は体調を崩される方も多いかと思います。咳や鼻水、発熱など人間の風邪には様々な症状が現れますよね。実は猫ちゃん達にも猫風邪と呼ばれる病気が存在します。人間と同じようにウイルスに感染し発症してしまうこの病気ですが、きちんと対策することで未然に防ぐことも可能です。 猫風邪とは 猫ちゃんがウイルスに感染し、鼻水や咳、発熱など人間の風邪とよく似た症状が出ている状態を総称して猫風邪と呼んでいます。免疫力が弱い子猫や、ワクチン接種をしていない野良猫に多く見られ、感染したウイルスの種類によって【猫ウイルス性鼻気管炎】【猫カリシウイルス感染症】と分けられます。ただし、同時に感染しているケースもあること、出ている症状に対しての治療がメインになることからウイルス判定はせず治療を進めていくことが多いでしょう。 猫風邪の症状 【猫ウイルス性鼻気管炎】ヘルペスウイルスが原因となる病気で代表的な症状はくしゃみ、鼻水、発熱、目ヤニ、目のしょぼつきなどがあげられます。目が開かなくなるほどの目ヤニが出てしまう事も。【猫カリシウイルス感染症】カリシウイルスに感染することで発症する病気です。猫ウイルス性鼻気管炎と症状はほぼ同じですが、こちらは口内炎やヨダレなどお口の症状が出るのが特徴的です。口内の痛みや鼻の不調から食欲不振になる猫ちゃんも多く見られます。上記二つは症状が無くなっても体内にウイルスが残留し、一度は改善しても免疫力が低下している時に再び症状が出てきてしまうケースも少なくありません。本来は命に関わる病気ではありませんが子猫やシニアの猫ちゃんが感染すると、重症化や治療が長期化してしまうことがあるため、症状が出始めたらすぐに動物病院にかかることが大切です。 治療方法やかかる費用 軽度の場合には抗生剤や点眼薬で対症療法を行います。食事が取れないようであれば注射での治療が優先的に行われるでしょう。1回あたりの治療費は約5,000円前後となります。重度の場合には免疫力をあげるインターフェロンという注射薬が使用されます。やや高価な薬剤ですが、数日続けて注射することが理想的と言われており、治療費は1回辺り10,000円前後がかかってきます。 予防するには 予防策として最も有効な方法は混合ワクチンを接種することです。 感染の可能性がゼロになるわけではありませんが、万が一感染しても重症化を防いでくれます。ヘルペスウイルスやカリシウイルスは非常に感染力が強く、あっという間に広がってしまう厄介者です。特に野良猫ちゃんはウイルスを持っている可能性が高いため接触するとうつってしまうかもしれません。 また多頭飼いの場合、毛繕いや食器、トイレの共有で広がってしまう可能性もあります。怪しい症状が出始めたときは他の猫ちゃん達から隔離しすぐに、動物病院へ連れて行ってあげましょう。少し可哀想ですが獣医師のお墨付きがもらえるまでは完全隔離の生活が安心です。 混合ワクチンには身近な感染症から猫ちゃんを守ってくれる効果があります。定期的な接種を行い安全な生活環境を整えてあげましょう♪ ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。
猫のかかりやすい病気Vol.2~猫風邪
季節の変わり目は体調を崩される方も多いかと思います。咳や鼻水、発熱など人間の風邪には様々な症状が現れますよね。実は猫ちゃん達にも猫風邪と呼ばれる病気が存在します。人間と同じようにウイルスに感染し発症してしまうこの病気ですが、きちんと対策することで未然に防ぐことも可能です。 猫風邪とは 猫ちゃんがウイルスに感染し、鼻水や咳、発熱など人間の風邪とよく似た症状が出ている状態を総称して猫風邪と呼んでいます。免疫力が弱い子猫や、ワクチン接種をしていない野良猫に多く見られ、感染したウイルスの種類によって【猫ウイルス性鼻気管炎】【猫カリシウイルス感染症】と分けられます。ただし、同時に感染しているケースもあること、出ている症状に対しての治療がメインになることからウイルス判定はせず治療を進めていくことが多いでしょう。 猫風邪の症状 【猫ウイルス性鼻気管炎】ヘルペスウイルスが原因となる病気で代表的な症状はくしゃみ、鼻水、発熱、目ヤニ、目のしょぼつきなどがあげられます。目が開かなくなるほどの目ヤニが出てしまう事も。【猫カリシウイルス感染症】カリシウイルスに感染することで発症する病気です。猫ウイルス性鼻気管炎と症状はほぼ同じですが、こちらは口内炎やヨダレなどお口の症状が出るのが特徴的です。口内の痛みや鼻の不調から食欲不振になる猫ちゃんも多く見られます。上記二つは症状が無くなっても体内にウイルスが残留し、一度は改善しても免疫力が低下している時に再び症状が出てきてしまうケースも少なくありません。本来は命に関わる病気ではありませんが子猫やシニアの猫ちゃんが感染すると、重症化や治療が長期化してしまうことがあるため、症状が出始めたらすぐに動物病院にかかることが大切です。 治療方法やかかる費用 軽度の場合には抗生剤や点眼薬で対症療法を行います。食事が取れないようであれば注射での治療が優先的に行われるでしょう。1回あたりの治療費は約5,000円前後となります。重度の場合には免疫力をあげるインターフェロンという注射薬が使用されます。やや高価な薬剤ですが、数日続けて注射することが理想的と言われており、治療費は1回辺り10,000円前後がかかってきます。 予防するには 予防策として最も有効な方法は混合ワクチンを接種することです。 感染の可能性がゼロになるわけではありませんが、万が一感染しても重症化を防いでくれます。ヘルペスウイルスやカリシウイルスは非常に感染力が強く、あっという間に広がってしまう厄介者です。特に野良猫ちゃんはウイルスを持っている可能性が高いため接触するとうつってしまうかもしれません。 また多頭飼いの場合、毛繕いや食器、トイレの共有で広がってしまう可能性もあります。怪しい症状が出始めたときは他の猫ちゃん達から隔離しすぐに、動物病院へ連れて行ってあげましょう。少し可哀想ですが獣医師のお墨付きがもらえるまでは完全隔離の生活が安心です。 混合ワクチンには身近な感染症から猫ちゃんを守ってくれる効果があります。定期的な接種を行い安全な生活環境を整えてあげましょう♪ ▼ この記事を書いたのは ▼クリックでライターの詳細がご覧いただけます。

猫のかかりやすい病気vol.1~下部尿路疾患
猫ちゃんは、「下部尿路疾患」の発症頻度が高く愛猫家の皆さんにはとても身近な病気です。 元来、砂漠で生活していた猫たちは少量の水分でも足りるように、尿の濃度を凝縮して排泄するよう適応していきました。 ところがその体質こそが、現在では尿路疾患を発症させてしまう原因となっているのです。 下部尿路疾患とは 「下部尿路疾患」とは別名FLUTDとも呼ばれ、尿結石や膀胱炎、膀胱腫瘍、尿路感染症など猫の膀胱から尿道間に起こる尿路疾患の全てを指します。 その中でも尿結石と膀胱炎は非常に発症頻度が高く1度症状が出ると繰り返しやすいのが特徴です。 下部尿路疾患は長期的な治療や食事の管理が必要となることも多く生涯お付き合いしていくケースも少なくありません。 下部尿路疾患の主な症状 下部尿路疾患を発症すると普段と違う症状がはっきり見られます。 ・粗相してしまう ・何度もトイレに行くが少量しか出ていない ・トイレで長時間排尿姿勢を取るが出ていない(または少量) ・血尿が出る ・排尿時に痛みを感じて鳴く ・尿臭が強い ・尿の色が濃いオレンジ、または白濁しているなど普段と異なる色をしている ・落ち着かずウロウロしている このような症状が見られたときは、速やかに動物病院に連れて行ってあげて下さい。 肉眼では通常の色に見えても、尿検査をすると血液反応が出ることもあります。尿がうまく排泄されないことで腎臓やその他の臓器に負担がかかり他の病気を併発してしまう可能性もあるのです。 オスの猫ちゃん、は尿道が長く細いためメスより発症率が高い病気となりますので、特に注意してあげて下さいね。 治療方法 猫の下部尿路疾患の治療方法は症状によって大きく変わります。 まずは、尿検査を行い尿内に結晶や細菌が出ていないか検査し、その上で抗生剤の内服や注射、膀胱内のPH値を整える食事療法などを始めていきます。 尿道が閉塞し排尿が全くできない状態の場合は、尿道カテーテルを設置し、強制的に排尿する状態にした上で、食事療法や抗生剤、場合によっては外科的な手術で治療を進めていきます。 また結晶、結石が確認できても尿道の閉塞がなく、食事で溶かせる石であれば外科的手術を避けることも可能です。 症状別の治療費 下部尿路疾患の治療費は、初期の膀胱炎で1万5千円前後、外科的な処置が必要になった場合は、入院費や術後の管理費を含め15~20万前後が相場になります。 ただし、この他に食事療法が必要となると、別途1ヶ月で約5000円の療法食代がかかります。 猫ちゃんの下部尿路疾患は発症率も高く、回復後も定期的なチェックやケアが必要となる事も多いので、ある程度の追加の費用もかかると考えておきましょう。 自宅で行う治療や予防方法...
猫のかかりやすい病気vol.1~下部尿路疾患
猫ちゃんは、「下部尿路疾患」の発症頻度が高く愛猫家の皆さんにはとても身近な病気です。 元来、砂漠で生活していた猫たちは少量の水分でも足りるように、尿の濃度を凝縮して排泄するよう適応していきました。 ところがその体質こそが、現在では尿路疾患を発症させてしまう原因となっているのです。 下部尿路疾患とは 「下部尿路疾患」とは別名FLUTDとも呼ばれ、尿結石や膀胱炎、膀胱腫瘍、尿路感染症など猫の膀胱から尿道間に起こる尿路疾患の全てを指します。 その中でも尿結石と膀胱炎は非常に発症頻度が高く1度症状が出ると繰り返しやすいのが特徴です。 下部尿路疾患は長期的な治療や食事の管理が必要となることも多く生涯お付き合いしていくケースも少なくありません。 下部尿路疾患の主な症状 下部尿路疾患を発症すると普段と違う症状がはっきり見られます。 ・粗相してしまう ・何度もトイレに行くが少量しか出ていない ・トイレで長時間排尿姿勢を取るが出ていない(または少量) ・血尿が出る ・排尿時に痛みを感じて鳴く ・尿臭が強い ・尿の色が濃いオレンジ、または白濁しているなど普段と異なる色をしている ・落ち着かずウロウロしている このような症状が見られたときは、速やかに動物病院に連れて行ってあげて下さい。 肉眼では通常の色に見えても、尿検査をすると血液反応が出ることもあります。尿がうまく排泄されないことで腎臓やその他の臓器に負担がかかり他の病気を併発してしまう可能性もあるのです。 オスの猫ちゃん、は尿道が長く細いためメスより発症率が高い病気となりますので、特に注意してあげて下さいね。 治療方法 猫の下部尿路疾患の治療方法は症状によって大きく変わります。 まずは、尿検査を行い尿内に結晶や細菌が出ていないか検査し、その上で抗生剤の内服や注射、膀胱内のPH値を整える食事療法などを始めていきます。 尿道が閉塞し排尿が全くできない状態の場合は、尿道カテーテルを設置し、強制的に排尿する状態にした上で、食事療法や抗生剤、場合によっては外科的な手術で治療を進めていきます。 また結晶、結石が確認できても尿道の閉塞がなく、食事で溶かせる石であれば外科的手術を避けることも可能です。 症状別の治療費 下部尿路疾患の治療費は、初期の膀胱炎で1万5千円前後、外科的な処置が必要になった場合は、入院費や術後の管理費を含め15~20万前後が相場になります。 ただし、この他に食事療法が必要となると、別途1ヶ月で約5000円の療法食代がかかります。 猫ちゃんの下部尿路疾患は発症率も高く、回復後も定期的なチェックやケアが必要となる事も多いので、ある程度の追加の費用もかかると考えておきましょう。 自宅で行う治療や予防方法...

愛犬・愛猫との別れに立ち直れない時は
先日、オーエフティースタッフの1人が、愛犬とのお別れを経験しました。普段は明るく元気いっぱいの同僚が、がっくり気を落としている姿を見て、少しでも気持ちを共鳴し、また同じ経験をされている飼い主さんの気持ちがほんの少しでも落ち着けたらと思い、こちらのブログを書かせて頂きました。ペットとの新しい出会いがある反面、悲しい別れを受け止めなければならない現実もまたあります。最愛のペットとの別れは突然色々な形でやって来ます。彼らとの思い出、残された生活空間は一層悲しみを深くし、自責の念にとらわれ、ただただ涙が溢れ、何も手に付かないそんな時間が過ぎて行きます。 どれだけ彼らによって自分が支えられていたのかを改めてひしひしと感じることもあるでしょう。 大切なペットを失い、悲しみのあまり塞ぎこんでしまう方は少なくありません。この様な感情の動きはペットロスと呼ばれ、時にペットロス症候群の始まりでもあるのです。 ペットロスとペットロス症候群 ペットロスとはペットを失った飼い主さん自身の悲しみ、喪失感、怒り、または罪悪感を持つといった感情です。ペットと一緒に暮らしていた方ならば誰にでも起こる可能性があるため、自分はおかしいのかな…など心配はしないで下さい。しかし、時に大きな喪失感が精神的・身体的な症状が強く出てしまい、治療を必要とするペットロス症候群になってしまうこともあるため、注意もまた必要です。 ペットロス症候群の症状とは ペットロス症候群の症状は様々で、頭痛、腹痛、肩こり、便秘、下痢、不眠、食欲不振、過食など身体の症状だけでなく、• 悲しみから立ち直れず突然涙が溢れてしまう。• 仕事や趣味に対して意欲や関心がうすれ、やる気がなくなってしまう。• ペットがいなくなってしまったのは自分のせいだと罪悪感に押しつぶされてしまう。といった精神的な症状もあるのです。無理やり感情を抑えこむ行為は逆効果になってしまうため、感情のままに目いっぱい悲しみ、思いきり泣いて下さい。しかし、このような状態が続くようでしたら、一度専門医に相談してみましょう。個々の疾患から症候群と自覚する事は難しく、精神面の変化から総合的に診断されるからです。 ペットロスとの付き合い方 無理に明るく振舞ったり乗り越えようとしたりせず、まずは別れを前向きに受け入れていけることが大切です。ペットとの思い出を何かしらの形で残すことは、一見思いが断ち切れずペットロスが長引いてしまいそうですが、気持ちの整理がつきやすくなる場合があります。使っていた道具などはすぐに処分せず、手元に残していても問題はありません。ペットの似顔絵やそっくりなぬいぐるみなど、楽しかった思い出を忘れないよう形として残しておくのも1つです。また、しっかりと別れと向き合えるようペット葬にてお別れをする方も増えています。人間と同じように葬儀をすることにより様々な思い出を振り返りながら、気持ちを整理することができるのです。それでも辛くなってしまう場合はSNSなどで同じ境遇の方と交流し、今の心境を話してみてはいかがでしょう。同じ体験をした方と話すことで抱えていたものが軽くなるかもしれません。また、お別れしたペットを取り上げた書籍も随分と支えになりますのでお勧めします。 新しい犬・猫を迎え入れて良いのか 「この悲しみや辛さはもう体験したくない。」「ペットはもう飼えない」と思う方もいれば、「またペットと共に生きる楽しさを感じたい。」「困っているペットを救いたい」と考える方もいるでしょう。二匹目をお迎えするということに正解・不正解はありません。先代のペットへの罪悪感から二匹目が飼えない方もいますし、先代同様たっぷりの愛情で新たな子を迎え暮らしていく方もいます。数年たって、心境や環境の変化から新しい子を迎えたという方も少なくはありません。飼い主さん自身でしっかり悩んで考えた結果であれば、どちらでも良いのです。 親しい人がペットロスになった時の接し方 親しい人がペットロスになったら、あなたはどのように声をかけますか?同じ経験をしたことがある、ないでも変わりますが、共通して言えることはその人の気持ちに寄り添うことです。何か提案をしたり、無理に励ましの言葉を探したりする必要はありません。とにかく相手の気が休まるまで話を聞き、その人の気持ちを受け入れてあげるだけで良いのです。この時、相手を責めるような言葉や安易な言葉を言わないことが大切です。話を聞こうと相手が言いたくないことまで言わせようとする質問もNGです。• 寂しいなら二匹目を飼ったらどうか• (まだ若いのに)(そんな亡くなり方は)可哀そうだね• どうして亡くなったの?このような言葉は相手を深く傷つけることがあるので口にはしないで下さい。あくまでも相手に任せ、聞き役として接してあげましょう。話を聞いてあげる以外にも、祭壇に飾るお花・線香を贈る行為もあります。あなたの優しい言動により、きっと相手も心が落ち着くはずでしょう。ペットと飼い主さんとの絆が深く、飼い主さん自身の感受性が高ければ高いほど、ペットロスの症状が強く出てきます。大切な家族との別れに、大きな喪失感を感じない人はいません。人に話しにくい、話したくないという思いもあるかもしれませんが、1人で塞ぎこんでしまい辛い時は、周りの親しい人や専門医に相談することも大切です。今の気持ちを伝えて心の支えとなってもらう事が大事なのです。 ▼ この記事を書いたのは ▼
愛犬・愛猫との別れに立ち直れない時は
先日、オーエフティースタッフの1人が、愛犬とのお別れを経験しました。普段は明るく元気いっぱいの同僚が、がっくり気を落としている姿を見て、少しでも気持ちを共鳴し、また同じ経験をされている飼い主さんの気持ちがほんの少しでも落ち着けたらと思い、こちらのブログを書かせて頂きました。ペットとの新しい出会いがある反面、悲しい別れを受け止めなければならない現実もまたあります。最愛のペットとの別れは突然色々な形でやって来ます。彼らとの思い出、残された生活空間は一層悲しみを深くし、自責の念にとらわれ、ただただ涙が溢れ、何も手に付かないそんな時間が過ぎて行きます。 どれだけ彼らによって自分が支えられていたのかを改めてひしひしと感じることもあるでしょう。 大切なペットを失い、悲しみのあまり塞ぎこんでしまう方は少なくありません。この様な感情の動きはペットロスと呼ばれ、時にペットロス症候群の始まりでもあるのです。 ペットロスとペットロス症候群 ペットロスとはペットを失った飼い主さん自身の悲しみ、喪失感、怒り、または罪悪感を持つといった感情です。ペットと一緒に暮らしていた方ならば誰にでも起こる可能性があるため、自分はおかしいのかな…など心配はしないで下さい。しかし、時に大きな喪失感が精神的・身体的な症状が強く出てしまい、治療を必要とするペットロス症候群になってしまうこともあるため、注意もまた必要です。 ペットロス症候群の症状とは ペットロス症候群の症状は様々で、頭痛、腹痛、肩こり、便秘、下痢、不眠、食欲不振、過食など身体の症状だけでなく、• 悲しみから立ち直れず突然涙が溢れてしまう。• 仕事や趣味に対して意欲や関心がうすれ、やる気がなくなってしまう。• ペットがいなくなってしまったのは自分のせいだと罪悪感に押しつぶされてしまう。といった精神的な症状もあるのです。無理やり感情を抑えこむ行為は逆効果になってしまうため、感情のままに目いっぱい悲しみ、思いきり泣いて下さい。しかし、このような状態が続くようでしたら、一度専門医に相談してみましょう。個々の疾患から症候群と自覚する事は難しく、精神面の変化から総合的に診断されるからです。 ペットロスとの付き合い方 無理に明るく振舞ったり乗り越えようとしたりせず、まずは別れを前向きに受け入れていけることが大切です。ペットとの思い出を何かしらの形で残すことは、一見思いが断ち切れずペットロスが長引いてしまいそうですが、気持ちの整理がつきやすくなる場合があります。使っていた道具などはすぐに処分せず、手元に残していても問題はありません。ペットの似顔絵やそっくりなぬいぐるみなど、楽しかった思い出を忘れないよう形として残しておくのも1つです。また、しっかりと別れと向き合えるようペット葬にてお別れをする方も増えています。人間と同じように葬儀をすることにより様々な思い出を振り返りながら、気持ちを整理することができるのです。それでも辛くなってしまう場合はSNSなどで同じ境遇の方と交流し、今の心境を話してみてはいかがでしょう。同じ体験をした方と話すことで抱えていたものが軽くなるかもしれません。また、お別れしたペットを取り上げた書籍も随分と支えになりますのでお勧めします。 新しい犬・猫を迎え入れて良いのか 「この悲しみや辛さはもう体験したくない。」「ペットはもう飼えない」と思う方もいれば、「またペットと共に生きる楽しさを感じたい。」「困っているペットを救いたい」と考える方もいるでしょう。二匹目をお迎えするということに正解・不正解はありません。先代のペットへの罪悪感から二匹目が飼えない方もいますし、先代同様たっぷりの愛情で新たな子を迎え暮らしていく方もいます。数年たって、心境や環境の変化から新しい子を迎えたという方も少なくはありません。飼い主さん自身でしっかり悩んで考えた結果であれば、どちらでも良いのです。 親しい人がペットロスになった時の接し方 親しい人がペットロスになったら、あなたはどのように声をかけますか?同じ経験をしたことがある、ないでも変わりますが、共通して言えることはその人の気持ちに寄り添うことです。何か提案をしたり、無理に励ましの言葉を探したりする必要はありません。とにかく相手の気が休まるまで話を聞き、その人の気持ちを受け入れてあげるだけで良いのです。この時、相手を責めるような言葉や安易な言葉を言わないことが大切です。話を聞こうと相手が言いたくないことまで言わせようとする質問もNGです。• 寂しいなら二匹目を飼ったらどうか• (まだ若いのに)(そんな亡くなり方は)可哀そうだね• どうして亡くなったの?このような言葉は相手を深く傷つけることがあるので口にはしないで下さい。あくまでも相手に任せ、聞き役として接してあげましょう。話を聞いてあげる以外にも、祭壇に飾るお花・線香を贈る行為もあります。あなたの優しい言動により、きっと相手も心が落ち着くはずでしょう。ペットと飼い主さんとの絆が深く、飼い主さん自身の感受性が高ければ高いほど、ペットロスの症状が強く出てきます。大切な家族との別れに、大きな喪失感を感じない人はいません。人に話しにくい、話したくないという思いもあるかもしれませんが、1人で塞ぎこんでしまい辛い時は、周りの親しい人や専門医に相談することも大切です。今の気持ちを伝えて心の支えとなってもらう事が大事なのです。 ▼ この記事を書いたのは ▼

犬のかかりやすい病気vol.1~外耳炎
犬の耳は入り口から鼓膜までがL字型になっています。そのため耳内が非常に蒸れやすく外耳炎を引き起こすことも珍しくありません。 特に梅雨~夏場は要注意シーズンになりますので、少しでも外耳炎について知り、もしもの時に落ち着いて対処できるようにしましょう。 犬の外耳炎とは 外耳炎とは耳内で細菌が増殖し炎症を起こしている状態を指します。 外耳炎になると耳内に赤みが見られ、強い痒みや痛みを感じるようになるため、耳の違和感から頭を振る、耳を床にこすりつけるなどの仕草が見られることも。 また症状が重篤化すると、膿状の耳ダレが出てくることや耳道が腫れ、聴力に支障をきたすこともあります。 原因となるマラセチア菌は常在菌ですから、他の犬や飼い主さんにうつることはないので安心して下さい。 治療について 外耳炎の治療期間や費用は、自由診療のため病院や症状の度合いによって大きく変わります。 症状が軽度であれば完治までにかかる期間は約2週間、費用は1~2万円前後ですが、重度の場合は定期通院の他、耳洗浄や外用薬、内服薬、顕微鏡検査、細菌培養検査などが必要となり期間は数か月から1年かかってしまうケースも。 また費用は数か月でも5万円前後になります。 治療方法 外耳炎の治療方法は様々ですが、「点耳薬」という耳の中に直接滴下する薬を使用した治療方法が一般的です。 耳垢や耳ダレがひどい場合には、まず「耳洗浄」を行い、耳の中の汚れを全て外に出してから点耳薬を使用します。耳洗浄、点耳薬で改善が乏しい場合や、治療開始時点で既に症状が重度の場合には抗生剤や抗菌剤の内服薬も併せて服用します。 点耳薬を滴下したあとは耳介部分にも指の腹を使って薬液を塗り込み、更に耳の外側から耳道部分を揉んであげるとより薬液が耳内に浸透し効果が発揮されます。 点耳薬が苦手な犬もいるため液体タイプの他に軟膏タイプや一度の滴下で効果が長期間継続するタイプの点耳薬など様々な薬も発売されています。 ■ウェルメイトL3 主に病院での治療に使用されることが多い液体タイプの点耳薬です。毎日1回~2回耳内に入れて使用します。 ■ヒビクス(ドルバロン) 軟膏タイプの点耳薬です。耳だけでなく皮膚に使用することもあります。※現在ドルバロンは廃盤になり、ヒビクスで代用されています。 ■オスルニア 1週間効果が持続する粘液状の点耳薬です。基本的には2回の使用で改善が認められます。 ■ネプトラ 1度の点耳で効果が28日間継続する粘液状の点耳薬です。症状が軽度の場合には追加の点耳は必要なく1回きりの点耳で治療は終了します。 間違いやすいその他の病気 外耳炎と似た症状が出る病気が「耳血腫」です。初期は外耳炎と同様に頭を振る、耳をこすりつける、など外耳炎によく似た症状が見られます。 耳血腫は外耳の皮膚と軟骨の間に血液がたまりぷっくりと腫れてしまう病気で、外傷や外耳炎の悪化が起因となり発症します。 外耳炎とは異なり外科的な処置が必要となりますが外耳炎を併発している場合にはそちらの治療も合わせて行っていきます。 予防しましょう 外耳炎は日頃のケアである程度予防できる疾患です。...
犬のかかりやすい病気vol.1~外耳炎
犬の耳は入り口から鼓膜までがL字型になっています。そのため耳内が非常に蒸れやすく外耳炎を引き起こすことも珍しくありません。 特に梅雨~夏場は要注意シーズンになりますので、少しでも外耳炎について知り、もしもの時に落ち着いて対処できるようにしましょう。 犬の外耳炎とは 外耳炎とは耳内で細菌が増殖し炎症を起こしている状態を指します。 外耳炎になると耳内に赤みが見られ、強い痒みや痛みを感じるようになるため、耳の違和感から頭を振る、耳を床にこすりつけるなどの仕草が見られることも。 また症状が重篤化すると、膿状の耳ダレが出てくることや耳道が腫れ、聴力に支障をきたすこともあります。 原因となるマラセチア菌は常在菌ですから、他の犬や飼い主さんにうつることはないので安心して下さい。 治療について 外耳炎の治療期間や費用は、自由診療のため病院や症状の度合いによって大きく変わります。 症状が軽度であれば完治までにかかる期間は約2週間、費用は1~2万円前後ですが、重度の場合は定期通院の他、耳洗浄や外用薬、内服薬、顕微鏡検査、細菌培養検査などが必要となり期間は数か月から1年かかってしまうケースも。 また費用は数か月でも5万円前後になります。 治療方法 外耳炎の治療方法は様々ですが、「点耳薬」という耳の中に直接滴下する薬を使用した治療方法が一般的です。 耳垢や耳ダレがひどい場合には、まず「耳洗浄」を行い、耳の中の汚れを全て外に出してから点耳薬を使用します。耳洗浄、点耳薬で改善が乏しい場合や、治療開始時点で既に症状が重度の場合には抗生剤や抗菌剤の内服薬も併せて服用します。 点耳薬を滴下したあとは耳介部分にも指の腹を使って薬液を塗り込み、更に耳の外側から耳道部分を揉んであげるとより薬液が耳内に浸透し効果が発揮されます。 点耳薬が苦手な犬もいるため液体タイプの他に軟膏タイプや一度の滴下で効果が長期間継続するタイプの点耳薬など様々な薬も発売されています。 ■ウェルメイトL3 主に病院での治療に使用されることが多い液体タイプの点耳薬です。毎日1回~2回耳内に入れて使用します。 ■ヒビクス(ドルバロン) 軟膏タイプの点耳薬です。耳だけでなく皮膚に使用することもあります。※現在ドルバロンは廃盤になり、ヒビクスで代用されています。 ■オスルニア 1週間効果が持続する粘液状の点耳薬です。基本的には2回の使用で改善が認められます。 ■ネプトラ 1度の点耳で効果が28日間継続する粘液状の点耳薬です。症状が軽度の場合には追加の点耳は必要なく1回きりの点耳で治療は終了します。 間違いやすいその他の病気 外耳炎と似た症状が出る病気が「耳血腫」です。初期は外耳炎と同様に頭を振る、耳をこすりつける、など外耳炎によく似た症状が見られます。 耳血腫は外耳の皮膚と軟骨の間に血液がたまりぷっくりと腫れてしまう病気で、外傷や外耳炎の悪化が起因となり発症します。 外耳炎とは異なり外科的な処置が必要となりますが外耳炎を併発している場合にはそちらの治療も合わせて行っていきます。 予防しましょう 外耳炎は日頃のケアである程度予防できる疾患です。...

小さな命をみんなで守る、ペット用支援物資
災害はいつ起こるかわかりません。いざという時のために用意していた避難道具も持参できず、避難することになってしまう場合もあるでしょう。また、準備しておいたものの、足りなかったり、入れ忘れがあったりするかもしれません。そんな時に助けてくれるのが支援物資です。ペット用支援物資とはどのようなものが届くのか、こちらから被災地にペット用支援物資を送るためにはどうしたらいいのかについて詳しくご紹介いたします。 災害時のペット達の現状 2021年7月3日に熱海で大規模な土砂災害が起こりました。大切なパートナーであるペットですが、まだまだ受け入れ体制が整っていないのが現状です。一緒に避難できず迷子になってしまうペット達も多いため、緊急状態の中で、救助したペットを保護するだけでも相当な労力を費やすことになります。 ボランティア団体は行き場をなくした小さなペット達の命を守るため、救助活動や保護活動に尽力してくれていますが、限界もあります。飼い主さんを探しながら、全国からの支援物資や寄附金を呼びかけ動物のレスキュー団体と共に活動しています。 全国から送られてくる支援物資が頼りになるのです。 災害時に届くペット用支援物資 災害時には全国から支援物資や寄附金を呼びかけますが、ペット用の支援物資はどのような物が届くのでしょうか。災害時に寄付をお願いする物資は次のように日常品が中心となっています。 • ペットフード • ペットシーツ • 毛布やタオル • 犬猫用ミルク • 犬猫用オムツ • サークルやケージ • 猫砂 • ティッシュペーパーやトイレットペーパー 普段の生活で使用しているものだからこそ、ペット達にとって貴重な物資となるのです。 自分で準備しておくべきもの ▲SOSペットバッグ 災害はいつ起こるかわからないからこそ、事前の準備が重要になります。欲しい物が支援物資に含まれていない場合もありますので、それを踏まえ何が必要なのか備えておきましょう。支援物資は届くまでに数日から数週間かかることもあるので、最低でも5日分は用意しておくとよいですね。【準備しておくべきもの】• ペットフード・水支援物資はドライフードがメインなので、決まったフードしか食べない子や療法食などの場合は特に準備が必要です。•...
小さな命をみんなで守る、ペット用支援物資
災害はいつ起こるかわかりません。いざという時のために用意していた避難道具も持参できず、避難することになってしまう場合もあるでしょう。また、準備しておいたものの、足りなかったり、入れ忘れがあったりするかもしれません。そんな時に助けてくれるのが支援物資です。ペット用支援物資とはどのようなものが届くのか、こちらから被災地にペット用支援物資を送るためにはどうしたらいいのかについて詳しくご紹介いたします。 災害時のペット達の現状 2021年7月3日に熱海で大規模な土砂災害が起こりました。大切なパートナーであるペットですが、まだまだ受け入れ体制が整っていないのが現状です。一緒に避難できず迷子になってしまうペット達も多いため、緊急状態の中で、救助したペットを保護するだけでも相当な労力を費やすことになります。 ボランティア団体は行き場をなくした小さなペット達の命を守るため、救助活動や保護活動に尽力してくれていますが、限界もあります。飼い主さんを探しながら、全国からの支援物資や寄附金を呼びかけ動物のレスキュー団体と共に活動しています。 全国から送られてくる支援物資が頼りになるのです。 災害時に届くペット用支援物資 災害時には全国から支援物資や寄附金を呼びかけますが、ペット用の支援物資はどのような物が届くのでしょうか。災害時に寄付をお願いする物資は次のように日常品が中心となっています。 • ペットフード • ペットシーツ • 毛布やタオル • 犬猫用ミルク • 犬猫用オムツ • サークルやケージ • 猫砂 • ティッシュペーパーやトイレットペーパー 普段の生活で使用しているものだからこそ、ペット達にとって貴重な物資となるのです。 自分で準備しておくべきもの ▲SOSペットバッグ 災害はいつ起こるかわからないからこそ、事前の準備が重要になります。欲しい物が支援物資に含まれていない場合もありますので、それを踏まえ何が必要なのか備えておきましょう。支援物資は届くまでに数日から数週間かかることもあるので、最低でも5日分は用意しておくとよいですね。【準備しておくべきもの】• ペットフード・水支援物資はドライフードがメインなので、決まったフードしか食べない子や療法食などの場合は特に準備が必要です。•...