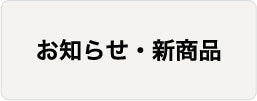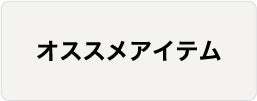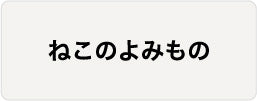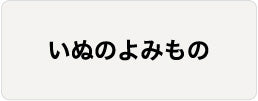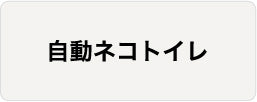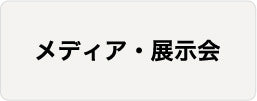2022年以降、販売される犬と猫にはマイクロチップ装着が義務化されました。
ワンちゃんは畜犬登録にマイクロチップの識別番号を使うようになり、飼い主さんへの浸透も早かったように感じています。それに対し猫ちゃんは役所で手続きをすることもなく、使うタイミングが少ないため、まだマイクロチップ自体を認知していない飼い主さんも多いようです。
そもそも使いどころがよくわからないと、必要なものなのかも判断できませんよね。
そこで今回は猫ちゃんのマイクロチップにまつわる情報をまとめてみました!
マイクロチップとは

マイクロチップは皮膚の下に挿入する電子チップのことです。直径1.2mm、長さ8mm程の小さなもので麻酔を使わず挿入できます。
皮膚の上から専用リーダーをかざすとマイクロチップに記憶された識別番号が表示され、その番号と紐付けされた飼い主さんの情報を見られるというシステム。
マイクロチップ本体は電波を発信することはありませんが、リーダーの電波に反応して番号を送り返すことができる仕組みになっており、一度入れると生涯交換の必要はありません。
猫ちゃんがマイクロチップをつける理由

完全室内飼いの猫ちゃんだと、マイクロチップの必要性を感じないかもしれませんが、どのような生活環境であっても装着はしておくべきです。
・脱走
・迷子
・災害時
こういった時に1つの安心材料となるのがマイクロチップなのです。
玄関が開いた瞬間や、窓の隙間から思わぬタイミングで脱走してしまうケースも少なくありません。
勤務先の動物病院にも保護された猫ちゃんが来院しますが、人懐っこく体も綺麗で迷子なんじゃないか…と感じる子もしばしばいます。ほとんどの動物病院がマイクロチップリーダーを持っていますので、マイクロチップさえ入っていればこの段階で飼い主さんにご連絡ができるのです。
マイクロチップの義務化は、遺棄や外での繁殖を防止する意味も兼ねていますが、飼い主さんにとっては行方不明時の手がかりの1つとしての意味が大きくなります。
マイクロチップの手続き

マイクロチップは、識別番号と飼い主さんの情報を紐付けすることが重要です。以下を参考に手続きをぜひ進めてみましょう!
■マイクロチップを挿入している子を迎えた
ペットショップやブリーダーさんからお迎えした子であれば、既にマイクロチップは装着されているはずです。チップ内には繁殖元、あるいは販売元の情報が記憶されているので、まずは飼い主さんの情報に書き換えましょう。
環境省の【犬と猫のマイクロチップ情報登録】のページから登録作業を行ってください。この時、販売元から渡される【登録証明書】が必要となりますので手元に用意しておくとスムーズです。
■動物病院でマイクロチップを挿入した
動物病院が発行する【装着証明書】を使って登録手続きを行います。
■マイクロチップは入っているが、番号がわからない
どこの動物病院でもいいので、リーダーを使ってマイクロチップが入っている事を伝え、その番号を確認してもらいましょう。
その後【マイクロチップ識別番号証明書】という書類を発行してもらってください。これが装着証明書の代わりになります。
■過去にマイクロチップを挿入しているが、環境省のデータベースに未登録
こちらは【移行登録申請】の書類を提出します。ただ装着日や装着した獣医師の名前などが必要で、書類作成が難しい場合は上記のマイクロチップ識別番号証明書を発行してもらう手順でも問題ないでしょう。
環境省:Q30移行登録手順
どこに該当するのかわからない時は、直接問い合わせてみてくださいね。
装着するか迷ったときは

マイクロチップを装着するか迷う方も多いと思います。体に電子チップをいれて大丈夫なのか、痛くはないのか、不安も心配もありますよね。
個人的には、若く持病がない子にはぜひ積極的に取り入れて欲しいと思いますが、ハイシニアや持病がある子は、かかりつけの獣医師に相談してみましょう。
愛猫がいなくなり、涙を流す飼い主さんをたくさん見てきました。マイクロチップで飼い主さんを見つけたこともあります。
ただ17年動物病院で勤務して、マイクロチップのせいで体調が悪くなった子は見たことがありません。いざという時に、飼い主さんと愛猫を繋ぐものは多いに越したことはありませんよね。
まずは相談だけでもOKです。悩んだ時は、かかりつけの動物病院で話を聞いてみてくださいね。